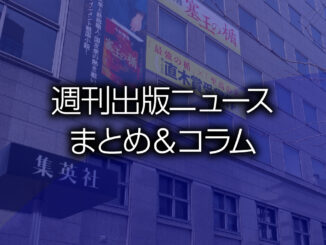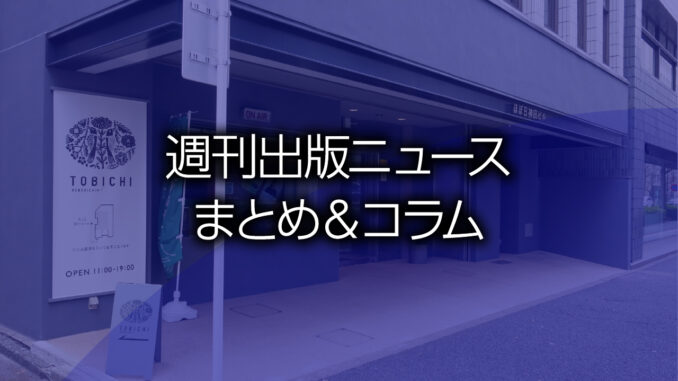
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2022年11月27日~12月3日は「インボイス制度、小規模事業者の負担軽減を経過措置に」「一太郎2023でブラウザ校正」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
ステマ広告検討会、報告書案を取りまとめ インフルエンサーやアフィリエイトも「PR」の表記必須に〈日本ネット経済新聞(2022年11月29日)〉
消費者庁「ステルスマーケティングに関する検討会」から報告書(案)が出ました。改めて目を通してみましたが、“事業者が「表示内容の決定に関与した」”ことが要件になっており、思っていたより緩い印象を受けました。これなら、#547で書いた“アフィリエイターが「Amazonアソシエイト」のリンク周辺に【広告】と表記しないと、ステマ規制に引っかかる”ようなことには、ならないかな。心配し過ぎだったかも。
ただ、「例えば、以下のような場合が考えられる」という例示の中で、「著名人やインフルエンサー」とだけ表現されている箇所が多いのが若干気になります。個人/法人問わず同じことが言えるわけですから、せめて「等」を付けて欲しい。p32で指摘されている「ノンクレタイアップ記事」=記事広告(タイアップ)なのに広告表示がなく編集記事を装っているような場合も、ステマですからね。パブリックコメントには、そういう意見を送ろうと思います。
小規模事業者のインボイス負担軽減へ、自公税調が一致〈日本経済新聞(2022年11月30日)〉
最終的に、既報の「売上高1000万円以下の免税事業者が課税事業者になる場合、納税額を売上税額の2割に抑える」という3年間の特例と、「売上高1億円以下の事業者は、1万円未満の少額取引はインボイスがなくても仕入税額控除が受けられる」という6年間の特例を設ける形に着地しました。
個人的には、時限措置である点には強い不満がありますが、もう止めるのが難しい実施直前まで来た段階でマイナス100をマイナス30くらいに押し戻した点は評価したいと思います。正直、参院選のころは、それさえ難しいと思ってましたから。まあ、マイナスはマイナスですが。あとはこの3年、6年という猶予を有効的に活用し、次の手を打つことを望みます。
なお、少額取引の特例について、#547で「事務処理件数が多い大規模事業者のほうが助かる措置」と書いてしまったのですが、元記事を改めて読んでみたら、当時から「売上高1億円以下」に絞る方向で検討されていることが明記されてました。こんなの見落とすかなあ……大変失礼いたしました。
インボイス制度の導入は増税地獄の布石である…「誰も得しない制度」を財務省が必死で通そうとするワケ そもそも「益税」という指摘が見当違い〈PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)(2022年11月29日)〉
インボイス制度関連で、こちらの記事はタイトルが若干煽り気味ではありますが、経緯や現状、財務省の狙い、問題点などがきっちりまとまっています。とくに、軽減税率の対象になっている新聞が「首根っこをつかまれた状態」であることを改めて指摘しているのが良い。インボイス制度は軽減税率ありきですから、新聞はうかつなこと書けないはずなんですよね。
つくばエクスプレス側に賠償命令 本社記事を無断使用〈日本経済新聞(2022年11月30日)〉
記事800本以上を画像データにして社内イントラで共有していたことが、著作権侵害と判断され459万5000円の損害賠償が命じられた判決。紙面のスクラップをスキャンして共有していた、ということなのでしょう。企業内だから、私的使用目的の複製(第30条)には該当しないんですよね。
実態として、企業内でそういうことやっちゃってる(しかも合法だと思っている)ケースはけっこう多い気がします。閉じた場であっても、内部告発等でバレるんですよね。クラウドストレージを使うと、カジュアルに共有できちゃうから怖い。気をつけましょう。
「言いがかりともいえる内容」 三才ブックス、鳥取県の“有害図書”指定理由をPDF公開〈ITmedia NEWS(2022年11月30日)〉
#535で取り上げた、鳥取県による「火の玉ストレートの表現規制」の続報です。当時は有害図書指定した理由も不透明だし、議事録もろくに残っていないありさまでした。その後、9月には具体的な指定理由の回答が届いており、今回は、審査用書籍の購入記録や購入手続きに関する資料が開示されたとのこと。
審査のために購入した10冊のうち9冊が有害図書指定されていることから、4月に電話で「無作為に選んだ」と回答されたこととの食い違いが起きていることなどが指摘されています。正直、こうした抗議で有害指定がひっくり返る可能性は低いとは思いますが、プロセスがおかしいという指摘には妥当性があります。おそらく、今後の審査は慎重になることでしょう。そういう意味で、意義のある抗議だと思います。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
「最近の若者は本を読まない」というのは本当か?調査からみえた「意外な実態」(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2022年11月28日)〉
全国学校図書館協議会「学校読書調査」2022年版についての、飯田一史さんによる毎年恒例の解説。「若者の本離れ」論は根拠レスでも根強く流布し続けてますから、毎年でも「それは俗説だ」と言い続ける必要があるでしょう。なお、#544でも書きましたが、この調査における「本」は、「電子書籍を含み、マンガや雑誌は除きます」です。中学生では人気マンガ(ジャンプ)のノベライズが多くランク入りしており、そりゃもちろんマンガも読まれてるだろうよ、という感があります。
経済
電子書籍出版における選択肢とは〈版元ドットコム(2022年11月30日)〉
フリードゲート社の方による、「電子書籍の販路獲得」についてのコラムです。書店からの戻し料率が、同じ新規取引でも取次や配信代行会社によってさまざまなので注意が必要、というあたりが興味深い。まあ、セルフ・パブリッシングやその延長上にあるディストリビューションサービスでも条件は各社各様なので、出版社でも同様なのだなという感じではありますが。
ちょっと気になったのが、選択肢3つの1番目「直接販売」について。これは「直接販売」ではなく、正確には「電子書店との直接取引」と呼ぶべきでしょう。「直接販売」という表現からは、たとえばネットショップを自社で運営できる「Shopify」の「Digital Downloads」機能を使うとか、WordPress+WooCommerceなどのやり方が想像されます。
つまり、選択肢は4つあるのではないか、と。本来の意味での「直接販売」は難易度が高いのは確かですが、出版社に入る額は最も高くなりますし、誰が購入したか? を把握できるのが非常に大きいと思うのです。販売がすべて他人任せだと、顧客を知ることが難しくなっちゃいます。デジタル出版論の連載でも書いたように「パブリッシャーはユーザーとの直接取引を増やしていくべき」だと思います。
「一太郎2023」にWebブラウザー上で文章校正をリアルタイムに行なう「JUSTチェッカー」が搭載〈窓の杜(2022年12月1日)〉
記事タイトルを読んで「どういうこと?」と思ったんですが、ブラウザでの文章入力時に校正を支援してくれるChrome/Edgeの拡張機能が「一太郎2023」本体とは別に提供される、という意味でした。従来、校正機能は「一太郎」の中にありましたが、これによりブラウザでも使えるようになることに。「一太郎2023」のインストールは必須とあるので、モジュールを共有しているんでしょうね。
問題はお値段。校正支援の専用ツール「Just Right!7 Pro」の個人向けダウンロード版が税込5万1700円に対し、今回から新設された「ATOK Passport ユーザー優待版」の「一太郎」なら税込4950円です。ATOK Passport[プレミアム]年間プラン(税込7920円)の契約が必要ではありますが、けっこう魅力的。私の場合、ブラウザでの入力が大半(Googleドキュメント)なので、ほぼ常用できそう。買おうかな。
オリジナルマンガは動画配信の成長に必要? U-NEXTがマンガを作る理由〈Impress Watch(2022年12月2日)〉
U-NEXTがオリジナルコミックレーベルを立ち上げ。プラットフォームが、オリジナルIP制作で差別化を図っていく動きの1つと言っていいでしょう。以前、菊池健さんに寄稿いただいた「ぶんか社グループ買収に見る電子コミック業界の成熟と再編 ―― プラットフォームビジネス成長の3ステップとオリジナルIP制作」と同種の動きです。U-NEXTオリジナル書籍は著名作家の書き下ろしが中心でしたが、コミックは「腰を据えてヒット創出に取り組む」とのこと。いつまで我慢して投資し続けられるか、注視したいと思います。
なお、映像配信系のニュースなので見落としそうになったのですが、このタイミングでDMMが映像配信サービスに新規参入、月額550円(税込)の「DMMプレミアム会員」制度によって「DMMブックス」など他サービスとの連携を始めています。アダルト系(FANZA)も見放題になるとのこと。映像配信系のダークホース的存在になりそう。映像系も熾烈ですね。
文藝春秋 定期購読モデルで「文藝春秋 電子版」本格スタート ※有料会員限定〈文化通信デジタル(2022年12月1日)〉
noteで展開している「文藝春秋digital」とは別に、自社で直接配信する定期購読モデルを開始しました。ニコニコチャンネル内で展開している「週刊文春デジタル」と、自社で直接配信している「週刊文春 電子版」の違いと近似と言っていいでしょう。
noteの仕様が若干わかりづらいのですが、「文藝春秋digital」は月額900円の定期購読で、契約開始前に配信された有料記事は別途購入しないと読めません(無料の過去記事は読める)。それに対し「文藝春秋 電子版」は月額1200円ですが、「過去10年3000本以上のアーカイブ記事も読み放題」と差別化が図られています。多少高くても、こっちのが魅力的に感じますね。
文藝春秋はnoteに資本を入れてますから(2020年12月)簡単に切り捨てるようなことはないと思いますが、プラットフォームに依存しない直接配信チャンネルも持っておくべきだと判断した、ということなのでしょう。あるいは、noteが上場(12月21日)するのを機に、資本関係にもなにか変動が……?
技術
Google検索におけるAI生成コンテンツ最新事情 #SearchCentralLive〈海外SEO情報ブログ(2022年11月30日)〉
Google検索のアルゴリズムが、AI生成コンテンツをどのように扱っているか? という話。検索チームの統一見解は「AIコンテンツはスパム」で、検索結果のランキング操作を目的としているならスパムポリシー違反になるとのことです。ただし、AI生成コンテンツそのものが悪いわけではなく、「人間によるレビューが必須」である、と。
確かに、自然な文章で回答してくれると話題になっている「ChatGPT」に対する感想には、「しれっと嘘をつく」という声があります。現状では、公開前のファクトチェックが必須ということなのでしょう。AI生成テキストをそのまま垂れ流されたら、それはただのスパムだと判断されるのも無理はない話に思えます。
つまりこれは、今後はゼロから書くWriterの能力より、書かれたものを整えるCopy Editorの能力が問われるようになることを意味している気がします。
Google launches Reading Mode app to help visually disabled to read easily〈Good e-Reader(2022年12月2日)〉
Googleが視覚障害や失読症の人のための「Reading Mode」というアプリをリリース。Android 9.0以降で動作します。すでに日本のGoogle Playでも「読み上げモード」という名称で配信されていますが、残念ながら現時点では英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のみ対応しています。恐らく今後のアップデートで多言語対応していくのでしょう。
面白いのは、これが既存のアプリの上に覆い被さる形で実行される点。機能をオンにすると、画面右下に半透明のボタンが常駐します。そして、他のアプリを利用中にそのボタンタップすると、そのとき画面に表示されているテキストを読み上げモードに変換します。「マルチタスク」=並行起動とも微妙に違うので、「オーバーレイアプリ」とでも呼ぶべきでしょうか。
実際に試してみたら、「Chrome」ブラウザで開いた英語の記事には対応していましたが、「Kindle」アプリで英語の書籍を開いて使ってみたら「読み上げられません」と表示されました。対象は「アプリやウェブサイト」とあるので、機能を有効化するにはアプリ側での対応が必要なのかもしれません。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
興味が薄くなっていたはずのサッカー日本代表ドイツ戦勝利について言及したら、次のコスタリカ戦では敗北。次のスペイン戦は、行われることすら気づかない状態でいたら、なんと逆転勝利。ぼくは逆神なのでしょうか。ベスト16入りとはいえ、ぼくは興味を持たないほうが良い結果が出そう(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。