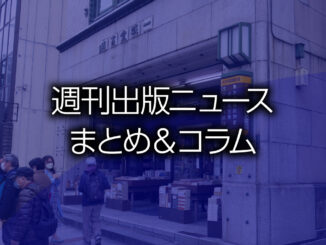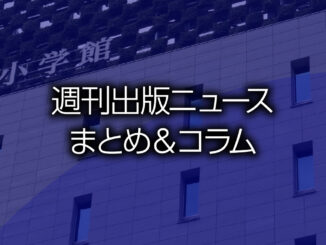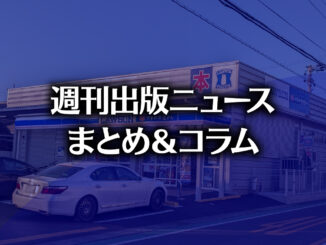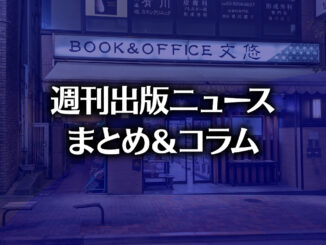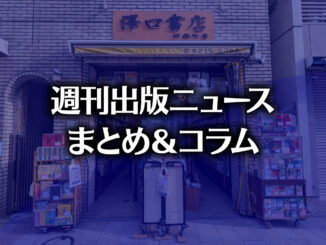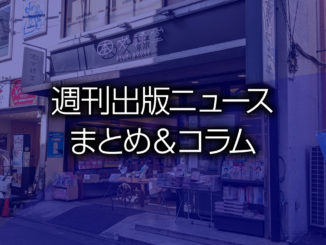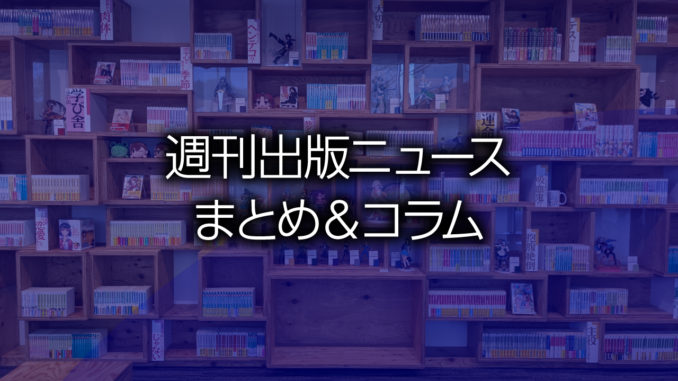
《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
2021年7月4日~10日は「汚染されたネット広告」「東大阪市、全小中学生の学習用端末に蔵書数3万4000点の電子図書館サービス」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
政治
米37州当局がグーグル提訴、アプリ市場で独禁法違反〈ロイター(2021年7月8日)〉
Google Playに対する反トラスト法違反の提訴。これ、よくわからないのが、AppleのApp Storeに対しては「同様の訴訟を提起する可能性を排除していないとの立場も示した」なのですよね。つまり、後回し。Androidはサイドロードできるし、他社の決済排斥もAppleに比べたら緩いくらいという認識なのですが、なぜGoogleが先に標的にされたんだろう?
社会
東大阪市、全小中学生の学習端末に電子図書館〈日本経済新聞(2021年7月5日)〉
端末が小中高校生に1人1台導入されたら、次は必然的にこうなるという実例。コンテンツホルダーから見たとき、一般ユーザー向けの電子書店では小中高校生向けのコンテンツが主に決済の問題で売りづらかったのが、電子図書館サービス向けなら顧客は行政だし需要もあるから格段に売りやすくなる。端末とサービスの普及によって、状況が激変しているわけです。
それにしても東大阪市の電子図書館、蔵書数3万4000点というのは凄まじい。この4月から「LibrariE」を導入し、7万点超のラインアップから半分近くを一気に買ってるわけです。新型コロナ感染症対応の地方創生臨時交付金を利用したというのもあるでしょうけど、おそらく億の桁に届く予算を組んでいる。自治体によって如実に差が出てしまう点でもあります。
高校生がニュースを知る方法、「新聞」は「TikTok」さえ下回り9位! 現状が明らかに【LINE調べ】 〈Web担当者Forum(2021年7月6日)〉
高校生に限った話ではないと思いますが、興味深いのでピックアップ。選択肢が「紙の新聞」と「電子版の新聞」と分散しているとはいえ、単純合計(※複数回答可ですが両方読む人は少ないだろうと予想)しても「Instagram」とほぼ同等です。とほほ。
ただ、2位「Twitter」や3位「ニュース系のサービスサイト(Yahoo!ニュース、LINE NEWSなど)」や6位「ニュース系のアプリ」へのニュース記事供給元には、実際には新聞が含まれてるわけですよね。Twitterはリンク先がなかなか読まれないし、外部配信は「新聞」だと気付いてもらえない。そして、信頼性の低いメディアと同じ土俵に並べられてしまうという。闇だなあ。
新聞記者は、先輩の指示で取材したら逮捕され、社から切り捨てられる職業である(藤代裕之)〈Yahoo!ニュース個人(2021年7月8日)〉
北海道新聞の新人記者が旭川医科大学に潜入取材して私人逮捕された事件について、公開された社内調査報告がツッコミどころだらけで各所から袋叩きにされています。新人に指示が行き届かなかった「ことにしておく」ことにより免責を図ろうとする、ずるいやり方が透けて見えます。藤代さんの「言論の自由の前に、まともな組織や業界かが問われている」という言葉が重い。メディアは影響力が大きいから「第四の権力」などと呼ばれているわけですが、それは決してなんでもやっていい「免罪符」などではないのです。
新型コロナ: KADOKAWAのラノベ図書館刷新 他出版社作品も収蔵〈日本経済新聞(2021年7月8日)〉
昨年夏にオープンしたばかりなので「え? もうリニューアル?」と少し驚きました。私は4月に行ってきたばかりですが、写真を見る限り中が大きく変わったわけではなさそう。KADOKAWA以外の出版社の作品も所蔵するようになった、というのが大きな変化でした。確かに、無かったかも。ラノベはKADOKAWAが圧倒的に強いからというのもあって、あまり意識して見てませんでした。
あと、この記事には載ってませんが、ダ・ヴィンチストアのサテライト店が、マンガ・ラノベ図書館の前にオープンしています。東所沢の駅から歩いてところざわサクラタウンへ向かうと、ダ・ヴィンチストアは角川武蔵野ミュージアムのさらに先の、一番遠い位置の建物裏手にあります。私は気付かず、立ち寄れず仕舞いでした。大型バスの発着ができる観光物産館「YOT-TOKO(よっとこ)」からの導線上にあるので、そちらからのアクセスは良いようなのですが。サテライト店ができたことで、本店(?)への誘導も図れるようになるのかな。
経済
汚染されたネット広告、大企業も関与 「バレなければ問題ない」2兆円市場の影〈J-CAST ニュース(2021年7月4日)〉
しっかり掘り下げた良い記事。ウェブの広告プラットフォームは、金を出す側の広告主や代理店に対し甘すぎると思うのです。メディア側では対処しきれないので、なんとかして欲しい。ちなみに、J-CASTには普段、他のウェブメディアと同程度には広告が出ているのですが、面白いことに、この記事には広告が出ていません。そんな制御ができるCMSなのか。まあ、そりゃ、こんな記事なのに不愉快広告が出ていたら、盛大にツッコミ入れられちゃいますもんね。
米アマゾン、ベゾスCEOが退任 創業27年で190兆円企業に〈共同通信(2021年7月6日)〉
ひとつの区切りとして。一代で巨大企業へ育て上げた手腕はお見事。では、後継者の育成についてはどうだったのか? については、答えはこれから。巨大IT企業を狙い撃ちした法規制が各国からバンバン出てくるようないまの状況で引き継ぐのは、舵取りが大変そうです。
電子書籍をPayPayで買うと最大100%還元、8月にキャンペーン開催〈ケータイ Watch(2021年7月9日)〉
PayPay=ヤフーですからグループ企業のebookjapanだけが対象かと思いきや、コミックシーモアとRenta!も対象になってて驚きました。この老舗3企業、ライバルだけどわりと仲が良いんですよね。とはいえこれって敵に塩というか、利益相反に当たるのでは。いいのかなあ。
消えた出版社の本はどこへ 著作権引き継ぎの課題とは〈日本経済新聞(2021年7月10日)〉
出版社が事業を畳むとき、他の出版社が書籍の出版権を継承するためには、改めて著作権者の許諾が必要になるためハードルが高いという話。いわゆる「孤児著作物」問題です。学識者から「著作権保有者を探す人を支援する仕組みがあってもいいのではないか」というコメントがありますが、著作権者不明等の場合の裁定制度をもっと利用しやすくするため、以前から権利者団体がすでにいろいろ動いてます。例えばこちらのオーファンワークス実証事業では、権利者の捜索や裁定申請などを実行委員会が代行する試みを行っていました(↓)。まあ、相続で権利が分散しちゃうんで、難しいところではありますよね。
技術
【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】大画面10.3型、スタイラスペンでの書き込みもできるE Ink端末「楽天Kobo Elipsa」〈PC Watch(2021年7月8日)〉
予約受付開始時の #473 でピックアップした際に、「リフロー型書籍のみ対応」への疑問と、文字の大きさを変えたらどうなる? という疑問を示しておきましたが、答えが出ました。前者は商品情報ページに「フィックス型(画像主体の形式)の書籍につきましては、今後のソフトウェア更新にて対応予定です」と記述されていました。後者は、単純に「ズレる」というもの。まあ、画像として保存するなら、そうなりますよね。「過去の書き込みを状態を保持するため、文字の大きさを変えたくても変えられない」なんてジレンマに陥りそう。うーむ。
ついに小説のタイトルとあらすじを「AIが評価」する時代が来た…!(飯田 一史)〈現代ビジネス(2021年7月10日)〉
なろう作家とAI専門エンジニアが開発したサービス「なろうRaWi」の「タイあら診断(タイトル・あらすじ診断)」という機能について。少し試してみましたが、点数が出るだけでなく「講評」の文章が出てくるのが面白い。文体が偉そうなのも、なんか良い。考えてみたら、これSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)と似たようなことをやってるわけですよね。なろう読者への最適化。ある程度の情報量がないと、傾向を解析するのは難しそうではあります。
お知らせ
【延期】大西寿男(校正者)×牧村朝子(文筆家)×仲俣暁生(編集者)「新時代の書き手が大切にしたい校正のこころ――リスクマネジメントと言葉のエンパワメント」(渋谷ロフト9)
ひさびさのリアルイベントの予定でしたが、緊急事態宣言発令を受け、秋以降に延期とさせていただきました。詳細はこちらのお知らせをご覧ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。