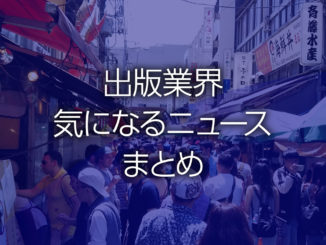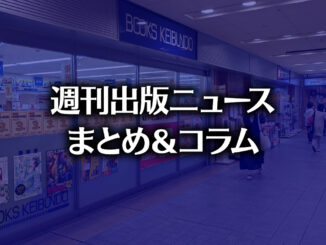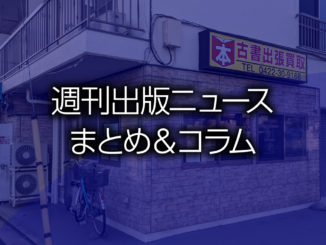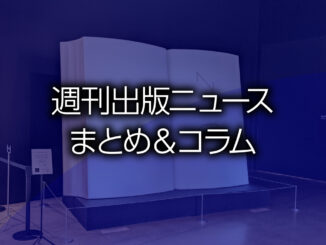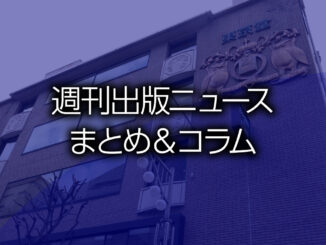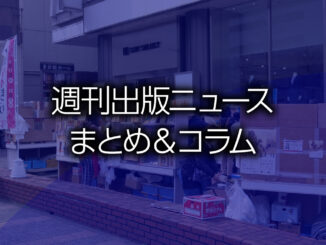《この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です(1分600字計算)》
2020年2月17日~23日は「講談社の決算が21世紀最高の数字に」「Cloudflare社が出版大手4社と和解」などが話題に。編集長 鷹野が気になった出版業界のニュースをまとめ、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- ポッドキャスト
- 国内
- 音声プラットフォーム「himalaya」でオーディオブック2万6000点以上が配信開始、聴き放題サービス対象は1万点以上〈HON.jp News Blog(2020年2月17日)〉
- ついに動き出した電子マンガ「中古売買」の成算〈東洋経済オンライン(2020年2月17日)〉
- 日経電子版、有料会員70万人に 20代や女性がけん引役〈日本経済新聞(2020年2月17日)〉
- 苫小牧市立図書館が整備計画を策定、電子書籍数2倍以上に〈室蘭民報(2020年2月19日)〉
- noteとcakesコラボの「cakesクリエイターコンテスト2020」開催〈HON.jp News Blog(2020年2月20日)〉
- 講談社決算発表 純利益が前年比2・5倍超に、野間社長「今期に事業収入が紙を上回る」〈文化通信デジタル(2020年2月20日)〉
- 講談社決算、「21世紀に入って最高の数字(利益)」(野間社長)〈新文化(2020年2月20日)〉
- 日販、2019年の年間店頭売上前年比調査を発表 ~ コミック、ビジネス書、新書が伸長〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
- Cloudflare社、海賊版サイトでの著作権侵害が裁判所に認定されたらデータ複製を中止する条件で出版大手4社と和解〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
- ボイジャー、片岡義男作品449点を国立国会図書館へ電子納本〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
- 読書量をグラフ管理、感想文投稿…大垣市が新図書サービス〈岐阜新聞(2020年2月21日)〉
- 著作権侵害していないのに…Twitterアカウントが突然凍結 対応の難しさも〈AbemaTIMES(2020年2月21日)〉
- メルマガについて
ポッドキャスト
国内
音声プラットフォーム「himalaya」でオーディオブック2万6000点以上が配信開始、聴き放題サービス対象は1万点以上〈HON.jp News Blog(2020年2月17日)〉
法人名は「シマラヤ」ですが、サービス名は「ヒマラヤ」です。誤記ではありません。昨年から有料コンテンツの配信も開始していましたが、ここへ来てどーんとオーディオブック2万6000点。しかも聴き放題サービスも同時立ち上げ。どこから仕入れているのかリリースには明記されていませんが、点数的にオトバンクかな……? 要注目です。
ついに動き出した電子マンガ「中古売買」の成算〈東洋経済オンライン(2020年2月17日)〉
メディアドゥが開発中のブロックチェーン技術を活用した流通プラットフォームと、JEPAアワード2019でチャレンジ・マインド賞を受賞したアソビモ「DiSEL」について。コンテンツホルダーが警戒するので、「中古」という表現は使わないほうがいいような……。あと、利用権を手放したあともスクショを使えば劣化しないコピーを手元に残すことが可能(私的使用目的の複製なので合法)という点を、権利者がどう捉えるか。まだ乗り越えなければならないハードルはいくつもありそうです。
日経電子版、有料会員70万人に 20代や女性がけん引役〈日本経済新聞(2020年2月17日)〉
先週のメルマガで、WSJの有料会員が200万人突破というニュースをピックアップしました。関連して、では日本でトップクラスの日経は? というコメントを書こうと思ったのですが、改めて調べてみたら、その時点では2018年6月の「60万人突破」というリリースが最新でした(↓)。
伸び悩んでいるのか? と思い、メルマガで触れるのはやめたんですが、週明けに70万人突破のリリースです。タイミング悪……いや、おめでとうございます。
苫小牧市立図書館が整備計画を策定、電子書籍数2倍以上に〈室蘭民報(2020年2月19日)〉
7414点を、1万5000点に。喜ばしいことですが、正直まだまだ少ない。電子書店で言えば、2011年ごろの水準です。なお、苫小牧市立図書館が導入しているのはTRC-DL&LibrariEなので、ラインアップ的には日本語コンテンツだけで7万点くらいはあるはずなのですが。
noteとcakesコラボの「cakesクリエイターコンテスト2020」開催〈HON.jp News Blog(2020年2月20日)〉
noteでハッシュタグを付けて投稿するだけという、気軽に参加可能なコンテスト。今回が3回目です。過去2回のコンテストは、HON.jpで取り上げていなかった……と思ったら、うちが株式会社hon.jpから事業継承して本格運用開始する前のことでした。なるほど。
講談社決算発表 純利益が前年比2・5倍超に、野間社長「今期に事業収入が紙を上回る」〈文化通信デジタル(2020年2月20日)〉
講談社決算、「21世紀に入って最高の数字(利益)」(野間社長)〈新文化(2020年2月20日)〉
講談社が好決算。当期純利益72億3100万円です。文化通信のほうが細かい数字が載っていますが会員限定なので、新文化もピックアップしておきます。電子書籍売上、ウェブ広告収入、海外版権事業が伸長。デジタル関連収入は465億円なので、電子出版市場の約15%を講談社が占めていることに。ちなみに私は以前からずっと、デジタル商品は複製コストが限りなくゼロに近いため、損益分岐点を超えると飛躍的に利益率が高くなると言い続けてきたのですが、嘘つきにならずに済んだようです。
日販、2019年の年間店頭売上前年比調査を発表 ~ コミック、ビジネス書、新書が伸長〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
コミックの伸びは、「鬼滅の刃」のヒットが大きな要因とのこと。確かに「少年」ジャンルの数字を見ると、アニメの放送が始まった4月と、放送終了後の10月以降の伸びが凄まじい。すごい作品です。
Cloudflare社、海賊版サイトでの著作権侵害が裁判所に認定されたらデータ複製を中止する条件で出版大手4社と和解〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
実は、2018年8月時点で仮処分申請を行い、2019年6月時点で和解が成立していました、というリリース。2018年8月って、ブロッキング法制化の議論が白熱していたころです。現行法で行える対策を、同時並行で進めていたんですね。ちなみに2018年10月に報道された、キャッシュファイル削除と発信者情報開示を命じる仮処分の決定(↓)とは別件のようです。
出版広報センター曰く「一定の効果が上がっていたため、詳細の公表を控えていた」とのことですが、正直、どうも腑に落ちません。なお、記事でも触れましたが、2020年1月には竹書房がCloudflare社に民事訴訟を提起しています。
ボイジャー、片岡義男作品449点を国立国会図書館へ電子納本〈HON.jp News Blog(2020年2月21日)〉
本件がなぜニュースになるか、前提を知らないと理解が難しいかもしれません。「現時点では有償またはDRM付きの電子書籍は、まだ納本対象になっていない」「2015年から50カ月間、電子出版への影響を調査する実証実験が行われてきた」「その実証実験を受託していた電書協が、終了間際に『リポジトリを立ち上げれば電子納本義務はないですよね?』と言い出した」という経緯があります。ボイジャー社はその流れに逆らって、単独で国立国会図書館に電子納本を行った、というわけです。なお、電書協がリポジトリを立ち上げ云々というのは、納本制度審議会平成31年3月18日の議事録に載っている公開情報です(↓)。
電子納本制度が法制化された際「無償かつDRM無し」に限定されたのも、出版業界の猛烈な抵抗があったからといいます。当時ようやく立ち上がり始めたばかりの電子出版市場に対し、国立国会図書館館内限定とはいえ公開することが悪影響を及ぼすかも? という危惧は、納得はできませんが理解はできます。しかし、実証実験の期間が50カ月というのはさすがに長過ぎだろと、当時少々腹を立てたのを覚えています。そしてようやく実証実験が終わるという直前に、裏技的な提案です。そうまでして電子納本したくないのでしょうか? 義務化されるのが、そんなに嫌なんでしょうか?
私は、自分が販売している電子書籍を納本して、公的機関に長期間保存して欲しいです。同じように考えている著者も、多いのではないでしょうか。しかし現時点では、仮に個人から申請をしても「無償かつDRM無し」でなければ受け付けてもらえません。ボイジャー社がそこをこじ開けたことは高く評価したい、という意味での記事化です。なお、実証実験は1月31日で終了していますが、現時点で結果がどうだったのか、電子出版市場に影響はあったのか、そして、電子納本制度がどうなるのかは明らかになっていません。今後も注視します。
読書量をグラフ管理、感想文投稿…大垣市が新図書サービス〈岐阜新聞(2020年2月21日)〉
図書館と「読書メーター」のシステム連携です。図書館のマイページに「読書メーターへ」という登録ボタンが付くようです。ちょっと調べた範囲では、システム的な連携を行っている事例は他に見つけられませんでした。珍しい事例なのは間違いないようです。
著作権侵害していないのに…Twitterアカウントが突然凍結 対応の難しさも〈AbemaTIMES(2020年2月21日)〉
DMCA侵害申告を悪用し、Twitterアカウントを凍結させる事件が急増。周囲でも被害者が出ています。2018年には、同様の手口で「艦これ」公式アカウントが凍結されるという事件がありました。Twitter以外では、Google検索からの悪評削除に利用したWantedlyや侍エンジニア塾が批判されるという事件もありました。虚偽の申請には賠償責任が発生するので、ただのイタズラでは済まされない事案です。実際、YouTubeが虚偽のDMCA侵害申告を行ったユーザーに対し訴訟を起こし、2万5000ドルの損害賠償支払で和解という事例もあります(↓)。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載された内容を、1週間遅れで掲載しております。最新情報を入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。