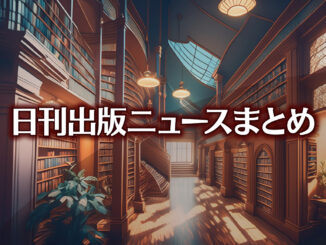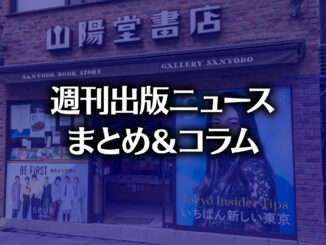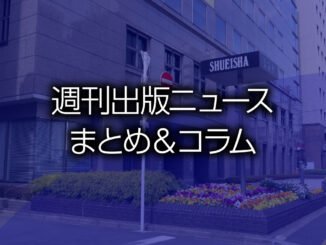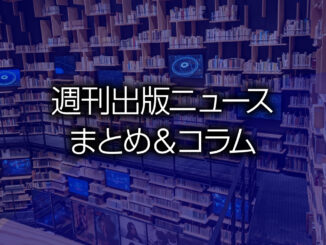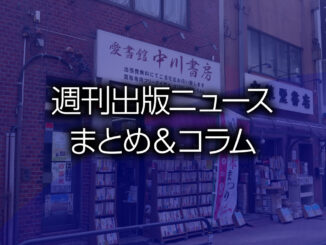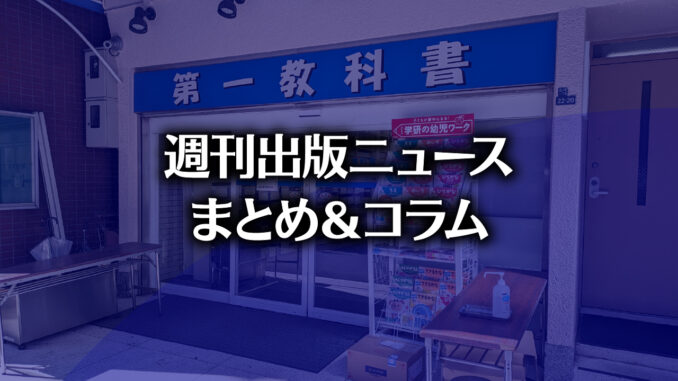
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2024年5月19日~25日は「知的財産推進計画2024(案)」「小学館決算は増収減益」「講談社、ワニブックスを子会社化」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 「いまは デジタル広告 の過渡期。10年後の未来を守るための行動を起こすときだ」:キヤノンマーケティングジャパン デジタルコミュニケーション企画部 部長 西田健 氏〈DIGIDAY[日本版](2024年5月21日)〉
- ネットメディア存続の危機 どの広告技術が収益維持の救世主になるか〈日経クロストレンド(2024年5月23日)〉
- GDNは提案しない〈LIFT合同会社(2024年5月23日)〉
- note、Tales & Co.株式会社を設立〈note株式会社のプレスリリース(2024年5月24日)〉
- 小学館 第86期は増収減益 版権、広告、デジタルが伸長 沢辺取締役が常務昇任〈The Bunka News デジタル(2024年5月24日)〉
- 講談社がワニブックスを完全子会社化 事業継承の相談を受けて〈朝日新聞デジタル(2024年5月24日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
社説:消える書店 「寂しい」で終わらせないで|社会|社説〈京都新聞(2024年5月19日)〉
リアル書店を救うのは物理メディアという論法ならまだ理解できるのですが、「紙の本に親しむ教育の重要さは論をまたない」という記述には頭を抱えました。なぜ教育を、わざわざ紙に限定するのか。市川沙央氏『ハンチバック』の芥川賞受賞が話題になり、紙の本だと読めない人もいることがやっと認知されるようになってきたのに。読書バリアフリーのことも、もう少し考えて欲しいところです。
AIを利用した創作物、発明者は「人間」…政府が知的財産計画で見解明記へ〈読売新聞(2024年5月24日)〉
5月24日開催の知的財産戦略本部 構想委員会について。傍聴できなかったのですが、資料の大半が「委員のみの配布」になっていて、内容が確認できません。とくに「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー」の再更新が非常に気になります。記事には「厳正な水際取り締まりの強化も推進する必要がある」とありますが、ということは……? これが国際標準戦略部会の設置に関係するのかしら?
また、読売新聞の「創作物」という表現にも違和感を覚えました。ただ、特許法を確認したら「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているのですね。発明も創作なのか。そりゃそうか。
ただ、この記事で「創作物」にかかるのは「発明者は」なので、ここは著作物ではないことが前提でしょう。特許権の取得には登録が必要ですが、著作権や著作隣接権は登録が不要(自然発生する権利)という大きな違いがあります。
社会
講談社の「創作の不思議」が期待以上だった。中高生が「人と仕事をするということの本質」を学べる講座〈with class(2024年5月19日)〉
with onlineは講談社のメディアで、with classは「子育て・教育」ジャンル。つまりこの記事は、講談社クリエイターズラボの中高生向け講座「創作の不思議」の自社広告です。それを前提としても、以下の記述に興味を引かれたのでピックアップしておきます。
ところが講座が実際始まってみると、中高生が数人でチームとなり、そのチームに1名ずつ「編集者」がサポートする中で漫画を創るということを軸にしながら、「人と仕事をするということはどういうことか、なせ(原文ママ)人と一緒に仕事をするのか」ということをスモールステップで学べる内容だったのです。
我々のNovelJamも「編集者」の存在にこだわったイベントなので、非常に親近感を覚えました。そうなんですよね。「創作活動は孤独だ」という声も多いのですが、なにもかもすべてを一人ではできません。作品を生み出すところまでは一人でできても、その作品を多くの人に知ってもらう段階で、一人でやれることの限界に気づきます。
自分でやってみると分かりますが、「セルフパブリッシング」と呼ばれている行為でさえ、なんらかのプラットフォームを使う必要があります。そして、なにかあればシステムの自動応答だけでは足らず、中の人とのやり取りが発生します。どうしたって他者と関わらざるを得ないのですよね。
承諾出版社の一覧〈版元ドットコム(2024年5月19日)〉
4月にレポートした「版元ドットコムとopenBDプロジェクトは“だれもが自由に使える書誌・書影”を再び提供するためホワイトリスト作成という正攻法に出た」の、ホワイトリストが公開されました。もちろんHON.jpの名前も載っています。これからは、直接出版社にお願いしていくそうです。コツコツ。
「情報 I・II」を学んだ高校生の技術レベルってどのくらい? 元エンジニア校長にホントのところを聞きました【フォーカス】〈レバテックラボ(2024年5月22日)〉
情報Ⅰを(ちゃんと)履修すると、ITパスポート試験に合格する可能性が高い、くらいのレベルなのですね。私も教科書を買って読んでみましたが、確かにこれが身についていれば、上の世代と大きな差ができるのは間違いないと思いました。いま大学でも「下の世代のほうが断然リテラシーが高い状況になるよ」と教えています。いやあ、こういう教科が学べるいまの子たちが羨ましい。
経済
「いまは デジタル広告 の過渡期。10年後の未来を守るための行動を起こすときだ」:キヤノンマーケティングジャパン デジタルコミュニケーション企画部 部長 西田健 氏〈DIGIDAY[日本版](2024年5月21日)〉
広告主側から、主にFacebookで問題になっていた詐欺広告に対する、かなり強い怒りの表明です。「我々も広告出稿を引き上げようか、と思ったほどだ」とありますが、一時的にでも「改善されるまでは出稿しません」と問答無用で引き上げても良かったのでは。あんな詐欺広告だらけの中に混ざっていても、良いことなかったと思うのですよね。
私は、広告3団体が広告品質認証機構「JICDAQ」の設立を発表したときから警鐘を鳴らし続けてきましたが、広告業界が掲げている「ビューアビリティ」「アドフラウド」「ブランドセーフティ」って、金を出す広告主のほうばかりを向いていて、広告を見る「ユーザー」のほうを向いていないんですよ。
実際、あれほど酷い詐欺広告が跋扈していたにも関わらず、Facebook JapanはJIQDAQの品質認証事業者のままです。そんな品質認証に、なんの意味があるというのか。認証団体として「このままなら認証を取り消します」と警告するくらいの態度が必要だったのでは。
結局、金を出すほうばかりを見ている「広告品質」だからこうなる。いまのような酷い状況になるのは必然と言っていいでしょう。
ネットメディア存続の危機 どの広告技術が収益維持の救世主になるか〈日経クロストレンド(2024年5月23日)〉
Apple Safariのサード・パーティー・クッキー規制って、CPMが半減するほどの影響が出ていたんですか? そこまでという認識がなかったので、ちょっと驚きました。調べてみたら、Safariでの規制が始まった2017年9月のすぐあとに「CPMは予想よりも10%程度低い状態」「広告収入が全体で1%から2%減少する可能性があると予測」といった記事が出ていたのが発掘できました。
Safariでサード・パーティー・クッキーが完全停止されたのが2020年3月。その後の2021年2月には、株式会社フォーエムというウェブ広告代理店が、自社データを分析して「iOS14/iOS13/Android11のそれぞれにおけるGoogle AdExchangeのCPMの数字」を公開していたのも見つけました。グラフを見る限り、確かにiOSの単価はAndroidの半分ほどになっています。なるほど。
GDNは提案しない〈LIFT合同会社(2024年5月23日)〉
クライアントに対し、Googleディスプレイネットワーク(GDN)を提案しないことにした理由について述べられています。メディア側からすると「Google Adosense」や「Google Ad Manager」の話です。「そもそもクリックしたら別のサイトに飛ぶ広告のほうが自社の記事より面積が大きい時点で、その記事の質は推して知るべしである」など、至極真っ当な意見で腑に落ちます。そりゃ、クライアントに提案したくなくなるのも無理はない。まあ、うちはもう3年以上前に運用型広告は止めましたが。
note、Tales & Co.株式会社を設立〈note株式会社のプレスリリース(2024年5月24日)〉
新会社の事業内容は「クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツ制作、外部企業からの企画受託等に関する事業」とのことです。noteからそういう機能を切り離して独立事業化するようなイメージでしょうか。代表取締役社長に就任した萩原猛氏は、カクヨム初代編集長だった2016年に日本出版学会での講演を拝聴したことがありました。
小学館 第86期は増収減益 版権、広告、デジタルが伸長 沢辺取締役が常務昇任〈The Bunka News デジタル(2024年5月24日)〉
減益の理由が書かれておらず、気になります。考えられるのは、紙代・印刷代の高騰、運賃高騰に伴う協力費の増大、PubteXなど流通改革関連への投資、などでしょうか。あとは、競争が激しくなっている電子コミックのプロモーション費用が増え、利益率が下がってきた、とか?
講談社がワニブックスを完全子会社化 事業継承の相談を受けて〈朝日新聞デジタル(2024年5月24日)〉
この記事には書かれていませんが、社長の横内正昭氏が4月に逝去されています。恐らくそこから事業継承の相談、という流れになったのでしょう。今後、アメリカのビッグ・ファイブと同じように、日本でも大手が中小出版社を傘下に入れる「インプリント」が進むのでしょうか。とくに「中堅が厳しい」という話はよく目にします。寄らば大樹の陰。
技術
10年前のWebページの38%が消失──Pew Research Center調べ〈ITmedia NEWS(2024年5月20日)〉
年鑑「出版ニュースまとめ&コラム」の編集をしていると、本欄で紹介した記事がたった数年で相当数消失していることに気づきます。リンク切れそのままというわけにもいかないので、Wayback Machineへのリンクに差し替えたりしています。
ところがいま、そのWayback Machineを運営しているInternet Archiveが法的脅威に晒されているのですよね……。
Google検索の生成AI「AI Overview」、「ピザに接着剤」「犬がNBAでプレイ」などと回答 Redditとの提携の影響か〈ITmedia NEWS(2024年5月24日)〉
Redditへ11年前に投稿されたジョークを、AI Overviewがソースにして要約を出力してしまったようです。当のRedditでも騒ぎになっていました。ソースとなった投稿は、すでにRedditから削除されたようです。
ちなみにRedditは、GoogleだけでなくOpenAIともパートナーシップを結んでいます。これ、こっちでも今後、同じようなことが起きそうな気がします。うへぇ。
Redditって、実態としてほぼ匿名掲示板ですよね? 私自身はほとんどチェックしたことがありませんが、ソースにしちゃいけない類いの代表格だと思うのですが。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
デジタル出版の演習授業で、学生の原稿チェックがあまりに大変で目が回りそうです。文章のうまいヘタではなく単純に物量の問題で、履修生が例年のほぼ倍の40人いるから。少なくとも1本あたり1~2時間はかかります。先週はずっと原稿に埋もれていました。ぎゃおー(鷹野)