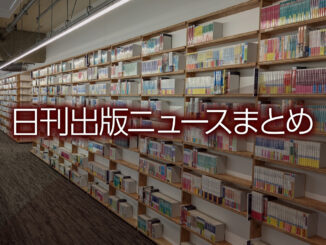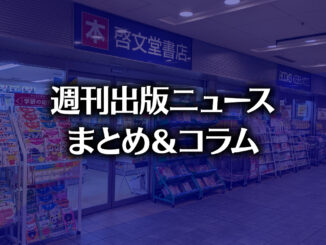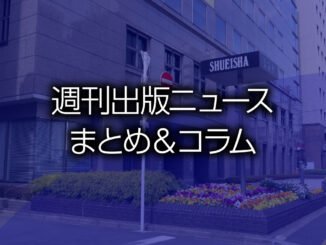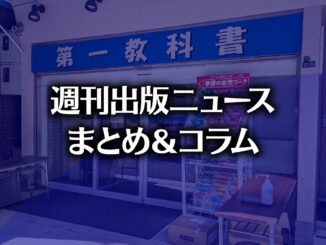《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2023年2月19日~25日は「2022年コミック市場は6770億円で過去最高更新」「2022年日本の広告費は7兆円超で過去最高更新」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
AI生成コンテンツめぐる法的責任、米最高裁が言及〈CNET Japan(2023年2月22日)〉
前提としてこの裁判で争われているのは、YouTubeのアルゴリズムによるレコメンデーションが、通信品位法230条の保護対象外になるか否かです。その議論の中で、判事が「生成AIは230条の保護の対象にならないだろう」と示唆した、というニュース。第三者の投稿コンテンツならプラットフォームは免責されるが、生成AIが生み出したコンテンツは免責されない――それは、ChatGPTや新Bingのような、いままさに大きな注目が集まっている領域に冷や水を浴びせるような話でしょう。現時点ではまだ判決が出たわけではなく、口頭弁論で示唆されたに過ぎない段階ではありますが、「アルゴリズムによるレコメンデーション」とは少し違った意味でも注目しておきたい裁判となりました。
悪質「誇大広告」抑止へ、行政処分経ずに罰金 消費者庁〈日本経済新聞(2023年2月24日)〉
景品表示法の改正案。行政指導や改善命令といった行政処分を経ず、ただちに違反者として罰則を科す「直罰規定」の創設が検討されているそうです。また、課徴金の額も売上高の3%→4.5%に引き上げる方針とのこと。1月13日付の消費者庁・景品表示法検討会報告書を確認したら「直罰規定導入を検討すべきである」(p21)と明記されており、その提言に則った方向で進んでいるということなのでしょう。違反表示の件数は増えるいっぽうで、もっと厳しくしないと抑止できないような状態になってきたようです。これはもう、やむなしか。
NHKのネット業務、「本業化」の方向で一致 総務省の有識者会議〈朝日新聞デジタル(2023年2月24日)〉
総務省・デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の公共放送ワーキンググループ(第5回)で、事務局によって示された「論点と考え方」に、構成員がおおむね賛成だったとのこと。ただし、「見逃し配信」は必須業務であっても、「オンデマンド」は必須じゃないという意見も出ているようです。また微妙なところで線引きを……。
あくまでこれは「放送」が検討の中心ではあるのですが、個人的にはネット業務の一環である「NHKニュース」の過去記事を消さないようにして欲しいと願っています。今回の資料内に「記事」という言葉は含まれていないようですが、過去に日本新聞協会がNHK配信記事の影響を懸念するような主張をしていたこともあり、今後の行方が気になります。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
太った少年→巨大な少年 『チャーリーとチョコレート工場』から体形・性別・肌の色描写が削除 「検閲」と作家ら危険視〈ねとらぼ(2023年2月21日)〉
ロアルド・ダールの作品に削除&修正、カミラ王妃も批判で出版社「原文も出版」 「チャーリーとチョコレート工場」仏翻訳版は“現代風”の編集を拒絶〈ねとらぼ(2023年2月25日)〉
過剰なポリティカル・コレクトネス問題。昔の作品を現在の価値基準で判断してしまうという愚行でもあります。批判を受け、改定前の版も出すことを発表して収束を図ったのですが、ロアルド・ダールが生前「もし出版社がカンマひとつでも変えるようなことがあれば、二度と私の本が出版されることはない」などと語っていたことも明らかになっていて、もう少しこの騒動は続きそう。
日本だと最近は、仮に現在では差別とされるような表現が残っていたとしても、あえて手を加えないという理由を説明する断り書きが巻頭や巻末に入っているケースが多いように思います。たとえば、手塚プロダクションは、作者に当時差別の意図はなかったことや、作者がすでに故人で作品の改訂が不可能であることなどを挙げています。
ウィズコロナへ転換した中国・天津の書店や図書館を訪う〈HON.jp News Blog(2023年2月22日)〉
中国在住の馬場公彦氏から久しぶりに原稿が届きました。ゼロコロナ政策が転換されたことで、やっと自由な国内旅行ができるようになったとのこと。今回は、天津の書店・図書館をレポートいただきました。中国で76年ぶりに復活した「内山書店」にも訪れています。
中川淳一郎に聞く雑誌の未来「ネットより雑誌のほうが自由な表現の場になっていく」〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月23日)〉
いや……「ネットより雑誌のほうが自由な表現の場」なんてのは、ただの幻想、ただの錯覚でしょう。マスを対象としたメディアではなくなったことで、多くの人の目に触れる機会が少なくなれば、結果、ダメな表現が発見される可能性が低くなるだけの話。東京オリンピック開会式の直前に炎上した小山田圭吾氏の事件はまだ記憶に新しいところ。あれは、30年近く前のインタビューが発掘された結果ですよね。ネットであろうと雑誌であろうと、記録に残る以上、いつまで経っても検証され続ける覚悟が必要です。
経済
講談社、減収減益の決算〈新文化(2023年2月21日)〉
講談社、22年11月の税引き益4%減 漫画ヒットの反動〈日本経済新聞(2023年2月21日)〉
【決算・人事】講談社 84期売上金額ベースでは前期超え〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
こうやって3つ並べると、同じ決算発表とは思えないほど見出しが違います。これは「収益認識に関する会計基準」の適用が影響しているから。文化通信によると、従来基準での売上高なら対前期比プラスとのこと。つまり、以前なら「増収減益」とされる実績だったということです。これが新会計基準だと、返品見込みやリベートなどを引いた額が売上高になります。その減額によって、前期と単純比較すると減収になってしまったことが、この3紙の見出しの違いになっています。じ、じつにややこしい……。
本件、私も認識があいまいだったのでこの機会に改めて調べてみたところ、上場企業や大企業以外にも関わってくる話だったので驚きました。出版社の場合、新会計基準の適用対象ではない中小企業でも、返品調整引当金が段階的に廃止されることにより、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があるそうです。詳しくはこちらの記事などをご参照ください。
KADOKAWA、タイ本格参入 電子書籍サイト3月から〈日本経済新聞(2023年2月21日)〉
年頭予想「マンガ」の「輸出」関連。「BOOK☆WALKER」では英語圏向け、繁体字向けに続く、海外展開です。日本からタイへの電子書店進出はこれが初めてとのこと。タイ語人口は約4600万人と、言語ランキングで見るとそれほど多いほうではないので、親日家が多いなど文化的な要因からの選択であることが予想できます。簡体字やスペイン語・アラビア語などのほうが市場は大きいでしょうけど、同時に、政治的圧力や文化・宗教に依る軋轢も多そうですからね。
2022年コミック市場は6770億円前年比0.2%増で微増ながら4年連続成長で過去最大を更新 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2023年2月24日)〉
毎年この時期恒例の。とうとうコミック市場で電子の占有率は3分の2になりました。なお、出版科学研究所のプレスリリースには「雑誌扱いコミックス」と「書籍扱いコミックス」の詳細が載っていなかったため、紙の「出版月報」が届くのを待っています。というのは、「書籍扱いコミックス」の実績次第で、コミック市場(紙+電子)が書籍市場(紙+電子)を逆転することになるのです。
2022年のコミック市場が6770億円(紙が2291億円、電子が4479億円)なのに対し、1月に発表された書籍市場は6943億円(紙が6497億円、電子が446億円)。ただし、この書籍市場には「書籍扱いコミックス」が含まれています。2021年実績で238億円が、2022年にどうなったか。173億円以上なら逆転です。
「2022年 日本の広告費」解説――過去最高を15年ぶりに更新する7兆円超え。インターネット広告は3兆円を突破〈ウェブ電通報(2023年2月24日)〉
2022年 日本の広告費 – News(ニュース)〈電通ウェブサイト(2023年2月24日)〉
こちらも毎年この時期恒例。個人的に「お?」と思ったのは、「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」のうち新聞(221億円)と雑誌(610億円)は微減なのに対し、テレビ(358億円)とラジオ(22億円)が急伸している点。額としてはまだ小さいのですが、動画広告や音声広告も着実に伸びているのだなあ、と。
あと、書かれている場所から判断するに、インプレス総合研究所が「無料マンガアプリの広告市場」として推計している270億円(2022年度)相当が、電通「日本の広告費」では「雑誌デジタル」に含まれている点。ここでも雑誌扱いなのかあ……なるほど。
技術
AIが書いた小説の投稿激増、ヒューゴー賞受賞SF誌が受付を一時停止〈テクノエッジ TechnoEdge(2023年2月21日)〉
アングル:チャットGPTに書かせた本、アマゾンでセルフ出版ブーム〈ロイター(2023年2月25日)〉
ジェネレーティブAIの「活用事例」と言うべきか「悪用事例」と言うべきか。まあ、「AIが書いた本」というだけで話題になるのは初めのうちだけで、肝心の内容が面白くなければあっという間に飽きられてしまうことでしょう。問題は、編集の手を加えなければ生成の手間は小さいため、物量がすさまじいことになることが容易に予想できる点。人の手で審査なんて、とてもやってられないでしょう。「下読みAI」が必要でしょうね。
「画像生成AIから自分のイラストを守る」学習・模倣の対策ツール「Glaze」無償公開へ〈KAI-YOU.net(2023年2月22日)〉
こちらはAIの学習を防御するツール。画像に微細な変更(style cloak)を加えることにより、ジェネレーティブAIが学習する際に誤って別の画風に解釈させるようなツールを無償で提供するとのことです。問題はその「微細な変更」がどの程度なのか? ですが、プロのアーティストに対する調査で、92%が対策処理は「作品の価値を損なわないほど小さい」と回答しているとのこと。
とはいえ研究者の方が言うとおり、AIが進化したらこの防御もいずれ役に立たなくなることも予想できてしまうわけですが、短期間の対処はできそう。ちなみにこういうのを文章でやろうと思ったら、よく似た違う文字――康熙部首を意図的に混入させる――みたいな、アクセシビリティを阻害する方向性しか思いつきません。まあ、難しいですよね。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
2月はただでさえ日数が少ないのに祝日が増えたことで営業稼働日も少なくなり、そのぶん平日にぎゅっと圧縮され、押し寄せる情報の波(主にプレスリリース)が大きくなっている気がします。だぱーん(鷹野)