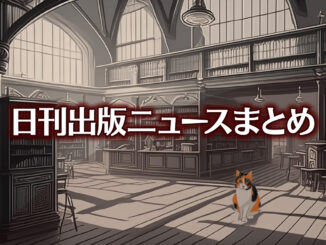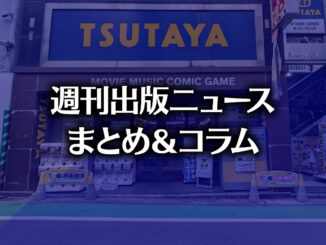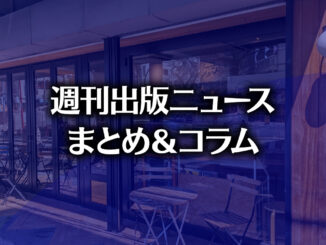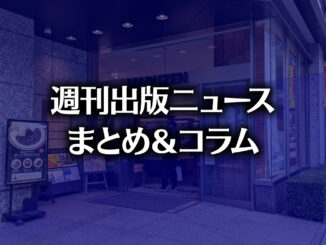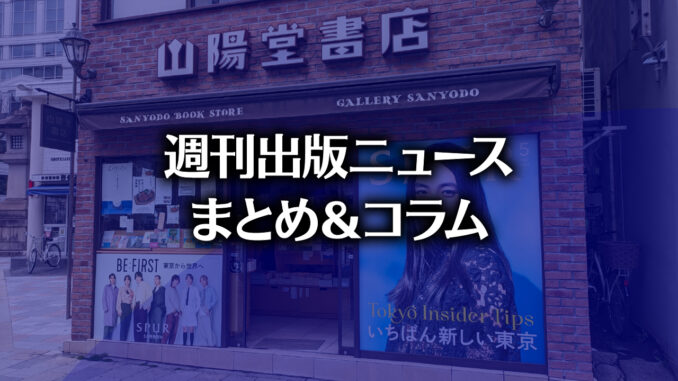
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2024年6月2日~8日は「小学館も『セクシー田中さん』調査報告書を公表」「東京都が“不健全図書”の表記変更を検討」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 「セクシー田中さん」原作者死亡、「日テレが意向受け入れなかった」…小学館が調査報告を公表〈読売新聞(2024年6月4日)〉
- 特別調査委員会による調査報告書公表および映像化指針策定のお知らせ〈小学館(2024年6月3日)〉
- 「セクシー田中さん」 原作者が亡くなったこと受け小学館が調査報告書を公表〈日テレNEWS NNN(2024年6月3日)〉
- 小学館『セクシー田中さん』調査報告書を公表 再発防止誓う コミュニケーションの問題も指摘「脚本家に要望が伝わっていなかった可能性高い」〈NEWSポストセブン(2024年6月3日)〉
- 「セクシー田中さん」問題 背景にTV局と出版社の「共存関係」〈朝日新聞デジタル(2024年6月4日)〉
- 識者が指摘する「小学館の責任」 セクシー田中さん問題〈毎日新聞(2024年6月3日)〉
- セクシー田中さん、日テレの調査報告書に「書かれていないことがある」、テレビマンが指摘する問題の核心〈弁護士ドットコム(2024年6月5日)〉
- 日テレ・小学館の「調査報告書」に釈然としない理由 「セクシー田中さん」問題はどこに向かうのか | テレビ〈東洋経済オンライン(2024年6月5日)〉
- ドラマ制作「十分な時間を」 「セクシー田中さん」問題 改善求める声〈日本経済新聞(2024年6月6日)〉
- 「セクシー田中さん」原作者死亡、「日テレが意向受け入れなかった」…小学館が調査報告を公表〈読売新聞(2024年6月4日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」–対策に動いた自民党、小林議員に聞く〈CNET Japan(2024年6月5日)〉
確かに、Facebookで「有名人を騙った詐欺広告」はほとんど見なくなりました。ところがこんどは「企業を騙った詐欺広告」が頻繁に流れてくるようになりました。まさにモグラ叩き状態です。
【ご注意】偽SNSアカウント、偽ウェブストアについて|紀伊國屋書店からの重要なお知らせ〈紀伊國屋書店ウェブストア(2024年5月27日)〉
紀伊國屋書店や蔦屋書店をかたったSNSの書籍プレゼント広告は詐欺!注意点は? #専門家のまとめ(前田恒彦) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2024年6月5日)〉
広告は、紀伊國屋書店の名前を騙ったFacebookページで「今1000名様だけ本1冊が無料でもらえます!」などといった内容。リンク先は「有名人を騙ったLINEグループ」へ入ることを勧めるランディングページでした。以前は「有名人を騙った詐欺広告」→「有名人を騙った詐欺LINEグループ」だったので、広告側の審査が厳しくなったぶん工夫をしてきた印象です。
ちなみに、そのランディングページのドメイン名をFacebook広告ライブラリで検索すると、同様の「企業を騙った詐欺広告」がごっそり見つかります。私が把握しているだけでも数週間は同じドメインが使われ続けています。こんなの、Metaがブラックリストを用意すれば、容易に自動で弾けるようになるはずでは?
なお、ドメイントップページには「恭喜,站点创建成功!(おめでとうございます! サイトは正常に作成されました。)」とだけ書かれています。aguse.jp で調べてみたところ、ブラックリスト判定結果は全て「SAFE」でした。ぜんぜんアテにならないな、これ。
「不健全図書」のレッテル、やっと解消? 東京都が表記変更を検討、「風評被害」に悩んできた漫画家は…〈東京新聞 TOKYO Web(2024年6月5日)〉
やっと! あくまでまだ「検討」ですが、これまで都は表記変更に否定的でしたから、巨岩が動いた感があります。森川ジョージ氏が言うように、まずは「ここが第一歩」でしょう。
グーグルマップの口コミ 「☆星4以上の投稿で割引」はステマ 消費者庁が初の措置命令|医療・健康〈NHK(2024年6月7日)〉
昨年10月から始まったステマ規制の初適用事例です。★4以上のクチコミを投稿すると、インフルエンザワクチン接種費用を割引するという、いわゆる「クチコミのヤラセ投稿」です。広告だと明示されていなければ、景品表示法違反。消費者庁、しっかり動いています。施行直後の事例というのが、ある意味、面白い。「無能な働き者」なんだろうなあ。
まあ、多くの人にヤラセ投稿を依頼すれば、誰かが消費者庁へ通報する可能性が高まります。Amazonなどの通販でも、商品と一緒にヤラセレビューの依頼が入っている場合がありますが、ああいうのはバンバン消費者庁へ情報提供すべきでしょう。
というか、恐らくすでにバンバン情報提供されていると思いますので、これから措置命令で名前が晒される事業者がたくさん出てくるんでしょうね。震えて眠れ。
社会
「セクシー田中さん」原作者死亡、「日テレが意向受け入れなかった」…小学館が調査報告を公表〈読売新聞(2024年6月4日)〉
特別調査委員会による調査報告書公表および映像化指針策定のお知らせ〈小学館(2024年6月3日)〉
小学館の調査結果も出ました。大手紙すべてで報じていましたが、ここはやはり親会社の読売新聞をピックアップしておきましょう。そして、それぞれの自社メディアの報道も。
「セクシー田中さん」 原作者が亡くなったこと受け小学館が調査報告書を公表〈日テレNEWS NNN(2024年6月3日)〉
小学館『セクシー田中さん』調査報告書を公表 再発防止誓う コミュニケーションの問題も指摘「脚本家に要望が伝わっていなかった可能性高い」〈NEWSポストセブン(2024年6月3日)〉
日テレNEWS NNNには、小学館の報告書を受けた日テレ側のコメントが出ています。NEWSポストセブン(小学館)は、側面支援でしょうか。
報告書が出た事実だけでなく、さらに踏み込んだ分析や意見が書かれた記事には、以下のようなものがありました。
「セクシー田中さん」問題 背景にTV局と出版社の「共存関係」〈朝日新聞デジタル(2024年6月4日)〉
識者が指摘する「小学館の責任」 セクシー田中さん問題〈毎日新聞(2024年6月3日)〉
セクシー田中さん、日テレの調査報告書に「書かれていないことがある」、テレビマンが指摘する問題の核心〈弁護士ドットコム(2024年6月5日)〉
日テレ・小学館の「調査報告書」に釈然としない理由 「セクシー田中さん」問題はどこに向かうのか | テレビ〈東洋経済オンライン(2024年6月5日)〉
ドラマ制作「十分な時間を」 「セクシー田中さん」問題 改善求める声〈日本経済新聞(2024年6月6日)〉
私は小学館の報告書を、日テレの報告書との違いに主眼を置いて読みました。まず、亡くなられた芦原妃名子氏とご遺族へのコメントが冒頭に置かれている点が、日テレの報告書とは大きく異なります。日テレの報告書は、「原作者の死亡原因を究明すること」や「責任の所在を明らかにすること」が目的ではない、から始まっています。
あとは、メール(記録)がしっかり残っている事項にも日テレ担当者が「その認識はない」などと言い張っている点が明らかになったこと。日テレの報告書にそういう記載はなかったはず。つまり、小学館は調査の過程で担当者のメールをちゃんと確認しているけど、日テレは聞き取りだけの調査である可能性が疑われます。
また、小学館の報告書の方が、脚本修正のやり取りについての解像度が高いのも印象的でした。①原作者→②小学館担当者→③日テレ担当者→④本件脚本家と意向が伝えられる中で、③から④のあいだで欠落した情報があまりに多いことが読み取れます。伝言ゲームになっています。
そのためか、本件脚本家のコメントに「聞かされていなかった」「知らされていなかった」があまりに多い。これが事実なら、本件脚本家も気の毒だと感じました。本件脚本家は、原作者が亡くなられたあとに「芦原氏がブログで書いたことは初めて聞くことばかりだった」と投稿しているのですが、実際そうならこうなるよな、という印象です。
あとは、日テレ担当者が「撮影は終わった」と嘘をつくに至った経緯が、小学館の報告書のほうが詳しい。結局、撮り直しになったわけですが、その前のやり取りの中で日テレの担当者が「ダンス監修者からOKの確認が取れた」と回答したことに「疑問が残る」と記されています。実は、嘘に嘘を重ねたのではないか? と。この点、いずれダンス監修者からコメントが出るかもしれません。
さて、どちらの報告書を読んでも、日テレの担当者があまりにひどいと感じたのですが――そのまま受け取っていいのだろうか? という疑問も少しだけ。
経済
AIによる漫画の大量翻訳、日本翻訳者協会が懸念を表明「作品の価値大きく損なう」〈KAI-YOU.net(2024年6月4日)〉
Japanese Association of Translators Shoot Down Govt-Backed Manga AI Translation Plan(日本翻訳者協会、政府支援のマンガAI翻訳計画を否定)〈Good e-Reader(2024年6月7日)〉
日本翻訳者協会が懸念を表明したことについて、海外の複数メディアでも記事が出ていました。反響までは確認できていないのですが、どのように受け止められているか気になるところ。個人的には、AI翻訳は「事実」や「論理的文章」には使えるけど、「創作的表現」はまだ難しいという認識です。
【詳報】小学館 第86期決算 児童書など「書籍」が好調 版権収入も映画、海外で伸長〈The Bunka News デジタル(2024年6月4日)〉
減益の要因が気になっていたのですが、「原材料費や物流費の上昇に伴いコストが増加し、利益率が低下した。また、デジタル関連などで中長期的な投資を積極的に進めた」とのことでした。「など」で丸められている「中長期的な投資」とは何かが気になります。PubteX関連でしょうか?
LINEマンガ 日本アプリマーケットで初の月間収益1位〈聯合ニュース(2024年6月4日)〉
「ん? 初の1位?」と一瞬疑問に思ったんですが、マンガアプリだけでなく、ゲームも含めた総合での1位です。2位がピッコマ、3位以下がゲーム「モンスターストライク」「Fate/Grand Order」「崩壊:スターレイル」と続いています。なお、いつも言ってますが、このランキングは「アプリストア決済限定」であることには留意が必要です。
Manhwa Is Surpassing Manga in Japan, and the Country’s Highest-Earning App Proves It(日本ではマンファがマンガを超えている、国内で最も収益の高いアプリがそれを証明)〈Screen Rant(2024年6月5日)〉
で、海の向こうではこんな報道が。LINEマンガ1位のニュースを受け、日本ではマンファ(韓国式縦漫画)がマンガ(日本式横漫画)を超えたのでは? という推測です。「海の向こうでそういうふうに見られてしまっている」という事実を認識しておく必要があると思い、ピックアップしておきます。
なお、「電子書籍ビジネス調査報告書2023」によると、日本の電子コミック市場は「コミックのうち約1割が縦スクロールカラーマンガであるWebtoon作品」です。つまり、マンガ(日本式横漫画)とマンファ(韓国式縦漫画)には2022年度時点でまだ9倍の差があります。それが2023年度にいきなり逆転するのは、さすがにあり得ないでしょう。
読者が安心して記事を読めるように、Publickeyでは適切な広告だけを掲載しています〈Publickey(2024年6月7日)〉
HON.jp News Blogも、運用型広告は掲載していません! こういうステートメントの表明、うちもやっておくべきだった……と反省させられました。本欄では何度も書いていますが、他にもたくさん書いている中に紛れてますので、単独の記事でやるべきでした。まあ、いまからやるとただの真似に見えてしまうでしょうけど。
技術
氾濫する生成AIアニメ 9万枚調査で見えた権利侵害〈日本経済新聞(2024年6月6日)〉
このタイトル、正確には「生成AIアニメ“絵”」です。氾濫しているのは、AI生成イラスト。「次にAI生成動画が来るぞ」という話に繋げてますが、メインは投稿画像の解析結果です。見せ方を工夫した手の込んだ記事なのですが、うーん……AI生成イラスト“以外”はどうなっているんだ? と思ってしまいました。
つまり、調査対象は「投稿サイト」ですから、AI生成ではない二次創作やファンアートの類いが他にも大量にあるはずなんですよ。それらは「厳密に言えば権利侵害の可能性」があるけど、ファンアートだからと許容されてきた領域です。人間が描いたなら許されるけど、AI生成なら許されないのでしょうか?
AIは生成に要する時間が短い=量が問題になる、という見解もあるでしょう。しかし、人間が描いたにせよ、AI生成にせよ、投稿サイトにあるファンアートが既存の正規市場と競合する可能性は低いと思うのですよ。「売ってる」なら話は別ですが、そうではないわけで。必要以上に危機感を煽っている印象を受けました。
NIKKEI Film 蝕まれる日本アニメ 生成AI時代、横行する「新・海賊版」〈日本経済新聞(2024年6月6日)〉
こちらは動画。テキスト記事側にはない、佐藤秀峰氏へのインタビューなどが含まれています。最後まで観ましたが、おどろおどろしいBGMによる演出など、こちらも必要以上に危機感を煽っている感があります。
グーグルの生成AIサービス「NotebookLM」が日本でも一般公開、調査と制作を助けてくれるAIパートナー〈ケータイ Watch(2024年6月6日)〉
自分用のRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)が作れるサービスです。Googleドライブにある資料もソースにできるので、非公開の取材メモをまとめたりするのに使えるかも? ……と思ったのですが、ソースにした資料は「AIの学習には使わない」けど「Googleの人(レビュアー)が見る可能性がある」そうなので、少なくとも機密情報は絶対に食わせてはダメです。
むしろ、膨大な公開情報を整理させるのが良さそう。たとえば、政府から大量に公開されている、ページ数がめちゃくちゃ多い報告書とか。「知的財産推進計画2024」のPDF(A4で100ページある)を食わせて、要点をまとめさせ、さらにその中から、AI関連だけ深掘りする――みたいな。
こちらの画面キャプチャは、右が「AI関連の課題について箇条書きでまとめて」という問いへの回答です。文末にある番号をクリックすると、ソースの該当箇所を左のように表示してくれます。まだ試してませんが、毎年出ている報告書なら、過去との差や一貫性なんかを調べるのにも使えそう。
まあ、まだ嘘をつく(ハルシネーション)こともあるようなので、そのまま使うのではなく、予備調査に使うのが無難でしょうね。「ソースは読むべき文書か?」「どこを重点的に読むべきか?」を調べるために使うのが良さそう。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
某公共図書館協会研修大会の講演準備、NPO法人の決算処理、日本出版学会春季研究発表会ワークショップの準備など、日々のタスクとは別に、ちょっとベクトルの違うタスクの大波が連続で押し寄せていました。なんとか乗り切って……いや、まだNPO法人の総会準備ができていません。あかーん(鷹野)