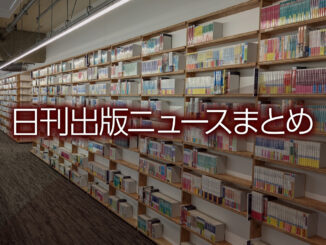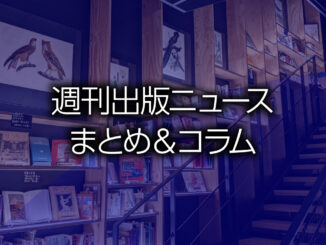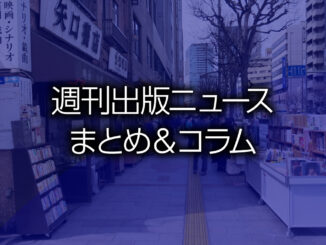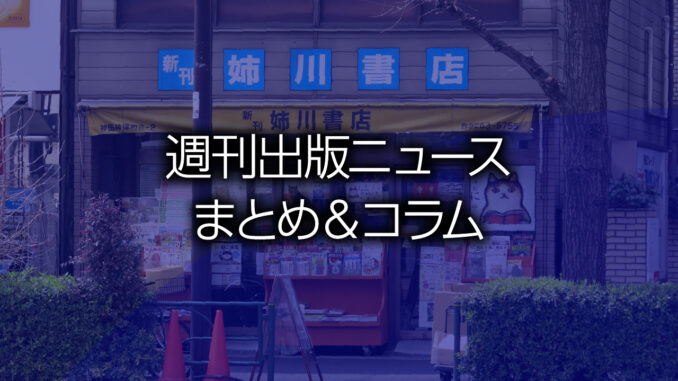
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2023年2月5日~11日は「MicrosoftとGoogle、AI+検索で激突」「Twitter APIの無料アクセス終了へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
社説:「ステマ」広告 消費者欺く行為を放置するな〈読売新聞オンライン(2023年2月6日)〉
消費者庁で検討が進んでいる「ステマ」規制についての読売新聞社説。「実効性のある規制」を求めており、そこに大きな異論はありません。ただ、あたかも「インフルエンサー」と「プラットフォーム事業者」だけが規制対象になるかのように記述されている点には違和感を覚えました。
これ、既存メディアも規制対象なんですよね。決して他人事ではありません。もちろん「新聞広告倫理綱領」とか「雑誌広告倫理綱領」など自主規制を図ってきたのは知ってますけど、あくまで倫理的、訓示的な規定であって、「拘束力がない」のは同じなんですよね。
公取委、アプリストアの競争環境を調査「アップル/グーグルに独禁法問題となる懸念」〈ケータイ Watch(2023年2月9日)〉
「モバイルOS市場」と「アプリ流通サービス市場」についての調査。自社アプリの優遇や、税金にも例えられるストアの手数料などが、独占禁止法上の「私的独占」や「取引妨害」といった問題になる恐れがあると指摘しています。正直、「いまさら?」という気もしますが。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
Twitter APIの無料アクセスは2月13日まで延長 ~その後も毎月1,500ツイート&ログインを無料提供〈窓の杜(2023年2月9日)〉
スパムボットを削減するための施策――だったはずなのですが、結局「1カ月あたり1,500ツイートまで作成できるフリーアクセスが提供される」ことになりました。「良いボット」を残すという「エコシステムの維持に配慮」した結果のようですが、これじゃ悪いボットも排除できないのでは? という声も散見されます。
本件、あえて「社会」に分類しました。それは、ツイートを取得して分析する利用に大きな影響が出そうだから。たとえば鳥海不二夫氏(東京大学大学院工学系研究科教授)が「ツイートを分析したら実態はこうだった」という分析記事をよくヤフーニュース個人などで公開していましたが、恐らく今後はできなくなります。
実は私も、キュレーション運用している「HON.jp News Blog」のツイートを、自動取得してGoogleスプレッドシートに流し込み、本欄を書く前段階のピックアップや分類などに活用していました。せっかく自動化したのに、恐らく来週以降は止まってしまいます。簡単には代替できそうにないので、また手作業が増えることになります。他にもいろいろ影響が出そうで辛い。とほほ。
韓流「縦読み漫画」に押され、日本の漫画は「ガラパゴス化」してしまうのか 澤田克己〈週刊エコノミスト Online(2023年2月9日)〉
えーっと……いろいろ言いたいことはあるのですが、一つだけ。「ガラパゴス化」って表現、そろそろ止めませんか? 外界から隔絶された環境下で独自の進化を遂げたガラパゴス諸島の生態系――というもともとの意味がどこかへ消え失せ、単に自虐的な、揶揄する表現と化してますよね。
日本の横読みマンガについて言えば、「化」どころか、とっくの昔に独自の進化で独自の生態系を形成していると思うのですよ。横読みマンガって「縦書き・段組み」文化をベースとしたフォーマットですから。縦書き文化圏って世界的にはレアなんですよね。それじゃダメなのか? というと、決してそうではないわけで。
経済
個人作家向けの電子書籍配信取次システム「BLIC」、BookLiveが提供開始〈INTERNET Watch(2023年2月8日)〉
BookLiveのブリック出版が電子取次事業へ参入。「個人作家・クリエイター向け」とありますが、基本的にマンガだけがターゲットのようです。プレスリリースのブリック出版の説明にも「当社はマンガの創作系個人誌を専門として配信する出版社」とありますし。まあ、マンガは儲けやすいイメージから、社内稟議も比較的通しやすいのでしょう。儲かるようになってからでもいいので、文字ものにも目を向けて欲しいです。
「神絵が1分で生成される」 進化するAI、イラストレーターの仕事を奪うのか|オリジナル 特集〈Yahoo!ニュース(2023年2月4日)〉
「ChatGPTを競争戦略上どう生かすか、なくなる仕事は?」を議論した〈Forbes JAPAN 公式サイト(2023年2月6日)〉
イラストと文章、手段は違えど、どちらの記事も今後は「AI使い」が重宝されるのではないか、という方向性で一致しているのが興味深い。絵描きも文章書きも、AI生成コンテンツが社会に与える影響を避けて通ることはできないでしょう。ただ、結局は「新しい便利な道具」を、どれだけうまく使いこなし、新しい価値を生み出せるか? という勝負になりそう。いまどき、原稿用紙に万年筆で書く人はほとんどいないわけで。
技術
「ChatGPT」の言語モデル統合で「Bing」はグーグルの牙城を崩せるか〈CNET Japan(2023年2月7日)〉
現状、ウェブ検索エンジンはGoogleの寡占状態ですが、そこへMicrosoftの「Bing」がAIチャットボットを搭載することにより対抗していこうとしています。まだ私は試せていませんが、周囲ではさっそく試してみた方がすでにチラホラ。想像以上に、すごいようです。
なかでも、ビッグデータと人工知能の技術ベンチャー企業データセクション創業者・橋本大也氏がFacebookで「Googleは早く対応しないと検索エンジンだけでなくChromeブラウザーのシェアも失う」とコメントしていたのが非常に印象的でした。そこまでか! と。
レポート記事も、すでにいくつか出ています。「IT navi」のレポートはわかりやすかったです。回答文には脚注番号が表示され、回答の下に「詳細情報」として参照先のリンクが表示されるようになっているようです。ちゃんとソースが提示される、というのは大きい。しかし……
ソースとして提示されるメディア側の立場としては、従来型の検索結果なら1位以外にもそれなりにアクセスがあった(2021年の調査によると日本では1位のCTRが約14%)のが、恐らくAI検索ではソースとして選ばれなければアクセスは皆無になることが予想できます。恐ろしい。
利用者側として考えても、複数のソースを見比べるのが難しくなるのは、けっこう困るかも。検索結果の上位しか見ない、という使い方だったら影響は小さいのでしょうけど。あと、ソースとして提示されるのが、ウェブに情報が残りやすいメディアばかりに偏りそう。それはそれで怖い。
一つ言えるのは、これがユーザーにとっては単に「新しい便利な道具」だとしても、システムとか構造全体を見たときには、プラットフォームと呼ばれてきた事業者の根幹を揺るがすような事態がいままさに起きているということ。恐ろしいし、怖いけど、面白いなあ。
Googleの会話AI『Bard』発表、検索に統合。複雑な質問に文章で回答する「実験的会話型AIサービス」〈テクノエッジ TechnoEdge(2023年2月7日)〉
で、早々に社内で「レッドアラート」が宣言されたGoogleから、Microsoft対抗の新サービスが発表されました。まだいまのところクローズドβのようですが、「今後数週間のうちにもより広い範囲で一般向けに公開する予定」とのこと。ところが……
Googleの会話AI『Bard』が広告で誤情報を回答。親会社Alphabetの株価急落〈テクノエッジ TechnoEdge(2023年2月9日)〉
デモの時点で、さっそく誤回答をしてしまっていたというオチがつきました。現場の担当者が、AI生成コンテンツの信頼性にはまだ疑問が残る点を示そうと、わざとこの回答を選んだんじゃないか、なんて穿った予想まで流れる始末です。まあ、ファクトチェックの重要性を示すという意味では、Googleにとっては悪いけど、世の中にとっては良い事例になったかも。
AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス|Google 検索セントラル ブログ〈Google Developers(2023年2月8日)〉
そのGoogle検索で、AI生成コンテンツがどういう扱いになるか? についての公式ガイダンス日本語版が出ました。スタンスは従来と変わらず、重要なのはコンテンツの作成方法ではなく品質である、というもの。つまり、AI生成コンテンツだから一律ダメというわけではなく、人間にとって有用か否かで判断されるということです。
ただ、「検索結果のランキングを操作することを主な目的としてコンテンツ生成に自動化(AIを含む)を取り入れることは、Google のスパム ポリシーに違反」します。先日、さっそく「ChatGPTの技術を活用したWebメディア記事自動作成ツール」などというプレスリリースが流れてきました(リンクは貼りません)が、スパムポリシー違反でペナルティを食らう可能性は高いでしょう。くわばらくわばら。
画像生成AI、元データをほぼそのまま出力 著作権侵害の恐れ〈MIT Tech Review(2023年2月9日)〉
以前、アメリカの画家やストックフォトサービスが、画像生成AIサービス「Stable Diffusion」や「Midjourney」を提訴したニュースをピックアップしましたが、その主張を補完するような調査結果が出てきました。100万分の1くらいの確率で、学習元データがそのまま出力されてしまう場合があるとのこと。末尾の「ゼロではないという事実が重要なのです」というコメントが重い。
恐らくアメリカでは今後、画像生成AIだけでなく、文章生成AIも訴訟ラッシュに襲われる気がします。Microsoftも、Googleも。アメリカは訴訟大国ですし。メディア側としても、AI検索にソースとして利用されユーザーの流入が激減するような状態になったら、いままで以上に「ふざけるな」という話になりそうです。
日本の著作権法にはいち早く、そういったAI開発での訴訟リスクを軽減するため、機械学習目的なら権利侵害にならない例外規定(30条の4)が設けられています。ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除くため、ほんとうに「ふざけるな」状態になってきたら日本でも訴訟になるかも。まあ、そのときにはもう手遅れかもしれませんが。
なお、日本の著作権法では、偶然の類似(依拠してない)はセーフです。しかし、学習元データとして使っているなら「依拠していない」と言い切るのは難しそう。でも、それが著作権侵害となるかどうかについては、さまざまな学説があってまだ定かではないそうです。詳しくは、STORIA法律事務所の弁護士・柿沼太一氏の解説を参照してみてください。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
都内で珍しく雪が積もりました。珍しく、とはいえ、1年に1回くらいは遭遇する気がします。転ぶのが怖くて出不精が捗りますが、散歩ができないと気分転換が図りづらくて困る。とはいえ、翌日にはほとんど溶けてしまいました。日陰に残る、恐らく雪だるまだったであろう痕跡が哀愁を誘います(鷹野)