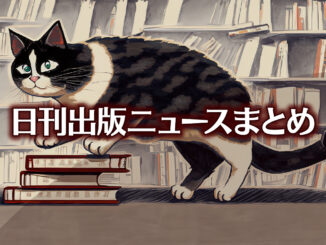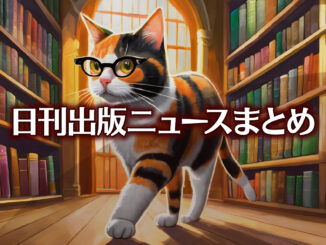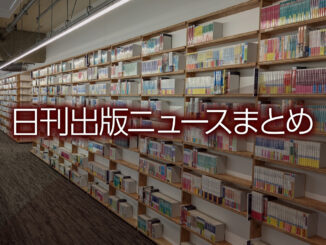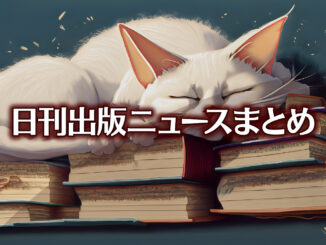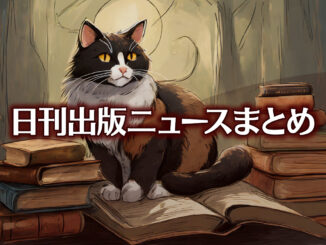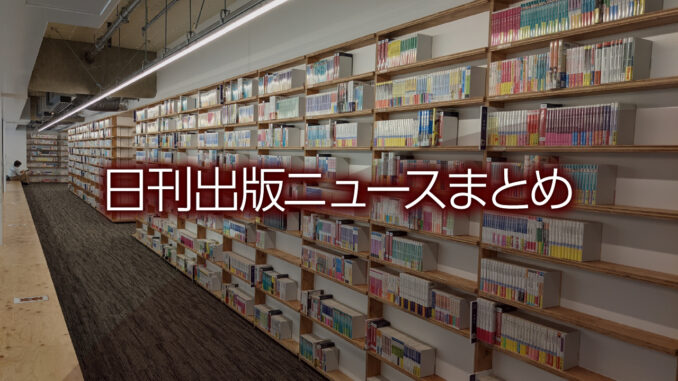
《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
伝統的な取次&書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。
【目次】
- 総合
- 国内
- 電子コミックから「名作」は生まれるのか? “インパクト”重視で分業制も進む中…漫画制作の是非〈ORICON NEWS(2023年2月6日)〉
- 電子コミックの伸び、急速に鈍化「成熟期に入った」 2022年の出版市場、4年ぶり前年割れ〈J-CAST(2023年2月6日)〉
- 書店が増えている!? 「行きたい本屋」から「やりたい本屋」へ〈週刊朝日〉〈AERA dot.(2023年2月6日)〉
- 獲得キーワードが5倍!マンガアプリ「comico」に聞く、攻めと守りのアプリマーケティング〈MarkeZine(2023年2月6日)〉
- 社説:「ステマ」広告 消費者欺く行為を放置するな〈読売新聞オンライン(2023年2月6日)〉
- 令和5年度我が国アートのグローバル展開推進事業〈文化庁(2023年2月6日)〉
- 「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書(案)」に対する意見を提出しました〈一般社団法人クリエイターエコノミー協会(2023年2月6日)〉
- 西尾維新デビュー20周年記念ロング・ロングインタビュー 20タイトルをキーに語る、西尾ワールドの変遷(第1回)〈ダ・ヴィンチWeb(2023年2月5日)〉
- 「図書館は住民たちの広場」 国の蔵書介入で、元名物館長が抱く懸念〈朝日新聞デジタル(2023年2月5日)〉※有料会員限定
- マンガの博物館は不要ですか?〈日本経済新聞(2023年2月5日)〉※有料会員限定
- 「神絵が1分で生成される」 進化するAI、イラストレーターの仕事を奪うのか|オリジナル 特集〈Yahoo!ニュース(2023年2月4日)〉
- 新聞は「学級委員」になりがち PV追求は逆に読者をナメていない?〈朝日新聞デジタル(2023年2月4日)〉※有料会員限定
- 「視覚障害と文学」巡り対談 マイノリティーが書く小説の可能性〈毎日新聞(2023年2月4日)〉※有料会員限定
- 「発禁処分を受けたと誤解される」 知られざる「不健全図書類」の実態…マンガ家ら改称熱望〈J-CAST ニュース(2023年2月3日)〉
- 世界
- イベント
- 文化審議会著作権分科会(第66回)〈文化庁(オンライン)/2月7日〉
- オンラインモール利用事業者向けオンラインセミナー「透明化法の運用状況と出店者が気をつけたい法律知識(商標権)について」〈経済産業省(オンライン)/2月10日〉
- ジャパンサーチAPIハッカソン「ミュージアム、図書館、地域で使えるサービスを作ろう!」〈ジャパンサーチ(オンライン)/2月11日・19日〉
- SPARC Japan セミナー2022「電子ジャーナルの転換契約とAPC問題で変わるオープンアクセスの現状と課題」〈SPARC Japan(オンライン)/2月17日〉
- 友利昴×沢辺均「その著作権、エセじゃないですか?」〈版元ドットコム(オンライン)/2月18日〉
- 海外マンガ交流部会 第15回公開研究会「『ビランジ』と日本のマンガ研究」「ベルギーBDとはなにか」「イスラエルのマンガ事情」〈日本マンガ学会(オンライン)/2月18日〉
- 本の校閲オンライン講座「デジタル時代に生きる校正のこころ」講師:大西寿男〈毎日文化センター(オンライン)/2月21日〉
- 報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
- 国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
- 報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
- 10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
- 海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
- 読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
- 本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
- 第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
- 第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
- 2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
- 宣伝
- お知らせ
総合
「LINE BLOG、サービス終了へ」「OpenAI、AI生成テキストの判別ツールを提供開始」など、週刊出版ニュースまとめ&コラム #557(2023年1月29日~2月4日)〈HON.jp News Blog(2023年2月6日)〉
【マンガ業界Newsまとめ】ウェブトゥーンから見た日本漫画の帝王「集英社」、KADOKAWA決算発表、WT中国事情 など|2/5-88〈菊池健|note(2023年2月5日)〉
ZHD、ヤフー・LINE 合併へ Publidia #98〈Publidia(2023年2月5日)〉
国内
電子コミックから「名作」は生まれるのか? “インパクト”重視で分業制も進む中…漫画制作の是非〈ORICON NEWS(2023年2月6日)〉
電子コミックの伸び、急速に鈍化「成熟期に入った」 2022年の出版市場、4年ぶり前年割れ〈J-CAST(2023年2月6日)〉
書店が増えている!? 「行きたい本屋」から「やりたい本屋」へ〈週刊朝日〉〈AERA dot.(2023年2月6日)〉
獲得キーワードが5倍!マンガアプリ「comico」に聞く、攻めと守りのアプリマーケティング〈MarkeZine(2023年2月6日)〉
社説:「ステマ」広告 消費者欺く行為を放置するな〈読売新聞オンライン(2023年2月6日)〉
令和5年度我が国アートのグローバル展開推進事業〈文化庁(2023年2月6日)〉
「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書(案)」に対する意見を提出しました〈一般社団法人クリエイターエコノミー協会(2023年2月6日)〉
西尾維新デビュー20周年記念ロング・ロングインタビュー 20タイトルをキーに語る、西尾ワールドの変遷(第1回)〈ダ・ヴィンチWeb(2023年2月5日)〉
「図書館は住民たちの広場」 国の蔵書介入で、元名物館長が抱く懸念〈朝日新聞デジタル(2023年2月5日)〉※有料会員限定
マンガの博物館は不要ですか?〈日本経済新聞(2023年2月5日)〉※有料会員限定
「神絵が1分で生成される」 進化するAI、イラストレーターの仕事を奪うのか|オリジナル 特集〈Yahoo!ニュース(2023年2月4日)〉
新聞は「学級委員」になりがち PV追求は逆に読者をナメていない?〈朝日新聞デジタル(2023年2月4日)〉※有料会員限定
「視覚障害と文学」巡り対談 マイノリティーが書く小説の可能性〈毎日新聞(2023年2月4日)〉※有料会員限定
「発禁処分を受けたと誤解される」 知られざる「不健全図書類」の実態…マンガ家ら改称熱望〈J-CAST ニュース(2023年2月3日)〉
世界
OpenAIのCEOが見据える、検索を「超えたはるかその先」にあるChatGPTの未来〈CNET Japan(2023年2月6日)〉
デマサイトへの広告、グーグルが仲介を独占…非英語圏で排除に遅れ〈読売新聞オンライン(2023年2月5日)〉
イベント
文化審議会著作権分科会(第66回)〈文化庁(オンライン)/2月7日〉
オンラインモール利用事業者向けオンラインセミナー「透明化法の運用状況と出店者が気をつけたい法律知識(商標権)について」〈経済産業省(オンライン)/2月10日〉
ジャパンサーチAPIハッカソン「ミュージアム、図書館、地域で使えるサービスを作ろう!」〈ジャパンサーチ(オンライン)/2月11日・19日〉
SPARC Japan セミナー2022「電子ジャーナルの転換契約とAPC問題で変わるオープンアクセスの現状と課題」〈SPARC Japan(オンライン)/2月17日〉
友利昴×沢辺均「その著作権、エセじゃないですか?」〈版元ドットコム(オンライン)/2月18日〉
海外マンガ交流部会 第15回公開研究会「『ビランジ』と日本のマンガ研究」「ベルギーBDとはなにか」「イスラエルのマンガ事情」〈日本マンガ学会(オンライン)/2月18日〉
本の校閲オンライン講座「デジタル時代に生きる校正のこころ」講師:大西寿男〈毎日文化センター(オンライン)/2月21日〉
報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉

【満席につき受付終了】本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館 - 大阪府立中之島図書館
近年、活字離れが叫ばれて久しい中、それでも私たちは毎日の生活の中で「本」を手放せないでいます。電子書籍やネット通販は便利で魅力的ではありますが、やはり実店舗で手に取って本を選びたい。そんな方も多いのではないでしょうか。私たちと「本」をつないでくれている本屋さん。その現状と未来について考えるため、モデレーターに梅田 蔦屋書店の北田博充氏をお迎えし、本屋の“リアル”をトークセッション形式で掘り下げてい...
www.nakanoshima-library.jp
第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
http://www.mslis.jp/monthly.html
www.mslis.jp
第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
宣伝
HONꓸjpの新刊が出ました。
出版ニュースまとめ&コラム2016
出版ニュースまとめ&コラム2017
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。