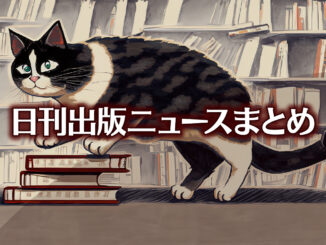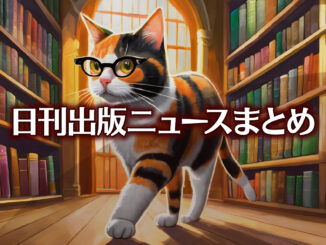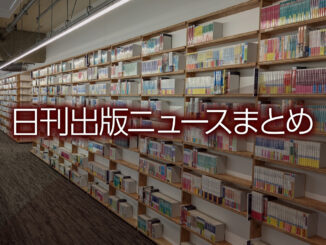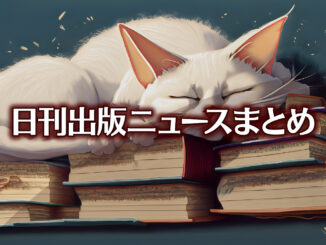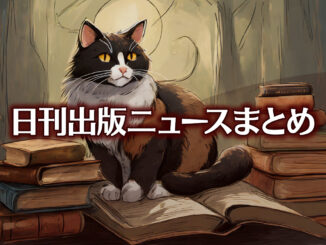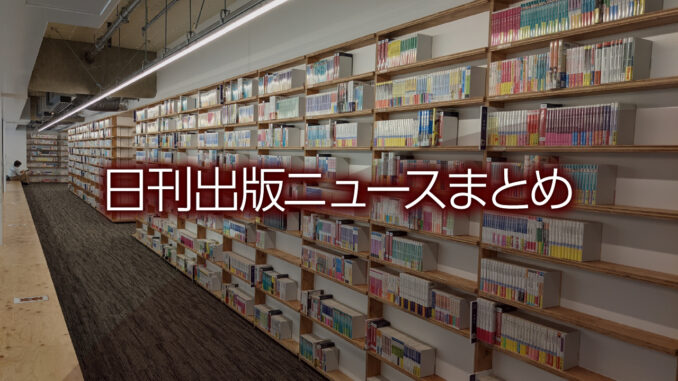
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
伝統的な取次&書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。
【目次】
- 国内
- 「不健全図書」の名称変更求め漫画家が声上げる 「はじめの一歩」森川ジョージさんらが都に陳情 「人間の好みで不健全指定されたら、たまらない」〈zakzak:夕刊フジ公式サイト(2023年2月8日)〉
- 【約8割で薬機法違反の恐れ】REGAL CORE、薬機法などに抵触する記事LPを調査〈日本ネット経済新聞(2023年2月8日)〉
- 「デイリーポータルZ」がサイト改善で入会数54.6%増! ウェブ解析士マスターと語る裏話 | 【レポート】Web担当者Forumミーティング 2022 秋〈Web担当者Forum(2023年2月8日)〉
- 個人作家向けの電子書籍配信取次システム「BLIC」、BookLiveが提供開始〈INTERNET Watch(2023年2月8日)〉
- 【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】専用GPUを搭載、Google Playストアも使える13.3型E Ink端末「BOOX Tab X」〈PC Watch(2023年2月8日)〉
- note、チャットAIを活用した創作支援ツールの近日公開にあたり先行ユーザーの募集を開始〈CreatorZine(2023年2月8日)〉
- 本の世界に浸れる選書専門店で、思考をアップデート/双子のライオン堂(赤坂)〈AdverTimes.(2023年2月8日)〉
- 電子図書館(電子書籍サービス)実施図書館(2023年01月01日)公表の件〈電流協(2023年2月8日)〉
- 編集者・伊藤里和はなぜ「変わった本」をつくるのか?〈Forbes JAPAN 公式サイト(2023年2月7日)〉
- 権利者不明のドラマや個人創作、二次利用迅速化へ答申〈日本経済新聞(2023年2月7日)〉
- リスキリングの手段、「書籍」を超えて最も多いのは? 正社員エンジニア300人へ調査:レバテック調べ〈ITmedia ビジネスオンライン(2023年2月7日)〉
- 海賊版サイトで漫画「ただ読み」、昨年の被害は5069億円…巨大サイト閉鎖で半減〈読売新聞オンライン(2023年2月7日)〉
- 【株式会社主婦の友インフォス】 アニメーション・WEBTOON事業譲受について〈株式会社主婦の友インフォスのプレスリリース(2023年2月7日)〉
- 世界
- サブスク型「ディープフェイクス」の世論工作が月額4,000円、親中国ネットワークの狙いとは?〈新聞紙学的(2023年2月8日)〉
- 「ChatGPT」製のテキストを見分ける特徴が明らかに–皮肉を言わず、人より礼儀正しい〈CNET Japan(2023年2月8日)〉
- 「令和5年度コンテンツ海外展開促進事業(知的財産権侵害対策強化事業)」に係る公募(入札可能性調査)の実施について〈METI/経済産業省(2023年2月8日)〉
- 東京工業大学とTaylor & Francis、電子ジャーナル転換契約を締結〈Taylor&Francis Japan合同会社のプレスリリース(2023年2月8日)〉
- 文章・画像生成AIは著作権侵害か 訴訟に発展も〈WSJ(2023年2月7日)〉
- Microsoft launches the new Bing, with ChatGPT built in〈TechCrunch(2023年2月7日)〉
- アマゾン、大減速で“守りの経営”に戦略転換? それでも「死んでない」と言えるワケ 連載:米国の動向から読み解くビジネス羅針盤〈ビジネス+IT(2023年2月7日)〉
- Our Digital History Is at Risk〈Internet Archive Blogs(2023年2月7日)〉
- 「ChatGPTを競争戦略上どう生かすか、なくなる仕事は?」を議論した〈Forbes JAPAN 公式サイト(2023年2月6日)〉
- イベント
- オンラインモール利用事業者向けオンラインセミナー「透明化法の運用状況と出店者が気をつけたい法律知識(商標権)について」〈経済産業省(オンライン)/2月10日〉
- ジャパンサーチAPIハッカソン「ミュージアム、図書館、地域で使えるサービスを作ろう!」〈ジャパンサーチ(オンライン)/2月11日・19日〉
- SPARC Japan セミナー2022「電子ジャーナルの転換契約とAPC問題で変わるオープンアクセスの現状と課題」〈SPARC Japan(オンライン)/2月17日〉
- 友利昴×沢辺均「その著作権、エセじゃないですか?」〈版元ドットコム(オンライン)/2月18日〉
- 海外マンガ交流部会 第15回公開研究会「『ビランジ』と日本のマンガ研究」「ベルギーBDとはなにか」「イスラエルのマンガ事情」〈日本マンガ学会(オンライン)/2月18日〉
- 本の校閲オンライン講座「デジタル時代に生きる校正のこころ」講師:大西寿男〈毎日文化センター(オンライン)/2月21日〉
- &DC3「『DC3』で実現する、Web3時代のデジタルコンテンツ流通 ーデジタルコンテンツを唯一無二の “モノ“ に」〈日本電子出版協会(オンライン)/2月22日〉
- 商人としての編集者セミナー「ノンフィクション書籍企画の発想と設計」〈KADOKAWA(オンライン)/2月22日〉
- 報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
- 「クリエイター必見!海賊版ってなんだ?被害者だけでなく加害者になることだってあるってホント? 」〈ニコニコ生放送(オンライン)/2月26日〉
- 国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
- 電流協オープンセミナー「電子出版での海外展開の具体的な可能性 ~有望な海外市場とデジタルコミック流通の実際~」〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/3月2日〉
- 報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
- 10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
- 海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
- 読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
- 本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
- 第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
- 第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
- 2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
- 宣伝
- お知らせ
国内
「不健全図書」の名称変更求め漫画家が声上げる 「はじめの一歩」森川ジョージさんらが都に陳情 「人間の好みで不健全指定されたら、たまらない」〈zakzak:夕刊フジ公式サイト(2023年2月8日)〉
【約8割で薬機法違反の恐れ】REGAL CORE、薬機法などに抵触する記事LPを調査〈日本ネット経済新聞(2023年2月8日)〉
「デイリーポータルZ」がサイト改善で入会数54.6%増! ウェブ解析士マスターと語る裏話 | 【レポート】Web担当者Forumミーティング 2022 秋〈Web担当者Forum(2023年2月8日)〉
個人作家向けの電子書籍配信取次システム「BLIC」、BookLiveが提供開始〈INTERNET Watch(2023年2月8日)〉
【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】専用GPUを搭載、Google Playストアも使える13.3型E Ink端末「BOOX Tab X」〈PC Watch(2023年2月8日)〉
note、チャットAIを活用した創作支援ツールの近日公開にあたり先行ユーザーの募集を開始〈CreatorZine(2023年2月8日)〉
チャットAIで記事作成を支援〈note株式会社のプレスリリース(2023年2月8日)〉
本の世界に浸れる選書専門店で、思考をアップデート/双子のライオン堂(赤坂)〈AdverTimes.(2023年2月8日)〉
電子図書館(電子書籍サービス)実施図書館(2023年01月01日)公表の件〈電流協(2023年2月8日)〉
編集者・伊藤里和はなぜ「変わった本」をつくるのか?〈Forbes JAPAN 公式サイト(2023年2月7日)〉
権利者不明のドラマや個人創作、二次利用迅速化へ答申〈日本経済新聞(2023年2月7日)〉
リスキリングの手段、「書籍」を超えて最も多いのは? 正社員エンジニア300人へ調査:レバテック調べ〈ITmedia ビジネスオンライン(2023年2月7日)〉
海賊版サイトで漫画「ただ読み」、昨年の被害は5069億円…巨大サイト閉鎖で半減〈読売新聞オンライン(2023年2月7日)〉
【株式会社主婦の友インフォス】 アニメーション・WEBTOON事業譲受について〈株式会社主婦の友インフォスのプレスリリース(2023年2月7日)〉
世界
サブスク型「ディープフェイクス」の世論工作が月額4,000円、親中国ネットワークの狙いとは?〈新聞紙学的(2023年2月8日)〉
「ChatGPT」製のテキストを見分ける特徴が明らかに–皮肉を言わず、人より礼儀正しい〈CNET Japan(2023年2月8日)〉
「令和5年度コンテンツ海外展開促進事業(知的財産権侵害対策強化事業)」に係る公募(入札可能性調査)の実施について〈METI/経済産業省(2023年2月8日)〉
東京工業大学とTaylor & Francis、電子ジャーナル転換契約を締結〈Taylor&Francis Japan合同会社のプレスリリース(2023年2月8日)〉
文章・画像生成AIは著作権侵害か 訴訟に発展も〈WSJ(2023年2月7日)〉
Microsoft launches the new Bing, with ChatGPT built in〈TechCrunch(2023年2月7日)〉
AI の時代を迎えるにあたって: 責任ある AI で未来の発展へ〈Microsoft News Center Japan(2023年2月7日)〉
AI の次の重要な一歩〈Google Japan Blog(2023年2月7日)〉
アマゾン、大減速で“守りの経営”に戦略転換? それでも「死んでない」と言えるワケ 連載:米国の動向から読み解くビジネス羅針盤〈ビジネス+IT(2023年2月7日)〉
Our Digital History Is at Risk〈Internet Archive Blogs(2023年2月7日)〉
「ChatGPTを競争戦略上どう生かすか、なくなる仕事は?」を議論した〈Forbes JAPAN 公式サイト(2023年2月6日)〉
イベント
オンラインモール利用事業者向けオンラインセミナー「透明化法の運用状況と出店者が気をつけたい法律知識(商標権)について」〈経済産業省(オンライン)/2月10日〉
ジャパンサーチAPIハッカソン「ミュージアム、図書館、地域で使えるサービスを作ろう!」〈ジャパンサーチ(オンライン)/2月11日・19日〉
SPARC Japan セミナー2022「電子ジャーナルの転換契約とAPC問題で変わるオープンアクセスの現状と課題」〈SPARC Japan(オンライン)/2月17日〉
友利昴×沢辺均「その著作権、エセじゃないですか?」〈版元ドットコム(オンライン)/2月18日〉
海外マンガ交流部会 第15回公開研究会「『ビランジ』と日本のマンガ研究」「ベルギーBDとはなにか」「イスラエルのマンガ事情」〈日本マンガ学会(オンライン)/2月18日〉
本の校閲オンライン講座「デジタル時代に生きる校正のこころ」講師:大西寿男〈毎日文化センター(オンライン)/2月21日〉
&DC3「『DC3』で実現する、Web3時代のデジタルコンテンツ流通 ーデジタルコンテンツを唯一無二の “モノ“ に」〈日本電子出版協会(オンライン)/2月22日〉
商人としての編集者セミナー「ノンフィクション書籍企画の発想と設計」〈KADOKAWA(オンライン)/2月22日〉
報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
「クリエイター必見!海賊版ってなんだ?被害者だけでなく加害者になることだってあるってホント? 」〈ニコニコ生放送(オンライン)/2月26日〉
国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
電流協オープンセミナー「電子出版での海外展開の具体的な可能性 ~有望な海外市場とデジタルコミック流通の実際~」〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/3月2日〉
報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
宣伝
HONꓸjpの新刊が出ました。
出版ニュースまとめ&コラム2016
出版ニュースまとめ&コラム2017
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。