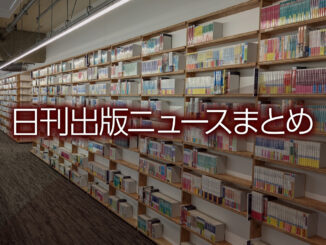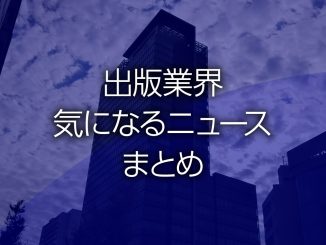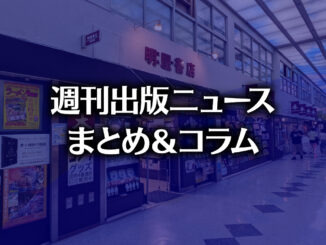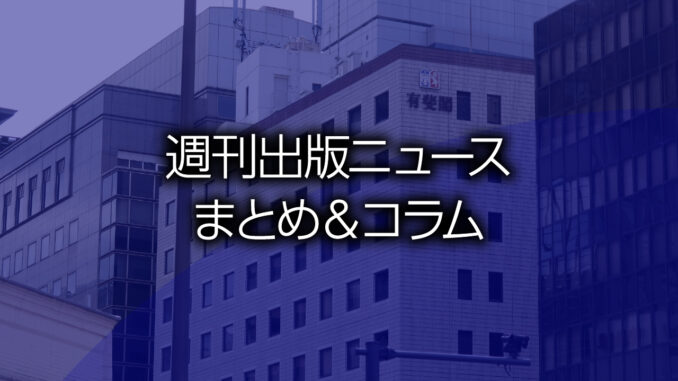
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2023年1月29日~2月4日は「LINE BLOG、サービス終了へ」「OpenAI、AI生成テキストの判別ツールを提供開始」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- Twitterを使い続けるか、やめるべきか。迷っている人が検討すべき6つの選択肢〈WIRED.jp(2023年1月30日)〉
- LINE BLOG、6月29日にサービス終了〈ケータイ Watch(2023年1月30日)〉
- なぜいま「日本産ウェブトゥーン」の「中国アニメ化」なのか…中国の動画配信サービス大手ビリビリが見据える未来(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2023年1月31日)〉
- 講談社が“イッキ読みできる教養新書”を創刊した理由──現代新書・編集長と副部長に聞く、多忙で不透明な時代の「教養」のかたち〈XD:クロスディー(2023年2月1日)〉
- 漫画雑誌も苦境の時代? 漫画編集者に聞くそれでも出版社が雑誌を重視する理由〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月1日)〉
- 「dマガジン」未契約のdアカウントでも、毎週3分無料で雑誌が読める「3分サク読みチケット」〈ケータイ Watch(2023年2月4日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
権利者不明のドラマや動画、二次利用促進へ法改正 ※有料会員限定〈日本経済新聞(2023年1月30日)〉
文化審議会著作権分科会法制度小委員会で検討されてきた「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元の制度化」(記事で触れているのはこれだけ)と、「立法・行政・司法のデジタル化に対応した著作物等の公衆送信等」「海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し」「研究目的に係る権利制限規定の創設」の4つについての報告書案が、パブコメを反映した上で了承されたことを受けての報道です。確定した報告書はすでに文化庁のサイトで公開されています。
次のステップである文化審議会著作権分科会(親会)が2月7日に開催されますが、傍聴申し込むのを忘れてました……まあ、法制度小委員会でもすんなり決まったので、恐らく親会でもとくに波乱などなく進むのではないかと思われます。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
読書バリアフリー法を知ってますか?出版業界で対応がはじまります〈Romancer(2023年2月2日)〉
「ABSC準備会レポート」創刊号(2022年7月号)が、リフロー形式のEPUBで公開されました。ボイジャー「BinB」ブラウザビューアで閲覧できます。JPOのお知らせを確認したら、2号のリフローEPUBは準備中、PDF版は2号ともすでに公開済み、マルチメディアDAISY版も準備中とありました。いろいろ進捗してますね。
日本出版学会でも、アクセシビリティ対応の研究をしなければと、いろいろ動いています。「InDesign」から書き出したEPUBはやっぱりダメだね、とか。紙版のページ番号(ノンブル)を電子版に埋め込む作業は結構大変だね、とか。せっかくページ番号を埋め込んでも、対応しているビューアがほとんどないよね、などなど。現時点でどういった課題があるのかを、抽出している段階です。
5月13日の春季研究発表会では、ワークショップをやる予定で準備しています。とくに、EPUB制作ツールやビューアの開発運営関係者には、ぜひご参加いただきたいと考えています。詳細はまた後日。お楽しみに。
経済
Twitterを使い続けるか、やめるべきか。迷っている人が検討すべき6つの選択肢〈WIRED.jp(2023年1月30日)〉
Twitterの代替手段についての話題が続いています。この記事では「Mastodon」「Post」「Hive Social」といった新興サービスや、「Instagram」「Facebook」「LinkedIn」などのすでに定着したサービスの名前が挙がっています。
私の周囲でも「Bondee」や「Nostr」を始めましたという報告が多く観測されます。私もいろいろ試しています。ただ、このWIREDの記事にも書かれているように、結局のところ「実力が未知数のソーシャルネットワーク」に労力を費やすのはリスクが大きいんですよね。「Google+のような末路」って、やかましいわ(泣)
イーロン・マスク氏がTwitterを買収してからの動きは、正直言えば、方向性はそれほど間違っていないと思うのです。でも、やり方に問題がありすぎる。それだけ切羽詰まった状況だった、ということなのかもしれませんが。
LINE BLOG、6月29日にサービス終了〈ケータイ Watch(2023年1月30日)〉
またひとつ、ブログサービスがお亡くなりに。2019年4月には「Yahoo!ジオシティーズ」が終了し、2019年12月には「Yahoo!ブログ」が終了しています。[2023年2月16日追記:同グループ系では他にも、2020年9月に「NAVERまとめ」、2022年5月に「BLOGOS」が終了していますね。抜けてました。]つまり、これでZHD系からはブログサービスがすべて消滅することに。
まあ、個人発信のコンテンツは検索で上位に出づらくなっていますから、ブログサービスを無料で提供して広告で収益を得るようなビジネスモデルはもう限界なのかもしれません。ZHD、LINE、ヤフーの合併という発表もありましたし、不採算事業は今後もバシバシ終了していくことでしょう。次はなにが終わるかな?
で、こういう事態になってから初めて知ったんですが、「LINE BLOG」ってエクスポート機能がなかったんですね。サービス終了が決まってから他社サービスへの移行手段の準備を始めるというのが、なんとも……もちろん、用意しないより断然マシではありますが。
なぜいま「日本産ウェブトゥーン」の「中国アニメ化」なのか…中国の動画配信サービス大手ビリビリが見据える未来(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2023年1月31日)〉
今年の予想「マンガの輸出」関連でピックアップ。韓国のウェブトゥーンは、アニメ化をあまり想定していない(実写ドラマ化はよくある)というのが、少し意外でしたがなるほど感。垂直統合と水平分業の違いといった話なども、興味深い。
ただ、このインタビューでは触れられていませんが、ビリビリって上場後もずっと赤字続きなんですって。知らなかった。この記事とちょうど同じ日に、ビリビリが「オタクによって生かされ、オタクによって殺される」という記事が出ていました。つまり表題の「なぜ」には、懐事情があるのかもしれません。
講談社が“イッキ読みできる教養新書”を創刊した理由──現代新書・編集長と副部長に聞く、多忙で不透明な時代の「教養」のかたち〈XD:クロスディー(2023年2月1日)〉
薄型新書シリーズ「現代新書100」についてのインタビュー。どういう経緯、どういう発想で始められたのかがじっくり語られており、興味深いです。オックスフォード大学出版局から出ている「Very Short Introductions」というシリーズがロールモデルなのですね。
そのいっぽうで、どうしても紙の本の話が中心になってしまうのだなあ……という思いも。同じ判型のバリエーションを増やすことにより、書店の棚を少しでも確保したいという狙いがある(けど語られていない)ようにも感じます。ページ数が少ないのにわざわざ厚い紙を使って束を確保しているあたりは、逆のほうがいいんじゃないかな……という気も。
短い本といえば「イーシングル」。すぐ読み切れるから、読まれた数に応じて収益配分される読み放題サービスとの相性は良いはず、と私は思っています。しかし「現代新書100」は、Kindleストアには配信されているものの、単品販売のみ。つまり「Kindle Unlimited」には非対応です。なぜ。
漫画雑誌も苦境の時代? 漫画編集者に聞くそれでも出版社が雑誌を重視する理由〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月1日)〉
雑誌は新人漫画家の認知手段としての役割が大きい――といまだに語っている「現役の漫画雑誌の編集者」が、どこの出版社・編集部所属なのかが気になります。いや、もちろんいまでもそういう役割が残っていることは否定しません。しかし、新たな認知手段として「TwitterやInstagram、YouTubeなど」ではなく、「マンガアプリ」について一言も触れないのはどうなのか。「少年ジャンプ+」の成功が目に入っていないのでしょうか。
「dマガジン」未契約のdアカウントでも、毎週3分無料で雑誌が読める「3分サク読みチケット」〈ケータイ Watch(2023年2月4日)〉
「なるほど!」と声が出ました。時間制限付きのお試し機能。「BOOK☆WALKER」には、小説・ライトノベルを1日10分だけ読み放題の「まる読み10分」がありますが、それを少しアレンジして「dマガジン」へ持っていった感じでしょうか。
本は、中身を読んでみないと価値判断ができない「経験財」ですから、こういうリアル書店やコンビニでの「立ち読み」に似たお試し機能って、効果が出そう。読み放題だけでなく、単品購入への誘導があってもいいように思います。「dマガジン」だと読めない記事も多いですし。
技術
AIが生成した文章、判別の研究進む AI研究団体などデモを公開〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2023年1月31日)〉
「ChatGPT」を開発・提供しているOpenAIが、AI生成テキストかどうかを判別するツールの提供も開始しました。まるで、地雷をばら撒くいっぽうで地雷探査機を提供する、武器商人みたいな動きです。「現時点では英文のみに対応」とありますが、試してみたら日本語でもチェックは可能でした。ただ、精度が落ちるみたいですね。
残念ながら「最低でも1000字」という制限があるので、私が講義で学生に課している程度の短いレポートだとチェックできません。まあ、ある程度の長さがないとAI特有の癖が判別できない、というのは理解できます。そういう意味では、AI生成画像のほうが検出はしやすいでしょうし、ニーズも高そう。
ChatGPTが鳴らした号砲、グーグルは自ら主力ビジネスを破壊できるか〈日経クロステック(2023年2月3日)〉
「ChatGPT」がいきなり話題になりましたが、GoogleがAIの分野で負けているわけではない、という話。AI倫理での批判を避けるためであったり、広告ビジネスへの影響を考慮した結果、遅れをとったように見えてしまっている、という状況なのでしょう。学習用データはどこよりも持っているはずの企業ですし。今年の「Google I/O」では「これでもか!」と言わんばかりの新技術が披露されそう。楽しみです。
実際のところ「ChatGPT」は、ジェネレートされた文章そのものより、人間が自然文で入力した質問をあたかも「AIが理解している」ように見える答えを返すことができるあたりが長けてるように感じます。つまり、AIというより、チャットで受け答えするUIが優れている、ということなのでは。
Googleの検索窓は、キーワードを入力しやすいインターフェースです。しかし、自然言語処理技術の「BERT」が出たころ、英語なら文章で質問したほうが精度の高い検索結果が返ってくる、みたいな話を読んだ記憶があります。あるはずなのですが、掘り出せない……ぐぬぬ。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
法人として「弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等」で「同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの」は、1月末までに支払調書と法定調書合計表を税務署へ提出する必要があります。もちろん終わってますが、意外と面倒なのです。でも、e-taxでオンライン手続きできるぶん、意外とラクだったりもします(鷹野)