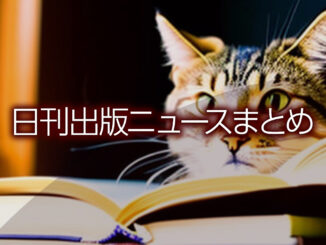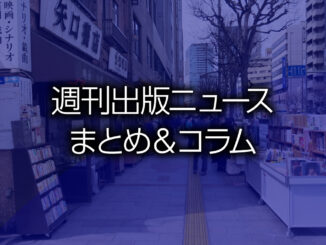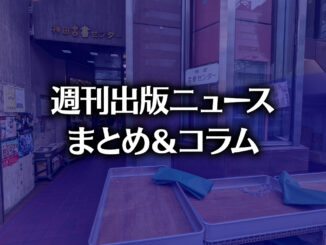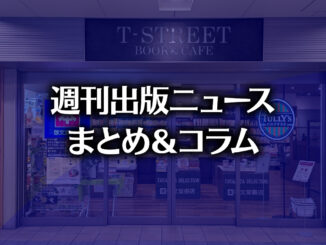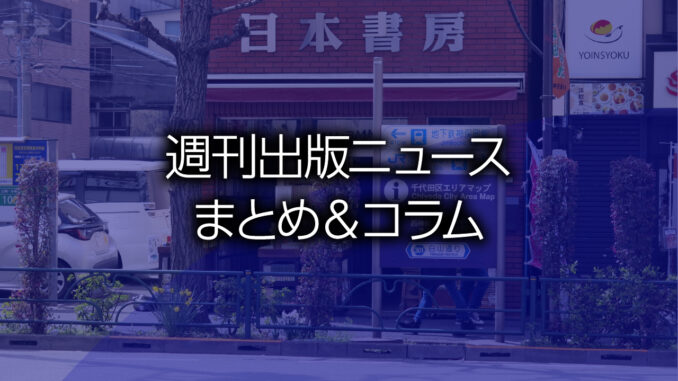
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2023年3月5日~11日は「国立国会図書館デジタルコレクションの送信対象に約32万点追加」「Amazon、縦スクマンガ配信に参入」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
コンテンツ流通円滑に、著作権法改正へ データ集約課題〈日本経済新聞(2023年3月11日)〉
本欄でも何度かお伝えしてきた、文化庁著作権分科会法制度小委員会で審議されてきた「簡素で一元的な権利処理と対価還元の制度化」の報告書を受けた著作権法改正案が閣議決定されました。文部科学省が公表している法律案の概要などはこちら。なお、同時に改正される予定の、立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置と、海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しは、2024年1月1日施行予定です。
著作権管理団体などで集中管理されておらず、利用の可否に関する著作権者等の意思が円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等のことを「未管理公表著作物等」とし、その利用を円滑化することを目的とした改正案です。今国会で成立すれば、2026年度までに施行される予定になっています。
法制度小委員会での審議を傍聴していて印象的だったのが、この「利用の可否に関する著作権者等の意思」について。例えば出版物の奥付などには「禁無断転載」といった定型的な表示がありますが、委員の福井健策氏から「それのみをもって意思の明示ありとすべきではない」という意見があり議論になりました。
出版物の場合、いわゆる「品切重版未定」で権利だけが出版社に保持されているケースも多いですからね。古い本を電子版で復刻しようと思ったら、著者には連絡が付いてOKも出ているのに、出版社に連絡を無視されて困っている――といった話を伺ったことがあります。法改正の趣旨からすると、こういうケースは「意思表示なし」とみなされるのが自然でしょう。
最終的に報告書では、「過去の時点での利用の可否が示されているものの、現在市場に流通していないなどにより現在の意思が確認できない場合の扱いについては、実態等を踏まえて引き続き今後の検討課題とする」と記されました(p6)。法文に明記される領域ではないので、今後、ガイドライン等で詰めていくという話になるのでしょう。
実際のところ、2014年以前の出版契約をまき直していないなら紙の出版権(1号)だけですから、電子の出版権(2号)を別で設定しても法律的には問題ありません。ただ、著者と出版社の関係を考えたら、礼儀として話を通しておく必要がある――という、実務レベルでは頻出する境界事例と言っていいでしょう。日経に、この新制度について「権利の上に眠らせない」という解説が出ていました。法律格言なのですね。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
国立国会図書館、「国立国会図書館デジタルコレクション」収録の図書・雑誌等約32万点を図書館向け/個人向けの送信対象資料に追加〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月7日)〉
入手可能性調査と事前除外手続が昨年行われた資料がドカッと追加されました。これで送信サービスの対象資料は約184万点、インターネット公開資料と合わせると約242万点という規模に。素晴らしい。ちなみにこれって、前述の「権利の上に眠らせない」典型事例なのですよね。眠っているなら公共に資することになるので、眠っていないならそう申し出てください、と。つまり、オプトアウトです。
国立国会図書館による入手可能性調査は、現状では「①著作物の流通の確認(e-hon及びHonya Club)」「②オンデマンド出版流通の確認(万能書店及びAmazonプリントオンデマンド)」「③電子書籍流通の確認(Books)」と、少し網の目が粗いものになっています。つまり、事前除外手続の段階での出版社自身によるチェックの重要度がけっこう高い。チェックが漏れたら送信対象資料です。眠らせてもらえません。
あと、3月6日のJPRO説明会でも強調されていましたが、「③電子書籍流通の確認」は「Books」で行われるわけですから、電子版があるなら必ずJPROに登録しておくこと。そして、底本情報と結びつけておく(そのためにはISBNもしくはJP-eコードが必須)ことが重要です。そうすれば入手可能性調査の時点で除外されます。ところが現時点で、電子版の約半数が底本ISBNなしの迷子とのこと。たくさん眠っているなあ。
Vaundyがマンガのセリフで作詞、海賊版対策キャンペーンに楽曲提供(動画あり / コメントあり)〈音楽ナタリー(2023年3月9日)〉
これはなかなかすごい。「STOP! 海賊版」キャンペーンの新たな取り組みです。マンガのセリフがそのまま歌詞に使われ、動画ではそのマンガのコマがそのまま出てきます。どの作品のどのコマが用いられているかは、ABJの特設ページに一覧があります。つまりもちろん、すべて許諾をとったうえで利用しているわけです。一昔前によくあった、無断で切り貼りした「MADムービー」とはわけが違う。
ありがとう、君の漫画愛。〈STOP! 海賊版(2023年3月9日)〉
そしてさらに言えば、これまでこのキャンペーンは「きみを犯罪者にしたくない。」のようなネガティブなメッセージが中心でしたが、今回は「ありがとう」というポジティブなメッセージ。良いなあ、実に良い。なお、この特設ページは「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の共通目的基金の助成を受けて制作されています」とのこと。なるほど! 良い使い道ですね。
ソウル、10代の半数「インターネット新聞も読書のうち」と認識 写真枚 国際ニュース〈AFPBB News(2023年3月9日)〉
韓国での調査結果。10代では、ウェブトゥーンを読書と考えるケースも37.3%に及ぶそうです。遠い昔――私が小学生のころ、読書についての調査で「マンガや雑誌は対象外」とされていることに納得ができず、先生に食ってかかったのを思い出しました。まあ、いまでもそういう風潮ありますから、いまだに納得できていないんですけどね。
経済
中国出版業界の熱気が戻ってきた!――第35回北京書籍受注内覧会を参観して〈HON.jp News Blog(2023年3月6日)〉
おなじみ馬場公彦氏による「北京書籍受注内覧会」のレポートです。業者間取引のイベントなのですが、その現場からライブコマースで一般向けにも展開するというのは、じつに商魂たくましい。コロナ禍を受け、ライブコマースが急成長した中国ならではとも言えるでしょう。日本でもライブコマースが伸びるかも? という予想(2021年)をしていたのですが、いまのところ見事に外しましたねぇ……。
note、ついにインポート/エクスポートに対応〈Impress Watch(2023年3月6日)〉
ついに。この「ついに」という記述に、いろんな思いをくみ取ってしまいました。本文にもあるように「noteでは2021年4月にインポート/エクスポート対応を予告していたが、約2年弱で実装されたこととなる」なのですよね。いやあ、時間かかったなあ。このタイミングは、昨年末に上場したことや、直近で「LINE BLOG」が終わることなども影響しているのでしょうか。
なお、エクスポート機能がないことに関しては、サービス開始当初から指摘があったのを覚えています。それが、2020年に堀正岳氏による問題提起「noteからコンテンツをエクスポートする方法がないというリスク」がバズったことによって、広く認知されたという認識です。この投稿に対し、noteのCXOである深津貴之氏が「たぶん1年以内想定ぐらい」とコメントしてからは、もうすぐ3年経つところでした。いやあ、ほんっと時間かかったなあ。
エクスポート対応がなされないままだと、「noteを利用する」イコール「noteに囲い込まれる」なので、周囲へ積極的には勧めづらかったのが正直なところ。これでようやく、安心して勧められるサービスになりました。サービス終了のタイミングになって初めて「エクスポート機能を準備します」と告知するようなサービス(他にも複数あり)に比べたら断然マシです。
Amazon、縦読み漫画サービス開始 国内独占タイトルも〈日本経済新聞(2023年3月7日)〉
ついに大物参入。サービス名は「Amazon Fliptoon(フリップトゥーン)」と、あえて「Kindle」のブランド名を使わない形になっています。Kindle端末やKindleアプリから読めるわけではないので、混同されるのを避けたのでしょう。あと、日本語以外では情報が見つかりません。どうやらアマゾンジャパン独自展開っぽい。日本でうまくいったら、世界展開するんでしょうか?
PV数が価値を持たなくなる時代に我々は何を作るべきか。メディアの可能性をこじ開けるスイーツサイト「ufu.」坂井勇太郎さん【シリーズ編集者の時代/第4回】〈CORECOLOR(2023年3月10日)〉
PV数を追いかけ広告収入を稼ぐ――という一般的な戦略に背を向けたウェブメディアの中の人へのインタビュー。ヤフーなどの外部配信で読まれても、その読者がファンになってくれるわけではない、などの考え方に筋が通っていて非常に共感できます。ケヴィン・ケリーの“1000 True Fans”をウェブメディアで実践している感じです。
技術
AI記事制作で所要時間「10分の1に短縮」 一方で懸念も…話題ツール提供企業に聞く手ごたえと課題〈J-CAST ニュース(2023年3月4日)〉
ChatGPTのAPIが開放される前から「ChatGPTの技術を活用したWebメディア記事自動作成ツールのβ版提供を開始」などというプレスリリースを配信して物議を醸していた企業に、J-CASTが取材しています。「今まで培ったSEO知見」というワードも相まって、SEO対策を目的とした記事の粗製濫造に繋がるかも? といったネガティブな懸念が多く見受けられました。私もそれは強く懸念しています。
ただ、J-CASTの取材によると、このサービスで想定している記事作成フローは「(1)生成要件の設定」から始まっています。ペルソナやニーズ・目的などの設定や、ターゲットキーワードの設定、検索意図の設定などです。そういう前工程って、記事制作(執筆・編集)の経験やノウハウのない人が一朝一夕にできるものではないと思うのですよね。
段取り八分と言いますが、準備段階がダメならアウトプットもダメになるというのは摂理(法則)です。このサービスやジェネレーティブAIに限った話ではありません。裏を返せば、その道の経験やノウハウのある人にとっては、ジェネレーティブAIは非常に利便性の高いツールになるのではないでしょうか。
AI関連で最近よくお名前を拝見する清水亮氏が、この週末に「クリエイターの時代」という記事を公開していました。そこにも「ChatGPTに関して言えば、クリエイターの能力の差をより広げるものになっている」とあり、なるほどやはりそうか、と。
すごい人がすごい道具を使うと、さらにすごいアウトプットができる。同じ道具を素人が使うと、一定レベルまで底上げはされるけど、すごい人のすごいアウトプットには及ばない。使いこなすにはやはり経験やノウハウと習練が必要で、恐らく圧倒的大多数がその前に挫折しちゃうんだろうな、と。
Microsoft DesignerとAI「サービス化」競争の幕開け【西田宗千佳のイマトミライ】〈Impress Watch(2023年3月6日)〉
Microsoft Designerのウェイティングリスト、登録したのをすっかり忘れたころに“The wait is over! You’re in!”というメールが届きました。私も試してみましたが、西田宗千佳氏と同様「うーん?」と首を傾げてしまいました。プロンプトだけで出力すると、あまりにクオリティが低い。ただ、結局はこれも「便利な道具」です。丸投げではなく、うまく使いこなすとさらにすごいアウトプットができるという代物なのでしょう。
ちなみに最近、「Canva」に「Text to Image」機能が追加されたので、せっかくだからと思い「日刊出版ニュースまとめ」のアイキャッチを日替わり更新にしました。練習、練習。日本語で指示できるのですが、たとえば「5匹の」という具体的な指定が無視されるなど、なかなか思い通りにはいきません。来週からは英語でやってみます。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
暖かくなってきたなあと思っていたら、昨日・今日は屋内だと暑いくらいに。室温計を見たら、29度。思わず扇風機のスイッチを入れてしまいました。春だなあ(鷹野)