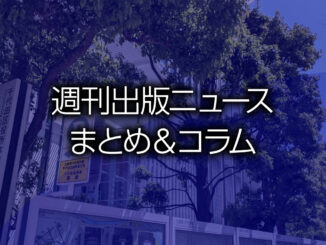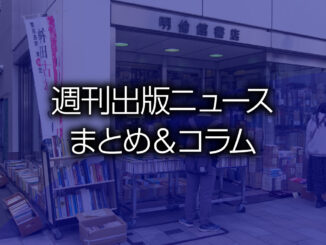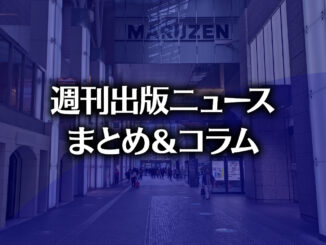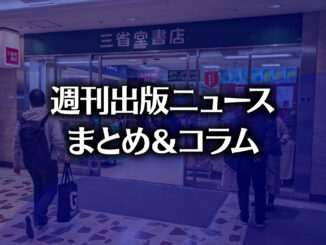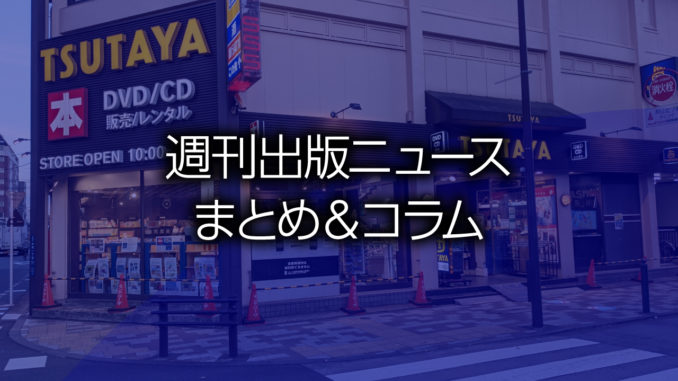
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2021年2月21日~27日は「マンガ市場過去最大に」「マス4媒体広告費にネット肉薄」「中国民法典」「Twitter有償サービス追加予定」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 私権の保障を規範化した中国民法典(前編)――施行までの道のりとその意義〈HON.jp News Blog(2021年2月22日)〉
- 私権の保障を規範化した中国民法典(中編)――人格権 新設の背景とその中身〈HON.jp News Blog(2021年2月23日)〉
- 私権の保障を規範化した中国民法典(後編)――迫られるメディア界の対応〈HON.jp News Blog(2021年2月24日)〉
- 仏独禁法当局、米グーグルが命令違反と指摘 メディアとの協議で〈ロイター(2021年2月24日)〉
- Facebook 、豪でニュースを再開へ(だが、詳細は不透明) : 要点まとめ〈DIGIDAY[日本版](2021年2月26日)〉
- 社会
- 教育IT「GIGAスクール」の“実質勝者”Googleの衝撃データ……「対象自治体の半数を獲得」はなぜできた?〈Business Insider Japan(2021年2月18日)〉
- 震災の記録445万件収集 国会図書館8年で倍増〈共同通信(2021年2月22日)〉
- 本の背表紙画像をAIが解析する「AI蔵書点検サポートサービス」が提供開始〈Digital Shift Times(2021年2月25日)〉
- ネット広告費がマス4媒体に並ぶ 2020年の広告費、コロナ禍の影響受け二ケタ減〈AdverTimes(2021年2月25日)〉
- 日本電子出版協会(JEPA)、小中学校への電子図書館サービス提供に関する緊急提言を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年2月25日)〉
- 経済
- コロナ時代の読書スタイルに?…人気広がる要約サービスとオーディオブック〈産経ニュース(2021年2月22日)〉
- 「○○殺人事件」がクレカ決済NGに? 大手クレカ会社から通達との噂にユーザー反発【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2021年2月22日)〉
- 伸びる電子書籍、恩恵は大手に集中? 進まぬ人文・専門書、「出版文化の多様性」は道半ば〈朝日新聞デジタル(2021年2月23日)〉
- 評価の高いノンフィクションが読めるサブスク型の新サービス「SlowNews」提供開始〈BOOKウォッチ(2021年2月24日)〉
- Twitter、クリエイターに金銭を支援できる「SUPER FOLLOWS(スーパーフォロー)」発表 支援者向け特典機能も実装〈ねとらぼ(2021年2月26日)〉
- 2020年コミック市場は紙+電子で6126億円、前年比23.0%増と2年連続急成長で過去最大規模に ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2021年2月26日)〉
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
政治
私権の保障を規範化した中国民法典(前編)――施行までの道のりとその意義〈HON.jp News Blog(2021年2月22日)〉
私権の保障を規範化した中国民法典(中編)――人格権 新設の背景とその中身〈HON.jp News Blog(2021年2月23日)〉
私権の保障を規範化した中国民法典(後編)――迫られるメディア界の対応〈HON.jp News Blog(2021年2月24日)〉
毎月おなじみ、北京大学・馬場公彦さんのコラム。今回は、2021年1月1日から施行された中国民法典について。中国の著者やメディア企業と取引している方や、これから取引を始める方は要注意、という解説です。私は、恥ずかしながら中国で民法典が制定されたこと自体を知らなかったんですが、調べてみたら「離婚申請にクーリングオフ」みたいな報道が数件見つかる程度でした。人格権とか契約のルールとか、いろいろ気をつけるべき点があるようですよ。
仏独禁法当局、米グーグルが命令違反と指摘 メディアとの協議で〈ロイター(2021年2月24日)〉
フランスの報道各社が「Google News Showcase」の有償提供で合意という発表が1月にありましたが、Googleが政府の命令を遵守していないという指摘を受けているそうです。Googleがしたたかなのか、当局が必要以上に厳しいのか。このあたりの動向、油断も隙もない感じです。
Facebook 、豪でニュースを再開へ(だが、詳細は不透明) : 要点まとめ〈DIGIDAY[日本版](2021年2月26日)〉
オーストラリアの法規制も、条文を修正する・しないという情報が錯綜していましたが、結局修正案が可決されることに。先週、Facebookがニュースフィードからオーストラリアのメディアを締め出して大騒ぎになっていましたが、修正されたため復活したそうです。前述のGoogleもそうですけど、ずいぶん荒っぽい駆け引きをなさる。
社会
教育IT「GIGAスクール」の“実質勝者”Googleの衝撃データ……「対象自治体の半数を獲得」はなぜできた?〈Business Insider Japan(2021年2月18日)〉
Googleによる発表。いままで国内ではMicrosoftの圧勝でしたが、これで一気に勢力図が変わったことになります。残りも、iPadの割合のほうが多いんじゃないかしら。ちなみにタイトルにある「なぜ」は記事内に書かれておらず、拍子抜けしました。
個人的には、2020年の年始動向予想で「実用性を考えると恐らくアメリカと同様にChromebookが採用される可能性が高いものと思われます」と書いた通りになったなあと(↓)。あまり驚きはありません。
クラウドサービスの乗り換えはかなり面倒なので、この割合でしばらく固定化されるだろう、というのは、元記事筆者のおっしゃる通り。スイッチングコストが高いというやつです。結果、どうなるか? うーん、複雑怪奇なWordより、シンプルなGoogleドキュメントのほうが、構造化された文書を書ける子に育ちそうな気がします。もちろん、教え方次第ではありますが。
震災の記録445万件収集 国会図書館8年で倍増〈共同通信(2021年2月22日)〉
東日本大震災からもうすぐ10年。国立国会図書館による震災記録のデジタルアーカイブ「ひなぎく」の現状について発表がありました。教訓を後世に伝える、意義深い国家事業です。記憶は薄れるけど、記録は残る。
本の背表紙画像をAIが解析する「AI蔵書点検サポートサービス」が提供開始〈Digital Shift Times(2021年2月25日)〉
京セラコミュニケーションシステムが、図書館の蔵書点検業務に使うことを想定したシステム「SHELF EYE(シェルフアイ)」を提供開始。棚に並んでいる蔵書をタブレットで撮るとAIが自動解析して本を特定。所在不明の書誌リストを作成したり、貸出頻度の低い本を書架から外したりといった業務に活用できるそうです。図書館蔵書の背表紙には書籍用背ラベルが貼られているはずですが、それを織り込んだ上で解析できるってことですよね。面白い。
ネット広告費がマス4媒体に並ぶ 2020年の広告費、コロナ禍の影響受け二ケタ減〈AdverTimes(2021年2月25日)〉
毎年恒例、電通「日本の広告費」が発表されました。マス4媒体が前年比86.4%と落ち込んだのに対し、インターネット広告費は同105.9%と成長を続けた結果、246億円差まで迫っています。とくに雑誌広告費は同73.0%と激減。2005年に対象誌を増やして4842億円と推定したのがピークで、2020年はとうとう1223億円に。15年間で4分の1になってしまいました。ぎゃーっ。
また、私は雑誌デジタルはもっと伸びるだろうと思っていたんですが、前年比は鈍化という結果に(120.2%→110.1%)。まあ、インターネット広告費全体の成長率よりは高いので、鈍化はコロナ禍のせいかもしれませんが。
日本電子出版協会(JEPA)、小中学校への電子図書館サービス提供に関する緊急提言を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年2月25日)〉
JEPAから「今こそ国は学校電子図書館の準備を!」という緊急提言が出ています。「全ての小中学校に5万点の読み放題電子図書館サービス提供」「利用料は全額国の負担」の2つ。ちなみに昨年11月の図書館総合展でも同様の緊急提言が行われていますが(↓)、比べてみたら答申の委員会設置が削られていることに気がつきました。おや?
経済
コロナ時代の読書スタイルに?…人気広がる要約サービスとオーディオブック〈産経ニュース(2021年2月22日)〉
記事に取り上げられている中で、要約サービスの「SERENDIP(セレンディップ)」は知らないなあ……と思っていたら、個人ブログ時代の2014年にピックアップしてました(↓)。すっかり忘れてましたよ。トホホ。
2012年くらいに、某著名な方が無断で要約サービスを始めて問題視された騒ぎが印象に残っていて、でもこのサービスは「※ダイジェストは出版社または著者の許諾を得て作成、配信しております。」と書いてあった(↓)ので、ちゃんとしてるなあと思った記憶が蘇ってきました。というか、ブログに書いてありました。記憶は薄れるけど、記録は残るんです!
でも、いま「SERENDIP」のサイトを見ても、この記述が見つからない……勘違いする人が出るとアレなんで、ちゃんと明記しておいたほうが良いように思うのですが。
「○○殺人事件」がクレカ決済NGに? 大手クレカ会社から通達との噂にユーザー反発【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2021年2月22日)〉
こういう動きは、2006年に金融業界などが「児童ポルノの撲滅」という目的で団体を結成したことが発端だったようです(↓)。それがだんだん問題視する領域を広げてきて、こんどは「殺人」というワードにも難色を示すようになった模様。
反響で「カード会社は決済商品の名前を把握できないのでガセ」といった声も見かけましたが、決済のタイミングで判定しているはずもなく。誰でも見られるラインアップの時点で「こういう商品は困ります」と圧がかかる、という話です。しかも、基準が不明瞭で、相手を選んでいるっぽい。
政府による表現規制とはレベルが若干異なり、法人には経済活動の自由、契約締結の自由があります。そのいっぽうで、社会インフラに近い企業に求められる役割と責任、というのもあるでしょう。そのバランス、という問題なのかな、と。いずれにしても、基準が明確じゃないと困っちゃいますよね。
伸びる電子書籍、恩恵は大手に集中? 進まぬ人文・専門書、「出版文化の多様性」は道半ば〈朝日新聞デジタル(2021年2月23日)〉
言い回しがいろいろ微妙で、無駄に分断を煽っているように感じてしまう記事。たとえば「恩恵は漫画のラインアップが豊富な大手に集中しているという指摘もある」とありますが、恩恵は「大手」に限った話ではありません。スクウェア・エニックスとか、スターツ出版とか、アルファポリスあたりも好決算なわけで。「指摘もある」ではなく事実を見ろ、と言いたい。
あとは、見出しの「出版文化の多様性は道半ば」というのも微妙。多様性はすでにあります。でも、雑誌市場の落ち込みにより取次・書店流通が危機的状況に陥り、結果、書籍市場にも致命傷を与えかねない(結果、多様性が損なわれる)ので、少量生産の出版物は早くデジタル(POD含む)へ移行したほうがいい、という話なら理解できるのですが。
評価の高いノンフィクションが読めるサブスク型の新サービス「SlowNews」提供開始〈BOOKウォッチ(2021年2月24日)〉
スマートニュースが2019年に設立したスローニュースが、ついにサービス展開を開始。骨太ノンフィクションの新原稿と、既刊の電子版が100点くらい読み放題になっています。月額1650円(税込)と少々値が張りますが、調査報道に取り組むジャーナリストへ取材費用の支援などを行うと明言していますし、月に単行本1冊分程度と思えば……と、申し込んでみました。基本横書きですが、任意で縦書きにも変更できるというのが面白い。ビューアは独自開発だそうです。
Twitter、クリエイターに金銭を支援できる「SUPER FOLLOWS(スーパーフォロー)」発表 支援者向け特典機能も実装〈ねとらぼ(2021年2月26日)〉
そうきたか。「note」の定期購読マガジンとかサークルに近い感じでしょうか。今年中にサービス開始予定とのことです。最初からペイウォールがある前提のサービスとは異なり、基本無料のオープンな形で普及したサービスにこういう仕組みが導入されると、生態系にどういう変化が起きるのかが気になります。現時点の反響を見ていると、反発や危惧する声のほうが目立つ感じがします。
2020年コミック市場は紙+電子で6126億円、前年比23.0%増と2年連続急成長で過去最大規模に ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2021年2月26日)〉
1990年代後半を上回る市場規模まで一気に拡大。すごい伸びです。グラフにすると、インパクトが大きい。こうやって過去からの推移を見ると、紙のコミックス(単行本)については比較的堅調で、コミック誌が壊滅的だというのがよくわかります。新作マンガの認知媒体は、ウェブまたはアプリにすっかり移行しちゃいましたね。
ブロードキャスティング
毎週ライブ配信している映像番組、2月28日のゲストは竹田信弥さん(書店主 / 双子のライオン堂)西島大介さん(漫画家)でした。番組のアーカイブはこちら。
次回のゲストは吉川浩満さん(文筆家・編集者)です。配信終了後はZoom交流会もあります。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。