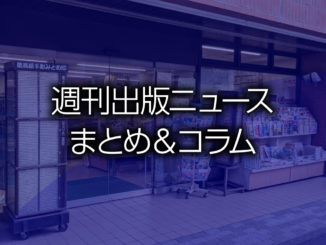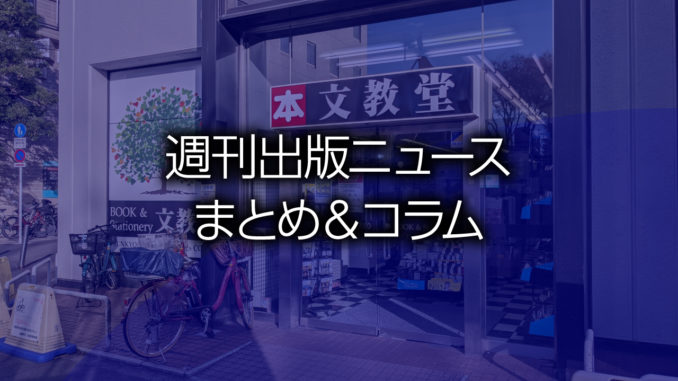
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2020年12月27日~2021年1月9日は「2020年回顧と2021年予想」「中国動漫産業の実態と動向」「海賊版ダウンロード違法範囲拡大」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。今回から編成を少し変え、総合+政治・経済・社会・技術の5ジャンルに分類しています。
【目次】
- 総合
- 政治
- 社会
- 経済
- 「はじめの一歩」「FAIRY TAIL」「DAYS」マガポケで無料公開、森川ジョージらコメントも〈コミックナタリー(2020年12月30日)〉
- 【独自】ネットに無断掲載の「海賊版」漫画、ひと月で被害350億円…ダウンロードは違法に〈読売新聞オンライン(2020年12月31日)〉
- コロナ禍でもブログでメシが食えるか? Publickeyの2020年[特別編]〈Publickey(2021年1月1日)〉
- NewsPicksは経済メディアをDXした。これからは映像メディアの変革を。 佐々木紀彦、退任を語る。〈Business Insider Japan(2021年1月7日)〉★
- 『FACTFULNESS』発売から2年で100万部突破、先生向けガイド配布も 事実にもとづき「世界の見方」を学ぶベストセラー〈ほんのひきだし(2021年1月7日)〉
- ドワンゴ、オーディオブック「ListenGo」(リスンゴ)開始 月額300円から〈ITmedia NEWS(2021年1月8日)〉★
- 『週刊文春』『ナンバー』など文藝春秋のデジタル化の加速ぶりは要注目だ(篠田博之)〈Yahoo!ニュース個人(2021年1月9日)〉★
- 中国の若者文化を育んだ日本の漫画・アニメ――中国動漫産業の実態と動向(前編)〈HON.jp News Blog(2021年1月7日)〉★
- オリジナル作品のIPビジネス展開に乗り出す中国動漫――中国動漫産業の実態と動向(後編)〈HON.jp News Blog(2021年1月8日)〉
- 2020 has been surprisingly good for the publishing industry〈Good e-Reader(2021年1月6日)〉
- 33% Growth for Digital Books from Public Libraries and Schools in 2020 Sets Records〈OverDrive(2021年1月7日)〉
- 技術
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
総合
国内コラム記事年間アクセスランキング(2020年)〈HON.jp News Blog(2020年12月29日)〉
海外コラム記事年間アクセスランキング(2020年)〈HON.jp News Blog(2020年12月29日)〉
2020年に配信したコラム記事のアクセスランキング、国内1位は授業目的公衆送信補償金制度の解説、海外1位は馬場公彦さんによる『武漢日記』出版をめぐる騒動の解説でした。
2020年出版関連動向回顧と年初予想の検証〈HON.jp News Blog(2020年12月31日)〉
2021年出版関連の動向予想〈HON.jp News Blog(2021年1月8日)〉
毎年恒例、年末の振り返りと、年初の予想です。2本合わせて2万5000字ありますので、お時間のあるときにどうぞ。今年の予想は、以下の5つです。
- 出版社系ウェブメディアの飛躍
- 既刊の電子化が急がれる(というか急げ)
- 描き手争奪競争の更なる激化
- 電子図書館サービスの普及がついに始まる
- 映像コンテンツの需要がより高まる
政治
“海賊版のダウンロードは違法” 著作権法改正 来月1日から〈NHKニュース(2020年12月27日)〉
違法ダウンロード範囲拡大の改正著作権法、いよいよ施行です。2021年予想でも書きましたが、一般ユーザー向けには幾重ものセーフティーネットが用意されています。とはいえ、アナウンス効果に加え、「あそこは海賊版サイトだから、ダウンロードは違法ですよ」と名指しできるようになったことが大きい。これからABJや出版広報センターがどういう動きをするか、注目です。
主要国におけるGAFA、デジタルプラットフォーム事業者への競争法適用の動き〈公益財団法人 公正取引協会(2020年12月30日)〉
日本を含めた各国の、巨大IT企業に対する規制強化の動きがまとめられています。とくにGoogleとFacebookが、各国政府から目の敵にされている感。
肖像権ガイドライン案 パブリック・コメント募集 (2021/2/7まで)〈デジタルアーカイブ学会(2021年1月8日)〉
デジタルアーカイブ学会の法制度部会が、肖像権ガイドライン案へのパブリック・コメントを募集しています。大量のコンテンツを扱うデジタルアーカイブ機関の現場で、撮影者の著作権だけでなく、被写体の肖像権をどう扱うべきか? という問題への道しるべです。
ロジックは、公開によって予想される影響をポイント換算して、公開に適するか否かを判断しましょう、というもの。たとえば公人や著名人などは、公開へのハードルが低くなる、といった評価方法になっています。
米国でデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の改革議論…プラットフォームからメディアへの補償に道を開く可能性〈Media Innovation(2020年12月29日)〉
これもプラットフォームに対する規制強化の動き。notice and takedown 手続きを「著作物データベース」の共有化により簡素化する方向性や、プラットフォームでのコンテンツ利用に対する補償を定めた「補助的著作物(Ancillary Copyright)」の導入などが検討されているそうです。
日本では2018年に「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」が導入され、権利者の利益を害さない、あるいは軽微な場合の利用は制限が緩やかになったわけですが、アメリカでは逆に、規制を強める方向へ舵を切ろうとしているわけです。さて、どうなるか。
社会
「青空文庫規準」で著作権保護期間中の作品を公開する新サイト、本の未来基金が立ち上げへ〈INTERNET Watch(2021年1月5日)〉
青空文庫では、保護期間が満了した作品だけでなく、著作権者が公開に同意した作品も受け入れてます。これをもっと円滑にするための仕組みを、新たに立ち上げる予定とのこと。
現状、各自のオフライン作業が中心なのに対し、オンライン共同作業ツールを実験導入して、アーカイブ技術の継承や育成を目指すとしています。詳細は近日発表予定とのこと。楽しみですね。
経済
「はじめの一歩」「FAIRY TAIL」「DAYS」マガポケで無料公開、森川ジョージらコメントも〈コミックナタリー(2020年12月30日)〉
単なる無料公開以上の意味があるニュース。森川ジョージさんの「はじめの一歩」単行本は、以前は電子版が普通に販売されていたのが、2015年9月以降配信停止され、「週刊少年マガジン」での連載も電子版からは除外されているという状態が続いていました。こちらは配信停止が予告された当時の記事(↓)。
実は昨年4月の緊急事態宣言時にも無料公開の提案をしていたけど、編集部・製版所が対応できず実現できていなかったそうです。このたびようやく体制が整った、と。これが期間限定の無料配信に留まらず、販売を再開するのかどうかは分かりませんが、いつでも再開できる状態になったとは言えそうです。期待。
4月の緊急事態宣言の時に提案したのですが編集部も製版所も大変で実現できませんでした。このほど体制が整のったとのことなので期間限定ではありますが60巻を無料公開します。ステイホームのお供になれば幸いです。皆様ぜひマガポケを覗いてみて下さい。 https://t.co/xJiYvpBZO2
— 森川ジョージ (@WANPOWANWAN) December 30, 2020
【独自】ネットに無断掲載の「海賊版」漫画、ひと月で被害350億円…ダウンロードは違法に〈読売新聞オンライン(2020年12月31日)〉
前掲の、違法ダウンロード範囲拡大の改正著作権法施行に伴う広報活動の一環、でしょうか。とくに悪質な5サイトのアクセス数合計が、2020年1月の1300万から、11月には約9倍の1億1600万になっているとのこと。
「漫画村」が社会問題になった当時、月間アクセス数は最大で1億超(↓)という試算が出ていましたので、同じツールで分析しているのであれば、5サイト合計とはいえ当時を上回る状態になっている、ということが言えそうです。むむむ。
コロナ禍でもブログでメシが食えるか? Publickeyの2020年[特別編]〈Publickey(2021年1月1日)〉

ITジャーナリスト・新野淳一氏が主宰するブログメディア「Publickey」から、2年ぶりの売上報告です。コロナ禍でも堅調。素晴らしい。運用型広告(Google AdSense)やアフィリエイトに依存しないウェブメディアの成功事例として、ロールモデルにさせてもらっています。
NewsPicksは経済メディアをDXした。これからは映像メディアの変革を。 佐々木紀彦、退任を語る。〈Business Insider Japan(2021年1月7日)〉★
2020年12月末に NewsPicks 取締役と NewsPicks Studios のCEOを退任した佐々木紀彦さん、まずはお疲れさまでした。新会社を作り、映像メディアに注力するそうです。Business Insider Japan 統括編集長を奇しくも同タイミングで退任した浜田敬子さんがインタビュアーで、質問が鋭い。これからのメディアの在り方について、いろいろ考えさせられます。
『FACTFULNESS』発売から2年で100万部突破、先生向けガイド配布も 事実にもとづき「世界の見方」を学ぶベストセラー〈ほんのひきだし(2021年1月7日)〉

累計100万部のうち、紙が84万部、電子が13万部超、Audibleで3万超という数字が公表されています。こういう事例を待ってました。芥川賞を受賞した又吉直樹さんの『火花』(文藝春秋)が、2017年の時点で紙が220万部、電子が17万ダウンロードという実績が明かされたことがありました(↓)が、当時に比べると、だいぶ電子の比率が高くなっています。もちろんジャンルの違いもあるとは思いますが、ユーザー側の変化も大きいのでは。
ドワンゴ、オーディオブック「ListenGo」(リスンゴ)開始 月額300円から〈ITmedia NEWS(2021年1月8日)〉★
ドワンゴがオーディオブック配信サービスへ参入。月額コースへ入会することにより付与されるポイントを使って購入する方式です。コンテンツは、オトバンクやピコハウスのほか、KADOKAWA、小学館、双葉社などの出版社から提供されているとのこと。音声コンテンツ市場も、引き続き要注目ですぞ。
『週刊文春』『ナンバー』など文藝春秋のデジタル化の加速ぶりは要注目だ(篠田博之)〈Yahoo!ニュース個人(2021年1月9日)〉★
月刊「創」毎年恒例の出版業界特集から、文藝春秋のデジタルサービスについてのレポートが公開されています。月間4億PVを突破した「文春オンライン」のことはもちろん、月間5200万PV突破の「Number Web」や、週刊文春電子版の記事バラ売りでの売上詳細とか、「電子書籍の売り上げは大幅に伸びました」など、文藝春秋のデジタルシフトが順調である様子が伺えます。
中国の若者文化を育んだ日本の漫画・アニメ――中国動漫産業の実態と動向(前編)〈HON.jp News Blog(2021年1月7日)〉★
オリジナル作品のIPビジネス展開に乗り出す中国動漫――中国動漫産業の実態と動向(後編)〈HON.jp News Blog(2021年1月8日)〉
北京大学・馬場公彦さんによる、中国動漫産業の歴史や動向についてのレポート前後編。「動漫」は動画と漫画の複成語で、どちらも日本文化の影響を強く受けているそうです。「快看漫画」ってなんか見覚えあるなと思ったら、2019年にエブリスタと双葉社の共同出資会社と戦略的提携を結んでいました(↓)。縦スクロール・フルカラーのウェブトゥーン。Googleレンズで翻訳すれば、なんとか読めます。
2020 has been surprisingly good for the publishing industry〈Good e-Reader(2021年1月6日)〉
パンデミック下のアメリカでも、電子版はもちろん、紙版の売上も伸びているというニュース。紙が8%増加、電子が16%増、オーディオブックが17%増だったそうです。“Reading books proved to be the best thing to do while remaining shut indoors.(本を読むことは、屋内に閉じたままで行うのが最善であることが証明されました)” というコメントがあり、アメリカでも「巣ごもり需要」と解釈されているようです。
33% Growth for Digital Books from Public Libraries and Schools in 2020 Sets Records〈OverDrive(2021年1月7日)〉
OverDrive社のプレスリリース。電子図書館サービスも前年比33%増だったとのこと。強い追い風が吹いています。結果論ですが、楽天はこうなる直前に手放したということに……。
技術
【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】Chromebookは電子書籍に使えるか? レノボの2in1「IdeaPad Duet Chromebook」で検証〈PC Watch(2020年12月30日)〉
キーボードやスタンドカバーを取り外して、タブレットとしても利用できる2in1スタイルの Chromebook。Androidタブレットは選択肢の幅が狭いので、こういうのもアリですね。「BOOK☆WALKER」アプリが非対応なのが若干痛い(ブラウザビューアで観られますけど)。
2021年、インターネットとITは大きな転換期へ イノベーションから規制、倫理の時代に 〜Google、Facebookへの大型訴訟が示すもの〜〈INTERNET Watch(2021年1月2日)〉★
ITジャーナリスト星暁雄さんによる、GoogleとFacebookに対する規制の動きについての解説。「イノベーションを追求する段階から、あるべき社会を議論する段階へ」という中見出しが、いま世の中が目指している方向性を短く・鋭く表していると思います。
検索エンジンを経由した海賊版サイトへのアクセスが激減している〈GIGAZINE(2021年1月5日)〉
Google検索の「コアアップデート」によるものと推測されているそうです。アルゴリズムの勝利。本文中に「およそ3分の1に減少」とありますが、出典元には“dropped by roughly a third.”とあるので「約3分の1減少」が正と思われます。
ブロードキャスティング
毎週日曜日21時から配信しているライブ映像番組、1月10日のゲストはゲームデザイナーの山崎剛さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本について掘り下げています。番組のアーカイブはこちら。
1月17日のゲストは、海猫沢めろんさん(文筆業)です。
1月24日のゲストは、牧村朝子さん(文筆家)です。
配信終了後はZoom交流会もあります。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。