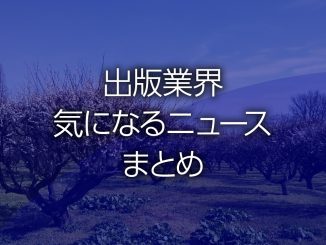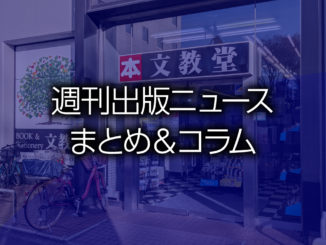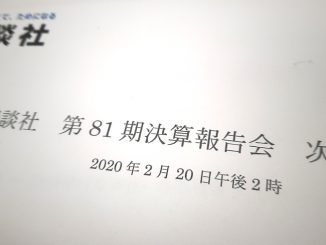《この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です(1分600字計算)》
特集≫コラムの国内を扱った記事から、2020年に多く読まれた記事をピックアップしました。10位から1位までのカウントダウン形式でご紹介します。
10位
講談社がこれから“紙”回復に期待する理由 ~ 電子版プロモーションで得た価格施策ノウハウを紙にも
出版ジャーナリストの成相裕幸氏に、講談社の決算発表会を取材して感じたことをコラムとして寄稿いただきました。
9位
著作権の保護と制限の規定がもうすぐ変わる ~ 保護期間延長、非親告罪化、柔軟な権利制限、教育の情報化対応など、まとめて解説
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。
8位
「図書館の本、スマホで閲覧可能に」とは? ―― 図書館等での権利制限規定のデジタル化・ネットワーク化への対応が検討中
コロナ禍による図書館休館問題を受け、文化庁はいま著作権法第31条 図書館等での権利制限規定を見直す検討を進めています。「図書館の本、スマホで閲覧可能に」という報道に喜ぶ声や、出版関係者が「民業圧迫だ」と反発している報道もあります。実際のところ、いまどのような制度になっていて、どのように改正されようとしているのでしょうか?
7位
“いまだけ無料”の先にあるもの ~ 社会貢献とマーケティングの狭間
いわゆる「コロナ休校」対応で、書籍・雑誌を“いまだけ無料”にする事例が続出しています。ユーザーからは感謝の声も多いですが、提供側はそろそろ少し先のことも考えておきたいところ。フリージャーナリストの西田宗千佳さんに、そんなコラムを寄稿いただきました。
6位
実効性のない法律に意味はあるのか?「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」レポートと考察
2月8日に参議院議員会館で開催された「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」では、マンガ家の竹宮惠子氏や赤松健氏など、本来は著作権法で権利を守られる立場であるクリエイター側から、このような疑問や反対の声が上がりました。本稿ではこの集会のレポートを交えながら、いまどのような改正が行われようとしているのか、どのような影響が考えられるのかを考察しました。
5位
司書教諭が図書室という場を失って取り組んだこと ~ 学校図書館の存在意義とデジタルトランスフォーメーション(DX)
新型コロナウイルス感染拡大を受け、全国の小中高校などが臨時休校となった。そんな中でも「学びを止めない」ため、学校図書館はどのような取り組みを行っているか? また、そこにはどのような問題があるのか? 司書教諭の有山裕美子氏(工学院大学附属中学校・高等学校)に寄稿いただきました。短期集中連載の前編です。
4位
【更新】図書館閉鎖が校正・校閲の大きな障害に ~ 新型コロナ感染症対策の思わぬ影響
新型コロナウイルス感染拡大を受け、多くの図書館が休館になりました。出版の仕事はリモートでできることも多いですが、情報の品質を担保する校正・校閲に大きな支障があることに気がつきました。
3位
生徒向けの使えるリンク集が「学校図書館の自殺行為」と言われた ~ 学校図書館の存在意義とデジタルトランスフォーメーション(DX)
学校図書館は、紙の本を貸出したり本を紹介するだけの場所ではないと、司書教諭の有山裕美子氏(工学院大学附属中学校・高等学校)は訴えます。では学校図書館には、どのような役割があるのでしょうか? 短期集中連載の中編です。後編はこちら。
2位
侵害コンテンツのダウンロード違法範囲拡大は、どういう目的で導入されようとし、どういう制度になろうとしているのか?
共同通信や産経新聞などによると、自民党文部科学部会などの合同会議が2月25日に開催され、海賊版対策の「ダウンロード規制法案」を了承したそうです。本稿では、そもそもこの「ダウンロード規制」はどういう目的で導入されようとしているのか? 現行はどういう制度なのか? それがどう変わろうとしているのか? などについて、改めて、なるべくかみ砕いて解説しました。
1位
遠隔授業を阻む著作権の問題をクリアにする「授業目的公衆送信補償金制度」とは?
新型コロナウイルス感染拡大を受け、学校で遠隔授業のニーズが急速に高まりました。その際の障壁とされていた著作権の問題をクリアにすべく、「授業目的公衆送信補償金制度」が前倒し施行される見通しでした。そこで本稿では、この新制度がどのようなものなのか、筆者の理解の範囲で解説しました。