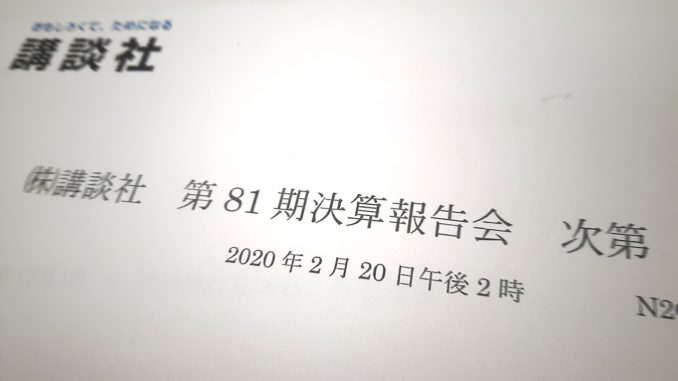
《この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です(1分600字計算)》
出版ジャーナリストの成相裕幸氏に、講談社の決算発表会を取材して感じたことをコラムとして寄稿いただきました。
原価削減と返品減少で利益率改善
2020年2月20日に公表された講談社の第81期決算(2019年11月期)は、後年、出版界のターニングポイントとして語られるかもしれない。各種報道にも出ているが、売上高1358億3500万円で前年比12.7%増、当期純利益は72億3100万円で同152.9%増(約2.5倍)の大幅な増収増益。「21世紀に入ってから最高の数字」(野間省伸社長)となった。
牽引したのは電子書籍・コミック販売を含めた事業収入と海外版権収入だ。広告収入59億2600万円(同18.4%増)、事業収入613億7000万円(同38.5%増)で、うちデジタル関連収入が465億円(同39.2%増)、国内版権81億円(同36.5%増)、海外版権が66億円(同39.5%増)。紙書籍・雑誌の売上が年々減る一方で、近年同社が強化してきたデジタルとライツが収益の大きな柱となっているのは間違いない。
だが、それ以上に筆者が注目したのは、講談社が今後、紙媒体の回復に大きく期待をしている、と見えたことだ。実は、決算説明会の冒頭で、野間社長は次のように語っている。

紙製品、とはあまり聞きなれない言い回しだが、講談社は前期から決算資料では紙の書籍と雑誌の販売数字を「製品」としてまとめた形で公表し、細かい数字は口頭で説明している。前期は書籍が160億3000万円、雑誌が509億円に対して、今期は書籍が159億6000万円で微減、雑誌は483億5000万円と前年比で5%ほど落ち込み。業界のリーディングカンパニーといえども、雑誌不況の大波にはかなり苦戦している。
それを踏まえて先の野間社長の発言を考えると、やや奇異な感じを受けなくもない。だがこの発言を、紙書籍・雑誌の流通、販売を前提にしている書店、取次会社への「配慮」と受け流してしまうのは早計だ。
決算数字を説明した吉富伸享取締役によると「以前より進めてきた企画の厳選、発行部数の適正化にむけた取り組みが原価の削減、返品減少をもたらし利益率改善が大きく貢献した」という。
わかりやすく言い換えれば、「作り過ぎ・刷り過ぎ」に一定の歯止めをかけ、出版企画をこれまでよりもより採算が見込めるものに絞り込み、初版部数もおさえて市場の反応を見ながら小刻みに重版していく体制になりつつある、ということだろう。
紙でも価格施策が試みられている
もう一つ見逃せないのが、各ジャンルですすめた新刊価格の値上げだ。実は、講談社に限らずコミックを刊行する大手出版社は、2018年から定価を数十円程度値上げしている。講談社で言えば、『進撃の巨人』は2017年12月に刊行された24巻は429円(本稿以下すべて税別)、2020年12月に刊行された最新刊30巻は450円。ページ数は変わっていないが、20円ほどの値上げだ。

ほかにも同ジャンルで本体価格は変わらないが、ページ数が3分の2程度になっている例もある。2016年4月刊の『漢字と日本語』(高島俊男)と2020年2月刊の『日本人のための漢字入門』(阿辻哲次)はどちらも880円だが、前者は336ページで後者は224ページ。これは特定タイトルに限った値上げというよりも、新書の「価格帯」そのものが上がっていると考えるべきだろう。
ただし、講談社は単純に定価を高くしたわけではない。ここ数年、意識的に柔軟な価格設定を進めてきた。「出版業界は再販制度のなかで価格施策についてあまり敏感ではなかった」と野間社長が反省を込めて言うように、紙書籍・雑誌は一部を除き書店の判断で値引き販売できないことから、販促の手法が限られてきた。
しかし、近年伸び続ける電子市場のなかで、とくに電子書籍・コミックの期間限定無料や人気シリーズのセット販売が、有効なプロモーションとして効果的であることがわかってきた。そのノウハウを紙媒体に応用し、例えばコミック映像化の際の既刊販促として、単巻購入と異なる価格のセット商品を投入するような事例が出ている。
昨年7月に実写映画化された『アルキメデスの大戦』では、それぞれ630円の1~3巻をセットにした「お買い得パック」を900円で、10月にはアニメ3期が放送される前に『ちはやふる』の1~3巻(各429円)のセットを600円で発売。むろん、単巻で1冊ずつ買うよりも確実に安い商品を投入して、店頭での購入動機を高める狙いがある。出版科学研究所はこの施策について「コンテンツによって差はあるが、増売効果があったようだ」としている。
この価格施策は仕掛けがしやすいコミックが中心だが、野間社長は「(価格を)上げるものは上げる、下げるものは下げる。そのバランスを考えながらやっていく」と語っており、今後、文字もののシリーズ作品にも展開することは十分に考えられる。
ヒットを支えたのは書店店頭での大展開

電子コミックの伸びをみると、店頭で紙コミックを購入する機会は減っていくことはおそらく避けられない。また、講談社のコミック価格施策は、基本的に映像化のタイミングでのプロモーションであり、まだ実験的な段階であろう。
その成果を、通常の新刊発売時や、根強いファンがいるが映像化まではいたらないコミックを売り伸ばすために、どう結びつけるか。さらに、どのように書店店頭と接続するか。まだはっきりとした正解はないが、この価格施策は、落ち込みが続く「紙」回復のヒントになりうるだろう。




