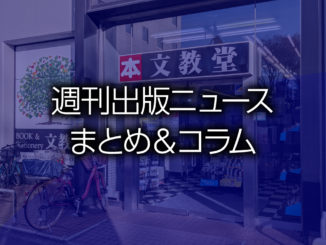《この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です(1分600字計算)》
特集≫コラムの海外を扱った記事から、2020年に多く読まれた記事をピックアップしました。10位から1位までのカウントダウン形式でご紹介します。
10位
過熱する中国の出版界、冷淡な日本の出版界――中国出版界が日本文学に注ぐ熱い視線(後編)
中国における日本文学の翻訳事情について、北京大学・馬場公彦さんによるレポート後編をお届けします。前編はこちら。
9位
アメリカの書籍出版産業2020:これまでの10年と、これからの10年について(2)~ 大きくなって交渉力をつけるか、小さくやってニッチを突くか/アメリカ出版業界の海賊版対策
大原ケイさんに、アメリカの書籍出版産業の過去10年と、これからの10年について解説いただきました。第2回は、「大きくなって交渉力をつけるか、小さくやってニッチを突くか」と「アメリカ出版業界の海賊版対策」です。
8位
アメリカの書籍出版産業2020:これまでの10年と、これからの10年について(4)~ 出版社のこれからの10年を握るカギはやっぱりアマゾン/書店の二極化:大手チェーンとインディペンデント書店
大原ケイさんに、アメリカの書籍出版産業の過去10年と、これからの10年について解説いただきました。第4回は、「出版社のこれからの10年を握るカギはやっぱりアマゾン」と「書店の二極化:大手チェーンとインディペンデント書店」です。
7位
アメリカの書籍出版産業2020:これまでの10年と、これからの10年について(5)~ インディペンデント書店はなぜリバイバルできたのか?
大原ケイさんに、アメリカの書籍出版産業の過去10年と、これからの10年について解説いただきました。第5回は、「インディペンデント書店はなぜリバイバルできたのか?」です。
6位
中国出版業界・書店業界はコロナ禍にどう立ち向かったか
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていた中国では、出版業界や書店業界はどのような取り組みが行われていたのでしょうか? 馬場公彦さんによる中国出版事情解説です。
5位
全米図書賞の翻訳部門を受賞した柳美里『JR上野駅公園口』の功労者は誰か
2020年全米図書賞(National Book Awards 2020)の翻訳部門に柳美里『JR上野駅公園口』(Tokyo Ueno Station)が選ばれました。近年、日本の女性作家作品が海外で評価されることが多くなっているように感じますが、これは日本の女性作家に限った話では「ない」そうです。おなじみ、大原ケイさんによる解説です。
4位
アメリカの図書館はコロナ禍にどう立ち向かっているか?
アメリカの図書館は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、どのような対応を行っているのでしょうか? 大原ケイさんによる解説です。
3位
アメリカの人種差別問題は出版界をも変えつつある
白人警官が黒人男性を殺害する事件が起き、ハッシュタグ #Blacklivesmatter とともに抗議活動が始まりました。これを受け、アメリカの出版はどう変わろうとしているのでしょうか? 大原ケイさんによる解説です。
2位
アメリカの書籍出版産業2020:これまでの10年と、これからの10年について(1)~ Eブックで起こったディスラプション/米司法省対アップルと大手出版5社の談合の結末
大原ケイさんに、アメリカの書籍出版産業の過去10年と、これからの10年について解説いただきました。第1回は、「Eブックで起こったディスラプション」と「米司法省対アップルと大手出版5社の談合の結末」です。
1位
共感を呼び称賛された『武漢日記』が一転、海外版の翻訳出版で批判と中傷に晒されたわけ
出版社を定年退職したのち北京大学で教鞭を執る馬場公彦氏に、中文圏の出版事情についてコラムを連載いただくことになりました。1回目は、新型コロナウイルス感染症のため都市封鎖された中華人民共和国湖北省の武漢市の様子を綴った『武漢日記』出版をめぐる騒動についてです。