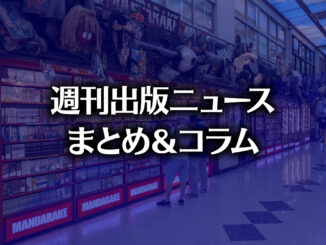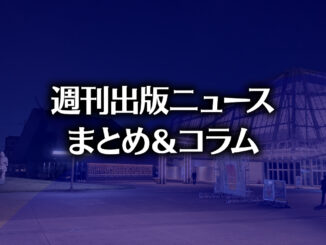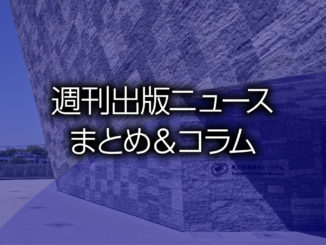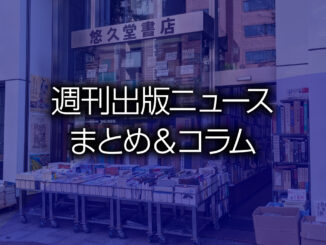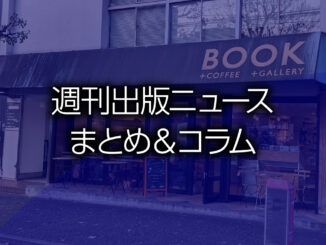《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2020年12月6日~12日は「文藝春秋とnoteが資本業務提携」「ジャンプルーキー!でインディーズ連載枠新設」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- 入場料払う書店「文喫」岩田屋本店に2021年3月開店〈西日本新聞(2020年12月7日)〉
- DX推進でKADOKAWAはいかに変わったか KADOKAWA Connected・各務茂雄社長インタビュー〈文化通信デジタル(2020年12月7日)〉
- ShoProがマーベル・コミックスと翻訳出版独占契約、日本で電子配信もスタート〈アニメーションビジネス・ジャーナル(2020年12月8日)〉
- ネット取引、出品者開示を義務化 新法案、消費者保護へ〈共同通信(2020年12月8日)〉
- 文藝春秋とnoteが資本業務提携、老舗出版社にもDXへの危機感〈日経クロステック(2020年12月10日)〉★
- 電子書籍ブーム、今回は本物? 新常態、隙間時間にまとめ読み〈日本経済新聞(2020年12月10日)〉
- 週1時間以上マンガを読む人は2割台。それでもSNS広告で見たいのは「マンガ」が強かった【トレンド ・プロ調べ】〈Web担当者Forum(2020年12月10日)〉
- 資格スクエアが出版社らと和解 予備試験テキストの著作権侵害〈弁護士ドットコムニュース(2020年12月10日)〉
- ジャンプ+:インディーズ連載枠新設 個人で自由に連載 原稿料も〈MANTANWEB(2020年12月10日)〉★
- Android版「CLIP STUDIO PAINT」が登場。Chromebookもサポート〈PC Watch(2020年12月10日)〉
- 「総額表示を考える出版事業者の会」 消費税法改正を提言、現状維持を求め180事業者が賛同〈文化通信デジタル(2020年12月11日)〉
- ビジネス特集 ビジネス書 コロナ禍で注目のワケとは?〈NHKニュース(2020年12月11日)〉
- 村上春樹氏の小説8作が電子書籍化 『海辺のカフカ』『1Q84』『騎士団長殺し』など〈ORICON NEWS(2020年12月11日)〉
- 今年は100誌以上の雑誌が休刊 コロナ不況の追い討ちで歯止めがかからない雑誌不況〈SEVENTIE TWO(2020年12月11日)〉★
- 「フィクションってことにしませんか」で炎上 プラットフォームメディア「cakes」 編集姿勢に批判〈毎日新聞(2020年12月12日)〉★
- 海外
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
入場料払う書店「文喫」岩田屋本店に2021年3月開店〈西日本新聞(2020年12月7日)〉
日販グループのリブロプラスが2018年に始めた「文喫」が、福岡天神に2号店を展開するというニュース。入り口付近はともかく、奥へ行くには入場料が必要ということで、人通りの多い東京・六本木ならではの業態だと思っていたのですが、他の地域でも成り立つのかどうか。なお、この11月に閉店した書店「リブロ福岡天神店」の区画に入るそうです。実質、リニューアルオープン?
DX推進でKADOKAWAはいかに変わったか KADOKAWA Connected・各務茂雄社長インタビュー〈文化通信デジタル(2020年12月7日)〉
ドワンゴの改革後、KADOKAWAのDXに取り組んでいる方へのインタビュー。「最初のミーティングで紙の資料がカラーコピーで30ページほど配られたことに衝撃を受け」たというのは、なかなか象徴的。ただ、これが出版業界に限った話なのかというと……どうなんでしょうね? 部署によってやり方が違っていて、なかなか業務が標準化できないというのも、あるあるだなあ、と。だからといってもちろん、この取り組みの価値が下がるわけではありませんが。勤め人時代、部署横断の顧客管理と経理システム統合プロジェクトが頓挫して、巻き添えで大変な思いをした記憶が蘇りました。
ShoProがマーベル・コミックスと翻訳出版独占契約、日本で電子配信もスタート〈アニメーションビジネス・ジャーナル(2020年12月8日)〉
2021年1月の新規契約分から、マーベルのアメコミ邦訳版はすべて小学館集英社プロダクションの「ShoPro Books」での刊行になるとのこと。同時に、電子版の配信も始まるのが大きな変化。スパイダーマン、バットマン、アイアンマン、X-MENなど、アメコミの翻訳版ってこれまでほとんど電子版未配信だったんですね。
なお、これまでマーベルの翻訳コミックスを出版してきたヴィレッジブックスによると、現時点で出版権を保有している未刊行タイトルは来年以降も引き続き刊行、既刊は契約期限が切れたものから書店在庫分のみとなるそうです(↓)。
ネット取引、出品者開示を義務化 新法案、消費者保護へ〈共同通信(2020年12月8日)〉
消費者庁が1年がかりで進めてきた「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」の、報告書作成に向けた議論が12月24日に行われます。記事に「8日、分かった」とある新法案の骨子はまだ公開されていないようですが、8月24日時点の「論点整理」でおおよそは把握できます(↓)。
記事に書かれていること以外に、「消費者の信頼を損なうレビュー」「ターゲティング広告」「複雑・膨大で専門的な利用規約」なども問題視されており、出版関係者も無縁ではいられない規制になりそうです。議論の行方が気になるんですけど、この検討会は原則非公開議論とのこと。ぐぬぬ。
文藝春秋とnoteが資本業務提携、老舗出版社にもDXへの危機感〈日経クロステック(2020年12月10日)〉★
両社からのリリースとほぼ同時に、詳報が。noteには日経も2018年に資本を入れている(↓)ので、そりゃ事前に知ってただろうな、とは思うのですけど。記事の無料で読める部分に関係性の情報開示がないのは、正直どうかと思うのです。
業務提携内容の3つ目として挙げられている、文藝春秋側はデジタル技術や知識、note側は編集技術を習得、というのがどうしても目に留まります。折しも「cakes」の炎上案件が連発しているさなか、タイミングが良いのか悪いのか。
電子書籍ブーム、今回は本物? 新常態、隙間時間にまとめ読み〈日本経済新聞(2020年12月10日)〉
スマートニュース藤村厚夫氏による連載コラム。いまの電子市場拡大は「ブーム」(一時的に盛んになるという意味)なのでしょうかか。「失速を繰り返してきた」とは言うけど、過去に電子市場が縮小したのは2011年のみです(インプレス「電子書籍ビジネス調査報告書」より)。まあ、細かなところですが、ツッコミを入れずにはいられなかった……。
週1時間以上マンガを読む人は2割台。それでもSNS広告で見たいのは「マンガ」が強かった【トレンド ・プロ調べ】〈Web担当者Forum(2020年12月10日)〉
一般的なマンガを読む時間が「週1時間未満」で76%って、世の中の人はそんなに読んでないのか? というのが、正直な印象でした。慌てて他社の調査レポートをいくつかチェックしてみたのですけど、週に何時間読んでいるか? という調査が見つからず。利用の有無や頻度、1回あたりの利用時間までは見つかったんですが。「それでもSNS広告で見たいのはマンガ」については、正直、手前味噌感は拭えない。広告マンガ制作企業によるリサーチだし。
資格スクエアが出版社らと和解 予備試験テキストの著作権侵害〈弁護士ドットコムニュース(2020年12月10日)〉
司法試験などのオンライン学習サービス「資格スクエア」が、日本評論社、岩波書店、有斐閣などの出版物を不正利用していた事件。すべての著作者、出版社との和解が成立したとのことです。法律を教えるサービスが著作権侵害、というのはシャレにならない。ところが日本評論社のリリース(↓)末尾には「現時点でも未だに著作権意識が低い機関や指導者、関係者等が存在するようでしたら、この機会に認識を改め、著作権意識の向上を図っていくきっかけとして頂ければと考えております。」とあり。なんというか、31条や35条関係で神経質になるのも無理はない、くらいの事情があるのだなと思いました。
ジャンプ+:インディーズ連載枠新設 個人で自由に連載 原稿料も〈MANTANWEB(2020年12月10日)〉★
集英社「ジャンプルーキー!」の新展開。編集者のネームチェックを経ず、自由に連載できる枠の提供開始です。その権利は「連載争奪ランキング」で勝ち取れ! という、シンプルだけどシビアなもの。編集部員が担当に付かないやり方はある意味、『バクマン。』に代表される「編集者不要論」に則っているとも言えるでしょう。同じ出版社系投稿サイトでも、講談社「DAYS NEO」とは真逆の方向性。あえてそういうチャレンジをやってくるとは、面白い。詳細はこちら(↓)。
Android版「CLIP STUDIO PAINT」が登場。Chromebookもサポート〈PC Watch(2020年12月10日)〉
これで主要なプラットフォームを網羅。Chromebookもサポートというのは、さすがだなあという印象です。Chromebookで動かないAndroidアプリ、意外と多いんですよね。GIGAスクール構想で予算がついて、安価だけどキーボードが付いているChromebookが選ばれるケースも多いようなので、他社も見習って欲しいところです。
「総額表示を考える出版事業者の会」 消費税法改正を提言、現状維持を求め180事業者が賛同〈文化通信デジタル(2020年12月11日)〉
総額表示再義務化に対する業界側の動きについて、最初に火を付けるきっかけとなった文化通信から改めて。総額表示を考える出版事業者の会の提言は1カ月前に公開されたものですが、12月8日にプレスリリースが流れており(私も受け取った)、それを受けての記事と思われます。
記事内の記述「総額表示義務の違反について、消費税法上の罰則はない」のは確かですが、景品表示法における有利誤認とみなされる可能性はある(↓)点にも触れたほうが良いのでは。
ビジネス特集 ビジネス書 コロナ禍で注目のワケとは?〈NHKニュース(2020年12月11日)〉
コロナ禍で、ビジネス書が売れているそうです。先行き不透明な中、道しるべが欲しい、ということなのでしょうか。Twitterなどでは「鬼滅しか売れてない」みたいな言説も観測されてますが、んなこたない、ということでピックアップ。
村上春樹氏の小説8作が電子書籍化 『海辺のカフカ』『1Q84』『騎士団長殺し』など〈ORICON NEWS(2020年12月11日)〉
年の瀬に大物が。今年は春の緊急事態宣言のころから、東野圭吾氏、森絵都氏、百田尚樹氏など、これまで作品の電子化に慎重だった作家の作品がついに配信開始、という事例が目に付きました。自ら出版社に提案して、電子版に踏み切っているケースも増えているとか。文芸も潮目が変わった感があります。
今年は100誌以上の雑誌が休刊 コロナ不況の追い討ちで歯止めがかからない雑誌不況〈SEVENTIE TWO(2020年12月11日)〉★
まさに追い討ち。弱り目に祟り目。それにしても100誌以上とは。出版月報に毎月載っている「休刊誌」を数えてみたところ、12月5誌、1月6誌、2月8誌、3月10誌、4月17誌、5月8誌、6月4誌、7月11誌、8月8誌、9月3誌、10月9誌という推移でした。感染拡大第三波が来ているこの11月12月は、果たしてどうなるか。
「フィクションってことにしませんか」で炎上 プラットフォームメディア「cakes」 編集姿勢に批判〈毎日新聞(2020年12月12日)〉★
とうとう全国紙でニュースに。10月のDV相談、11月のホームレスに続き、連載消滅での炎上が連続で発生しています。そういうタイミングで、前述の文藝春秋との資本業務提携が発表された、と。そりゃ「(文藝春秋から)編集技術を習得する」というのが、業務提携内容の1つに入るわけです。
2012年に「cakes」が始まった当時、私は「これは面白そうだ」とブログを書いていました(↓)。あらためて読み返してみたのですが、『もしドラ』担当編集者だった加藤貞顕氏がCEOということで、「著者が提供するコンテンツをただ垂れ流すのではなく、プロの編集者として内容に関与することで高い質を保ってくれるのではないか?」と、とくに編集機能に強い期待を寄せていたことを思い出しました。残念ながら、そうはならなかったわけですが。
実際のところ、後から始めた「note」が急激に成長したことにより、「cakes」の立ち位置が歪な状態になってしまったのかな? という気がします。以前「cakes」で連載していた岡田育氏からの、「オーサーシェア機能がカイゼンされないまま放置されてる」という暴露(↓)を見て、頭を抱えてしまいました。あーうー。
海外
近代の名作小説、現代の流行小説を網羅――中国出版界が日本文学に注ぐ熱い視線(前編)〈HON.jp News Blog(2020年12月7日)〉★
過熱する中国の出版界、冷淡な日本の出版界――中国出版界が日本文学に注ぐ熱い視線(後編)〈HON.jp News Blog(2020年12月8日)〉
おなじみ、北京大学・馬場公彦氏のコラムです。前編後編ともに、よく読まれています。輸出超過で輸入が少ないのは中国に限った話ではないようですが、そういう状況を当事者以外にも知ってもらう、関心を持ってもらうことも重要なのではないかな、と思います。
なお、中国の著作権保護期間は死後50年間なので、三島由紀夫は中国では来年からパブリックドメインであること。そして、海賊版対策で来年から懲罰的賠償制度などが盛り込まれた改正著作権法が施行されること。この2点を編注で入れたのですが、もう1つ「SF小説の騎手 劉慈欽」のところに『三体』の著者である旨を入れておけば良かった……と反省。著者名だけだと、わからない人も多いですよね。
FBの一部事業の売却要求も 米当局、GAFA包囲網〈共同通信(2020年12月9日)〉
グーグルに続いて、フェイスブックも提訴。「Instagram」と「WhatsApp」の売却が要求されているとのこと。買収した上で潰すような他社の事例も多い中、「Instagram」に関しては「Facebook」と連携したことによって更に伸びた、という印象があるのですけど、どうなんでしょう? 「WhatsApp」は使ってないのでわかりませんが。
アップルの新プライバシー強化機能、受け入れないアプリは排除へ=幹部〈ロイター(2020年12月9日)〉
導入が延長されてきた、トラッキングをユーザーがブロックできるようになる新機能について。フェイスブックなどが反発しています。しかし、「デジタル広告会社は大半のユーザーがそうしたトラッキングを許可しないと予想している」というのは、嫌われている自覚があるわけですよね。まあ、似たような広告が延々追いかけてくる体験は、「うっとうしいわ!」と言いたくなることも多いので、ユーザーに選択肢を委ねるというのは正しい方向性に思えます。
仏当局、クッキー利用巡りグーグルに1億ユーロの制裁金〈ロイター(2020年12月10日)〉
巨大IT企業を巡る各国の動きの1つ。グーグルだけでなく、アマゾンにも3500万ユーロの制裁金を科しています。他にもいくつか「これから規制する予定」という記事がありましたが、ひとまず今週はこれくらいに留めておきます。多すぎる。
ブロードキャスティング
12月13日のゲストはゲーム作家の米光一成さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本について掘り下げました。番組アーカイブはこちら。
次回のゲストは、人狼伝道師の眞形隆之さんです。ZoomではYouTubeへのライブ配信終了後、オンライン交流会を開催します。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。