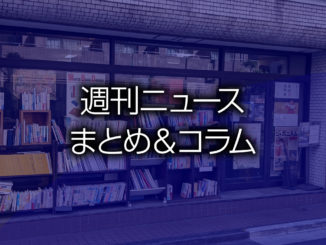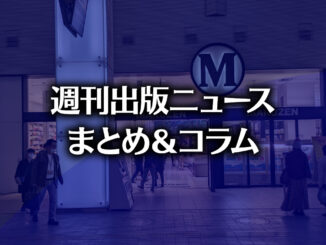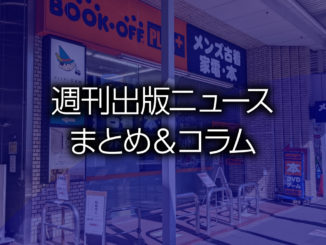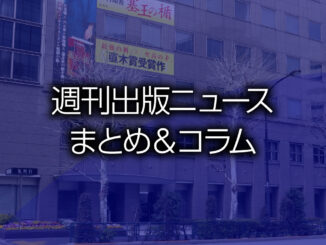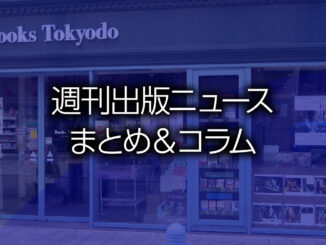《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2020年10月18日~24日は「映画・鬼滅の刃も大ヒット」「米司法省、グーグルを独禁法違反で訴追」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- 図書館 家庭配信へ始動 文化庁、著作権改正へ議論〈日本経済新聞(2020年10月18日)〉★
- あの「まんが王国」が老舗出版社を買収した必然〈東洋経済オンライン(2020年10月18日)〉★
- 一般社団法人ABJ、設立後初の臨時社員総会を開催〈株式会社メディアドゥ(2020年10月20日)〉
- 求人サイトに「パクリ記事」大量掲載 誤字まで同じ、怒る権利者…運営会社「管理側が気づかなかった」〈J-CASTニュース(2020年10月21日)〉
- Adobe、ストック素材7万点を無料で公開 商用利用も可〈ITmedia NEWS(2020年10月21日)〉
- Adobe、「Creative Cloud」の大規模アップデートを発表 ~“Adobe MAX 2020”〈窓の杜(2020年10月22日)〉
- “海賊版サイト”への対応 要請 出版社の団体や超党派議連など〈NHKニュース(2020年10月22日)〉
- Chromebookのシェアが1%から13%に急増。2021年には24%へ〈PC Watch(2020年10月22日)〉
- Gaudiyが少年ジャンプ「約束のネバーランド」向けにブロックチェーン活用公式コミュニティ提供〈TechCrunch Japan(2020年10月22日)〉
- 空前の『鬼滅の刃』現象 映画興行は「なりふりかまわない」新基準へ〈Real Sound(2020年10月22日)〉★
- 映画「鬼滅」の熱狂に見たアニメの新しい稼ぎ方〈東洋経済オンライン(2020年10月23日)〉
- 環境省、著作権法に触れる対応 許諾得ず新聞記事を職員にメール〈共同通信(2020年10月23日)〉
- 『カイジ』を担当したベテラン編集者が語る、編集の極意。ゲームの話を聞きに行ったら、講談社111年の歴史に触れることになった〈電ファミニコゲーマー(2020年10月23日)〉★
- 電子書籍リーダーとタブレット型端末の所有・利用状況をさぐる(2020年公開版)(不破雷蔵)〈Yahoo!ニュース個人(2020年10月23日)〉★
- 「触れない」立ち読みが人気 売れ行き「2割増」〈産経フォト(2020年10月24日)〉
- 海外
- 中国共産党が重視し普及したいテーマを刊行 ―― 中国出版界の主要ジャンル「主題出版」(前編)〈HON.jp News Blog(2020年10月20日)〉
- 国営出版社がしのぎを削る主戦場 ―― 中国出版界の主要ジャンル「主題出版」(後編)〈HON.jp News Blog(2020年10月21日)〉
- 米司法省がGoogle提訴 独禁法違反「検索で競争阻害」 (写真=ロイター)〈日本経済新聞(2020年10月21日)〉
- 米司法省がグーグルを独禁法違反で訴追、その訴状内容と判決の見通しは?〈HON.jp News Blog(2020年10月24日)〉
- 「Facebookの更新は、広告プラットフォームを破壊した」:あるメディアバイヤーの告白〈DIGIDAY[日本版](2020年10月22日)〉
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
図書館 家庭配信へ始動 文化庁、著作権改正へ議論〈日本経済新聞(2020年10月18日)〉★
文化審議会著作権分科会の図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームで、これまで3回議論された内容の概略です。ワーキングチームでの議論は私もずっと追っていて(#437まとめ、#439まとめ、#442まとめなどを参照)、本稿を配信する10月26日には第4回が開催されます。オンラインで聴講予定。13時ごろに、下記URLで資料が公開されるはずです。
この記事は結構丁寧に議論の状況を追っていて良いと思うのですが、反響を見ていると、前提になっている制度への世の中の理解が圧倒的に不足している感があります。国立国会図書館デジタルコレクションでは、著作権切れの図書だけですでに約35万点が一般公開され誰でも閲覧可能になっているわけですが、認知度はまだまだ低いということでしょう。『エロエロ草紙』が話題になったのが2012年、文化庁eBooksプロジェクトが2013年。当時私も何本か関連記事を書いてますが(↓など)、いま改めて、再認知のための掘り起こしが必要かもしれません。
なお、ワーキングチームで検討されてることのうち、「図書館送信」の対象となる「入手困難資料(絶版等資料の言い替え)」は、シンプルに考えると判断の要点は市場で入手可能かどうかのみ。古書市場は諸外国同様、考慮しないという結論が出ています。出版社の立場から考えると、通常の紙の取次書店流通とは別に、POD版または電子版を出しておけば「入手困難資料」にはなりません。電子版で復刻すれば、図書館送信の対象からは除外されます。これは、電子化率向上への強い圧となるでしょう。
あの「まんが王国」が老舗出版社を買収した必然〈東洋経済オンライン(2020年10月18日)〉★
ぶんか社グループを「まんが王国」のビーグリーが買収した件について、詳細な解説。今回の件で「口火が切られた」というのはちょっと言い過ぎ感もありますが、電子書店&アプリのプレイヤーが新規IPを創出し、差別化を図ろうとする流れはどんどん進むでしょう。そして、自社配信だけだと旨味が少ないことに気付き、いずれ他店へのディストリビューションも始めることに。
一般社団法人ABJ、設立後初の臨時社員総会を開催〈株式会社メディアドゥ(2020年10月20日)〉
ABJは、ネット上の海賊版対策の中核として、KADOKAWA、講談社、集英社、小学館、メディアドゥ、日本漫画家協会の設立時社員6名によって7月1日に設立されたばかりの一般社団法人。設立後初の臨時設立社員総会が開催され、2020年度(半期)活動計画案と予算案が承認されたという報告がリリースされました。社員47法人、賛助団体8法人。代表理事にはメディアドゥ取締役副社長COO 新名新氏が就任しています。
2018年に始まったABJマークは、デジタルコミック協議会と日本電子書籍出版社協会が設立した「正規版マーク事業組合」が制定し、電子出版制作・流通協議会(電流協)に委託・運営されていました(当時の記事↓)。
ABJ公式サイトの事業概要(↓)には、1番目にこのABJマークの付与事業が挙げられています。ただ、交付に関する事務作業は、今後も電流協が担うことになるそうです。ホワイトリストを見る限りいまだ未参加の、アマゾン、アップル、グーグルをどう引き込むかは、今後も課題になりそうです。
求人サイトに「パクリ記事」大量掲載 誤字まで同じ、怒る権利者…運営会社「管理側が気づかなかった」〈J-CASTニュース(2020年10月21日)〉
DeNA「WELQ」「MERY」など無断コピペ量産型メディア(キュレーションサイト)が大炎上したのはまだ記憶に新しい、のですが、あれからもう4年も経っているのですね。時が経つのは早い。とはいえ、いくら「経験の浅い社員が対応した」といっても、同じようなことが繰り返されてしまうというのは情けない。
Adobe、ストック素材7万点を無料で公開 商用利用も可〈ITmedia NEWS(2020年10月21日)〉
HON.jp News Blogでもアイキャッチ画像の選定にはいつもそれなりに苦労しているので、選択肢が増えるのはとても助かります。ありがたやありがたや。
Adobe、「Creative Cloud」の大規模アップデートを発表 ~“Adobe MAX 2020”〈窓の杜(2020年10月22日)〉
Adobe CCの大規模アップデート。「Photoshop」がAIプラットフォーム「Adobe Sensei」を活用した新機能でかなりパワーアップしたこと、「Illustrator」にiPad版が追加されたこと、「Premiere Pro」に自動テキスト書き起こし機能が追加されたことなどが気になります。
“海賊版サイト”への対応 要請 出版社の団体や超党派議連など〈NHKニュース(2020年10月22日)〉
海外のサーバーを利用して日本人向けに提供される海賊版サイトは、国内だけでは対応できないため、政府に外交チャンネルを使った対応をして欲しい、という要請です。赤松健さんによると、日本漫画家協会、出版広報センター(出版9団体)のほか、コミケ準備会とコミティア代表も同行しているそうです(↓)。
“海賊版サイト”への対応 要請 出版社の団体や超党派議連など | NHKニュース https://t.co/uqVP682Wlk
★本日、私(日本漫画家協会)も提言書提出に同行しました。出版広報センター(出版9団体)・コミケ準備会・コミティア代表も。この4団体が揃って首相官邸へというのは、一昔前では考えられない。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) October 22, 2020
Chromebookのシェアが1%から13%に急増。2021年には24%へ〈PC Watch(2020年10月22日)〉
MM総研のレポート。文科省「GIGAスクール構想」の影響で、Chromebookの出荷台数が急速に伸びているそうです。まあ予想通り。iPadも伸びています。スマホ以外のパーソナルデバイスの勢力図が変わってきそう。詳細はリリース(↓)にて。
Gaudiyが少年ジャンプ「約束のネバーランド」向けにブロックチェーン活用公式コミュニティ提供〈TechCrunch Japan(2020年10月22日)〉
少年ジャンプ『約束のネバーランド』公式ファンコミュニティ「みんなのネバーランド」(↓)に、Gaudiyが新たに開発したブロックチェーン基盤の顧客ID管理システム「Gaudiy-DIDシステム」を提供した、というニュース。
個人情報を企業ではなくユーザー自身が管理したうえで、アニメ・マンガ・ゲーム・映画などクロスメディア展開での連携をコストを抑えて行える、ということのようですが、正直わかりづらい。同社が開発者にインタビューしたnote(↓)によると、AWS KMS(Key Management Service)を活用してウォレットの秘密鍵を保有しない仕組みになっており、改正資金決済法の規制には該当しないため、暗号資産交換業者の登録を必要としないのだとか。ううむ、ちょっと理解が追いつかない。
なお、#432まとめでもピックアップしましたが、Gaudiyは7月に「GANMA!」のコミックスマートと提携し、イーサリアム基盤の「データ所有型」電子書籍事業の展開を発表したばかりですが(↓)、これは本件とは別の枠組みのようです。
空前の『鬼滅の刃』現象 映画興行は「なりふりかまわない」新基準へ〈Real Sound(2020年10月22日)〉★
映画「鬼滅」の熱狂に見たアニメの新しい稼ぎ方〈東洋経済オンライン(2020年10月23日)〉
映画も爆発的ヒット。さまざまな切り口の分析がいくつも出ていますが、本稿ではこの2本をピックアップ。東洋経済のほうは、鬼滅アニメ化企画の発起人で、劇場版プロデューサーのアニプレックス高橋祐馬氏へのインタビュー。副題に「裏側を語り尽くした」とあるとおり、舞台裏を当事者が語っています。それに対しReal Soundのほうは、シネコンの異常なスクリーン割りについての考察。作品の力はもちろんだけど、コロナ禍で他の新作公開が止まっている影響や、興行側の配給側への不信感から来るものではないか、と。裏側のさらに奥、という感じ。
環境省、著作権法に触れる対応 許諾得ず新聞記事を職員にメール〈共同通信(2020年10月23日)〉
記事を一定数コピーできる契約(ELNETでしょうか)を結んでいたのに、それとは別に、記事の切り抜きをPDFにしてメール回覧してしまったとのこと。著作権法第30条(私的複製)の権利制限は、職場での共有には適用されないので注意が必要です。コピーして回覧とか、ついやりがち。公益社団法人日本複製権センター(JRRC)に管理委託されている著作物なら、まとめて権利処理できます。
『カイジ』を担当したベテラン編集者が語る、編集の極意。ゲームの話を聞きに行ったら、講談社111年の歴史に触れることになった〈電ファミニコゲーマー(2020年10月23日)〉★
インディーゲームを支援する「講談社ゲームクリエイターズラボ」立ち上げ人の、講談社取締役 森田浩章氏と「ヤンマガのスズキ」こと鈴木綾一氏への、電ファミニコゲーマーTAITAI氏によるインタビュー。なぜ講談社がインディーゲーム支援を? というところからはじまり、マンガ編集者としての経験やあるべき姿、講談社のパトロン精神など、非常に興味深い話が山盛りです。ちなみに鈴木綾一氏には私も、マンガ投稿サイト「DAYS NEO」が始まった直後にインタビューしています(↓)。
電子書籍リーダーとタブレット型端末の所有・利用状況をさぐる(2020年公開版)(不破雷蔵)〈Yahoo!ニュース個人(2020年10月23日)〉★
情報通信白書でタブレットの世帯所有率が4割を超えているのは知っていたのですが、これは個人の所有・利用状況。総務省・情報通信政策研究所の調査結果です。電子書籍リーダー(電子ペーパー端末)の利用率は5.7%。イノベーター(2.5%)はなんとか超えているけど、私のようなごく一部のマニア層だけが使っている状況はあまり変わっていないようです。授業で学生に触ってもらうと「印象が変わった」という反応があるのですが、今年はコロナ禍で対面授業がなく、そういう反応ももらえない……(涙)。
「触れない」立ち読みが人気 売れ行き「2割増」〈産経フォト(2020年10月24日)〉
フライヤーと日販のコラボ。全国の書店約300店に「非接触型立ち読みコーナー」を開設しています。正確には「要約」が読めるのですが、立ち読みと言ったほうが伝わりやすいのでしょうね。
海外
中国共産党が重視し普及したいテーマを刊行 ―― 中国出版界の主要ジャンル「主題出版」(前編)〈HON.jp News Blog(2020年10月20日)〉
国営出版社がしのぎを削る主戦場 ―― 中国出版界の主要ジャンル「主題出版」(後編)〈HON.jp News Blog(2020年10月21日)〉
おなじみ馬場公彦さんの連載コラム。今回は中国国営出版社による「主題出版」について。日本語への翻訳はあまり人気がないジャンルのようですが、隣接する大国がなにを考えどういう方針で動いているか、まず知らなければ批評もできないのでは? という問題提起でもあります。
米司法省がGoogle提訴 独禁法違反「検索で競争阻害」 (写真=ロイター)〈日本経済新聞(2020年10月21日)〉
米司法省がグーグルを独禁法違反で訴追、その訴状内容と判決の見通しは?〈HON.jp News Blog(2020年10月24日)〉
とうとう提訴。マイクロソフト以来、約20年ぶり。大原ケイさんに解説いただきました。本件、ずっと追っているのに「ニューヨークを含む7州が協力している別の訴訟」は知りませんでした。ただ、そもそも「消費者に被害があった」ことを判断基準とするのであれば確かに、Googleのような無料ビジネスモデルに適用するのは無理筋に思えます。
「Facebookの更新は、広告プラットフォームを破壊した」:あるメディアバイヤーの告白〈DIGIDAY[日本版](2020年10月22日)〉
Facebookの新UI、日本語入力がうまくいかないとか、旧UIにあった機能が欠けているなど、私の視界の範囲ではかなり不評なのですが、事業の要である広告まわりもボロボロになっているようです。これとは別に、発売されたばかりの新型VRゴーグル「Oculus Quest 2」ではFacebookアカウントとの紐付けが必須になっていて、そのために新規アカウントを作成した人が何人も何回も誤BANされるという阿鼻叫喚地獄も展開されています。なんというか、いい加減な仕事しやがって感。
ブロードキャスティング
10月25日のゲストはまんが家の出口竜正さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本について掘り下げました。
次回のゲストは漫画家でDomixプロデューサーの樹崎聖さんです。ZoomではYouTubeへのライブ配信終了後、オンライン交流会を開催します。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。