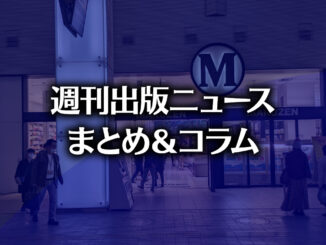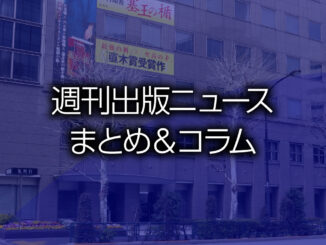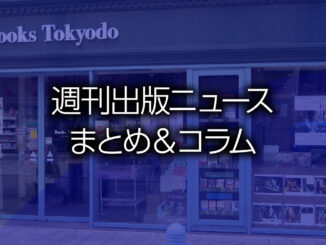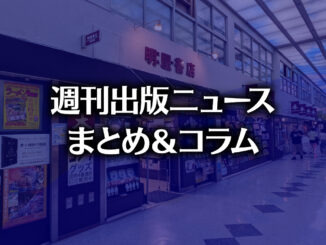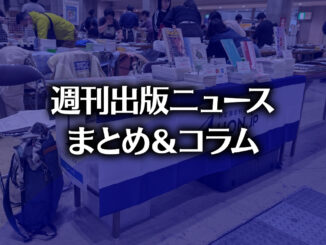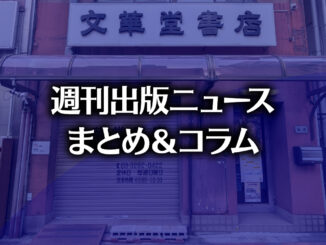《この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です(1分600字計算)》
2021年7月18日~24日は「気象庁のウェブ広告収入、2021年度は800万円の見込みに」「五輪開会式プログラム発売中止」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
政治
気象庁、Web広告を再開 2021年度の収入は800万円の見込み〈ITmedia NEWS(2021年7月20日)〉
2020年9月から広告掲載を開始したら、規約に反する「不適切」な広告が運用型広告によって掲出される問題が発覚した件の続報です。当初は2億4000万円の収入を見込んでいたそうですが、純広告に切り替えた2021年1月~2月の収入が約180万円だったため、年度で800万円の収入見込みに修正したとのこと。2022年3月までの9カ月間とすると、月90万円弱といったところでしょうか。
開始当時のニュース(↓)によると、気象庁のウェブサイトは2019年度に年間79億PVと省庁公式サイトではトップクラスで、年間2億4000万円かかるサーバ運営費に充当する目的で広告掲載を始める、という目論見でした。当初は2億4000万円の収入を見込んでいたなら、広告掲載で収支トントンにできるという試算だったのでしょう。それが20分の1以下になってしまうという、なんともトホホな顛末に。
ただ、これ、単純に運用型広告を純広告に切り替えたから、という問題でもなさそうです。2021年から広告運用事業を受注したホープ社のリリース(↓)によると、気象庁のウェブサイトは2021年4月実績で月間約5.1億PVですが、括弧書きに「ボット等による機械的な自動アクセスを含む」とあります。つまりこれ、スクレイピングでデータを自動収集しているような、広告効果がまったく見込めないアクセスが、実際には「PV」の大半なのではないか、と。仮に、人間によるアクセスが2%程度だとしたら、月100万円の収入見込みでも納得できます。
で、なぜこのニュースを「政治」に入れたかというと、根本的な問題は、気象庁の予算が少ないからではないか? と思うからです。省庁の公式サイトという「公共」の場に「広告」を載せなければならないような事態というのは、どこかがおかしい。政治の不作為と言ってもいいのではないかと思うのです。
著作権者不明でも利用しやすく 許可不要の仕組み検討へ〈朝日新聞デジタル(2021年7月24日)〉
いわゆる「拡大集中許諾制度」の検討が始まった、というニュース。なのですが、本文に「拡大集中許諾制度」という言葉は出てこず。また、現行の「著作権者不明等の場合の裁定制度」にも触れず。意図的なのかなあ。7月19日に開催された文化審議会著作権分科会(第61回)の資料はこちら(↓)。
思いは受け継がれなければならない~「知的財産推進計画2021」に思うこと(後編)〈企業法務戦士の雑感 ~Season2~(2021年7月21日)〉
企業法務戦士さんによる「知的財産推進計画2021」の解説。終盤に書かれているように、「拡大集中許諾制度」といえばこの人、という瀬尾太一さんの訃報が衝撃的だったのもあり、ピックアップさせていただきました。前述の文化審議会著作権分科会、「令和3年7月15日現在」の委員名簿(↓)にはお名前が載っているのに、7月19日に傍聴したら欠席されてて「あれ?」と思ったらまさかの、でした。ご冥福をお祈りいたします。
社会
インターネットの利用環境は「スマホのみ」が最多 60代はスマホ利用者が7割超に【LINE調査】〈MarkeZine(2021年7月19日)〉
LINE社による調査なので、先入観で「LINE」アプリ利用者への調査? バイアスめちゃくちゃキツそう……と思ってしまったのですが、末尾の調査概要を見たら「調査員による個別訪問留置調査」でびっくり。信頼性がそこそこ高い数値が出ていそうです。とはいえ、総務省「通信利用動向調査」のほうがはるかに大規模ですし、信頼性も高そうではありますが(↓)。
経済
開会式のプログラム発売中止 KADOKAWA〈共同通信(2021年7月22日)〉
五輪関係ではこのニュースだけピックアップ。開閉会式の演出担当者が、直前に解任されたことによる余波をモロに食らってしまった事例です。お気の毒に。書店には「返品不可・買切」条件で卸されていたようです。そのためか当初、書店側で破棄して欲しいという連絡が回っていたようですが、一部ネット書店が予約分の発送を取り消せず、7月24日には「届いてしまった」という報告がSNSで散見されました。書店員の「着払いで返送に変わった」という声も。まあ、こういう場合の常ですが、個人間オークションでは価格が高騰しているようです。
技術
はてながヤフーのコメント評価AI採用、「はてブ」の投稿を健全化〈日経クロステック(2021年7月19日)〉
Yahoo!ニュースのコメント欄を健全化する目的で開発されたAI評価が、はてなブックマークの「人気コメント」に採用というニュース。プレスリリースより前に“人気コメント算出アルゴリズムの一部にヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています”という表示が出て、「建設的とは?」と物議を醸していました。
ところが、どうも文字数による足切りがあるようだというのがすぐにバレて、「ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ 」と草ならぬ熊を生やしたコメントが多く観測される事態に。まあ、これもすぐ対策されるとは思いますが。むしろ婉曲表現や皮肉が増え、これまでよりさらにギスギスした場になりそうな予感もします。手斧が飛び交う、はてブだし。
イベント
NovelJam 2021 Online 開催のお知らせと参加者の募集〈NPO法人HON.jp(オンライン)/8月13日~15日〉※参加者募集〆切は7月30日
「いましかできないNovelJamをやろう」――短期集中型創作&販売企画、NovelJamが今年はオンライン開催! 参加者募集中です。詳細はリンク先の参加要項をご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。