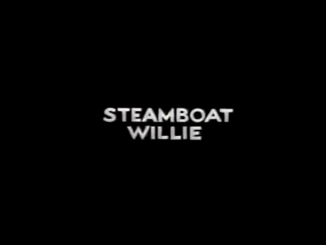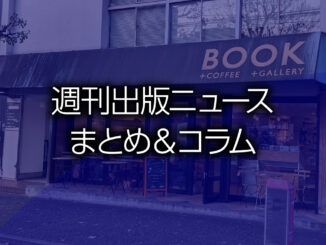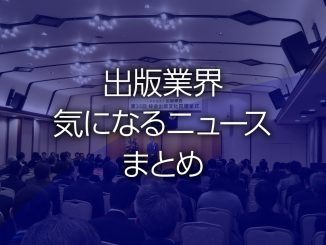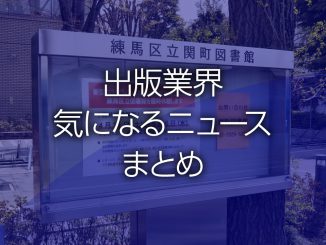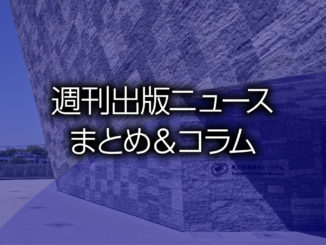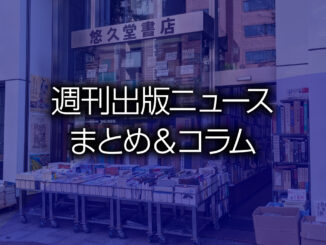《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2020年9月6日~12日は「アマゾン、公取委への改善計画で1400社に20億円返金へ」「図書館関係権利制限規定のワーキングチームで流通外作品(アウトオブコマース)について議論」などが話題に。編集長 鷹野が気になった出版関連ニュースをまとめ、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- 書体・レイアウトで読み心地改革 進化する電子書籍〈日本経済新聞(2020年9月6日)〉
- 《新型コロナ》茨城県内公立図書館 電子書籍の貸し出し増 ネット利用 外出自粛にマッチ〈茨城新聞クロスアイ(2020年9月6日)〉
- 活字嫌いが「ラノベユーチューバー」に おすすめ紹介や「聖地巡礼」で「本を読むきっかけに」〈京都新聞(2020年9月7日)〉
- マンガは横読み?縦読み? 韓国発〝読まれ方〟が覇権握るか〈47NEWS(2020年9月8日)〉
- “メディアが自分で技術を持たなくていいの?” ボトムアップで始まった講談社のデジタル変革、その舞台裏〈朝日新聞デジタル&M(2020年9月8日)〉
- アマゾン、1400社に20億円返金 公取委が改善計画認定〈日本経済新聞(2020年9月10日)〉
- 漫画「キン肉マン」スクショ問題で声明 ネタバレに「刑事告訴も」と週プレ、ゆでたまご「思いやり持って」〈弁護士ドットコムニュース(2020年9月10日)〉
- 文化庁、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第2回)」の議事次第・配布資料を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2020年9月11日)〉
- 同人誌即売会「コミケ」中止で印刷業苦境 成長市場に水、「作家の意欲減退」〈中国新聞(2020年9月12日)〉
- 海外
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
書体・レイアウトで読み心地改革 進化する電子書籍〈日本経済新聞(2020年9月6日)〉
最近の事例である、星海社の電子書籍専用オリジナルフォント、大日本印刷の「読書アシスト」、岩下智氏の「一行文庫」について、簡単なまとめ。「読書アシスト」は、9月12日の日本出版学会 2020年度 春秋合同研究発表会のワークショップに、開発担当者の小林潤平氏が登壇、詳細な説明を行っていました。
横書きの話ばかりだったので、縦書きはどうなのか? と質問したところ、縦横は慣れが大きいとも言われているが、今回の被験者では横書きのほうが10%くらい早かったので、横書きだけで実験を行った、とのこと。そのまま縦書きには応用できないかもしれない、とのことでした。まあ、そりゃそうでしょうね。コンテンツへ実装するのではなく、ビューア側の設定でユーザーが任意に切り替えられるなら、良いかもしれません。
《新型コロナ》茨城県内公立図書館 電子書籍の貸し出し増 ネット利用 外出自粛にマッチ〈茨城新聞クロスアイ(2020年9月6日)〉
記事でピックアップされている龍ケ崎市と潮来市の電子図書館は、OverDrive Japan。他の名前だけ挙がっている筑西市、水戸市、守谷市、土浦市、鹿嶋市はTRC-DLもしくはLibrariEと、サービスによって取り上げ方が違っているようです。なぜ(なんとなく想像はつきますが)。
ちなみに「7市にとどまる」とありますが、調べてみたところ、44市町村中の7カ所なので、全国的に見ると結構上位です。いちばん実施自治体数が多いのは兵庫県で、41市町村中12カ所(ただし4市町合同運営というのがある)。次いで東京都の62区市町村中7カ所+都立(いずれも2020年7月1日時点・電流協調査より筆者調べ)。
ただ、ニュースを見ていると、7月1日以降でも何カ所か新規でサービス開始しているので、すぐに変動するかもしれませんが。9月12日の日本出版学会 2020年度 春秋合同研究発表会で、電流協の長谷川智信氏が「7月1日時点の数字から、年内に恐らく30カ所くらい増える見込み」とおっしゃってました。全国的には、ようやくアーリーアダプターへの普及段階です。
活字嫌いが「ラノベユーチューバー」に おすすめ紹介や「聖地巡礼」で「本を読むきっかけに」〈京都新聞(2020年9月7日)〉
本のYouTuber(ブックチューバー)と言えば、HON.jpでも何度かお世話になってる文学YouTuberベルさん(チャンネル登録者数 12.5万人↓)ですが、
気がついたらいろんな方が本の紹介動画に参入しているようです。この記事で紹介されている、やまさきりゅうさん(チャンネル登録者数 3.56万人↓)は基本ライトノベルですが、マンガやアニメも紹介するオタク向けなチャンネル。
この記事を読んで「いまブックチューバー界隈どうなっているんだろう?」と思い、いろいろ検索してみたら、「要約」系のチャンネルがいくつか立ち上がっていました。恐らく許諾はとってないでしょうから「おいおい著作権大丈夫か?」と心配に。企業のやっている要約サービス(動画ではない)はいくつもありますが、いずれも権利者から事前に許諾をとってやっているはず。「紹介」系チャンネルも、中身をチラ見せするくらいなら引用の範疇とは思いますが、ラノベの挿絵をバンバン使って見栄えを良くしているような動画は、「これ大丈夫か?」と心配になって動画に集中できない……。
マンガは横読み?縦読み? 韓国発〝読まれ方〟が覇権握るか〈47NEWS(2020年9月8日)〉
韓国発の縦スクロール(縦読み)マンガ「ウェブトゥーン」の現況について。カカオジャパン「ピッコマ」と、縦スクロール特化の漫画賞を開催している集英社「ジャンプ+」を中心に、詳しくまとめています。「ピッコマ」アプリの月間販売金額が、7月に「LINEマンガ」を逆転したってマジデスカ?
読んでいて若干違和感があったのが、「コマをつなげ日本のマンガでは考えられないほど縦長にし」という表現。手塚治虫マンガで1ページを縦に3分割~4分割する超縦長コマ割り、結構あったような。確かに、最近はあまり見ませんが。
ちなみにこの記事、9月7日午前に一度公開されていたのですが、私が読もうと思った時点ではすでに削除されてました。「なんぞ?」と思ったら、「画像の著作権クレジット表示にミスがあったため、直して再公開した」とのこと。なるほど。
“メディアが自分で技術を持たなくていいの?” ボトムアップで始まった講談社のデジタル変革、その舞台裏〈朝日新聞デジタル&M(2020年9月8日)〉
7月に立ち上げられたKODANSHA tech合同会社の責任者インタビュー。最初の見出しにある「5ピクセル動かすだけで5万円」って、ほんとに5ピクセル動かすだけなのか、周囲への影響を考えたら実はそこそこ工数かかる作業なのかも……といった疑問も、多少はHTMLやCSSといったウェブの技術を知らないと疑問に思わない、というのはありますよね。会社設立を二つ返事でOKしてくれる役員もすごい。
そして、こうやって技術開発部門を組織化できるのは、充分な資本を持った大手に限られるという現実も。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、中小企業ほど遅れてしまう傾向があるように思います。
アマゾン、1400社に20億円返金 公取委が改善計画認定〈日本経済新聞(2020年9月10日)〉
本件、2018年2月の日経スクープ報道時から気になって追ってきましたが、ここへ来てようやく出版関係者から「うちも要求されていた」という声が視界の範囲で観測できました。恐らく“ベースコープ(協賛金)”の要求と思われます。“値引き額の一部補填”については、紙は定価販売で値引きできないので、あり得るとしたら電子のホールセールモデルのみでしょう。
ところで、取次の“運賃協力金”や“分戻し”は、公取委的にはどういう扱いになっているか若干気になります。本件で問題となったAmazonの要求と、実態としてはあまり差がないようにも思えるのですが。もちろん、“正常な商慣習”とみなされているなら、問題ないのですが。
漫画「キン肉マン」スクショ問題で声明 ネタバレに「刑事告訴も」と週プレ、ゆでたまご「思いやり持って」〈弁護士ドットコムニュース(2020年9月10日)〉
スクショの無断アップロードが著作権侵害になる場合がある(引用にあたる場合は除く)から、やめて欲しいというのは権利者として正しい主張。ですが、ネタバレ行為(文章含む)に対しても刑事告訴などの法的手段を講じることもあると週プレ編集部が公式見解を出し、ジャンプ+編集長がそれに追従したことが、物議を醸していました。
どうやら、いままで週プレNEWSでのウェブ連載で、公開後は誰でもどこからでも閲覧可能な形だったのが、8月17日から週プレ本誌との同時連載に変わった(↓)ことにより、いままで黙認されていた行為が黙認されなくなった、という背景があるようです。
映画でもなんでも、あまりに早過ぎるネタバレ感想が未読のファンの怒りを買うというのもよくある話。権利者側としても勘弁して欲しいという気持ちは理解できますが、引用要件を満たしたネタバレ感想に法的措置を講じることはできません。法的措置をチラつかせることにより、ファンを委縮させてしまうのではないかという危惧もあります。
ただ、著者のゆでたまご氏の言う「ネタバレ」と、編集部側の「ネタバレ」に、恐らくズレがあるのではないでしょうか。あくまで想像ですが、ゆでたまご氏はキャラ的に、合法か非合法かは関係なく「ネタバレ許さん!」と言い出しそうです。でも編集部側は、無断転載と文章であらすじをほとんど書いてしまうような、公式配信を読まずに済んでしまう行為を指して「ネタバレ」と言っているのではないか、と。あくまで想像ですが。編集部コメントで「悪質な著作権侵害、ネタバレ行為(文章によるものを含みます)」と、並列にしてしまった辺りが失敗の要因に思えます。
文化庁、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第2回)」の議事次第・配布資料を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2020年9月11日)〉
第1回のヒアリングは図書館など利用者と直接相対する立場の方々でしたが、第2回は権利者側から。今回も傍聴しました。やはり、どちらかといえば慎重・反対意見が目立ちます。実況ツイートしておきました(↓)
日本漫画家協会(赤松健氏)からの「“絶版”の一般認識は法律用語とは若干異なるので、例えば“流通外作品(アウトオブコマース)”などと改称しよう」という提言は、非常に良いと思いました。出版権設定契約は放っておくと自動更新され、品切重版未定という業界慣習により“絶版”にはなりません。このワーキングチームの議論が記事になった際などに、“絶版”と見出しに入ると誤解され炎上する可能性があるのでは、という指摘でした。
あと、生貝委員からの質問で、権利者側の利用ニーズはどうなのか? というのも良かった。日本文藝家協会はさすがに、自身も図書館のヘビーユーザーであるという認識(だからこそリスク面も見えるという回答でしたが)。同じ質問に対し、日本雑誌協会・日本書籍出版協会(村瀬拓男氏)からは、校正・校閲という観点が“出てこなかった”のとは対照的でした。大手出版社は、社内ライブラリーが充実しているから困らない? そんなことないと思うのですけどね。
また、同じく書協・雑協が「5~10年前に比べたら、はるかに多くの著作物を電子出版で入手可能にしてきた」と主張していたことに対しては、いや、確かにそりゃ5~10年前に比べたらずいぶんマシになってますけど、2019年の新刊でもまだ3分の1しか一般向け電子書店には並んでませんよ? と反論しておきたいところ。ちょうど、9月12日の日本出版学会 2020年度 春秋合同研究発表会で、私と堀正岳さんの共同研究で直近の電子化率について発表しています。詳細は公開した資料をご参照ください(↓)。今春に発表予定だったのが、コロナ禍で中止(延期)になってしまったのが悔しい……。
同人誌即売会「コミケ」中止で印刷業苦境 成長市場に水、「作家の意欲減退」〈中国新聞(2020年9月12日)〉
中国新聞なので、中国地方の同人誌印刷業者の状況についての報道ですが、恐らく全国的に同じような状況に陥っているだろうと想像できるニュース。売上半減とは恐ろしい。以前、トキワ荘プロジェクトが「あなたの才能に必要なのは、〆切です」というキャッチコピーを使っていましたが、締め切りがないと創作意欲が減退してしまうのは、実際そうなんですよね。トホホ。
ところでつい先日、藤末健三参議院議員が文化庁に問い合わせて、文化芸術活動の継続支援事業に同人印刷会社は「対象になる」という回答を得ています(↓)。第3次申請受付は9月30日17時まで。
海外
Amazonのレビュアーランキング上位10名中7人が「ステマレビュー」を投稿、Amazonは2万件のレビューを削除〈GIGAZINE(2020年9月7日)〉
イギリスAmazonの話。フィナンシャル・タイムズ誌の調査によって「ステマ」が明らかになったのち、Amazonがレビューを削除したとのこと。記事内にリンクされている「The Verge」によると、Amazon広報担当者は「レビューを公開する前に分析し、毎週1000万件の投稿を処理している」と述べているそうです。「分析」ということは、AIによる自動処理でしょうかね?
先週のまとめでは「アマゾン星1つやらせ投稿の依頼者に刑事罰」という日本の事例をピックアップしましたが(↓)、不正行為と対策がイタチごっこになっている感があります。
Amazonは巨大な市場であるのと同時に、誰でもレビューが投稿できるCGM(Consumer Generated Media)でもあります。ステマ☆5レビューや嫌がらせ☆1レビューは、ずいぶん前から常態化しています。そしてそれは、私がAmazonをあまり利用しなくなった理由の一つでもあります。英FT紙のような外からの指摘を受けてから削除するのではなく、最初からもう少しちゃんとチェックして欲しいものです。
ブロードキャスティング
毎週日曜日21時から配信する、30分間のライブ映像番組。上記のニュース紹介や解説をゲストとともに、より掘り下げた形でお届けしています。9月13日のゲストは株式会社BCCKS 代表取締役COOの山本祐子さんでした。
次回のゲストはO2O Book Biz株式会社 代表取締役 落合早苗さんです。ライブ配信終了後、交流会もあります。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。