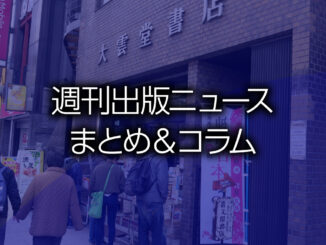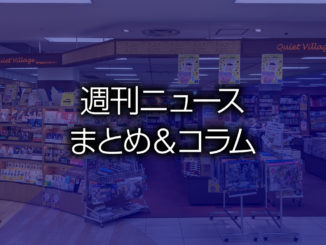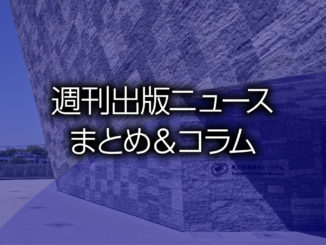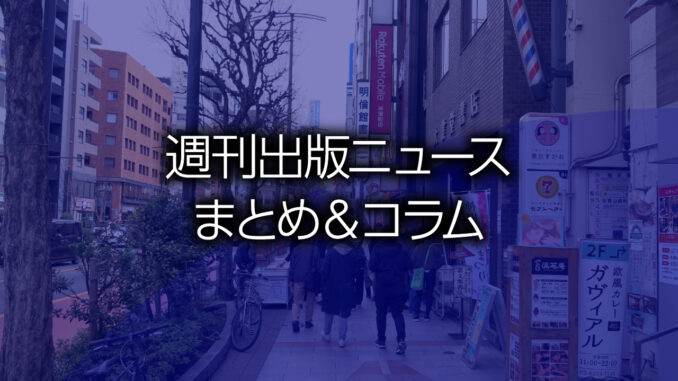
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年7月31日~8月6日は「消費者庁、晋遊舎に1231万円の課徴金」「AIでイラストを自動生成するサービス」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 旧統一教会の“著作権違反主張”に「テレビ業界が戦々恐々中」〈FRIDAYデジタル(2022年8月3日)〉
- ドイツにおける『東京リベンジャーズ』問題|Kataho@フランクフルト〈日経COMEMO(2022年7月31日)〉
- 2021年のフランス出版市場は4冊に1冊がコミックス、うち2冊に1冊が日本の漫画〈HON.jp News Blog(2022年8月4日)〉
- デジタル出版のデメリット ―― デジタル出版論 第3章 第8節〈HON.jp News Blog(2022年8月5日)〉
- openBD、10月から出版社サイトでの書影取得スタートへ〈新文化(2022年8月1日)〉
- 本の試し読みから発注までオンライン完結、書店向けソリューション/選書・仕入に活用できる電子ゲラサービス「NetGalley™」、書籍オンライン受発注システム「BookCellar」と連携キャンペーン開始〈株式会社メディアドゥ(2022年8月1日)〉
- 明屋書店、店頭で電子書籍販売の実証実験〈日本経済新聞(2022年8月1日)〉
- JR東日本、駅の個室ブースで電子雑誌閲覧 利用増へ実験〈日本経済新聞(2022年8月3日)〉
- 「無断転載が横行」物議の小説アプリ「テラーノベル」 運営が対応策を発表「信頼回復に努める」〈J-CAST ニュース(2022年8月3日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
パズル誌出版社に課徴金 懸賞品発送に最長1年8カ月の遅れ〈産経ニュース(2022年8月5日)〉

なんと1231万円の課徴金です。景品表示法の課徴金は売上額の3%なので、4億1033万円の売上があったということなのでしょう。「半年以上過ぎたものは不当な誘因に当たる」と判断されています。消費者庁による発表はこちら。
株式会社晋遊舎に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について〈消費者庁(2022年8月5日)〉
社会
旧統一教会の“著作権違反主張”に「テレビ業界が戦々恐々中」〈FRIDAYデジタル(2022年8月3日)〉
著作権を盾に報道の自由を脅かす事例。記事内では触れられていませんが、法第41条(時事の事件の報道のための利用)があるので、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において」は無断で利用可能です。問題は、その条件に合致するかどうかでしょう。
以前、暴力団山口組の一斉摘発が行われた際に、TBSが襲名式のビデオ映像をニュースに使い、訴えられた事件があります。そのときは法第41条に該当するとして、訴えは退けられています。今回の旧統一教会の映像を報道に用いているケースが同様と見做されるかどうか。どのような使われ方をしているか次第とは思うのですが、実際の映像を観てみないとなんとも言えず。
ちなみに細かなことですが、FRIDAYデジタルのタイトルにある「著作権違反」は、「著作権侵害」もしくは「著作権法違反」と書いて欲しい。権利侵害、法律違反なので。
ドイツにおける『東京リベンジャーズ』問題|Kataho@フランクフルト〈日経COMEMO(2022年7月31日)〉
国境を越えた表現が現地の文化と衝突する問題。本件は、マンジ(卍)とハーケンクロイツが似ていることから発生しています。マンガはオリジナル表現を守ったけど、ファンアートやコスプレイベントでは使用禁止令が出ているそうです。「作品本来の文脈を離れることで、政治的な使用と判断される場合がある」というのがその理由。アニメも、謎の光で隠されていますね。
2021年のフランス出版市場は4冊に1冊がコミックス、うち2冊に1冊が日本の漫画〈HON.jp News Blog(2022年8月4日)〉
以前本欄で、GFKのフランス出版市場統計にデジタルが含まれていないことに疑問を呈したことがあります(#492)。そのとき「現状では市場規模が小さすぎるため、計算に加える意味合いが低い」と情報提供いただいたことでご縁ができ、寄稿いただくことになりました。今後、数字以外の面でもさまざまな情報提供をいただけるとのことで、非常に楽しみです。
ちなみに、フランスのデジタル出版市場は、2021年でもシェア5%未満なんですって。Amazon「Kindle」を徹底的に抑え込んだからでしょうか?
デジタル出版のデメリット ―― デジタル出版論 第3章 第8節〈HON.jp News Blog(2022年8月5日)〉
連載21回目。私から見たメリットとデメリットという整理をしていますが、ステークホルダー単位でまとめて欲しいというご意見をいただきました。なるほど。あとは、メディア型の海賊版サイトと同じことを正規版でやるのは「普通に考えたら無理」と書いた上で、いちおう脚注で「マンガ図書館Z」に触れておいたのですが、本文中で触れたほうがよかったかも? マンガアプリ広告市場の小ささ、という傍証も記しておくべきだったか。
openBD、10月から出版社サイトでの書影取得スタートへ〈新文化(2022年8月1日)〉
私もopenBDのユーザーフォーラムには参加していたんですが、「10月から取得開始」というのは聞きもらしていました。この記事を見て慌ててアーカイブを再確認したところ、冒頭のポット出版沢辺さんのパートで説明されていました。一部出版社サイトから、事前に連絡をしたうえで、クロールによる自動収集を開始するそうです。取得停止を申請すれば止めるというオプトアウト方式。
HON.jpの正会員向け「Maruzen eBook Library」のラインアップ一覧を作成するのに版元ドットコム(≒openBD)の書影を活用しているんですが、無いものが結構あるんですよね。充実すると嬉しい。そもそも書誌情報が無いものはともかく、書影だけ無いものも意外とあります。電子図書館サービス向けと一般向けとで、出版社側の力の入れ方が違うのかも?
本の試し読みから発注までオンライン完結、書店向けソリューション/選書・仕入に活用できる電子ゲラサービス「NetGalley™」、書籍オンライン受発注システム「BookCellar」と連携キャンペーン開始〈株式会社メディアドゥ(2022年8月1日)〉
これはよい座組み。発売前作品のゲラが読める「NetGalley」と、書店向け受発注システム「BookCellar」の連携です。ゲラで試し読みやレビューを確認したうえで、そのまま予約発注できる、と。参加出版社がまだ8社とちょっと少ないのが気になるところですが、うまくいけば他にも広がっていくことでしょう。
明屋書店、店頭で電子書籍販売の実証実験〈日本経済新聞(2022年8月1日)〉
リアル書店の店頭で電子書籍を販売する試み。#516でピックアップした実証実験に、愛媛県を地盤とする書店チェーンの明屋書店が加わるというニュースです。4月に開始された実証実験は東京都内3店舗(ブックファースト新宿店と中野店、八重洲ブックセンター本店)限定なので、地方で展開してみてどうなるか。
 今回のこれは、店頭で専用QRコードをスキャンし、書籍バーコードスキャン画面を開く工程を挟むことで、リアル書店にも手数料が落ちるという仕組みです。以前もコメントしたように、QRコード決済が普及したいまならユーザーにも比較的受け入れやすいかもしれません。物理在庫が無い場合は電子も買えない点が弱点でしょうか。バーコードさえあればいいので、他のなにかで代替できそうではありますが。いままで数多の失敗事例(BooCaとか)を見てきましたので、今度こそなんとか成功させて欲しい。
今回のこれは、店頭で専用QRコードをスキャンし、書籍バーコードスキャン画面を開く工程を挟むことで、リアル書店にも手数料が落ちるという仕組みです。以前もコメントしたように、QRコード決済が普及したいまならユーザーにも比較的受け入れやすいかもしれません。物理在庫が無い場合は電子も買えない点が弱点でしょうか。バーコードさえあればいいので、他のなにかで代替できそうではありますが。いままで数多の失敗事例(BooCaとか)を見てきましたので、今度こそなんとか成功させて欲しい。
あとは、購入可能な電子書店がメディアドゥの「スマートBookストア」に限られている点も、今後を考えると気になるところ。他の電子書店からすれば、電子取次をやりつつ自社の電子書店への囲い込みを図るのは利益相反行為に見えるわけで。いまは実証実験だから許容できるかもしれませんが、本格稼働が始まったときにこのままだとダメなのではないかという気がします。
ユーザー側からしても、普段使い慣れている電子書店で利用したいニーズが強いでしょう。個人的にも、もうこれ以上ライブラリを分散させたくないという思いがあります。これを機に、ライブラリの連携を図るなどの追加施策が必要ではないでしょうか。「スマートBookストアと連携すれば、好きな電子書店へライブラリを移行できる」といった形になっていれば、囲い込みの懸念も払拭できます。「BOOK☆WALKER」と、「ブックライブ」「ブックパス」の本棚連携のような事例を、もっと広げて欲しいところです。
JR東日本、駅の個室ブースで電子雑誌閲覧 利用増へ実験〈日本経済新聞(2022年8月3日)〉
初めて見た「TechnoBlood eSports」という名前に、どういう電子雑誌のサービスなんだろう? と興味を持ち、プレスリリース [PDF]を調べてみました。日経のタイトルは「電子雑誌」だけですが、実際には「タブホ(雑誌)」と「flier(要約)」と「LEC(資格)」のパッケージでした。
このJR東日本の個室ブース、私がよく利用する三鷹駅のホームにも最近できました。Wi-Fi・電源完備で15分275円(税込)という料金設定。うーん……近くにWi-Fi・電源有の喫茶店が無くて、めちゃくちゃ急いでるときならアリかも? でも、たとえば「タブホ」って月額550円(税込)で読み放題ですから、個室ブース内で30分電子雑誌を読んだら等価ということに。ちょっともったいない気が。
「無断転載が横行」物議の小説アプリ「テラーノベル」 運営が対応策を発表「信頼回復に努める」〈J-CAST ニュース(2022年8月3日)〉
#531でピックアップした、キッズの遊び場状態になってしまっていた「テラーノベル」から、かなりまともな対応策が発表されました。とくに、削除請求に以前は印鑑登録証明書や本人確認資料の郵送が必要とされていたフローが簡素化されたのは大きいでしょう。あとは、対象年齢が17歳以上に変更された点。これで小中学生は締め出されることに。これだからCGMの運営は難しい。
技術
NFTを活用した地域文化のデジタル実装に向け「御朱印NFT」の頒布が開始〈Digital Shift Times(デジタル シフト タイムズ)(2022年8月2日)〉
半年ほど前に、実証実験を開始したという記事がありましたが、有効性の検証が完了したようです。現地に行って御朱印を申し込んだ人にだけNFTが配布される仕組みなので、集客促進にも繫がります。実証実験開始のときにもコメントしましたが、これはNFTの正しい活用法であり、「御書印プロジェクト」にもそのまま応用可能と思われます。「FanTop」あたりと連携するのが良いのでは。
洋風イラスト自動生成「Midjourney」 AIが1分で描いたと思えない濃密な世界観 -〈KAI-YOU.net(2022年8月2日)〉
適当なテキストを入力すると、自動でイラストを生成してくれるAIの登場。夢中になって生成している方を周囲で何人も見かけます。狙ったイラストを生成されるにはコツがいるようで、こちらの意図をAIにきっちり汲んでもらうには、それなりに具体的かつ詳細な指示が必要になるようです。
出力されたイラストにはかなり癖がある(洋風?)ので、学習用データセットに偏りがあるのか、出力時に偏らせているのか。「Midjourney」で検索するとシェアされた自動生成イラストが大量に見つかるので、参考まで。廃墟っぽいイラストを得意としているようです。エログロは無いので、出力できないようにしているっぽい?
気になるのは権利関係。KAI-YOU.netの記事には “なお、Midjourney社は、Discordの「#rules」チャンネルで、作成されたイラストなどの著作権が同社に帰属することを明記しています。” とあります。確かに利用規約には “By using the Services, you grant to Midjourney,(略)irrevocable copyright license to reproduce,(略)” とあります。
しかし、アメリカの著作権局審査委員会 [PDF]はすでに、AI生成画像への著作権登録要求を却下しています。理由は、人間の作者による十分な創造的入力または介入に関する証拠がないこと。「サルの自撮り」事件と同様、人間の創造性が関与していない限り著作物ではない、という判断です。
Midjourney社創業者へのインタビューによると、彼もそのことは把握しているようです。逆に、機械学習で用いている学習用データセットはフェアユースにもとづきインターネット上から収集しているが、学習用データセットが充分ではない場合に、元画像と非常に似たものが出力される可能性があり、それはトレーニング段階での著作権侵害だと判断される可能性が高いとも述べています。まあ、元の画像が分かっちゃうようなレベルだと、そうなっちゃうでしょうね。
なお、日本の著作権法は第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)と第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)できっちりカバーされていて、「機械学習パラダイス」(上野達弘氏)と呼ばれるような状態になっています。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
新型コロナウイルス感染症の第7波が猛烈な勢いで広がり、感染事例をかなり身近なところで見聞きするようになってきました。みなさまくれぐれもご用心を。おだいじにどうぞ(鷹野)