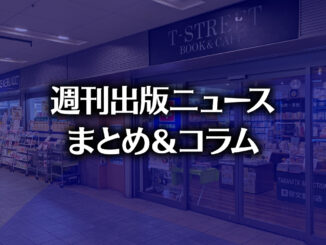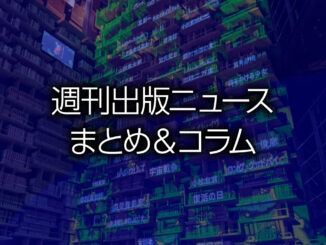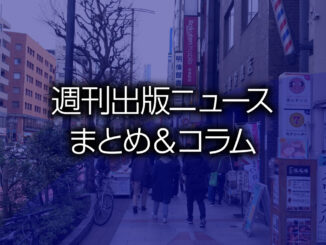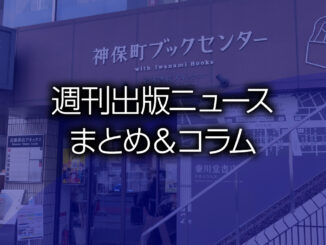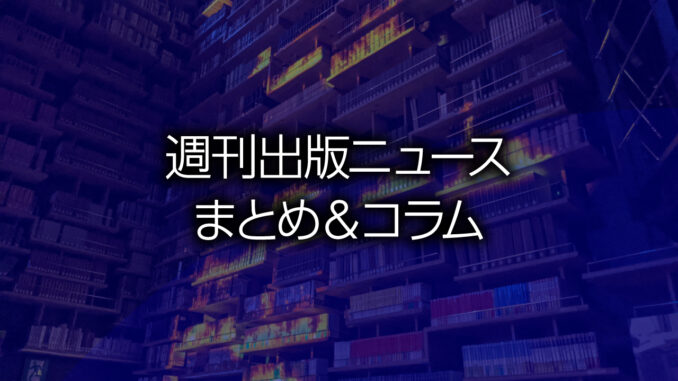
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2021年10月3日~9日は「メディアドゥのVR電子書籍ビューア正式リリース」「中国が民間企業の報道事業禁止案を公表」「アニメの引用」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 許諾なく要約してKindleで販売する行為〈Publidia(2021年10月4日)〉
- 書籍の要約動画サービス「ムビ本」実証実験開始~話題のビジネス書を“10分動画”で提供~〈サッポロ不動産開発株式会社のプレスリリース(2021年10月4日)〉
- フランスで「日本マンガの人気」再沸騰している訳 | ゲーム・エンタメ〈東洋経済オンライン(2021年10月6日)〉
- デイリーポータルZに来ている人はどのくらいいる? ウェブ解析マスターが教える「見るべき指標」 | 楽しく学ぶアクセス解析&サイト改善【DPZ×ウェブ解析士】〈Web担当者Forum(2021年10月7日)〉
- 商品情報誌「特選街」43年の歴史に幕 「ショック大きい」読者から惜しむ声〈J-CAST ニュース(2021年10月7日)〉
- Google、気候変動を否定するサイトへの広告配信を停止〈日本経済新聞(2021年10月8日)〉
- 技術
- メルマガについて
- 雑記
政治
【独自】海賊版サイト増加、文化庁が削除費支援へ…「巣ごもり需要」も被害に拍車 : エンタメ・文化 : ニュース〈読売新聞オンライン(2021年10月3日)〉
文化庁が海賊版被害対策で、削除要請を専門業者に依頼する際などの資金を支援する制度を新設するとのこと。確認できた範囲では、いまのところ読売新聞だけで報じられているニュースです。大手はともかく、中小出版社では太刀打ちするのが難しいケースも多いでしょうから、良い対策なのではないかと思います。来年度予算の概算要求に、海賊版対策で2億4600万円を盛り込んだそうです。予算、通るかな?
中国、民間企業の報道事業禁止案を公表 統制強める〈日本経済新聞(2021年10月9日)〉
まだ「案」の段階ですが、「民間企業に新聞、通信社、出版、テレビ、ネットニュースなどでの取材・編集を認めない」「政治、経済、軍事、外交、重要な社会問題、文化、科学技術、衛生、教育、スポーツなどのほか、世論を導く実況中継を手がけることも許さない」など、なかなか衝撃的な内容です。
少し前から、芸能、アニメ、ゲームなど映像系を中心とした表現規制強化の動きが報道されるようになっていて、気になっていたのですが(↓)、これで新聞や出版系も統制が強められることになりそう。うーん、これは……HON.jp News Blogへ寄稿いただいている北京大学・馬場公彦さんにも影響があるんじゃないでしょうか。心配。
歴史教育が「分断」の火種に 米テキサス州で児童書撤去〈日本経済新聞(2021年10月9日)〉
自由の国アメリカでも、表現規制の政治的な動きが。共和党が地盤を持つ複数の地域で、人種差別や性差別の教育を制限する法律が成立しているそうです。「批判的人種理論」を教える児童書が「不適切な教材」として、撤去を求める署名活動が展開され、学校側が応じるといった動きもあるとか。なんなんでしょうね、あっちもこっちも。
社会
日本のウェブトゥーン業界に必要なのはどう考えても作品の紹介記事だろ【2021年10月マンガコラム】〈TV Bros. WEB(2021年10月4日)〉
飯田一史さんによる、面白いウェブトゥーン作品の紹介記事。そういう記事が決定的に不足しているのでは、という問題提起でもあります。ウェブトゥーンはエモーショナルな表現が強い印象があるので、文字メディアよりTikTokみたいな映像メディアで展開したほうがリーチしそう。作品紹介による直接的なメリット(アフィリエイト)があれば、またちょっと違ってくるんでしょうけどね。
アニメはいかにレンズの効果を模倣してきたか〈メディア芸術カレントコンテンツ(2021年10月4日)〉
アニメの記事をピックアップしたのは、アニメの場面カットを記事へ引用することについての好例だからです。実は先日、朝日新聞「好書好日」に掲載された『著作権は文化を発展させるのか 人権と文化コモンズ』の書評に、「15年ほど前、私は映画評論の本を刊行したことがある。作品写真を使いたかったが、使用料が多額になるので、文字ばかりの本になった。当然売れなかった」という記述がありました(↓)。
なぜ使用料を払う(=許諾を得る)ことが前提なのか? 著作権法32条「引用」の出番ではないか? と疑問に思い、その旨をツイートしました。すると、複数のアニメ評論関係者から「映像の引用は前例が少なく難しい」という趣旨の反応をいただきました。
スタジオジブリの社内で「アニメコミックス」から引用した本が「脱法行為だ」と批判されていた、などの事例を教えていただいたのですが、正直、まったく納得できませんでした。というのは、著作権を盾にされ、批判的な評論が萎縮させられるようでは、「引用」の権利制限が存在する意味が無くなってしまうと思うからです。まあ、前例が少ないと「怖い」というのは理解できますが。
その直後に、このアニメ場面カットをふんだんに使っている記事が公開されるという偶然。これは間違いなく引用だろうという確信のもと、掲載メディアを運営している文化庁に問い合わせました。もちろん引用要件です(許諾は得ていない)と回答が得られたため、記録に残しておきます。文化庁を後ろ盾とした前例ができた、ということで。
25年後のインターネットは監視社会? 「Wayback Machine」のパロディサイトが怖いと評判【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2021年10月5日)〉
Internet Archive 25周年記念特設ページで、「Wayback Machine」ならぬ「Wayforward Machine」が公開されています(↓)。URLを入力すると、そのページの25年後の姿が表示されるという設定で、監視社会をイメージしたエラー表示だらけになります。
下のほうにあるタイムラインには、2025年に名誉毀損訴訟によって「Wayback Machine」が閉鎖されるとか、2044年にジョージ・オーウェル『1984』の最後の物理コピーが破壊される、など、ディストピアな未来が皮肉交じりに想像されています。こわっ。
経済
許諾なく要約してKindleで販売する行為〈Publidia(2021年10月4日)〉
ayohataさんのニュースレターで、Kindleストアにファスト映画の書籍版が登場していた騒動について触れられていました。無断要約騒動だと思っていたのですが、どうやらそれどころではなかった模様。許諾を得て要約サービスを展開している「フライヤー」から、無断でスクレイピングして売っていた疑いがあるようです(消えちゃったから確認できない)。
ちゃんと許諾を得て要約サービスを展開しているところを真似て、無断で要約を始めちゃう人が現れるあたりまでは想定していたのですが(要約なのか引用なのか判断が難しいというのはさておき)、まさかパクってそのまま売るアホが現れるとは。想像の斜め上でした。
書籍の要約動画サービス「ムビ本」実証実験開始~話題のビジネス書を“10分動画”で提供~〈サッポロ不動産開発株式会社のプレスリリース(2021年10月4日)〉
……という騒動が起きているときに、偶然このリリースを目にしました。タイミング的にちょっと面白かったのでピックアップ。書籍要約動画サービス「WISQ」を展開する株式会社VooKとのパートナーシップです。ABOUTに「WISQに掲載している動画は、VooKが出版社と共同で作った完全オリジナル」とあり、当然のことながら、ちゃんと許諾を得てサービス展開しているようです。
フランスで「日本マンガの人気」再沸騰している訳 | ゲーム・エンタメ〈東洋経済オンライン(2021年10月6日)〉
こちらの記事、フランスのバンド・デシネ市場をずっとウォッチしてきた西野由季子さんから、急に再沸騰しているわけではなく、右肩上がりですよなどのツッコミが入ってました(↓)。
私が気になったのはもっと根本的なところ。冒頭いきなり「フランスは今や、日本に次ぐ世界2位の漫画市場」と始まるんですが、ソースは? いや、恐らくそうなんでしょうけど、市場規模が具体的にどれくらいで、恐らく3位の北米とどれくらい差があるのか、気になるじゃないですか。
というわけで少し調べてみました。ドイツの調査会社GfKによると、2020年フランスのバンド・デシネ市場は5億9100万ユーロで、うち42%がマンガ市場とのこと(↓)。つまり、2億4822万ユーロ(約322億円)という計算になります。ただしこれは物理メディアのみ。デジタル市場は含まれません。
で、他国はどうなのか? というと、GfKのサイト内を調べてみたのですが、残念ながら見つけられません。米国のポップカルチャービジネス情報誌ICv2によると、2020年北米マンガ市場は2億4000万ドル(約269億円)とのこと(↓)。こちらもデジタル市場は含まれません。
同じ土俵の調査ではないので、単純比較はできません。また、日本の市場も2020年にはデジタルの市場占有率が55.8%に達しているくらいですから(↓)、海外市場もここ数年で構造が激変している可能性もあります。そもそも、デジタルを加味しない市場比較にどれだけ意味があるだろうか? と考え込んでしまいました。
デイリーポータルZに来ている人はどのくらいいる? ウェブ解析マスターが教える「見るべき指標」 | 楽しく学ぶアクセス解析&サイト改善【DPZ×ウェブ解析士】〈Web担当者Forum(2021年10月7日)〉
DPZの「はげます会の会員(有料会員)を増やす」という目標へ向かって、改善プロセスを公開で行うという企画。DPZ、丸裸です。ウェブサイトをどう分析すればよいのか? という基本のキが分かる良記事。
商品情報誌「特選街」43年の歴史に幕 「ショック大きい」読者から惜しむ声〈J-CAST ニュース(2021年10月7日)〉
今後はウェブサイト「特選街web」で情報発信するわけなので、「幕」というかデジタルメディアへの移行です。2013年にマガジン航へ寄稿した「情報誌が歩んだ道を一般書籍も歩むのか?」に、物理メディアの維持は「撤退戦」であると書きました(↓)が、難しい戦いをよく勝ち抜いた、と称えたい気持ちです。あ、ちなみに私の古巣は「特選街」ではありません。念のため。
Google、気候変動を否定するサイトへの広告配信を停止〈日本経済新聞(2021年10月8日)〉
巨大IT企業による表現規制、ではあるのですが、政府による法規制と一緒にしたくないなと思い、経済カテゴリーに入れました。Google AdSenseのアカウントがBANされたところで、競合他社が代替手段になっちゃいますからね。より低品質で悪質なアドネットワークへ落ちていく、とも言えますが。
技術
教室から宇宙まで、VR空間で読書するビューワー〈Impress Watch(2021年10月5日)〉
メディアドゥのVR電子書籍ビューアが正式リリース。自社ストアの「コミなび」での提供開始とともに、各ストア向けにも供給を開始しています。個人的には、背景空間を変えることより、大画面で観る没入感を楽しみたい気がします。「Oculus Quest」「Oculus Quest 2」に対応しているそうですが、持ってないので試せない……。
Koboが電子書籍リーダーの新モデル2種類発表、Bluetoothヘッドフォンでオーディオブックを聴ける〈TechCrunch Japan(2021年10月5日)〉
翻訳記事であることにご留意ください。Rakuten Koboは、英語圏においては2017年からオーディオブック市場に参入しています(↓)。
ところが、日本の楽天Koboはオーディオブックをまだ扱っていません。英語圏のニュースで先に、Bluetoothヘッドフォンでオーディオブックを聴けるE INK端末投入という情報を見たので、もしかしたら日本でもオーディオブックの扱いを始めるかも? と思っていたのですが、蓋を開けたら一切触れられておらず(↓)。がくっ。
源氏物語が好きすぎてAIくずし字認識に挑戦でグーグル入社 タイ出身女性が語る「前人未到の人生」 |〈Ledge.ai(2021年10月7日)〉
くずし字認識スマホアプリ「みを(miwo)」の開発者、カラーヌワット・タリンさんへのインタビューです。タイ語版『あさきゆめみし』に出会ったことで、日本の古典文学に興味を持ったというバックグラウンドが素晴らしい。まさに、好きこそ物の上手なれ。
しかし、AIくずし字認識の研究をしていたら、国文学研究者たちから「こんな研究は良くない」と否定された話が心の底から悲しい……なんだろうその狭量さは。グーグルに入社されたということなので、恐らく Google Lens にくずし字翻刻機能が載る日も近いのではないかと。楽しみにしています。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
夕方、日課のサイト巡回と翌朝公開の記事セットが終わった時点で19時を回っていなければ、少し散歩をするようにしています。近ごろは日が落ちるのが早くなったので、暗い中を歩くことになります。数日前、見事に転びました。歩道のすぐ脇にある駐車スペースになんとなく足を踏み入れてしまい、車止めに足を止められました。痛ぇ。幸い、擦り傷と打ち身程度で済みましたが、散歩の時間を朝など明るいときに変えたほうがいいかも、と思いました(鷹野)