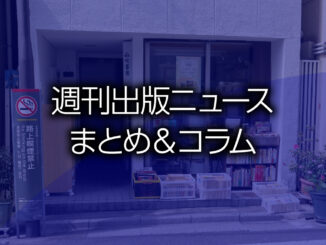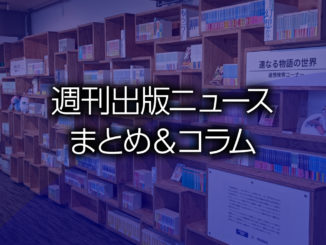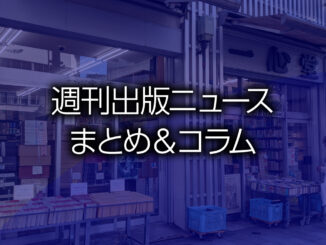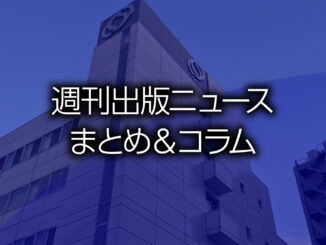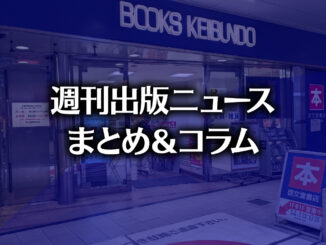《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2020年12月13日~19日は「米大手出版社が巨大化する理由」「中国投稿サイト(網絡文学)事情」「NHKが公式noteアカウント」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- 岩波少年文庫創刊70年記念 電子書籍70点一斉配信(12/24配信開始)〈岩波書店(2020年12月12日)〉★
- 海賊版サイトは「漫画界の将来に暗い影」 赤松健さんら被害の深刻さ訴える〈弁護士ドットコムニュース(2020年12月14日)〉
- hontoにあった怖い話 「サービス誤登録削除を依頼したら当方のメアド変更を提案される」の巻〈ITmedia NEWS(2020年12月14日)〉
- シャープも参入。2020年、日本で飛躍したChromebook〈Impress Watch(2020年12月14日)〉
- Spotifyがメディアと組んだ「#聴くマガジン」を配信開始、「ムー」「美術手帳」「TRANSIT」のポッドキャストシリーズ開始〈Media Innovation(2020年12月14日)〉
- NHKが公式noteアカウント立ち上げ 取材過程やノウハウ公開〈ITmedia NEWS(2020年12月14日)〉★
- ヤフーがレポート発表 2020年度上半期は約1億1千万件の広告素材を非承認に〈AdverTimes(2020年12月15日)〉
- プロのマンガ家を対象にした作品募集企画がジャンプ+で〈コミックナタリー(2020年12月15日)〉★
- 日本最大の個人向けPOD出版販売サービス「ネクパブ・オーサーズプレス」がKindle電子書籍の取扱いを開始〈株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース(2020年12月15日)〉
- 電子ブックを誰でも無料で制作・閲覧できるプラットフォーム「VOUTIQUE(ブティック)」〈MdN Design Interactive(2020年12月15日)〉
- 日経電子版、エキスパートによる解説投稿機能「Think!」を開始〈Media Innovation(2020年12月16日)〉
- 著作権法における図書館関係の権利制限規定の見直しに関するパブリック・コメントへの意見の提出について〈国立国会図書館―National Diet Library(2020年12月16日)〉
- 電子書籍の利用実態調査、2人に1人が利用経験あり、電子書籍に使うお金は0円が最多。よく利用するサービスは「Kindle」「LINEマンガ」(おたすけスマホ情報サイト「Appliv TOPICS」調べ)〈ナイル株式会社のプレスリリース(2020年12月16日)〉★
- メディアドゥ 集まったレビューを冊子に、第1弾くすのきしげのり特集〈文化通信デジタル(2020年12月16日)〉
- 国会図書館図書のデジタル化、補正予算60億閣議決定!視覚障がい者にも多くのメリット(後編)〈山田太郎(ヤマダタロウ)|選挙ドットコム(2020年12月16日)〉
- TikTok、人生を変えた本やおすすめしたい本の紹介動画を募集する「#本の紹介」を 12/16から開催! 出版社社員によるおすすめの1冊も紹介!〈Bytedance株式会社のプレスリリース(2020年12月16日)〉
- 大修館書店、大学向け電子教科書配信サービス「eTextbooks.jp」を4月から提供開始〈ICT教育ニュース(2020年12月18日)〉
- KADOKAWA松原社長「出版拠点を集約 制作コスト減」〈日本経済新聞(2020年12月18日)〉
- 遠隔授業での著作物利用、21年度以降は有償に〈読売新聞オンライン(2020年12月18日)〉
- 「鬼滅の刃」ヒット桁違い 経済波及効果2000億円超〈日本経済新聞(2020年12月19日)〉★
- 海外
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
岩波少年文庫創刊70年記念 電子書籍70点一斉配信(12/24配信開始)〈岩波書店(2020年12月12日)〉★
古今東西の名作をラインアップした岩波少年文庫の電子版、複数巻のものもあるので、70点81冊(冊?)の一斉配信です。「どんなデバイスでも読みやすいリフロー型でお届いたします」とのこと。善哉。モーリス・ルブラン、宮沢賢治、新美南吉など、青空文庫に収録されている作品も多いですが、それはそれとして。
ちなみに岩波新書の青版・黄版など100タイトルが初めて電子化したのは約1年前でした。その際の記事はこちら(↓)。
海賊版サイトは「漫画界の将来に暗い影」 赤松健さんら被害の深刻さ訴える〈弁護士ドットコムニュース(2020年12月14日)〉
赤松健氏、弁護士・福井健策氏と、集英社で海賊版対策をしている伊東敦氏が、外国特派員協会で記者会見。10月からリーチサイトが違法化され、現時点ではどういう状況にあるかという情報共有が行われています。海賊版サイトの再増加と同時に、対策が効かない相手が増え、手口の巧妙化も進んでいるようです。来年1月からはダウンロード違法範囲拡大の改正著作権法が施行されますが、アナウンス効果がどれだけ奏功するか。
hontoにあった怖い話 「サービス誤登録削除を依頼したら当方のメアド変更を提案される」の巻〈ITmedia NEWS(2020年12月14日)〉
自分のメールアドレスを他人に間違えて登録されてしまったので、サポートに問い合わせたら「推測されにくいようメールアドレスの文字数を増やすこと」という斜め上の提案をされた、という話。見事に炎上です。
しかしこれ、私はITmedia eBook USERで2012年と2013年に「honto」の徹底レビューをやったのですが、当時はちゃんと受信メールからアクティベート、という手順になっていたはずなのですよね(↓)。いつ、どういう判断でこれが変わってしまったのか。ちょっと不思議。
シャープも参入。2020年、日本で飛躍したChromebook〈Impress Watch(2020年12月14日)〉
西田宗千佳氏の論考。2020年にChromebookが飛躍した要因は、GIGAスクール構想で採用されるケースが急増したから、と。補助金1人あたり4万5000円ですもんね。iPadだとキーボードがない。Windowsだとスペック的に厳しい。年始に「実用性を考えると恐らくアメリカと同様にChromebookが採用される可能性が高いものと思われ」ると書きました(↓)が、予想通りになりました。個人的には、あとはATOKさえ対応してくれれば、外出時でも困らずに済むのですが……。
Spotifyがメディアと組んだ「#聴くマガジン」を配信開始、「ムー」「美術手帳」「TRANSIT」のポッドキャストシリーズ開始〈Media Innovation(2020年12月14日)〉
音声メディアでの新展開。「雑誌の専門性や世界観はそのままに、ストーリーや体験を音声で提供する」とのこと。超常現象、美術、旅と、視覚に頼ることが多そうなジャンルの媒体が、音声のみでの情報発信にチャレンジというのが面白い。
NHKが公式noteアカウント立ち上げ 取材過程やノウハウ公開〈ITmedia NEWS(2020年12月14日)〉★
放送には尺があるので、使われなかった部分が膨大にあるわけですが、その「取材ノート」を「note」に公開していくとのこと。NHK公式サイトでやらないのはなぜだろう? 文藝春秋など出版社は、クリエイターの発掘を目的にしているので、クリエイターが集まる場に拠点を設けるのは合理的と思うのですが。NHKは、そういうわけではなさそう。
ヤフーがレポート発表 2020年度上半期は約1億1千万件の広告素材を非承認に〈AdverTimes(2020年12月15日)〉
8月に「2019年度は約2億3千万件の広告素材が非承認に」というレポートを初公開(↓)、今回は2回目となります。半期で1億1千万件なので、ペース的には大差ない感じでしょうか。相変わらず「ユーザーに不快感を与えるような表現」が非承認となるケースが多いようです。それにしても、運用型広告は闇が深い。
プロのマンガ家を対象にした作品募集企画がジャンプ+で〈コミックナタリー(2020年12月15日)〉★
ジャンプ+の新企画。応募資格は「Webを含む商業誌で過去に読み切りが掲載された、もしくは連載を経験した作家」。つまり、主に他社から作家を奪おうとしている、ということになるでしょう。猛烈に儲かっているいまこそ、攻めの姿勢で積極的に。弱肉強食です。
日本最大の個人向けPOD出版販売サービス「ネクパブ・オーサーズプレス」がKindle電子書籍の取扱いを開始〈株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース(2020年12月15日)〉
いままでPODだけだったネクパブ・オーサーズプレスに、Kindleでの販売支援サービス「ネクパブ電子出版」が追加されました。ロイヤリティは販売価格の40%で、他店での展開も可能。マルチストア展開している場合のKDPは35%ですから、それより好条件。マジか。ヘルプなど一通り目を通した限りでは、PODでは対応している「支払額の分配」機能が現時点では無さそうなのがちょっと残念ですが。
電子ブックを誰でも無料で制作・閲覧できるプラットフォーム「VOUTIQUE(ブティック)」〈MdN Design Interactive(2020年12月15日)〉
新しいセルフパブリッシング・プラットフォーム。とはいえ、いまのところ販売には対応していないようです。試してみたんですが、選択できるカテゴリーが「BEAUTY」「LIFE STYLE」「TRIP」「FASHION」のみと、ちょっとおしゃれな感じの、ページめくりに対応した「デジタル・パンフレット」の作成サービスという感じ。これ、どうやってビジネス化するんだろう?
日経電子版、エキスパートによる解説投稿機能「Think!」を開始〈Media Innovation(2020年12月16日)〉
専門分野のエキスパートがニュースの解説を投稿という、まるで「NewsPicks」の向こうを張ったような新サービス。ジャーナリストの池上彰氏、ジャパネットたかた創業者の高田明氏、ライフネット生命保険創業者の出口治明氏、弁護士・福井健策氏といったそうそうたる顔ぶれは、さすが日経。無料会員だと、どんなコメントが書かれているのか、確認すらできないのがちょっと残念。気になるじゃないか! 思うつぼ?
著作権法における図書館関係の権利制限規定の見直しに関するパブリック・コメントへの意見の提出について〈国立国会図書館―National Diet Library(2020年12月16日)〉
国立国会図書館が意見提出。入手困難資料についてのみで、複写サービスの公衆送信対応については触れられていないのが、おや? という感じでした。いいのか。範囲が法令上明確化されると柔軟な運用が損なわれ送信対象が現状よりも狭まってしまう可能性の懸念と、逆に、ストリーミングのみ対応でプリントアウトまで認めることへの懸念が表明されてます。
これ、前者はともかく後者については、ストリーミング配信でもスクショは撮れるし、ブラウザの機能で印刷できますし。正直、そこ制限する意味あるのか? という感じが。なお、パブリックコメントの実施期間は12月21日までです。まだ間に合いますよ。
電子書籍の利用実態調査、2人に1人が利用経験あり、電子書籍に使うお金は0円が最多。よく利用するサービスは「Kindle」「LINEマンガ」(おたすけスマホ情報サイト「Appliv TOPICS」調べ)〈ナイル株式会社のプレスリリース(2020年12月16日)〉★
Applivの調査って私は初めて見たんですが、「無作為に選出された」という一言がちゃんと添えられていることに好感が持てます。いや、こういう調査で無作為抽出って本来なら当たり前の話ではあるのですけど、そうじゃないアンケートも結構多いので。
利用している電子書籍サービスの上位は、Kindle、LINEマンガ、楽天Kobo、ピッコマ、めちゃコミック、ジャンプ+の順。インプレス「電子書籍ビジネス調査報告書2020」(↓)では、Kindle、LINEマンガまでは同じですが、次いでピッコマ、ジャンプ+、楽天Koboの順で、めちゃコミックはもっと下位である点が違い。まあ、傾向的には似てますが。
メディアドゥ 集まったレビューを冊子に、第1弾くすのきしげのり特集〈文化通信デジタル(2020年12月16日)〉
NetGalleyに投稿されたレビューを集めた小冊子を制作し、無料配布するという新企画。作品の認知向上はもちろんですが、電子ゲラ公開というサービスの認知向上や投稿意欲向上など、さまざまな波及効果がありそうです。良い企画ですね。
国会図書館図書のデジタル化、補正予算60億閣議決定!視覚障がい者にも多くのメリット(後編)〈山田太郎(ヤマダタロウ)|選挙ドットコム(2020年12月16日)〉
国立国会図書館所蔵資料のデジタル化は、2000年以降年間1~2億円で推移していたのが、民主党政権期の2009年に総額127億円という膨大な予算が計上され、一気に進んだ経緯があります。
自民党政権になってふたたび1~2億円で推移していたのが、今回の山田太郎参議院議員の提案により、どーんと60億円あまりの補正予算が閣議決定されたとのこと。これは喜ばしい。
今後、入手困難資料の家庭配信が始まったときに、1968年までのラインアップと、2000年までのラインアップでは、インパクトが大きく異なりますもんね。楽しみです。
TikTok、人生を変えた本やおすすめしたい本の紹介動画を募集する「#本の紹介」を 12/16から開催! 出版社社員によるおすすめの1冊も紹介!〈Bytedance株式会社のプレスリリース(2020年12月16日)〉
面白い企画。TikTokで本を紹介する動画が増え、『あの花が咲く丘で君とまた出会えたら』(スターツ出版)や『桜のような僕の恋人』(集英社文庫)など、TikTokをきっかけに販売部数を伸ばした本も複数出現しています。1分のショートムービーというのがポイントなんでしょうね。
大修館書店、大学向け電子教科書配信サービス「eTextbooks.jp」を4月から提供開始〈ICT教育ニュース(2020年12月18日)〉
紙の教科書同様、大学の書店で購入し、シリアルコードを「eTextbooks.jp」に入力すると、閲覧が可能になる、という面白い仕組み。リアル書店への強い配慮を感じます。ブラウザビューア対応ですが、iOS / Androidアプリも提供予定とのこと。どこの仕組みだろう?
KADOKAWA松原社長「出版拠点を集約 制作コスト減」〈日本経済新聞(2020年12月18日)〉
松原社長インタビュー。気になるのは「M&A(合併・買収)も検討する。同業者を買収して規模を広げる~」のくだり。文脈的には映像部門の話っぽいのですが、出版部門の話でもあると思うので。これまでもアスキー、メディアワークス、エンターブレイン、中経出版、メディアファクトリー、汐文社など、積極的にM&Aしてきてますからね。
遠隔授業での著作物利用、21年度以降は有償に〈読売新聞オンライン(2020年12月18日)〉
授業目的公衆送信補償金の額が文化庁に認可されました。ちょっと不穏な動きを耳にしたので心配していたのですが、これで一安心。今後も関係者協議は続くと思いますが、粘り強く取り組んで欲しいと思います。
ちなみに個人的には、授業の資料には著作権法第35条の権利制限を極力使わないようにしています。ただ、授業でYouTube動画を見せる(公衆伝達行為)のを、4月の改正法施行以降は無許諾で堂々とやれるようになったのは、授業の幅を広げる意味で大きいかも。授業目的でも、従来は許諾が必要だったのですよね。
「鬼滅の刃」ヒット桁違い 経済波及効果2000億円超〈日本経済新聞(2020年12月19日)〉★
コラボ商品の売上などの分析。ダイドーの缶コーヒーが15倍、丸美屋食品工業のレトルトカレーは57倍と、凄まじい伸びです。いやあ、ほんと凄まじい。
海外
ビッグ5からビッグ4へ、米大手出版社が巨大化する理由とは〈HON.jp News Blog(2020年12月16日)〉
おなじみ、大原ケイさんによる解説。アマゾンと価格交渉するため、というのは以前から挙げていただいていることではありますが、巨大化した結果失われるもの、という観点も重要と感じました。
「武漢支援日記」が日本で出版、コロナ禍の最前線で奮闘した中国女性医師の記録〈AFPBB News(2020年12月17日)〉
4月に馬場公彦さんに寄稿いただいた「共感を呼び称賛された『武漢日記』が一転、海外版の翻訳出版で批判と中傷に晒されたわけ」(↓)の最後で、「ぜひ翻訳出版に漕ぎつけてほしい」と言及されていた『查医生援鄂日记(査医師の武漢救援日記)』が、10月に日本で『武漢支援日記』として翻訳出版されていました(この記事で気付いた)。版元は岩波書店です。なるほど古巣。
ネット文学の網にかかった中国の若者たち――その巨大な収益モデルを探る〈HON.jp News Blog(2020年12月18日)〉
馬場公彦さんに次のテーマをリクエストして欲しいと言われ、ぜひ中国の投稿サイト(網絡文学)事情について深掘りして欲しいとお願いして書いていただいたコラム。おかげさまでたくさんの方に読まれています。反響を見ていると、読者による検閲システムというのが、結構衝撃的だったようですね。
「大きすぎる」GAFAはなぜ目の敵にされるのか?(平和博)〈Yahoo!ニュース個人(2020年12月18日)〉
アメリカの巨大IT企業がここ最近、各国から次から次へと規制対象にされようとしている状況の丁寧なまとめ。日本でも、ヤフーや楽天を含めた規制が動こうとしてますからね。「規模には責任が伴う」という言葉には、首を縦に振るしかない。
ブロードキャスティング
12月20日のゲストは人狼伝道師の眞形隆之さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本について掘り下げました。番組のアーカイブはこちら。
12月27日は年末特番として、フリージャーナリストの西田宗千佳さんをゲストに迎え、2020年を振り返ります。今回はYouTube Liveの配信のみで、どなたも無料で閲覧できます。チケットの入手は不要です。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。