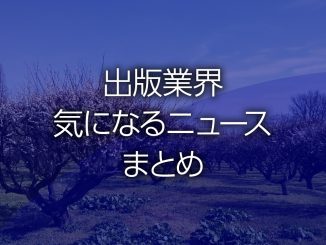《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
HON.jp News Blog 編集長の鷹野が、2018年の元旦に個人ブログで書いた出版関連動向予想を検証しつつ、2018年を振り返ります。
【目次】
年初にはこんな予想をしていた
まず、私が年初に予想していた2018年の動きについて。挙げたのは以下の5つです。
- 雑誌の人材がウェブへ流れる動きが加速する?
- デジタルファーストが拡大する?
- 大手企業を核とした業界再編(離合集散)が進む?
- 出版での FinTech 活用が進む?
- ドメスティックな産業からの脱却(コンテンツ輸出)が進む?
雑誌の人材がウェブへ流れる動きが加速した?
出版科学研究所発表の出版物推定販売額と、電通が毎年2月に発表している「日本の広告費」を合わせて考えると、増え続けているインターネット広告媒体費は、減り続けている雑誌販売と雑誌広告の合計売上を、2016年の時点で逆転しています。今後もその傾向は変わらず、さらに差は広がっていくことが予想されます。お金のあるほうへ人が移動していくのは自然なこと。そういう動きが2018年は加速していくだろう、と。
実際のところ、人の動きが個別にニュースになるようなケースは少ないので、正直、加速しているかどうかの判断は難しいところ。ダイヤモンド・オンラインで10月に配信された「朝日新聞から次々流出!新旧メディアの人材流動化マップ」という記事では、朝日新聞だけでなく、読売新聞・毎日新聞・産経新聞・中日新聞や、フジテレビ、講談社、週アス(KADOKAWA)など、いわゆるレガシー(伝統的)メディア全般からウェブメディアへの人材流出が起きていることを図示しています。本誌にはもっと詳しい特集が載っており、レガシーメディアとウェブメディアの年収格差など、なかなかシビアな側面も見て取ることができます。
目立った動きとしては、名作マンガ『うしおととら』初代編集担当の武者正昭氏が、小学館から「comico」へ電撃移籍して編集長へ就任したことが挙げられます。武者氏が登場する『読者ハ読ムナ(笑)~いかにして藤田和日郎の新人アシスタントが漫画家になったか~』を直前に読んでいたこともあり、なんてタイムリーなんだろうと驚愕しました。また、元『現代ビジネス』編集長の瀬尾傑氏が、スマートニュースでメディア研究所の所長に就任したことも、トピックスとして挙げられます。
デジタルファーストは拡大した?
雑誌のウェブ化、あるいは、ウェブの雑誌化という傾向は数年前からすでに顕著ですが、この予想は、次は「書籍」だ、というもの。「パッケージの無料化」ではなく「初出がデジタルメディア」という想定でした。たとえば2017年9月に、新潮社とYahoo!Japanがタッグを組んで上田岳弘『キュー』をウェブで無料連載するプロジェクトが始まりましたが、同じような事例がもっと増えてくるであろう、と。
実際のところ、マンガ誌が紙を休刊しウェブマガジン化することで、結果的にデジタルファーストが実現される事例は頻発した1年でしたが、残念ながら「書籍」については予想していたより動きが目立たなかったように思います。ただ、文系研究者向け出版支援サービス「アスパラ」と、理系研究者向け出版支援サービス「近代科学社DIGITAL」のような動きがあったことは特筆すべきでしょう。どちらもインプレスR&Dの「NextPublishing」を核として展開されており、PODによる紙の出版と電子出版がセットになっています。
縦書き表示が可能なブログサービス「g.o.a.t」と小学館「小説丸」が連携し、白河三兎のミステリー小説『無事に返してほしければ』を発売前後に無料公開したり、伽古屋圭市『冥土ごはん 洋食店 幽明軒』から「別れのライスオムレツ」を先行公開したりといった事例もありました。しかしこれは「初出がデジタルメディア」というより、「パッケージの無料化」と言ったほうがよさそうです。なお、前述の『キュー』は2018年5月に完結したのですが、本稿執筆時点でまだ書籍化されていないという、なんだかもったいない状態に留まっています。
マンガについては、講談社「コミックDAYS」の定期購読プランや、集英社「ジャンプ+」が広告収益のマンガ家還元開始など、IT企業に対する大手出版社の「逆襲」と言っていいような動きの目立つ1年でした。講談社「DAYS NEO」は当メディアでも何度か取り上げていますが、単なる投稿サイトではなく編集者とのマッチングが主眼に置かれている点が非常に興味深く、開始から7カ月で連載決定14人など、実際に結果も出ている点を高く評価したいです。また、Twitterなどで無料公開、話題になったのち出版社から声がかかり単行本化、という流れがもはや「普通」のことになったようにも思います。
大手企業を核とした業界再編(離合集散)は進んだ?
企業の集合離散を想定していたのですが、むしろサービス終了や事業継承が目立つ1年でした。主な動きをざっと列記します。リクルート「ポンパレeブックストア」が終了し、ユーザーはメディアドゥ「スマートブックストア」が引き継ぎ。「eBookJapan」が全面リニューアルされ、「Yahoo!ブックストア」の統合が発表。「読書メーター」のトリスタが、ドワンゴからブックウォーカーにグループ内移管。トーハン「Digital e-hon」のサービス終了。ネット書店「honto」が大日本印刷本体に吸収。「マンガ図書館Z」のJコミックテラスを、メディアドゥホールディングスが子会社化。「楽天マンガ」と「コミック★まんが学園」がメディアーノへ事業売却。「ニコニコ書籍」が「BOOK☆WALKER」へ統合。「日経ストア」が今年の夏でサービス終了を発表。電子書店「BookPlace」が「U-NEXT」へ統合、などです。
また、ブックオフがヤフーとの資本提携を解消(業務提携は継続)したり、2大取次の日販とトーハンが物流連携の検討を開始したりといった動きも話題になりました。
出版での FinTech 活用は進んだ?
FinTechは、金融: Finance と、技術: Technology を組み合わせた造語です。ブロックチェーン技術を活用した動きが、出版にも波及してくるという予想でした。実際のところ、仮想通貨取引所からの巨額流出が相次ぎ、金融庁が立ち入り検査を行うなど、引き締める動きは目立ちました。
また、仮想通貨相場が下落し続ける中、GMOやDMMがマイニング(採掘)事業から撤退するというニュースも流れました。そういう状況もあってか、残念ながら出版への波及はほとんど見られませんでした。今後は、ブロックチェーン技術が投機の対象から外れ、「技術の活用」という本来の方向へ動くことになるでしょう。
QR決済は「PayPay」など巨額のポイント還元が話題になりましたが、参入企業が多すぎて乱立気味になっているあたりが気がかりです。もっとも、QR決済がポイント経済圏の延長上にある「顧客の囲い込み手段の1つ」であると考えると、書店も今後は無関係ではいられないでしょう。導入コストも決済コストも圧倒的に低いという点は、小売店側にとって大きなメリットです。
ドメスティックな産業からの脱却(コンテンツ輸出)は進んだ?
人口減の国内マーケットだけを対象にしていては先細る一方ですから、生き残るためにはコンテンツの輸出は必然と言っていいと思うのですが、こと出版に関しては、私のアンテナにはあまり動きが引っかかってきませんでした。そんな中で、ポプラ社の絵本が中国で爆発的に売れているというのは明るいニュース。
その他の大きな動き
「その他」と言いつつ、むしろこちらが本編かもしれません。とてつもなく大きな動きが、いくつも起きた1年でした。
―― この続きは ――
《残り約1500文字》