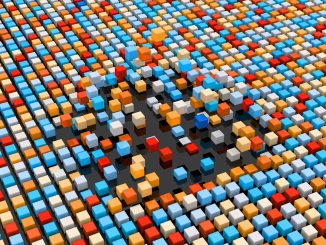《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
新年あけましておめでとうございます。
2019年も HON.jp News Blog をどうぞよろしくお願いいたします。
毎年恒例、編集長 鷹野凌による出版関連の動向予想です。
【目次】
2018年の予想と検証
2018年年初の予想は以下の5つ。自己採点の結果を右端に付けておきました。
- 雑誌の人材がウェブへ流れる動きが加速する? → △
- デジタルファーストが拡大する? → 〇
- 大手企業を核とした業界再編(離合集散)が進む? → 〇
- 出版での FinTech 活用が進む? → ×
- ドメスティックな産業からの脱却(コンテンツ輸出)が進む? → △
検証の詳細は、大晦日の記事をご覧ください。過去の予想と検証は、以下の通りです。
2018年概況
出版科学研究所が年末に発表した2018年の紙の出版物推定販売額は1兆2800億円台、コミックスを含む雑誌は5800億円前後、書籍は6900億円前後で、書籍と雑誌の販売額差は1000億円超にまで広がっています。雑誌のピークは1997年の1兆5644億円なので、約3分の1に。書籍のピークは1996年の1兆0931億円なので、約3分の2になっています。また、返品率は1月から11月の累計で書籍が36.4%、雑誌が44.1%です。
なお、ここまでの数字は紙のみで、電子出版の数字は加味されていません。出版科学研究所推計の2018年電子出版市場は、例年通りなら1月25日ごろに発表される予定です。参考までに、2017年の電子コミックは1711億円、電子書籍は290億円、電子雑誌が214億円でした。
2017年は紙のコミックス(単行本)が1666億円だったので、コミックスは紙と電子がついに逆転した、というのが大きな話題となりました。2018年の増減額はまだわかりませんが(こちらは2月25日ごろ発表予定)、さすがに2018年時点ではまだ、紙のコミックス+コミック誌の販売額のほうが、電子コミック+電子コミック誌の販売額より大きそうです。
マクロ環境分析
こういった現状を踏まえた上で、今度は2019年以降の出版を取り巻くマクロ環境を、PEST分析してみることにします。
政治的環境(Political)
- TPP11関連の改正著作権法施行(2018年12月30日)
- 柔軟な例外規定など改正著作権法施行(2019年1月1日)
- 学校教育法など一部改正で、デジタル教科書併用開始(2019年4月)
- マラケシュ条約批准、読書バリアフリー法制定?
- 改元、平成の終わり(2019年5月1日)
- 参院選(2019年7月)
- 消費税10%に(2019年10月1日)
- 東京都知事選挙(2020年7月)
- 東京オリンピック開催(2020年7月から8月)
- アメリカ大統領選挙(2020年11月)
- 安倍総裁任期満了(2021年9月)
- 衆議院任期満了(2021年10月)
- アメリカと中国の対立傾向
- 安倍政権のアメリカ重視方針
- 日中韓の関係冷え込み傾向
改正著作権法が1月1日に施行され、無許諾で横断検索が可能になりました。これまで個別に許諾を得ていたアマゾンの「なか見!検索」や「Googleブックス」や「BOOK☆WALKER」の「本文から検索」をチェックしましたが、1月1日からいきなり全書籍が横断検索の対象に、なんてことは、いまのところ起きていないようです。今後の動向を注視しておきたいところ。
今年の政治動向で最重要なのは、7月の参院選でしょう。この結果次第で、改憲発議が行われる可能性があります。そこへ向けて改憲議論が本格化し、関連書籍も多く発行されることでしょう。なお、改憲には両院で3分の2以上、国民投票で過半数の賛成が必要です。10月1日に予定されている消費税率10%への引き上げや、それに伴う軽減税率適用開始などがどう影響するか。また、東京オリンピックへ向け、表現規制への圧力がますます強くなることも予想されます。
経済的環境(Economic)
- 2018年末世界同時株安の影響
- 消費税10%に(2019年10月1日)
- 東京オリンピック開催(2020年7月から8月)
- 物理メディア販売ビジネスの縮小傾向
- 伝統的出版市場(とくに雑誌)の縮小傾向
- 電子出版市場(とくにマンガ)の拡大傾向
- インターネット広告市場の拡大傾向
- 物流コストの上昇傾向
- 同人誌市場の拡大傾向
- サブスクリプションの拡大傾向
昨年末にアメリカ発で発生した世界同時株安。東京オリンピックへ向けて行われてきた都市開発や投資の終焉。そこへ消費税10%という冷や水がかけられ、今後の景気がどうなるかとても気がかりです。物理メディアの縮小傾向と、電子メディアの拡大傾向は今後とも続くでしょう。
社会的環境(Social)
- 小中高校でデジタル教科書併用開始(2019年4月)
- 少子高齢化傾向
- 生産年齢人口の減少傾向
- 日本語人口の減少傾向
- 教育予算の減少傾向
- 外国からの労働者受け入れ拡大へ
- 排外主義の高まり
昨年末に可決された改正出入国管理法により、外国人労働者の受け入れ拡大が確定しました。農業、漁業、介護、建設、造船、宿泊、外食、航空、自動車整備など14業種が、特定技能1号の対象になっています。在留期間の上限は通算5年ですが、高い専門性を有すると認められた者については在留期間上限なしへの移行措置が整備される予定になっています。関連して、日本語教育や母国語書籍への需要が高まることなどが予想されます。
技術的環境(Technological)
- Windows 7の延長サポート終了(2020年1月)
- 第5世代移動通信システム(5G)のサービス開始(2020年春)
- QRコード決済など少額決済手段の普及
- デジタル化、ネットワーク化、モバイル化のさらなる進展
- アドブロックの普及傾向
- AIによる自動着色技術の飛躍的進歩
- ブロックチェーン、機械学習、VR / AR技術 …… etc.
現行のLTEの100倍の転送速度を実現すると言われている次世代型移動通信システム5Gは、2019年にプレサービス、2020年には商用サービスが始まる予定です。2019年時点での直接的なインパクトは薄いと思いますが、なにかと話題になることが多い年になると思います。
QRコード決済はすでにちょっと乱立気味ですが、導入コストも決済コストも圧倒的に低いため、小売店側にとって大きなメリットです。ポイント経済圏の延長上にある「顧客の囲い込み手段の1つ」であると思われるため、いずれ大手に収束していくものと思われます。
仮想通貨市場は、2018年に相次いだ不正流出事件で見事に冷え込んでしまいましたが、投機対象から外れただけで、ブロックチェーン技術の可能性は今後も模索され続けるものと思われます。
また、改正著作権法の柔軟な権利制限規定により、書籍横断検索サービスや、機械学習用のデータなど、著作物を無断で利用できる範囲が広がった点も、技術的なブレイクスルーを生み出すかもしれません。
2019年には何が起こる?
これらを踏まえた上で、2019年にはどんなことが起こるか、予想してみました。以下の5点です。
- メディア自体の信頼度がより一層問われるようになる
- 既刊も含めた書籍の電子化率が高まる
- マンガ表現の多様化が進む
- 学校や図書館向けの電書供給が本格化
- オーディオブック市場の拡大が本格化
―― この続きは ――
《残り約3800文字》