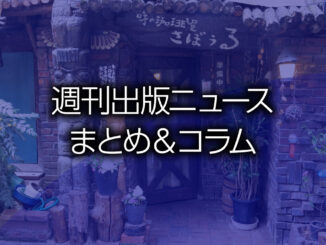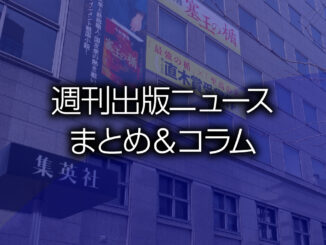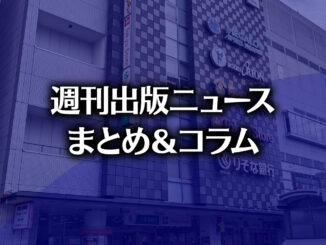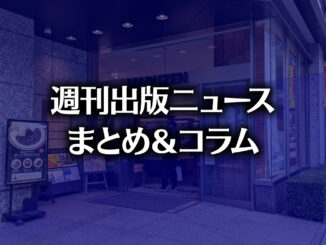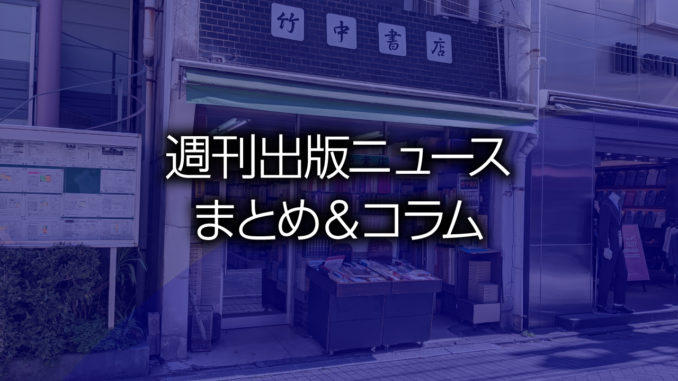
《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
2021年4月11日~17日は「パンデミック後のアメリカはどうなる?」「スローニュース瀬尾社長インタビュー」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 大胆な本音と、濃いコミュニティ。「メディアは不要」の時代に成長中、KAI-YOU Premiumのサブスク戦略を聞く〈Media × Tech(2021年4月13日)〉
- Amazon Announces Its Wattpad-Style ‘Kindle Vella’ Platform〈Publishing Perspectives(2021年4月14日)〉
- 出版社と書き手が報われる場所を提供する――調査報道サブスク「SlowNews」瀬尾傑社長インタビュー〈HON.jp News Blog(2021年4月15日)〉
- マンガアプリ・マンガBANG!が新レーベルを創刊、本日単行本4冊発売〈コミックナタリー(2021年4月15日)〉
- 技術
- HON.jp News Casting
- メルマガについて
政治
パンデミック後のアメリカから出版の将来図を読み解く〈HON.jp News Blog(2021年4月13日)〉
アメリカ巨大IT企業の労使問題や独占禁止法問題が、パンデミックが収まったあとどうなっていくのか? を大原ケイさんに解説いただきました。巨大IT企業に対抗して、出版社も巨大化を図ろうとしているけど、当然どちらの動きにも締め付けがある、と。バイデン政権に変わって、上下院とも民主党がギリギリ多数派になったので、政治的な動きは早くなるかもしれません。
なお、アマゾンの労組結成は、ロイターの表現を借りると「複合要因で圧倒的な敗北」に終わっており、「逆に、労組運動が直面する長年の課題を浮かび上がらせた」結果になっているようです(↓)。むう。
社会
意外と知らない…空前の「ショートショートブーム」が起こっている「これだけの理由」(飯田 一史)〈現代ビジネス(2021年4月13日)〉
飯田一史さんによる「短い小説」の動向まとめ。「5分後」シリーズって、朝読のニーズに合わせたフォーマットだったんですね。知らなかった。以前、作家の藤井太洋さんから「商業で短編を発表する場が減ってきている」という話を伺ったのを思い出しました。もちろんTwitterや投稿サイトなど「発表する場」はいろいろありますが、直接的な対価が見込めないので持続可能性が低い、という。なかなか悩ましいところです。
「物語」を作り出す出版創作企画「ノベルジャム」が初の地方開催、地域の新たな文化活動の場を目指して(江口晋太朗)〈Yahoo!ニュース個人(2021年4月14日)〉
敬和学園大学主催の「阿賀北ノベルジャム」が無事終わったことを受け、アドバイザーとして入っていた江口晋太朗さんによる総括記事です(HON.jpの元理事で、NovelJam立ち上げの中心人物の一人でもあります)。デジタル時代において、地域の創作活動をどう育んでいくか。インフラは整いつつあるものの、まだ「紙」での出版への意識が強い地域で、どうやったら作品の認知を高め流通促進できるか。個人的には、図書館など行政との連携という方向性もあるのかな、と思っています。
横浜市立図書館が「電子書籍」サービスを開始。横浜市在住者が試してみた〈ハーバー・ビジネス・オンライン(2021年4月16日)〉
TRC-DLを導入した横浜市立図書館電子書籍サービスを、在住者が実際に試してみたレポート。好感触のようですね。全国的にもコロナ禍以降急激に導入数は増えてますが、私の居住自治体(練馬区)はまだ。はよはよはよはよ!(バンバンバンバンAA略)
経済
大胆な本音と、濃いコミュニティ。「メディアは不要」の時代に成長中、KAI-YOU Premiumのサブスク戦略を聞く〈Media × Tech(2021年4月13日)〉
スマートニュースの「Media × Tech」ブログによる、カイユウ代表 米村智水さんへのインタビュー。「ゆくゆくは KAI-YOU.netでもアドネットワークをやめたくて」という部分に強い共感。うちは一足先にやめました。小さくて濃いメディアを台頭させましょう!
Amazon Announces Its Wattpad-Style ‘Kindle Vella’ Platform〈Publishing Perspectives(2021年4月14日)〉
アメリカのKDP限定で、新サービス「Kindle Vella」が開始されるという予告が出ています。短いエピソードを連載形式で公開していくという形式。ユーザーは先のエピソードをトークンを買って読む形になっており、50%は著者に入るようです。
記事のタイトルに“Wattpad-Style”とあるように、カナダの「Wattpad」対抗と受け止められているようです。日本にもいずれ展開されるかも? 英語ができる方は、さっさと英語圏向けに参入してしまうというのも手かもしれません。
イメージ画像には、1.99ドルで140トークンなどの記述が見えます。ただ、1トークンでどれくらい読めるのか? といった詳細はまだ不明です。ちなみに以前、北京大学・馬場公彦さんにレポートいただいた中国のウェブ小説「網絡文学」では、「1元(約15.8円)が100コインで章ごとに10コインほどが課金される」(つまり1章あたり1.58円)という情報がありました(↓)。
出版社と書き手が報われる場所を提供する――調査報道サブスク「SlowNews」瀬尾傑社長インタビュー〈HON.jp News Blog(2021年4月15日)〉
出版ジャーナリスト成相裕幸さんに取材・レポートいただきました。ノンフィクション記事特化型の会員制サービスですが、主なターゲットは「普段ノンフィクションを読まない人」なのですね。独自開発の縦横切り替えられるビューアは、なかなか使い勝手が良いです。これ、外部提供してもらえないかしら?
マンガアプリ・マンガBANG!が新レーベルを創刊、本日単行本4冊発売〈コミックナタリー(2021年4月15日)〉
Amazia の運営する「マンガBANG!」連載作品からの新レーベル。単行本は一二三書房からの発売です。以前、菊池健さんに解説いただいた「オリジナルIPを持つ」段階に入ったということなのでしょう(↓)。
ところで一二三書房って昨年、モバイルコンテンツプロバイダ エディアの完全子会社になっていたんですね(↓)。見落としてました。買収などの再編例として、脳内メモに加えておきましょう。
技術
「進研ゼミ」の編集を完全デジタル化、ベネッセが挑む千人のオンライン作業 – 深掘り先進事例〈日経クロステック Active(2021年4月12日)〉
ベンチャー企業が開発したクラウド型の編集ツール「Brushup」を、段階的に導入する計画で2020年初めから動いていたところに緊急事態宣言。すぐに導入する形へ切り替えたという、すごいタイミングの貴重な話がレポートされています。校正記号をオンラインで入力できる機能まで追加開発したとか。結果、「紙をやり取りするために出社する必要がなくなった」そうです。会員限定ですが、登録は無料なのでぜひ。
書店でNFT活用の“デジタル付録”集英社や角川など〈Impress Watch(2021年4月12日)〉
3月に発表されたトーハンとメディアドゥの資本業務提携で、メディアドゥのプレスリリースには「NFTを活用した事業」が真っ先に挙げられていることに#466で触れましたが、その続報です。講談社、集英社、小学館、KADOKAWAがこの仕組みを活用した施策の検討を開始しているとのこと。販売コンテンツそのものではなく、デジタル付録からやるというのは、NFTの特性をよく理解しているように感じます。さすが。
NFTのピークは過ぎ去ったのか?少数のアプリケーションに依存するNFT市場、その分析データを公開【ブロックチェーン講座】〈INTERNET Watch(2021年4月13日)〉
そのいっぽうで、アート分野でのNFT市場は、すでに取引量が減少傾向にあるとのこと。異様な盛り上がりは、特定のプラットフォーム上に限った現象だったようです。まあ、バブルですよね。数量限定とはいえコピーは防げないので、本のように「内容を楽しむ」コンテンツの「海賊版を防ぐ」用途には使えないはずなのです。
NFTの本当の可能性は「8月12日の三河屋のコーラ」にあり〈ITmedia NEWS(2021年4月16日)〉
上記とも関連しますが、ちょうどいいタイミングで西田宗千佳さんによる詳しい解説記事が出ました。先週(#468)、GMOのNFT事業参入のリリースについて、「NFTでコピーそのものが防げるわけではないので、アピールするポイントが若干ズレているような……?」と書きましたが、ぼくも数量限定のサイン入りデジタルコンテンツみたいな用途には可能性を感じているのです。「本物のサインである」というメタデータが、改竄不能な形で記録されるわけですから。
HON.jp News Casting
4月12日のゲストは後藤亨真さん(コトニ社代表・編集者)さんでした。番組前半の部のアーカイブはこちら。
次回のゲストは和泉佳奈子さん(株式会社百間代表・角川武蔵野ミュージアム館長補佐)さんで、「角川武蔵野ミュージアム」と「松岡正剛さん」をテーマにお届けします。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。