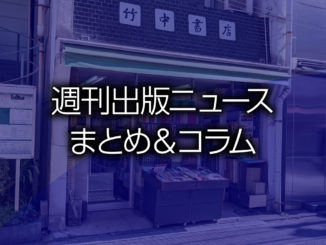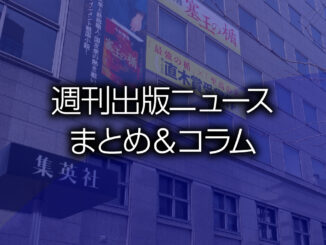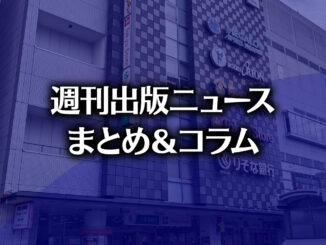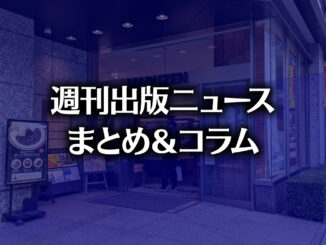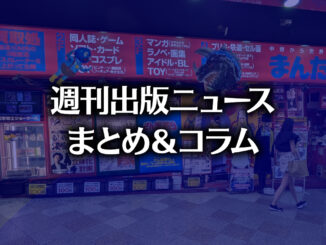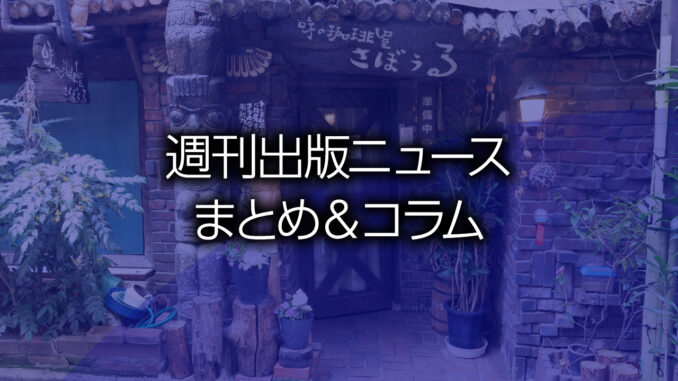
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2022年9月11日~17日は「図書館蔵書が書店販売に与える影響」「n次創作とブロックチェーン」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
FC2で無修正売った男性、前代未聞の刑事裁判で「わいせつ」の意味を問う「モザイクないだけで違法はおかしい」〈弁護士ドットコム(2022年9月14日)〉
控訴審での訴え。無修正の映像や画像がインターネットで国境を越えて簡単に見つけられる時代に「その時代の健全な社会通念」の判断が変わっていないのはおかしい、という主張は正論だと思いますが、なかなか裁判では認められません。
また、“刑法175条1項は「表現の自由」を侵害して、違憲である” という主張は、過去には「チャタレー判決」や「四畳半襖の下張」事件など、最近では「ろくでなし子裁判」などでも繰り返し争われてきましたが、最高裁判所は一貫して認めていません。まあ、今回も恐らく難しいでしょう。
とはいえ、この男性の言う “警察のさじ加減一つで逮捕されてしまう” 状況が恐ろしいのも事実。根本的には、誰の権利を侵害しているわけでもないのに表現の自由を規制できてしまう刑法175条の存在が歪なわけで。なお、山田太郎議員や赤松健議員は参院選前に「刑法175条は見直しが必要」と明言していますが、時間かかりそう。
ステマ規制も視野に 消費者庁、第1回ステマ検討会〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年9月16日)〉
#537 でもお伝えした、ステマ規制の検討会議が始まりました。残念ながらこちらは傍聴できなかったのですが、弁護士の壇俊光さんが「実態として日本はステマヘイブン(規制回避地)となっており、グローバル企業にとって、ステマの刈り取り場になっている。些細な例外を弄し、定義を考えていたら2年も3年もかかる。実効性のある規定を早急に設けるとともに、制度のらん用を防ぐ仕組みを考えたい」とおっしゃっていたようで、頼もしい限りです。
報道資料|「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会 現状とりまとめ」及び意見募集の結果の公表〈総務省(2022年9月16日)〉
パブコメも終わり、反映された「現状とりまとめ」も公開されました。こちらの検討会は傍聴できたのですが、Cloudflare社から「当社は、現状とりまとめ案において、Cloudflare のサービスの性質および影響について、誤解や事実とは異なる点が複数あると認識しております。」とパブコメでかなりの文量の反論が寄せられており、現状とりまとめ(案)の段階ではそれを「指摘」として反映した状態になっていました。
インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第10回)配布資料〈総務省(2022年9月15日)〉
ところが、複数の構成員から「そんな誤解は含まれていない」「そんな注記は要らない」「そもそも利用者が規約を守っていないことが問題」「個人情報の収集範囲を必要最低限に限定する原則には反しません」「法的手続きに則らないと情報を返さないのは誤った対応」「Cloudflare社の意見はパブコメの時点で新たに出てきた情報であり、検証できないから“指摘”というより“主張”では?」など、Cloudflare社の意見の影響を極力減らす方向で修正が施されることになりました。
個人的には、確定版のp34「CDNサービスに関する今後の取組の方向性」注59、田村構成員から指摘されている法律的観点が重要だと感じています。Cloudflare社が著作権侵害の悪用を防止する措置を取っていない場合、著作権法47条の4第1項「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」に該当しうるのではないか? というものです。
今年の2月に出版大手4社がCloudflare社を提訴しましたが、恐らくそういう方向で攻めるのが有効、ということなのだと思うのですよね。まだ本件は続報がないんですが、どうなってるんだろう?
社会
※デジタル出版論の連載は今週もお休みしました。
公共図書館での貸出が近隣の書店での同タイトルの書籍の売り上げをどの程度減らすか(文献紹介)〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年9月13日)〉
先週、大きな話題になっていた記事。公共貸与権のない日本で、図書館蔵書が書店販売にどれくらいの影響を及ぼすか? を調査した論文です。図書館蔵書数はカーリルのデータ、ベンチマーク書籍リストは紀伊國屋書店のベストセラーランキング(2014年から2016年の各年50点×3で雑誌・コミックは除く)、そして、書籍の販売データは「大手卸売業者2社のうち1社から提供」されたとあります。
記事には「ベストセラー本では1か月あたり0.52部」の売上を置き換えているとあり、反響でもその是非を論じているものが多いようです。実際の論文を参照してみたところ、ベンチマーク書籍リストの上位6分の1は月平均0.24部減少させているが、他のタイトル(つまり残りの6分の5)では無視できたとありました。つまり、図書館の蔵書により販売に悪影響が出るのは、紀伊國屋書店の年間ベストセラーランキング上位1桁クラスに限られる、と考えていいでしょう。
また、図書館での蔵書数は、ベンチマークリスト全体では平均0.132冊(購入してない図書館のほうが圧倒的に多い)に対し、ベストセラーは平均2.02冊とあります。つまり、端的に言えばやはり「複本購入が悪影響を与えている」ということなのでしょう。その影響はベストセラーで「1か月あたり0.52部」ですから、全国3280館とすると最大で年間約2万部くらいの減少要因になっている可能性があります。
この結論から公共貸与権を設計するとしたら、複本購入から補償金が発生するような形が合理的でしょうか。論文に課題として挙げられているとおり、もう少し長期のデータで検証してみたいところではあります。
経済
「ザ・ニューヨーカー」DXで稼ぐ 特集「出版不況をぶっ飛ばせ」 土方奈美〈文藝春秋digital(2022年9月11日)〉
こちら、無料部分もけっこう長いのに、ここから先は有料の時点で残り4000字超というボリュームです。無料部分だけでも面白く、すごいなあ……と思いつつ、続きを読むには定期購読以外ないのがちょっと辛い。この記事1本に100円くらい払うのはぜんぜん惜しくないんですけど、記事売り設定がないのですよね。いきなり月額900円を要求されるのはさすがにハードルが高い。noteだから記事売りもできるはずですが、あえてやっていないということなのでしょう。むむむ。
アマゾン、第11世代「Kindle」「Kindleキッズモデル」–ストレージは2倍、解像度は3倍〈CNET Japan(2022年9月13日)〉
最廉価モデルなのに、ストレージが16GBに、解像度が300ppiに、USBポートがType-Cに変わった……のはいいんですが、広告ありモデルでも1万円超え。円安ぅ……。
ニュース:日印産連、日本経済新聞に意見広告-価格転嫁への理解求める〈PJ web news【印刷ジャーナル】(2022年9月14日)〉
エネルギーや原材料の価格高騰などの影響で、印刷価格への転嫁が避けられないことへの理解を求める意見広告。すでにかなりの大幅値上げが始まっていて、重版するのをためらうような声も散見されます。このままだと今後、絶版(あるいは品切重版未定)となる本が増えてしまうだろうという観測も。
ちょうど同じようなタイミングで英語圏でもこんなニュースが。
Print price hikes force deeper focus on digital revenues | What’s New in Publishing〈Digital Publishing News(2022年9月12日)〉
要するに、印刷価格の上昇は日本だけでなく世界的な情勢なのです。パブリッシャーは収益確保のため、ますますデジタル事業へ注力する流れになってる模様。一般向けには電子版が中心で、紙の本は高級品・嗜好品・贅沢品という扱いになっていくのでしょう。
技術
古文書を解読できるスマホアプリ 凸版印刷が開発 くずし字対応AI-OCRを活用〈ITmedia NEWS(2022年9月13日)〉
新開発の古文書対応AI-OCRで、手書きと木版印刷それぞれに対応し、解読率は90%とのこと。達筆な文書は「この字が読めん」というのが人間でもふつうにありそうですから、なかなかのものではないかという気がします。なお、ちょうど1年前に、タイ出身の日本古典文学研究者が開発した「みを」というアプリがありましたが、データセットは同じ国文学研究資料館のものです。
サービス停止中のイラストAI「mimic」が不正対策を発表 審査設け10月に再開〈KAI-YOU.net(2022年9月14日)〉
#536 でピックアップした、サービスを一時停止した「mimic」の続報です。事前審査を導入し、自分でイラストを描いていると判断できたアカウントのみ利用できる形になるそうです。また、学習に利用されたイラストおよびmimic作成したイラストは透明性確保のため、透かしを入れたうえで公開が必須となります。
これで懸念されていた不正利用はかなり難しくなったのではないかと思われます。純粋に、イラストレーターのためだけのサービスになった感。当初は感覚的・感情的な反発によって炎上していたように見えましたが、今回の改善はおおむね好意的に受け止められているようです。文句を言ってるのは少数派で、外野だけっぽい。
「二次創作」描く巨大市場 DNPなど、テックで実証実験〈日本経済新聞(2022年9月17日)〉
正規に許諾を得た記録をブロックチェーンに残し、n次創作でも原著作者に収益分配という動きです。「ニコニ・コモンズ」の「コンテンツツリー」を外部に開いたようなイメージで、個人的にはわりと筋が良いほうの部類だと思いました。
ところが、権利者サイドで強い嫌悪感を示す方が何人も観測されています。ちょっと意外。まあ、NFT界隈で悪さをするところがあまりに多いので、クソもミソもみんな同じに見えてしまうのも無理はない、とも思いますが。この日経の記事も、冒頭で「デジタル技術で不正利用を防ぐ仕組みができた」と書いてしまうあたりは、いささか筋が悪い。
この場合の「不正利用」は無許諾での利用を指すと思うのですが、ブロックチェーンにDRMのようなコピーを防ぐ機能はありません。ブロックチェーンに記録された利用がシロで、第三者でもそれが判別できるのは確かですが、それ以外はせいぜい、疑わしい、可能性がある、くらいのグレーゾーンでしょう。なにをもって「不正利用を防ぐ」と言っているのか。
それはさておき、本件の座組みで言うと、3社のうちDNPは出版社がお得意様で、エイベックスは権利者サイドなので、あまり心配は要らないでしょう。ただ、GMOペパボに関しては……うーん、GMOがNFTマーケットへ参入する前に、あたかも違法コピーを防げるかのようなミスリードを誘っていたので、悪いけど正直、ちょっと不安要素です。
【NFTの凄さ】
インターネットの著作権管理の主流は、今までDRM(コピー防止)だった。
本に例えると読者は「読む権利」の購入をしていた。
NFTを使えば本そのものの「所有」が叶う。
そして、読み終わった本を中古本として売ることもできる。
— 熊谷正寿【GMO】🇺🇦STOP WAR🇺🇦 (@m_kumagai) April 10, 2021
ただ、「Adam byGMO」が開始したころには「所有できる」などの危ない言い回しは避けるようになっていたので、軌道修正が図られたようではあります。とはいえ、NFT界隈にはあまりにクソが多いので、どうしてもシビアな目で見たくなるのは避けられません。それは、当初のオーバートークを呪ってください。自業自得です。
これもさておき、記事の後半では、弁護士の出井甫さん(骨董通り法律事務所 for the Arts / 2020年5月から内閣府知的財産戦略推進事務局の参事官補佐)が「権利者としては作品の利用を許諾しても、それが適切に使われているのか常時管理するのは難しく、容易に許諾を出しにくい。利用促進を検討する際には権利者にも配慮することが重要」とコメントしています。
つまり、二次利用促進と同時に、権利者にも適切な対価還元がなされるべきだと。この記事で紹介されているのは、方向性としてはそういう仕組みです。私見ですが、恐らく、知的財産推進計画に基づき文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会で検討が進められている「簡素で一元的な権利処理と対価還元の制度化」に繫げようとしているのではないかと。
記事後半にチラッと出てくる一般社団法人JCBI(ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ)には、DNPやエイベックスも参加しています(GMOは未参加っぽい)し、政府検討会のヒアリングにも何度も呼ばれてます。有象無象とは異なり至極まっとうなことを言ってますから、クソと一緒にするのはちょっと可哀想かなあ。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
本稿執筆時点で、大型で非常に強い台風14号が九州に上陸。気象庁からは「これまでに経験したことのないような暴風や高波、高潮となるおそれ」と最大級の警鐘が鳴らされています。みなさまくれぐれもご注意ください(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。