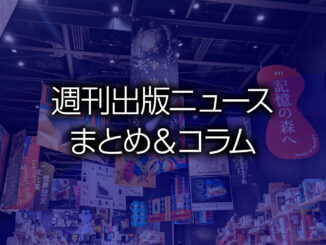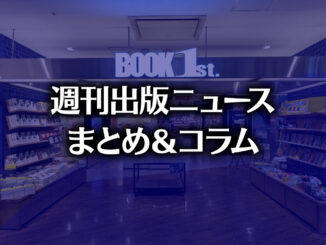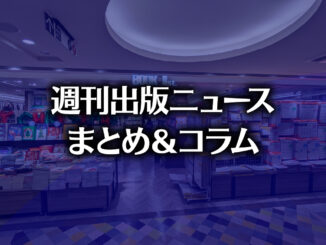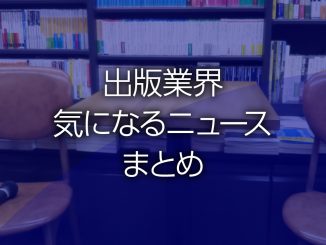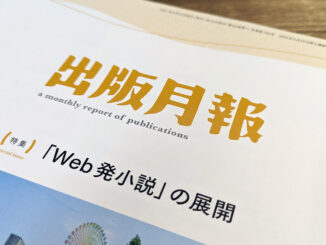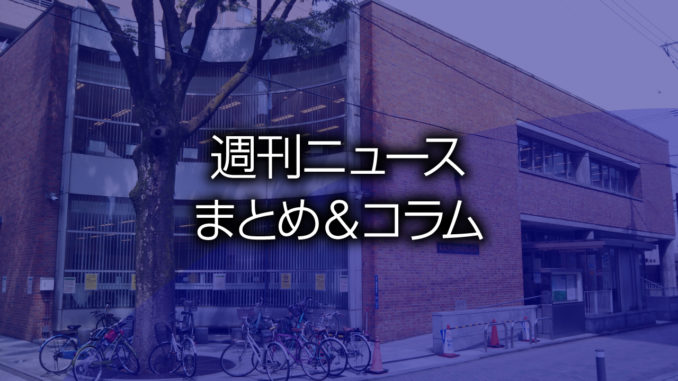
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2020年10月25日~31日は「コロナ禍で18歳前後の読書量増」「ぶんか社買収と電子コミック業界の成熟&再編」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- コロナ禍で読書量増が24% 17~19歳、日本財団調査〈共同通信(2020年10月26日)〉★
- 文化庁、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第4回)」の議事次第・配布資料を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2020年10月26日)〉
- 日本出版者協議会、アマゾンに抗議・要望書を提出…返品の質の悪さと量の多さに関して改善要望〈Media Innovation(2020年10月26日)〉★
- オープン前すでに圧巻 隈研吾氏デザインの巨大本棚に本3万冊を収納中 角川武蔵野ミュージアムの本棚劇場〈埼玉新聞(2020年10月27日)〉★
- オトバンク、約450作品が最大50%オフになるオーディオブックフェス〈マイナビニュース(2020年10月27日)〉★
- 民衆・大衆の姿を残し、伝え、使うために ―― 大宅壮一文庫の持続可能な存続に向けて〈HON.jp News Blog(2020年10月28日)〉
- 『鬼滅の刃』がランキング上位を席捲!映画も歴史的大ヒット 週間コミックランキング(2020年10月19日~25日)〈ほんのひきだし(2020年10月28日)〉★
- 【10月28日付社説】読書週間/本と向き合う時間つくろう〈福島民友新聞(2020年10月28日)〉
- 子の学び支える学校図書館 現役司書が語る役割と本音|WOMAN SMART〈NIKKEI STYLE(2020年10月28日)〉
- ぶんか社グループ買収に見る電子コミック業界の成熟と再編 ―― プラットフォームビジネス成長の3ステップとオリジナルIP制作〈HON.jp News Blog(2020年10月29日)〉
- KADOKAWA、2Q(4~9月)は売上高2%減ながら営業益は22%増で過去最高に 緊急事態宣言解除後も電子書籍やゲームなどコンテンツに根強い需要〈Social Game Info(2020年10月29日)〉
- 公文書の読点「,」から「、」に 半世紀以上前の通知変更へ〈共同通信(2020年10月30日)〉
- pixiv投稿作品がマンガ動画に! ピクシブが公式YouTubeチャンネル「コミティブ(COMITV)」開設〈ピクシブ株式会社のプレスリリース(2020年10月30日)〉
- 紙を買うと電子がもらえる。紙と電子書籍のハイブリッド体験「ニコニコカドカワ祭り2020」開催中!!〈株式会社KADOKAWAのプレスリリース(2020年10月30日)〉
- 11月1日は本の日。本屋さんに行ってみませんか?〈BOOKウォッチ(2020年10月31日)〉
- 海外
- ―メディアの課題8― 広告・課金そして寄付 メディアは非営利組織へ〈DG Lab Haus(2020年10月27日)〉
- 米上院公聴会にIT大手3社CEO、法改正の本題離れ政治論争に〈ロイター(2020年10月29日)〉
- GAFAとBATHが注目される理由とは?成長の秘訣を徹底解説〈Digital Shift Times(2020年10月30日)〉
- GAFA、3社が最高益 新型コロナ、際立つ好業績〈共同通信(2020年10月30日)〉
- アプリ手数料に経営リスク 米アップル、年次報告書で指摘〈共同通信(2020年10月31日)〉
- 米大統領選に向けたSNSでの“情報工作”の抑止策には、「インフルエンサー」という盲点がある〈WIRED.jp(2020年10月31日)〉
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
コロナ禍で読書量増が24% 17~19歳、日本財団調査〈共同通信(2020年10月26日)〉★
30回目となる日本財団の18歳意識調査は、「読む・書く」がテーマでした。「コロナ禍の影響で読書量は増えたか?」という問いに、「変わらない」が69.1%と最多で、「増えた」は24.9%、「減った」は6.0%という結果でした。まあ、多少なりとも増えたという実感がある若者のほうが多いなら、ヨシとすべきか。詳細は日本財団のリリースにて(↓)。
個人的には、月1冊以上読む人に対する「本をどの媒体で読んでいますか?」という問いに、「紙」が67.6%、「電子書籍」が5.9%、「どちらも活用している」が26.4%という結果が興味深いです。というのは、日本財団のこの調査では「本」にマンガやラノベも含まれる(除かれているのは雑誌のみ)のですが、他社の調査では、高校生・大学生のマンガアプリ利用率は6割近い数字が出ているのです(↓)。もちろん調査方法は異なるわけですが、それにしてもあまりに差が大きい。この違いは何なのか。
文化庁、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第4回)」の議事次第・配布資料を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2020年10月26日)〉
第4回目も傍聴、実況ツイートしました(↓)。これまでの議論については、#437まとめ、#439まとめ、#442まとめ、#445まとめなどをご参照ください。
事務局から冒頭、31条「図書館等」に学校図書館を含めるかどうかについて、関係者間で意見の相違があり、話し合いが行われているという通知がありました。日本図書館協会によると「含めることは望まない」と反対しているのは、全国学校図書館協議会(全国SLA)とのこと(↓)。根拠がよくわからないため、メール取材を申し入れました。現在、回答待ちです。
本件、今回のワーキングチームでは「3. 主体となる図書館等の範囲」で議論されましたが、事務局の叩き台は「必ずしも全ての図書館等において送信サービスを実施するニーズがあるわけではない」となっていました。これを受けた委員の意見は、そもそも送信主体となる側には大きな義務が課されることになるのだから、対象は自ずと絞り込まれる、というもの。「なるほど!」と目を開かされました。学校を含めるか否かの議論を、はるか上空で飛び越えていった感があります。
設備面では、パソコンや通信環境以外にスキャナも必要であること。また、流出防止措置を講じられる知識を持ったスタッフも必要であること。補償金制度が入るならその運用も必要になること。そしてそもそも、これらのハードルを乗り越える「意欲(≒ニーズ)」があるかどうか。確かに、国立国会図書館の「図書館送信」でさえまだやっていない公共図書館のほうが多数派なので、より難易度が高いと思われる複写サービスの公衆送信化に対応できるところがどれだけあるか。
とはいえ、そもそも対象になってなかったら、やりたいと手を挙げることも叶わないわけで。だから恐らく、31条「図書館等」に学校図書館を含めるよう著作権法施行令を改正することは前提としつつ、設備や人員・技術面などソフトローでのハードルによって絞り込む方向で着地するのではないかと。次回のワーキングチームは11月9日。事務局からまとめ案が提示される予定です。
日本出版者協議会、アマゾンに抗議・要望書を提出…返品の質の悪さと量の多さに関して改善要望〈Media Innovation(2020年10月26日)〉★
本件、某メーリングリストでは8月中旬くらいから「急に返品が増えた」と話題になり、関連して「e託で返品時の本の扱いが雑過ぎる」といった声が複数挙がっていました。クレームを入れたらちゃんと損失補填されたという報告もあったのですが、10月15日に出版協から抗議のリリースがあり、なぜか10月24日にバズって騒ぎが広がり、ニュースとしても取り上げるメディアが出てきた、という流れ。雑返品のクレームにはちゃんと応じているようなので、むしろ話題から消えてしまった「急に返品が増えた」ことのほうが問題ではないか、とも思うのですが。
オープン前すでに圧巻 隈研吾氏デザインの巨大本棚に本3万冊を収納中 角川武蔵野ミュージアムの本棚劇場〈埼玉新聞(2020年10月27日)〉★
なにげなくツイートしたら、意外と多くの反響が返ってきた記事。高所作業車を使ったインパクトのある絵に対し、素直に「すごい!」という声や、「見世物本棚」と揶揄する声や、高所にある本はどれくらいの頻度でメンテナンスするのか? という疑問など。ちなみにこの記事には書かれていませんが、プレスリリースには「グランドオープン後、 随時見直しを行い、 開架に置かれた図書も変化していきます」とありました。
オトバンク、約450作品が最大50%オフになるオーディオブックフェス〈マイナビニュース(2020年10月27日)〉★
42の出版社と連携した、過去最大規模のキャンペーンとのこと。今年は「神保町ブックフェスティバル」が中止になってしまうなど物理的に会う機会が減ってしまったので、「耳で聴く本」の会社としてなにかしたいと企画をしたそうです。オトバンクの企画者インタビューはこちら(↓)。
民衆・大衆の姿を残し、伝え、使うために ―― 大宅壮一文庫の持続可能な存続に向けて〈HON.jp News Blog(2020年10月28日)〉
メールマガジンARGにクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY)で掲載されていたコラムを、転載しました。故・大宅壮一氏の「重要か重要でないかは、だれが決めるんだね?」という言葉は至言。
『鬼滅の刃』がランキング上位を席捲!映画も歴史的大ヒット 週間コミックランキング(2020年10月19日~25日)〈ほんのひきだし(2020年10月28日)〉★

まさに席巻。22巻まででているコミックが、22位までを独占しています。思わず笑ってしまった。23位は『ありふれた職業で世界最強』7巻で、次いで24位にはまたしても『鬼滅の刃』21巻の特装版がランクインしています。もうね、お見事としか言えない。
【10月28日付社説】読書週間/本と向き合う時間つくろう〈福島民友新聞(2020年10月28日)〉
読書週間系の記事はシェアしておこうと目を通して、「気がかりなのは、子どもの読書量の減少だ」という記述にガクッとしました。続いて「県教委の調査によると、1カ月に1冊も本を読まない生徒の割合が、中学生の2割弱、高校生の4割強に上る」とありましたが、それは現在の値であって、「減少」していることは示していません。
こういう「若者の読書離れ」的な論説を見かけるたびに、全国学校図書館協議会と毎日新聞社共同調査の「学校読書調査」を参照しています(↓)。長期傾向は真逆で、20世紀の若者と比べたら、いまの若者の平均読書冊数は「増えている」し、不読者の割合は「減っている」のですよね。
つまり、問題とすべきなのは「子どもの読書量の減少」などではなく、子供のころはたくさん読んでいるのに、年齢を重ねるごとに減っていってしまうことではないかと思うのです。高校生の不読率50%前後というのは、大人の数字とほとんど同じなのですよね。
子の学び支える学校図書館 現役司書が語る役割と本音|WOMAN SMART〈NIKKEI STYLE(2020年10月28日)〉
学校司書の方々へのインタビュー。とくに後半の、非正規雇用が多いこと、民間委託だと指揮系統に難があること、他の教員が司書との良い協働体験があるかどうかにも依ることなどが、学校図書館の現状を考える上でのヒントになるように思います。この記事で触れられていないこととしては、司書教諭との違い、でしょうか。
ぶんか社グループ買収に見る電子コミック業界の成熟と再編 ―― プラットフォームビジネス成長の3ステップとオリジナルIP制作〈HON.jp News Blog(2020年10月29日)〉
漫画の助っ人マスケット合同会社代表の、菊池健氏に解説いただきました。電子コミック配信プラットフォーム勃興期のオリジナルIP(知的財産権)確保の動きと、最近の出版社買収の動きは、意味合いが異なるとのこと。いまは3段階目で、自社商品開発期、すなわち回収フェーズであり、「小売業のプライベートブランド(PB)に近い」という見解にはなるほど、と思いました。さすが。
KADOKAWA、2Q(4~9月)は売上高2%減ながら営業益は22%増で過去最高に 緊急事態宣言解除後も電子書籍やゲームなどコンテンツに根強い需要〈Social Game Info(2020年10月29日)〉
上半期決算。電子書籍・電子雑誌は、第1四半期に続いて、第2四半期でも四半期過去最高売上を更新したそうです。すげぇ。
公文書の読点「,」から「、」に 半世紀以上前の通知変更へ〈共同通信(2020年10月30日)〉
文化審議会国語分科会国語課題小委員会で2016年から議論されてきた「新しい公用文の作成の要領に向けて」の中間報告案が固まったというニュース。「やっとか!」という声をたくさん観測できました。中間報告案によると、テンマルだけでなく、今後は必要に応じて「!」や「?」も用いる、日本人の姓名ローマ字表記は「姓-名」順に表記するなど、多くの箇所に「新」マークが付いています。なお、「法令も広い意味では公用文の一部」だけど、「本報告では法令を直接の対象とはしない」そうです。詳細は文化庁の資料を参照。
pixiv投稿作品がマンガ動画に! ピクシブが公式YouTubeチャンネル「コミティブ(COMITV)」開設〈ピクシブ株式会社のプレスリリース(2020年10月30日)〉
本稿執筆時点でストレートに記事化した事例を見つけられないので、プレスリリースをピックアップ。マイシアターD.D.株式会社との提携で、pixivに投稿された未商業のオリジナル作品を「コミティブ」運営スタッフがスカウトし、作者と協力して声優録り下ろしのセリフや音声を加え、マンガ動画として新たに展開する試みとのこと。効果音だけではなく、声も付くのがすごい。すごいコストかけてる。収益化できるのかな? 関連して、こんな面白記事もありましたので紹介しておきます(↓)。
紙を買うと電子がもらえる。紙と電子書籍のハイブリッド体験「ニコニコカドカワ祭り2020」開催中!!〈株式会社KADOKAWAのプレスリリース(2020年10月30日)〉
こちらも本稿執筆時点で記事化事例を見つけられないので、プレスリリースをピックアップ。こういう試み、新しいものは久しぶりに見た気がします。調べてみたら、昨年3月に扶桑社「ESSE」紙版の購読者特典で電子版が無料配信、という試みを記事化していました(↓)。
ちなみに同様のサービスである文教堂「空飛ぶ本棚」は、今年の1月にサービス終了しています。会員登録時にメールアドレス情報を渡したはずなのですが、終了の案内メールは届いておらず、hontoへの移行期間が終了した後に偶然気付いたという……トホホ。試しにいくつか入手していたはずなのですが、電子の藻屑と消えました。
11月1日は本の日。本屋さんに行ってみませんか?〈BOOKウォッチ(2020年10月31日)〉

1並びが本棚に並ぶ背表紙ということで、2018年に新しく設立された記念日。一般社団法人日本記念日協会の認定です。公式サイトはこちら。
海外
―メディアの課題8― 広告・課金そして寄付 メディアは非営利組織へ〈DG Lab Haus(2020年10月27日)〉
編集長 北元均氏による連載8回目。アメリカの話ですが、もともと営利目的の新聞社が、非営利団体化する動きが目立つようになってきているとのこと。広告やコンテンツ課金以外に、寄付や助成金を資金源とするというもの。ウチはもともと非営利ですが、収入モデル的には同じところが多いので、興味深い記事でした。PV競争になる運用型広告はやめましたし、だからといってコンテンツ課金には踏み切れない。となると、会費や寄付で購うしかない、という感じです。
米上院公聴会にIT大手3社CEO、法改正の本題離れ政治論争に〈ロイター(2020年10月29日)〉
今度は、通信品位法230条の改正を巡る公聴会。問題のあるコンテンツが投稿されても、プラットフォームはパブリッシャーではないので免責されるという法律。トランプ大統領が「廃止すべきだ!」と大統領令に署名までした、そしてバイデン候補も廃止すべきと言ってる法律です。FacebookとGoogle、そしてTwitterのCEOが呼び出され(オンラインですが)詰問されています。さてこちらは選挙後、どうなるか。
GAFAとBATHが注目される理由とは?成長の秘訣を徹底解説〈Digital Shift Times(2020年10月30日)〉
中国の巨大IT企業、Baidu(バイドゥ)、Alibaba(アリババ)、Tencent(テンセント)、Huawei(ファーウェイ)の4社の頭文字をとって、「BATH(バス)」と呼ぶそうです。なるほどいつの間にこんな新語が。
GAFA、3社が最高益 新型コロナ、際立つ好業績〈共同通信(2020年10月30日)〉
前四半期はAlphabet(Google)が減益でしたが、こんどはAppleが減益。iPhone 12発売前の買い控えが影響とのことです。
アプリ手数料に経営リスク 米アップル、年次報告書で指摘〈共同通信(2020年10月31日)〉
そのAppleが年次報告書で初めて、アプリ決済の手数料が問題視されていることを「経営リスク」に挙げたそうです。下げざるを得なくなるかもしれない、という投資家に向けた前フリといったところか。
米大統領選に向けたSNSでの“情報工作”の抑止策には、「インフルエンサー」という盲点がある〈WIRED.jp(2020年10月31日)〉
政治広告が規制されたことを受け、フォロワー数1万人未満の「ナノインフルエンサー」が選挙運動に利用されている、という指摘があるそうです。ステマで偽情報というか、薄謝でサクラというか。とてもじゃないけど把握し切れなさそう。
ブロードキャスティング
11月1日のゲストは漫画家でDomixプロデューサーの樹崎聖さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本について掘り下げました。
次回のゲストは漫画家コミュニティー・コミチ代表の萬田大作さんです。ZoomではYouTubeへのライブ配信終了後、オンライン交流会を開催します。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。