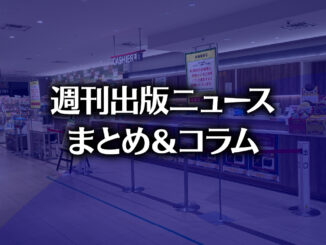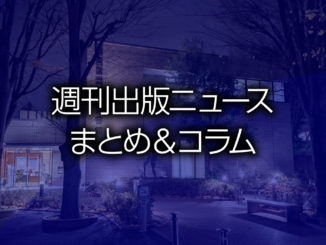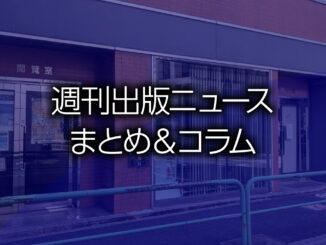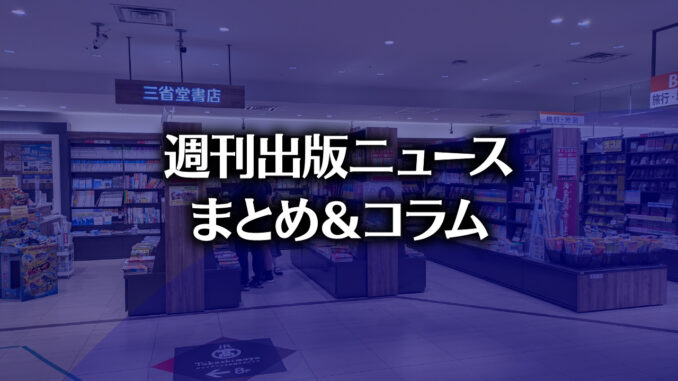
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2025年2月9日~15日は「週刊ダイヤモンド、編集ミスで書店販売を中止」「アメリカ地裁でAI学習のフェアユースを認めない判決」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 出版不況に「超豪華な無料雑誌」京都で爆誕のワケ 紙にこだわる大垣書店が勝算見込んだ本屋の未来 | 街・住まい〈東洋経済オンライン(2025年2月11日)〉
- 電子版「薔薇族」、Amazonで販売中止 「ポリシーにそぐわない」とアカウント即時停止に〈ITmedia NEWS(2025年2月10日)〉
- noteとTales & Co.、物語投稿サイトを今春始動〈CREATIVE VILLAGE(2025年2月12日)〉
- 電子書籍貸し出す「電子図書館」2026年度中にも県内全域で導入 先行の新潟市除く29市町村共同、サービス開設へ準備〈新潟日報デジタルプラス(2025年2月14日)〉
- メディアドゥ連結子会社(株式会社エブリスタ)の異動に関するお知らせ〈株式会社メディアドゥ(2025年2月14日)〉
- 週刊ダイヤモンド、最新号の発売取りやめ フジ関連アンケ結果に誤植〈毎日新聞(2025年2月15日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
E2768 – Internet Archiveのデジタル貸出を巡る著作権訴訟の経緯〈カレントアウェアネス・ポータル(2025年2月13日)〉
この判決、ちょっと誤解していました。Controlled Digital Lending(CDL)のフェアユースが全面否定されたわけではなく、「電子テキスト形式でのライセンスが提供されている書籍をデジタル貸出の対象とした場合」についてのみ否定されたのですね。市場で競合しない場合については、グレーゾーンのまま。
もしそのあたりをInternet Archiveがちゃんと厳格に運用していたら、裁判所の判断は変わったかもしれません。まあ、やはり同時アクセス制限を外してしまったNational Emergency Library(NEL)が「虎の尾を踏んだ」のでしょう。
ちなみにこれ日本では、国立国会図書館が入手困難資料のスキャン電子版を個人送信または図書館送信で提供するサービスをやっていますが、電子版やPOD版が販売していて入手可能なら送信対象外になります。市場と競合しないことがちゃんと考えられた制度になっているのです。
出版者には年1回、これから送信対象になる予定のリストが送られてきます。そこで「これは電子版を売ってます!」とあらかじめ除外する申請ができます。また、いちど送信対象になっても、あとから電子版の販売を始めた、あるいは、これから販売を始める予定の場合も、申請して除外することが可能です。つまり日本はこの点、かなり白黒はっきりしている運用になっています。
制度の検討段階で、朝日新聞が「図書館の本、スマホで閲覧可能に」などと若干ミスリード気味な記事を出したときはどうなることかと心配しましたが、入手困難資料の送信サービスはしっかり制度設計され、しっかり運用され、多くの方に活用され、喜ばれるサービスになっていると思います。良かった。ただ、複写サービスのFAX・メール対応のほうは……紆余曲折あって、今年になってようやく運用が始まりますが、補償金の高さが普及へのネックになりそう。
対AI企業の著作権訴訟でトムソン・ロイター側が勝利。AI訓練目的での「フェアユース」認められず〈WIRED.jp(2025年2月13日)〉
いろいろと激震が走りそうな判決が。アメリカの著作権法に特有な「フェアユース」規定には4つの要件がありますが、そのうち2つでトムソン・ロイターの主張が認められ、とくに「市場価値に及ぼす影響」が大きいとの判断だったそうです。まだ地裁判決ではありますが、負けたのはスタートアップ企業で、長期間の法廷闘争を戦い抜く体力がないとも言われています(もうサービスを止めている)。
ただ、この判決だけで「アメリカではAI学習にフェアユースは100%認められない」とするのは、いささか早計な判断でしょう。前出のInternet Archiveの事例にあるように、裁判所の判断はちょっとした条件の違いで変わる可能性があります。今後、OpenAIやMicrosoftなど大手の裁判がどうなるか。もし大手も負けるようだと、みんなこぞって著作権法第30条の4がある日本へ来るかも?
第3回構想委員会 議事次第〈知的財産戦略本部(2025年2月14日)〉
「知的財産推進計画2025」に向けた検討について、パブコメ結果や日本新聞協会の主張などの資料が公開されています。「IPトランスフォーメーション(2)」という資料の11ページや32ページに「AI開発者側の学習用データの情報開示が進んでいないことが、適切なライセンス市場の形成を阻み、又は生成AIの利活用を躊躇させる要因との指摘もある」という記述があって、なるほどと思いました。そういう方向での法規制はあり得るかも。日本新聞協会の資料4ページにもその指摘があります。
ちなみに、日本新聞協会の資料は「構成員限り」としている箇所が多くて、少しモヤッとします。以前「有料会員限定のコンテンツをもとに、回答を生成」などと事実誤認の可能性が高い主張をしていたこともあるので、あまり隠さないで欲しいなあ。主張の正しさが検証できないではありませんか。なお、この「有料会員限定のコンテンツをもとに、回答を生成」という主張はそのとき限りで、以降は消えています。
社会
版元ドットコム会員社の電子書籍に関して調べてみました〈版元ドットコム(2025年2月13日)〉
これは素晴らしい調査。版元ドットコム加盟社の登録済み出版物で「結果として全体では約14%の本が電子書籍化されていることになります」とのことです。ちなみに、私と堀正岳氏の5年前の調査では、国立国会図書館への納本ベースで11.9%でした。これは電子化率の高い大手も含む全出版社(ISBN有のみ)の数字なので、恐らく中小出版者に絞るともっと低かったことが予想できます。それを思うと、14%は「多少は伸びてる」と言っていいのかも? とはいえ、いまだにこういう状況だから「なぜ中小出版社はまだ電子出版に消極的なのか?」というセッションを企画したわけですが。
マット・アルト「日本は文化戦争への備えができていない」(2025年1月23日)〈経済学101(2025年2月12日)〉
トランプ大統領就任で、日本のコンテンツ輸出が厳しい状況になるかも、という予測です。日本の状況についてはいくつか誤解もあるように見受けられますが、日本のコンテンツがビッグテックのプラットフォームでキリスト教的価値観によって判断され排除されるのは従来もあった話ですし、その傾向がトランプ氏の大統領就任でさらに強くなるかもしれないという懸念には妥当性があります。というのは、トランプ氏は「反キリスト教的偏見を根絶する」ための大統領令に署名したからです。
恐らく、日本の創作表現で引っかかるものは多いでしょう。これからコンテンツ輸出を伸ばしていこうというときに、冷水をかけられてしまうかも。あるいは、日本国内向けでも、ビッグテックのプラットフォームではいま以上に表現規制が厳しくなるかもしれません。「リベラルが」とか「行き過ぎたポリコレが」とか言ってる場合じゃない。ぐえぇ。
キッズたちのコミック新世紀:『BONE』と「Scholastic」が変えたアメコミの未来〈WORKSIGHT(2025年2月11日)〉
おお、これは面白い。マーベルやDCのようないわゆる「アメコミ」は、キッズ向けだと見られると売れなくなるから避けていたため、むしろキッズ向けがブルーオーシャンになっていたとのこと。キッズ向けを提供していないと、未来の顧客が増えないという話でもあるでしょう。
経済
出版不況に「超豪華な無料雑誌」京都で爆誕のワケ 紙にこだわる大垣書店が勝算見込んだ本屋の未来 | 街・住まい〈東洋経済オンライン(2025年2月11日)〉
大垣書店の「超豪華な無料雑誌」は、ビジネスモデルはどうなっているんだろう? というのが非常に気になっています。残念ながらこの記事でも明確化はされていませんでしたが、書店が出版をやることにより「出版社とコラボできる」のが大きいようなので、無料配布の広報誌という位置付けなのでしょうか。それなら理解はできます。
また、この記事では最後のページで「自分で作って自分で売るほうが当然、利益率も高いですし、値段設定も自由にできます」という話も出てきます。無料雑誌の話が導入なのに、値段設定とは? どうも話が繋がっていない気がして、少し困惑しました
いや、「本が作れる本屋」というコンセプトはむしろ大賛成です。近代以前の出版社は書店も兼ねていたわけですし。メーカー直販の逆で、書店自身が製造小売をやるというのも、これからの時代に合ったやり方だとは思います。反対しているわけではありません。
電子版「薔薇族」、Amazonで販売中止 「ポリシーにそぐわない」とアカウント即時停止に〈ITmedia NEWS(2025年2月10日)〉
本件の反響で、トランプ大統領によるDEI推進プログラム廃止と結びつけるような意見も散見されていますが、まあ、あんまり関係ないと思いますよ。Amazon独占配信だったそうなのでKDPだと仮定しますが、KDPでアカウントごとBANされる事例は過去にいくつもあります。逆に、誤ってBANされた後に復活できた事例があるのも知っています。
また、最初のレビューが通って出版したあとに、第三者からの通報を受けて再審査を経てコンテンツガイドライン違反と言われることもあります。急に方針が変わったわけではなく、以前からよくある話です。その判断の是非は別として、それほど珍しいことではありません。理不尽だとは思いますが、売り手側にも扱う商品を選択する権利はあります。コンテンツの内容云々より、流通チャネルを限定するリスクが顕在化した事例でしょう。
noteとTales & Co.、物語投稿サイトを今春始動〈CREATIVE VILLAGE(2025年2月12日)〉
昨年5月の新会社設立からしばらく音沙汰がなかったのですが、ここへ来て「物語投稿サイト」のリリースです。新会社の設立当時、恐らくこれは「note」から「(フィクション系の)機能を切り離して独立事業化する」形になるのだろうと思ったのですが、おおむね予想通りかな? 「小説投稿サイト」ではなく「物語投稿サイト」と呼称している点もポイントです。
電子書籍貸し出す「電子図書館」2026年度中にも県内全域で導入 先行の新潟市除く29市町村共同、サービス開設へ準備〈新潟日報デジタルプラス(2025年2月14日)〉
県単位での広域連携は長野県「デジとしょ信州」という先行事例がありますが、これはどこのサービスを利用するのかな? 電流協のリストによると、現状、新潟県では「KinoDen」、新潟市では「LibrariE & TRC-DL」、三条市では「OverDrive」、燕市では「LibrariE & TRC-DL」と、けっこうバラバラです。新潟市以外がこのモデルに乗るということは……?
ちなみに先日、JDLSの説明会に参加したとき、今後「県主導の共同利用」モデルを始めるという話がありました。その共同利用モデルは、政令指定都市や中核都市は対象外といった説明もあったように記憶しています。これがその最初の事例なのか、それとも他社なのか。
メディアドゥ連結子会社(株式会社エブリスタ)の異動に関するお知らせ〈株式会社メディアドゥ(2025年2月14日)〉
メディアドゥ、電子書籍取次の取引拡大に向けた株式会社アムタスとの業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ〈株式会社メディアドゥ(2025年2月14日)〉
メールで届いたプレスリリースを見て「わ!」と声が出ました。エブリスタはもともとDeNAとNTTドコモの合弁でスタートしましたが、途中でNTTドコモが手を引き、現時点ではメディアドゥの完全子会社です。これが株式譲渡により、インフォコムのグループ会社で「めちゃコミック」を運営しているアムタスの完全子会社になります。今月末日予定です。
で、そのインフォコムは帝人グループでしたが、昨年ブラックストーンに買収されています。じつにややこしいのですが、シンプルに考えると、「めちゃコミック」を手にしたブラックストーンが、企業価値をもっと高めるため、小説投稿サイト「エブリスタ」とくっつけてシナジーを図っていく、という感じでしょうか。
昨年の「HON-CF2024」ではメディアドゥ経由でエブリスタの方に繋いでいただき、登壇いただいたばかりだったのですよね(だから驚いた)。そのとき、これまでは他の出版社やレーベルとの共同制作によるライセンス収入が多かったという話を伺っています。今後は「めちゃコミック」での直販や外販に繋げる、つまり自社でIPを持つほうの比重が高くなるのでしょうか。
週刊ダイヤモンド、最新号の発売取りやめ フジ関連アンケ結果に誤植〈毎日新聞(2025年2月15日)〉
おおおお……怖っ! 私も週刊誌を制作していた経験があるので、いろいろ思い出して背筋が寒くなりました。さすがに発売中止は経験ありませんが、少々ヤバイ誤植は何度か……。なお、タイミング的に定期購読分はもう発送したあとなので、発売中止になるのは書店売りのみです。
下山進氏の記事(AERA)によれば、書店売りは1万6862部とのことなので、掛ける定価税込780円で約1300万円の売上がダイヤモンド社と取次・書店から失われることになります。ダイヤモンド社はそれとは別に、破棄処理や広告主への損害賠償などの費用も必要になるでしょう。痛い、痛い。怖い、怖い。
技術
Amazon will stop allowing Kindle book downloads to your PC soon(アマゾンはキンドル本のダウンロードとバックアップを可能にする機能を廃止する)〈The Verge(2025年2月15日)〉
こちら、初報はGood E-Readerで見たんですが、自分がほとんど使ったことのない機能だったので、正直、いまいちピンと来てませんでした。数日後、こんどは「キンドル電子書籍リーダーはもう信用できない」なんて記事まで出てきたので、おいおいどうなっているんだ? と他メディアを調べたら、The Vergeでも報じられていたのでピックアップすることにしました。
 これは、日本語のメニュー名「ダウンロードしてUSB経由で転送」のことです。「コンテンツライブラリ」あるいは「コンテンツと端末の管理」あるいは「My Kindleページ」(ときどき呼び名が変わって表記が統一されていない)のメニューで、読み放題やお試しではなく購入した本の「その他のアクション」の中にあります。いま開いて見ると、この図のように「2月26日以降(略)ご利用いただけなくなります」という注意書きが出ます。
これは、日本語のメニュー名「ダウンロードしてUSB経由で転送」のことです。「コンテンツライブラリ」あるいは「コンテンツと端末の管理」あるいは「My Kindleページ」(ときどき呼び名が変わって表記が統一されていない)のメニューで、読み放題やお試しではなく購入した本の「その他のアクション」の中にあります。いま開いて見ると、この図のように「2月26日以降(略)ご利用いただけなくなります」という注意書きが出ます。
パソコンのブラウザで購入したのちこのメニューを使うと、azwファイルやazw3ファイルがダウンロードできます。USBケーブルでパソコンへ接続したKindle端末に、そのファイルを自分で転送することにより閲覧できる機能です。これ、わざわざUSBケーブルを使わなくても、Kindle端末にログインしていてWi-Fiが繋がる状態なら直接ダウンロードできるんですよね。だから私は、ほぼ使っていない機能でした。
ただ、自分で改めて試してみて「あーなるほど」と思ったのですが、ダウンロードしたファイルを保存しておけば、なにかあったときのためのバックアップになるわけです。これはGood E-Readerの「もう信用できない」記事でも言及されていますが、Amazonは2009年に「無断販売の可能性がある」と販売停止した作品を、購入したユーザーのライブラリから遠隔操作で無断削除し大炎上した事件を起こしています。これがいまだに尾を引いているのでしょう。つまり、バックアップ保存する手段がなくなってしまうから「もう信用できない」と言っているわけです。
ただ、これはなにもKindleに限った話ではなく、クラウド本棚にDRMで縛っている電子書店、つまり大半のところでは同じことが言えます。日本でもちょうど先週、Yahoo!IDがいきなり停止され「ebookjapan」で買った1000冊超が使えなくなるという事件が起きています。こちらは幸い、消費生活センターに相談しつつ粘り強くやり取りを重ねることにより、半月ほどで復旧できたようです。
クラウド本棚は非常に便利ですが、アカウントを止められる、あるいは、サービス終了などにより、アクセスできなくなる弱点があります。利便性の裏にはそういうリスクがあるのも事実です。「結局、物理メディアが最強」という声はもう飽きるほど目にしてきましたが、物理メディアには置き場に困るとか中身が検索できないといった不便さがあります。まあ、どっちも一長一短ありますよね。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』が各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
陽気に誘われ近所を散歩していたら、たぶん梅だと思いますが、咲き始めているのを見つけました。もうすぐ春だなあ……いや、まだ2月中旬だよな? さすがにちょっと早くないか?(鷹野)