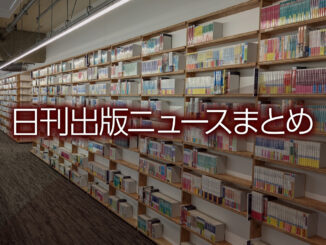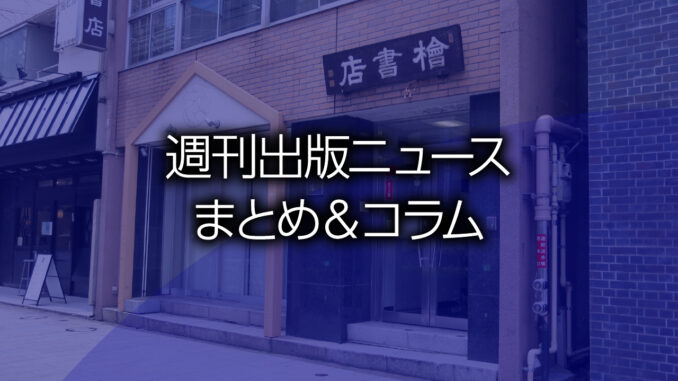
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年12月25日~2023年1月7日は「2022年回顧と検証」「電子納本制度開始」「バーンズ&ノーブルが復調、攻勢へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
総合
2022年出版関連動向回顧と年初予想の検証〈HON.jp News Blog(2022年12月31日)〉
毎年恒例の回顧と検証です。前回(#552)の配信直後から書き始めたのに、いろいろ手こずって結局公開できたのは大晦日の夜でした。なんとか年は越さずに済んだ、くらいのギリギリ感であります。余裕持って取り組んだはずなのにどうしてこうなった。文字数や脚注の数など我ながらちょっとおかしな量になっていますので、時間があるときにじっくりご覧ください。
「全部入りメディア」メタバースとAIの普及が進化を促進?・・・2023年のメディア業界展望(10)〈Media Innovation(2023年1月6日)〉
2022年回顧と2023年展望記事は年末年始にたくさん出ていますが、私の書いたもの以外では、コンテンツジャパン・堀鉄彦氏によるこちらをお薦めしておきます。私はメタバース系をあまり追っていないので、補完する意味でも。
政治
苦情・紛争解決でAmazonに課題も…経産省、透明化法に基づく評価公表〈通販通信ECMO(2022年12月23日)〉
経済産業省が「特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律」(透明化法)に基づき、アマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、Apple(iTunes)、Googleの取り組み評価結果を公表しています。今回が初めてなのですね。経産省の公開ページはこちらです。
「苦情・紛争」の件数はアマゾンが突出して多いとか、「取引拒否」についてもアマゾンにもっと丁寧なコミュニケーションを要望していたりとか、「返品・返金」でも海外勢3社の課題が指摘されていたりとか、アプリストアの手数料にも競争が十分に働いていない、などなど、巨大ECモールに対し経産省が相当な指導を行っているようです。やるじゃん!
これを受け、違法品等の取り締まりを強化したプラットフォームで、真面目にやってる業者が誤爆を食らっているケースもある、という話も目にしました。ちょっと現場で混乱が起きているのかも。とはいえ、これで取引の透明性とか公正性が図られるのであれば、総合的には良い方向へ進むのではないかと。
権利不明著作の二次利用促進、23年法改正めざす 文化庁〈日本経済新聞(2022年12月26日)〉
本欄でも何度かお伝えしてきた「簡素で一元的な権利処理方策」などが、年末に開催された文化審議会著作権分科会法制度小委員会にて報告書案がまとまったのを受けての報道です。すでに意見募集(パブコメ)も開始されています。
前回(#552)取り上げた際に「影響が大きいのはどちらかというと、(意思表示をする)習慣のなかったUGC、個人の作品ということになりそう」と書いたためか、勝手に利用されてしまうことを懸念する声も散見されました。警戒する気持ちはわかります。ただ、こういう制度がない今でも、悪党は勝手に利用してますよね。
本制度の場合、利用するには「使用料相当額に当たる利用料を(窓口組織に)支払う」ことが要件になっています。つまり、本当はちゃんと対価を払って利用したいのに連絡がつかない(意思が確認できない)場合を想定した制度なのです。むしろ、真面目にちゃんとやりたい人を対象とした制度と言っていいのでは。
そのうえで、いままで事前に意思表示をするような習慣のなかった個人クリエイターにも、簡単に意思表示ができるような仕組みをプラットフォーム側が用意することで、意識改革や利用促進を図っていけるのではないかなあ、と。個人的には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのような事前意思表示がもっと広がって欲しいと思っていますので。
ステマを不当表示に指定 23年秋ごろ施行へ、消費者庁〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2022年12月27日)〉
スケジュール感が明らかに。法改正ではない(内閣総理大臣による指定)ので、国会審議は要らないのですよね。あとは、公聴会の開催、消費者委員会の諮問・答申と、周知期間が必要となるそうです。意見募集結果の公示もすでに行われています。
なお、規制対象は「広告主」です。じゃあ、広告主が海外事業者の場合はどうなるんだろう? と思って調べてみたら、日本の消費者に被害が及ぶ場合は、海外事業者に対しても特商法や景表法に基づく行政処分は可能、という消費者庁の見解が出ている資料を見つけました。
ただし、強制権限の執行については、主権上の制約はあるそうです。まあ、そりゃそうだ。それでも、メディアやプラットフォームに対するある程度の抑止効果は期待できそう。「違法ですから」と、断る理由ができますから。
改めてGoogleトレンドで「ステマ」を調べてみたら、ピークは2012年1月の「食べログ事件」まで遡るんですねぇ……そう呼ばれる“事件”はいくつもありますが、このときはクチコミを有償で投稿する業者の存在が発覚した事件でした。もう10年以上経つのか。
ステマが違法ではないため、真面目に「記事広告」とか「PR」などと表示をしているほうが損をするような状態がずっと続いていました。もちろん「インフルエンサー」に限った話でもなく。メディアのごり押しが起きているときなど、なんとなくステマの臭いがする場合ってあるんですよね。具体例は挙げませんけど。施行後は状況が変わるといいなあ。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
大阪工業大学、読書普及へ絶版名作を復刊 書店経営も〈日本経済新聞(2022年12月25日)〉
せっかく年末にこういう報道が出ていたのに、2022年回顧で「埋もれていた名著の再発見と復刻が進む」の事例から漏れてました(追記済み)。ちゃんと見つけていたんですが、12月24日までの記事で集計ファイルを切り替えたので、2023年のファイルに入ってしまったという不覚。トホホ。
著作権が消滅した作品から候補を選ぶ形になっているそうですが、ぜひ「権利処理」にもトライしてみて欲しい(と外野が勝手なことを言います)。国立国会図書館の送信対象(入手困難だけど著作権は残っている)から候補を発掘し、著作権継承者が見つからない場合は裁定制度を使い……などなど、難易度は高いですが、そういうノウハウってこれからもっとニーズ高くなると思うんですよね。
有償等オンライン資料の制度収集の開始について〈国立国会図書館―National Diet Library(2023年1月4日)〉
有償またはDRM有の電子書籍・電子雑誌の納本制度が始まりました。HON.jpは昨年のうちに、送信システムのアカウントを申請・取得しており、いつでも電子納本できる状態になってます。実は新刊を準備中なのです。ほんとうは既刊を先に納本しておきたかったんですけど、そこまでまだ手が回ってません。がんばる!
経済
社員3分の1をリストラ「東スポ」が復活を遂げた訳 | メディア業界〈東洋経済オンライン(2022年12月26日)〉
1ページ目が「東スポ餃子が爆誕」の話で、これは Not for me かな……と思いタブを閉じそうになったんですが、ちょっと我慢して続きを読んでみたら興味深い数字が興味深い形で出ていたので、あえてピックアップします。4ページ目、ネット配信での売上が「1カ月で1億円から1億5000万円ほど」に対し、紙が「年間100億円近く」とあります。つまりこれ、同じ土俵で比較していないんですよね。
ネット配信を紙と同じ「年間」にすると、12億円から18億円ほどになります。「結局、紙の売り上げの方が桁違いに多いわけですから……」なんて言ってますけど、実は同じ2桁億円です。桁、違ってません。どうも過小評価している感が。むしろ、もうあとちょっと頑張ればデジタルが収益の柱に……というところまで来てるんじゃないか、なんてことを思いました。
電通 が広告費成長率予測を発表、2023年広告費の動向は:デジタル分野がけん引、緩やかな成長だが約100兆円に〈DIGIDAY[日本版](2022年12月27日)〉
電通が発表した「世界の広告費成長率予測(2022~2025年)」について。2022年にはインフレ率の上昇、高めの金利、市場の景気後退、企業や消費者の支出に影響を与える政情不安などの要因があったにも関わらず、8%増の成長だったそうです。また、2023年は景気が停滞するものの、3.8%増という予測。強気だなあ。ただ、デジタルの成長分野は「リテールメディア」や「CTV(Connected TV)」とのこと。メディアビジネス的には、広告予算がそっちへ奪われていく感がありますね。
電子書籍で失敗しAmazonに惨敗した老舗書店チェーンがリアル書店で売上を好転させた方法〈GIGAZINE(2023年1月5日)〉
バーンズ&ノーブルが復調しているそうです。立役者のジェームズ・ドーント氏がCEOに就任した当時、その手法について大原ケイさんが詳しく伝えてくれていました。「コアップ」と呼ばれる宣伝費を廃止することにより返品率が劇的に改善した、Eブックでアマゾンと対抗するのを止めた、などの内容です。
タイミングが悪いことに、その直後にコロナ禍へ突入しています。ただ、それを期に、棚に並んでいる本をすべて見直すよう指示。品揃えの改革を行うことで売上が改善、従業員のやる気も取り戻せた――という経緯を辿っていたようです。すごいなあ。
改めて調べてみたら、今年は30店舗を新たにオープンするなんて報道も出ていました。予定地のいくつかは、Amazonがリアル店舗を閉鎖した跡地も含まれるとか。この攻勢は、投資グループのエリオット・アドバイザーズが主導しているようです。
ちなみに、GIGAZINEのタイトルでは「電子書籍で失敗」と端的に書かれていますが、いちおういまでも電子書籍事業は継続しています。「NOOK」の新型端末は2022年にも出ています。力の入れ方を変えた、というのが正確なところでしょう。
技術
Windows 11の「Windows Subsystem for Android」、スマホアプリがなぜ動く〈日経クロステック(xTECH)(2022年12月27日)〉
3ページ目に「なぜ動く」の技術的な解説が載っています。が、電子出版関連で重要なのは、これが「Google Play」ではなく「Amazonアプリストア」である、という点でしょう。年末にWindows 11機を入手したので、ざっと確認してみました。もちろん「Kindle」はありますが、他の電子書店・電子雑誌系アプリは皆無でした(dマガジンさえ出てこない)。つまり現状ではこれが、少なくとも日本の電子出版市場に大きな影響を与えることはなさそうです。
「Apple Books」、AIナレーションによるオーディオブックの配信を開始〈CNET Japan(2023年1月6日)〉
オーディオブック系の市場にいろいろ影響が出そうな動き。「小規模または独立系の出版社が電子書籍をオーディオ形式に変換するための、より安価で利用しやすい選択肢」として提示されているそうです。制作コストが猛烈に下がりそうですから、オーディオブックの制作会社や声優・ナレーターにとっては厳しい変化。ラインアップ拡充と入手しやすさという意味で、読者にとっては嬉しい変化――という感じでしょうか。このような、AI生成コンテンツによる直接的な影響が今年は多方面で起きそうです。注視します。
チャットボットAIの返答は全て「幻覚」、最大の難関はハルシネーションの善悪問題〈日経クロステック(2023年1月6日)〉
自然言語処理分野では「入力に含まれない内容を出力してしまうこと」を「ハルシネーション(幻覚)」と呼ぶそうです。その定義からすると、厳密に言えば「ChatGPT」のようなチャットボットAIの出力は、むしろ「すべてハルシネーション」である、と。すべてハルシネーションだけど、良いハルシネーションと、悪いハルシネーションがあるのだそうです。なるほど、ちょっと目からウロコでした。やっぱりフィクションの分野で活用するのが良さそう。
お知らせ
イベント
2022年の出版関連ニュースをテクノロジーの観点で振り返る! フリージャーナリストの西田宗千佳さんをゲストに迎えた年末恒例「HON.jp News Casting」後半のアーカイブ視聴チケットは1月末まで販売しています。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
明けましておめでとうございます。正月早々、熱が出て数日ダウンしておりました。トホホ。そのせいもあって、年始恒例の予想記事が遅れに遅れて、本稿のほうが先に出ることになってしましました。トホホ(鷹野)