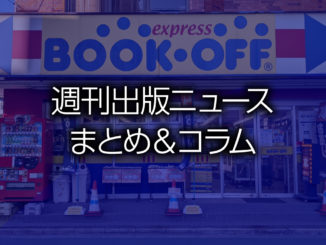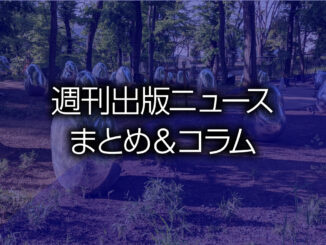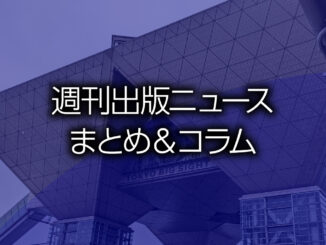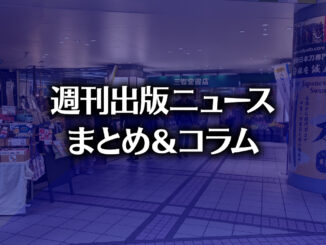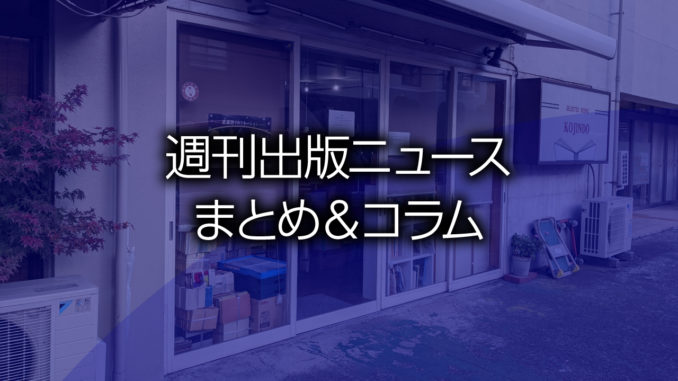
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2021年2月7日~13日は「高校生の約8割がふだん読書する」「枻出版社が民事再生法申請」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 社会
- 【LINEリサーチ】高校生の約8割がふだん「読書する」と回答。「紙の本」派が8割超、「電子書籍」派は1割未満と少数 「君の膵臓を食べたい」は、読書をする高校生の半数近くが読了〈LINE株式会社のプレスリリース(2021年2月8日)〉★
- 同人誌違法アップロードサイト「同人あんてな」を作家が訴えた裁判が決着 サイト運営者はVTuber「ゲーム部」にも関与〈ねとらぼ(2021年2月8日)〉
- 安心、安全なインターネット利用へ ー 中高生のインターネット利用白書 公開〈Google Japan Blog(2021年2月9日)〉★
- 図書館の本が真っ青 開放的過ぎた?「本に申し訳ない」〈朝日新聞デジタル(2021年2月12日)〉
- 海賊版漫画、被害再び拡大〈日本経済新聞(2021年2月13日)〉
- コロナ禍で読書SNSが人気〈日本経済新聞(2021年2月13日)〉
- 経済
- 【出版時評】電子化で文庫戦争再来か〈文化通信デジタル(2021年2月8日)〉
- YouTubeの「変貌」が、出版業界に大きなインパクトを与えるかもしれない(飯田 一史)〈現代ビジネス(2021年2月9日)〉★
- 第一回新世代YouTube漫画大賞結果発表!入選を『アンチヒーロージェネレーションズ』が受賞。読み切りアニメ化が決定。〈株式会社Plottのプレスリリース(2021年2月10日)〉
- データの流通体制をクラウド化、「AIDC Data Cloud」発表〈ZDNet Japan(2021年2月12日)〉
- 「Lightning」「ランドネ」などアウトドア・趣味系雑誌で知られる(株)枻(エイ)出版社が民事再生法を申請〈TSR速報(2021年2月10日)〉
- 株式会社枻出版社からの一部事業譲受に関するお知らせ〈実業之日本社(2021年2月10日)〉
- 株式会社枻出版社からの一部事業譲受に関するお知らせ〈株式会社ヘリテージのプレスリリース(2021年2月11日)〉
- 雑誌「子供の科学」が定額新サービス、電子書籍読み放題〈リセマム(2021年2月12日)〉
- 日本メディア数社に対価で合意 グーグル、提供のニュースに〈共同通信(2021年2月11日)〉
- スターツ出版【7849】、今期経常は2.4倍増益へ | 決算速報〈株探ニュース(2021年2月10日)〉★
- アルファPは21年3月期業績予想を上方修正 | 個別株〈株探ニュース(2021年2月12日)〉
- イラストコミッションサービスの「Skeb」、実業之日本社の子会社へ〈マイナビニュース(2021年2月12日)〉
- 「Amazon.co.jpで購入した新品の書籍が傷んでいた」利用者から悲鳴 梱包材削減によるもの〈ねとらぼ(2021年2月12日)〉
- 技術
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
政治
豪州、記事対価巡る法案を来週提出へ 今月にも成立の可能性〈ロイター(2021年2月12日)〉
先週、“米グーグル、豪で「ニュース・ショーケース」開始 記事に対価” という記事が出ていたのに、
「同法案を審議していた上院委員会は、法案に修正を加えるべきではないと勧告した」とのこと。まだ一悶着ありそうです。
図書館の資料をスマホで閲覧。法改正で利便性向上の反面、出版業界への懸念も〈wezzy(2021年2月13日)〉★

井奈波朋子弁護士による解説。複写サービスのデジタル対応(31条1項1号)と入手困難資料の家庭配信(31条3項)の、2つが対象であることをきっちり説明しています。見出しの「図書館の資料をスマホで閲覧」は若干釣り気味ですが、「利便性は高いのですが、自宅でスマホから自由に閲覧できるというのは言い過ぎではないでしょうか」と、きっちり否定されてます。
古書店に関する懸念に関しては、私はむしろ好影響が出ると思っています。埋もれて忘れられた存在になっていた本が、図書館送信で再認識され、実物が欲しくなる、というサイクルです。ウェブやアプリで無料公開することが新刊の販促に繫がる効果と同じことが起こるのではないかと。
メリーランド州がネット広告税 全米で初の導入、議会が決定〈共同通信(2021年2月13日)〉
デジタル広告売上が世界で年間1億ドル以上ある企業が対象。メリーランド州内でのデジタル広告売上に応じて2.5~10%の税金が課されるそうです。「メリーランド州内」かどうか、どうやって判断するんでしょうね? 広告出稿側の所在地を、対象企業に申告させる……?
社会
【LINEリサーチ】高校生の約8割がふだん「読書する」と回答。「紙の本」派が8割超、「電子書籍」派は1割未満と少数 「君の膵臓を食べたい」は、読書をする高校生の半数近くが読了〈LINE株式会社のプレスリリース(2021年2月8日)〉★
8割! と、驚きました。というのは、全国学校図書館協議会(全国SLA)の「学校読書調査」によると、2019年の高校生不読率は55.3%(↓)だから。LINEリサーチも「マンガやコミックを除いたもの」なので、条件は同じはず。
では、なぜそこまで差があるのか。リリースをよく読むと、LINEリサーチは「ふだん読書をするかどうか」で8割。全国SLAは5月の1カ月間に読書した冊数がゼロの率なので、たとえば2カ月に1冊など読む頻度の若干低い人が、たまたま5月に1冊も読んでいなかったら「不読」として扱われるわけです。つまり対象期間が違う。なるほど。
ただ、LINEリサーチの「月に1冊以上読む」人も6割以上なので、それでも全国SLAの調査結果より15ポイントほど高いのも確か。パネルの偏りかとも思ったのですが、「LINEユーザーを対象」とした調査なので、恐らくあまり偏ってはいないはず……?
同人誌違法アップロードサイト「同人あんてな」を作家が訴えた裁判が決着 サイト運営者はVTuber「ゲーム部」にも関与〈ねとらぼ(2021年2月8日)〉
いろいろと情報量の多い記事です。個人的には、他にもいろいろ問題のある人物が運営していたという前半より、後半の平野弁護士による「もしも自分の作品が転載されているのを見つけたら」どう対処すればいいか? という部分のほうが興味を惹かれました。
要するに、騒ぐ前にとにかく証拠保全、と。「一番いいのは、画面の横に電波時計を置いて、画面の外からカメラで撮影しておくことです」というのは、なるほどと思いました。データはデジタルですけど、手法はアナログ。こうかはばつぐんだ!
安心、安全なインターネット利用へ ー 中高生のインターネット利用白書 公開〈Google Japan Blog(2021年2月9日)〉★
Googleによる、中高生と教員を対象とした調査。生徒は教員の想像以上にネットを活用している、生徒は教員の想像以上にネットで不快な思いや詐欺に巻き込まれそうになっている、という認識のギャップが興味深いです。
私が中高生だった1990年代の初頭には「情報」という教科は存在しなかったわけですが、高校では2003年度から追加されているようです。学習指導要領を読む限り、結構高度なことをやっている印象。下手すると、情報科目を教えている教員以外は、置いてけぼりにされている可能性もあるのでは。
私も大学の非常勤でデジタル出版論とかデジタル編集論といった授業を担当させてもらっているのですが、スマホ世代で逆にパソコンの使い方がよくわからない、みたいなギャップは若干あるものの、知識レベルは年々上がっているように思います。今後、大学受験の科目になるかもしれないという情報もあり、若い世代の情報リテラシーは想像以上に高まっていきそうです。こりゃ負けていられないゾ。
図書館の本が真っ青 開放的過ぎた?「本に申し訳ない」〈朝日新聞デジタル(2021年2月12日)〉
本件、Twitterでバズっていた段階から把握していました。改めて記事になったので投稿してみたら、結構な反響が。日に焼けて青くなった背表紙が並んでいる写真は、インパクトありますもんね。
まあ、正確には「図書館」ではなく市民館の中にある「図書室」ですし、高い保存性を強く求められている場所でもないようなので、ある程度は仕方ないのかなとも思いますが。知らないうちに除籍図書として処分されていく本も、実はたくさんあるわけですし。
海賊版漫画、被害再び拡大〈日本経済新聞(2021年2月13日)〉
この傾向は先月、朝日新聞でも報道済みですが(↓)、「運営元が海外へ移っている」という新情報が。そのため、摘発が難しくなっている、と。なお、アクセス上位の大半はベトナムだそうです。
今年から私的使用目的でも違法となったのがダウンロード型だけで、ストリーミング型が対象外であることについての懸念も改めて表明されています。が、更なる国内規制強化より、国際協力体制強化のほうが先決なのでは。
コロナ禍で読書SNSが人気〈日本経済新聞(2021年2月13日)〉
「ブクログ」の会員数が急増、「Readhub」という読書管理SNSでも投稿数が前年同月比3倍になっているそうです。喜ばしい。ただ、普通なら「読書SNS」と言えばもう1つは「読書メーター」が挙がるのでは? とも思うのですが。
経済
【出版時評】電子化で文庫戦争再来か〈文化通信デジタル(2021年2月8日)〉
文化通信・星野渉さんのコラム。メディアドゥ・新名新副社長がセミナーで、いままで電子化を拒んでいた著名作家がコロナ禍もあって方針転換している状況を踏まえ、かつての文庫化権争奪戦のような状況が起きるだろう、と語っていたそうです。
私も、今年の年初予想で「既刊の電子化が急がれる(というか急げ!)」と書きましたが(↓)、恐らく新名さんも同じようなことを考えてらっしゃるのだと思います。出版社がやらなきゃ、国が、図書館が、一般向けに公開していっちゃうのはもうほぼ確実ですし。
そういえばちょうど2年前に、紙からの復刻が9割という電子専門出版社・アドレナライズの井手邦俊さんにインタビューしたのですが(↓)、いやがらせや苦情の電話がかかってきたり、「出版業界の慣習に反している、後でどうなっても知りませんよ!」などとと言われたこともある、という話が印象的でした。
イースト「電子復刻」のような、出版社の休眠資産を掘り起こし収益に繋げる動きもあります(↓)。これは改めて、強く、訴えかけるべきでしょう。急げ!
YouTubeの「変貌」が、出版業界に大きなインパクトを与えるかもしれない(飯田 一史)〈現代ビジネス(2021年2月9日)〉★
第一回新世代YouTube漫画大賞結果発表!入選を『アンチヒーロージェネレーションズ』が受賞。読み切りアニメ化が決定。〈株式会社Plottのプレスリリース(2021年2月10日)〉
前者は、YouTubeへの投稿作品から小説化、という動きが活発になりつつあるというコラム。後者は、漫画賞だけど、漫画やネームだけでなく、脚本や動画でも応募が可能というユニークなコンテストです。
カメラで撮ってそのまま配信するのと違い、イラストを動かしたり声を入れたりする動画って、制作コスト(労力)が結構高いと思うのです。そこから先のステップがこうやってできつつあるというのが、ただただ凄いなあと感心するばかり。制作に労力がかかるぶん、参入障壁が高いという側面もあるかもしれませんね。
データの流通体制をクラウド化、「AIDC Data Cloud」発表〈ZDNet Japan(2021年2月12日)〉
日本電子出版協会(JEPA)も構成員になっていて、代表理事・会長にはあの長尾真さんが就任している、AIデータ活用コンソーシアム(AIDC)の新たな動き。AI学習用データの「説明責任とデータ来歴」「知的財産と商流」「データ品質と偏り(バイアス)」といった課題に対応することを目的とした流通基盤の提供が始まる、というニュースです。なお、プレスリリースはMicrosoftから出ています(↓)。
「Lightning」「ランドネ」などアウトドア・趣味系雑誌で知られる(株)枻(エイ)出版社が民事再生法を申請〈TSR速報(2021年2月10日)〉
株式会社枻出版社からの一部事業譲受に関するお知らせ〈実業之日本社(2021年2月10日)〉
株式会社枻出版社からの一部事業譲受に関するお知らせ〈株式会社ヘリテージのプレスリリース(2021年2月11日)〉
枻出版社が民事再生法を申請、負債総額58億円。そして続けざまに、枻出版社からの事業譲渡に関するお知らせが。先週、枻出版社の24媒体を買収したコンサル&投資会社・ドリームインキュベータの記事(↓)をピックアップしましたが、これもその動きの一環だったわけです。これ、継承先をちゃんと見つけているのは偉いと思うのですが、枻出版社に残る出版事業って何があるんだろう? という状態に。ううむ。
雑誌「子供の科学」が定額新サービス、電子書籍読み放題〈リセマム(2021年2月12日)〉
誠文堂新光社の新サービス。月額税込770円の定額制で「コカネットプレミアム」という名称です。電子書籍読み放題のほか、「子供の科学」2015年3月号から最新号までの電子版読み放題や、オンライン講演会アーカイブ視聴、会員限定イベントなどが提供されます。
どこかと提携しているのかな? と思い調べてみたところ、「プレミアム会員登録がお済みの方はFujisan.co.jpにてお申込み頂いたアカウントにてログインしてください。」という記述が。なるほど。
日本メディア数社に対価で合意 グーグル、提供のニュースに〈共同通信(2021年2月11日)〉
日本でもいよいよ「Google News Showcase」が始まりそうです。「Yahoo!ニュース」や「SmartNews」などと同様、メディアに対価を払う形のサービス。合意に至ったメディア数社ってどこだろう?
スターツ出版【7849】、今期経常は2.4倍増益へ | 決算速報〈株探ニュース(2021年2月10日)〉★
アルファPは21年3月期業績予想を上方修正 | 個別株〈株探ニュース(2021年2月12日)〉
小説投稿サイトからの書籍化やコミカライズを中心とした出版社も好決算。2月13日のHON.jpブロードキャスティングにゲスト登壇いただいた飯田一史さんによるピックアップです。該当箇所から再生できるリンクを張っておきます。
イラストコミッションサービスの「Skeb」、実業之日本社の子会社へ〈マイナビニュース(2021年2月12日)〉
直前に「総登録者数が100万人、総取引高が18億円突破」というリリースが出ていて凄いなあと思っていたのですが、見事なエグジット。とはいえ今後もクリエイターファーストの方針に変更はなく、創業者が引き続き代表取締役を務めるとのことです。素晴らしい。
「Amazon.co.jpで購入した新品の書籍が傷んでいた」利用者から悲鳴 梱包材削減によるもの〈ねとらぼ(2021年2月12日)〉
私は最近、Amazonをなるべく使わないようにしているのですが、こういう場合は以前なら、クレームを入れればすぐ返品・交換してくれたような。替えの効かない希少な本なら話は別ですが。
昨年10月には出版社側から、返品で粗雑な扱いをされたというクレームも出ていました(↓)。Amazonの発送業務全般のクオリティが落ちているのかもしれません。
技術
「原稿の校正をAIに任せたい! しかも無料で」――急遽テレワークを導入した中小企業の顛末記(39) CMSを使わずに原稿をクラウド管理、しかも自動校正付き!【テレワーク顛末記】〈INTERNET Watch(2021年2月8日)〉
AI校正サービス単体ではなく、原稿執筆から版管理や相互レビューなどの共同作業まで行える「Shodo」というクラウドサービス。複数のツールを使ってやってる編集業務をある程度まとめられそうです。
開発理由が「代表の清原自身が必要だったから」というのが、率直で実に良い。オープンベータ版なので、いまなら無料で利用できます。剽窃チェック機能はまだなさそうなので、要望を送ってみようと思います。
ブロードキャスティング
毎週ライブ配信している映像番組、2月14日のゲストは飯田一史さん(ライター・批評家)でした。上記のタイトル後ろに★が付いている記事について掘り下げています。番組のアーカイブはこちら。
次回のゲストは西島大介さん(漫画家)さんです。配信終了後はZoom交流会もあります。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。