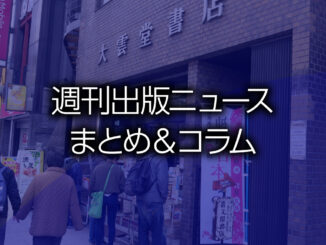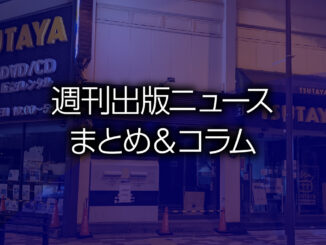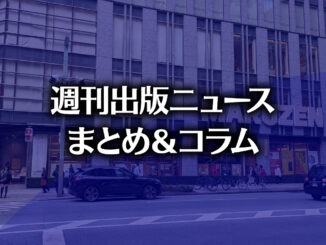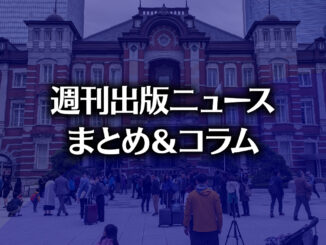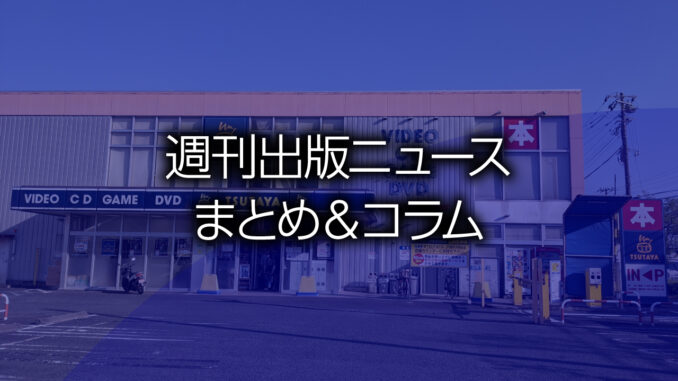
《この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です(1分600字計算)》
2021年11月14日~20日は「中国メディア規制の実際」「拡大集中許諾制度を軸とした簡素で一元的な権利処理、中間まとめ素案が公開」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
政治
【独自】著作物利用 一元窓口…文化庁 データベースで効率化〈読売新聞オンライン(2021年11月16日)〉
文化審議会著作権分科会基本政策小委員会で審議されてきた、拡大集中許諾制度を軸とした簡素で一元的な権利処理を可能とする仕組みについて。中間まとめの素案が出たのを受けた、観測気球的な報道です。JASRACと同一視して反発するような人は意外と少なく、比較的前向きな反響が多いように思います。パブコメを先に実施したうえで中間まとめという異例のやり方も功を奏しているのかも。故・瀬尾太一さんの遺志は、これで実るでしょうか。
中国「メディア規制」について考える――求められるのは出版人の「匠人精神」〈HON.jp News Blog(2021年11月19日)〉
最近、ウェブ・アニメ・ゲームといった新興メディアに対する、中国当局からの規制がいくつか話題になっていました。実際のところはどうなのか、出版業界はどうなのか、といった疑問に、北京大学・馬場公彦さんが応えてくれました。確かに、中国の出版業界はずっと以前から規制され続けているわけですよね。つまり、当局が急に規制のベクトルを変えたわけではなく、既定路線をアップデートしたに過ぎない、ということなのでしょう。そんな中でも、過度な干渉を受けないよう巧みに立ち回る職人芸で、出版の営みを続けている当地の方々に共感します。
社会
LibraroEの導入館数が500館に到達しました。〈株式会社日本電子図書館サービス(2021年11月18日)〉
マイルストーンとして。「250館到達」のリリースが昨年9月なので、1年2カ月で倍増ということに。内訳は、公共図書館233館、大学・短大132館、高校・中学校128館、その他7館です。
Lawmakers Expand Inquiry into Library E-book Market〈Publishers Weekly(2021年11月19日)〉
アメリカの話。電子図書館サービスのライセンスが法外に高いのではと、議員がディストリビューターへのヒアリング調査を始めたそうです。アメリカでは公共図書館への普及率が90%以上と、日本とは状況がまったく異なりますが、いずれ日本でもそういう議論になるかもしれません。
ただ、ディストリビューター側では複数のプランを用意していても、どれを選択するか、また、いくらで出すかは出版社側が決めることです。コラム「電子図書館(電子書籍貸出サービス)がコロナ禍以降も普及拡大を続けるための課題は?」でも書いたように、電子版配信には貸与権の権利制限が及ばないため、なにをするにもすべて権利者の許諾が必要となります。
アメリカにはフェアユースがあるとはいえ、ビジネスに直接影響する領域には及ばないはずなので、この辺りの事情は同じだと思うのですよね。Publishers Weeklyの記事によると、議員は先に出版社へヒアリングしており、恐らく締め付けを食らうとしたらディストリビューター側ではなく出版社側なのかな、と。
経済
漫画海賊版サイト「漫画BANK」に集英社など4社が法的措置へ | IT・ネット〈NHKニュース(2021年11月14日)〉
まとめ#496でのピックアップ時点では「集英社の訴訟準備」とのことでしたが、集英社だけでなくKADOKAWA・講談社・小学館の大手4社がそろい踏みで法的措置の準備を進めていることが明らかになりました。刑事処罰はもちろんですが、民事の賠償額も大変なことになりそうです。
なお、本稿の見出しには「NHKが報じている」という意味を込めてNHKの記事を持ってきましたが、ねとらぼでは顧問弁護団の一人である中島博之弁護士と集英社の伊東敦編集総務部部長代理に取材し、どうやって運営実態を解明したのか? などを詳細に報じています。参考まで。
ヤフー、地方メディア配信料増額 今月から読者評価を反映〈共同通信(2021年11月16日)〉
PVだけで収益分配するのではなく、PVに対する読者のリアクション比率で上乗せ額を多くするという施策。Googleニュースショーケース対策でしょうか? 日本の場合、Yahoo!ニュースが圧倒的すぎちゃうので、もう少し競争してサービス改善を図って欲しいものです。
Webtoon Heads to Print Publishing with Webtoon Unscrolled〈The Hollywood Reporter(2021年11月18日)〉
NAVER傘下のWattpad Webtoon Studioが、以前DCにいた編集者を迎え入れて「印刷出版」へ参入、Webtoon Unscrolled(スクロールしないウェブトゥーン)を展開するそうです。それは日本でかつて「comico」が通った道のような気が。「ページ」へ再編集する手間とコストが大きな足枷となる未来が待っているように思います。市場でまだ印刷版が支配的な、いまのうちはいいのかもしれませんが。
技術
QRコードでスキャンして聴く? 書籍のDXは“非接触”サービスでますます多様化へ〈Real Sound|リアルサウンド テック(2021年11月16日)〉
中国の話。実店舗をショールーム化し、オーディオブックの購入・聴取へ誘導する仕掛けです。マクドナルドの一角にデジタル図書コーナーというのが、既存の流通網を飛び越え拡張している感じで良いですね。
NFTで新刊販促、米作家が100万部売る〈WSJ(2021年11月17日)〉

新刊を12部購入した人にNFTをプレゼント。アメリカ版AKB商法といったところでしょうか。著者で仕掛け人のゲイリー・ベイナチャック氏のことを調べてみたら、暗号資産が盛り上がる前は「広告業界のトランプ」と呼ばれていたとか、CryptoPunksを376万ドル(約4億3000万円)で購入してNFTへ投資が急増するきっかけの1つとなったとか、NFT企業Candy Digital創業者の1人とか、いろいろ出てきてえーっと……うん、単純に「NFTで新刊販促」という事例だと思わないほうが良さそうです。
楽天による「NFTの民主化」は日本のIPコンテンツの世界をどう変えていくのか〈Business Insider Japan(2021年11月19日)〉
楽天が2022年に開始する「Rakuten NFT」マーケットについて、事業部のゼネラルマネージャーにインタビューしています。楽天IDのクレジットカード決済によって利用のハードルを下げる、二次売買で権利者に収益を還元する、一次出品は誰でもできるわけではなく楽天の認めたIPホルダーのみが「ホワイトレーベル」として扱われる、などの特徴があるようです。メディアドゥ「FanTop」と似ていますが、最大の違いはプライベートチェーンであること。
これ、中央集権のクライアントサーバー型とほぼ同じなのですよね。楽天がサービス提供をやめた瞬間にNFTも消えます。利用者の意思がどうあれ、楽天の決断に従うしかない仕組みなわけです。プライベートチェーンが悪いとまでは言いませんが、それを「NFTの民主化」と言ってしまうのはちょっと違うんじゃないの? と。「大衆化」なら分かるんですけど。
プライベートチェーンを選んだのは、管理者が存在することで要望が反映しやすいこと、セキュアであること、処理が速く環境負荷が少ないこと、と理由を挙げていますが、素直に「楽天ポイント経済圏へ引き込むこと」と言われたほうが理解しやすいし、納得もできると思うのですけど。
「漫画家の名刺代わりに」 集英社、過去作をまとめられるポートフォリオ作成サービスを提供〈ITmedia NEWS(2021年11月19日)〉
4月にオープンした集英社のマンガ投稿サイト「マンガノ」に、ポートフォリオ作成サービス「MangaFolio」が追加。マンガやイラストを投稿せず、ポートフォリオだけの利用も可能となっています。わざわざ別途名称を付けたのは、単体でも使って欲しいからでしょうか。5月のインタビュー記事で、ユーザーからの期待度が高いことから優先度を上げて開発している、というコメントがあったのを思い出しました。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
本稿を執筆しているあいだに、久しぶりの雨が降ってきました。11月下旬ともなると、さすがに太陽が出ていないと肌寒い感じ。今夜は鍋にしようかな(鷹野)