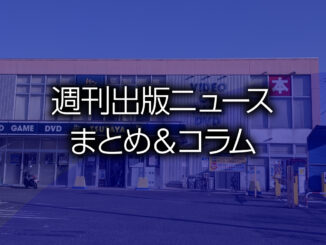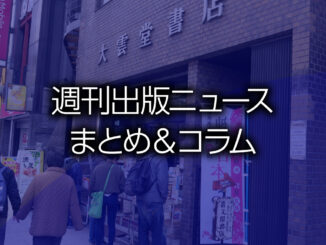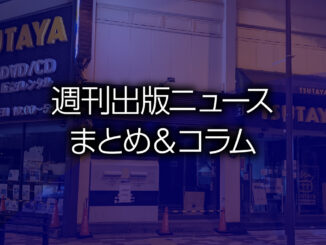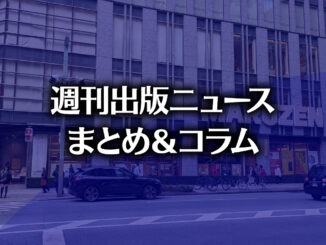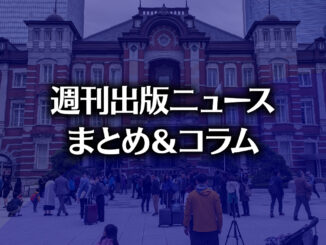《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2021年3月14日~20日は「デジタル教科書、検討会議から中間まとめ」「スクエニ、NFTデジタルシールを今夏発売」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 漫画界の逆転現象…?“漫画家が編集者を選ぶ時代”のWEBマガジン「comic gift」の仕掛けとは〈ウォーカープラス(2021年3月14日)〉
- Twitter、Clubhouseのような音声チャット機能「スペース」を実装へ。詳細が公開〈PC Watch(2021年3月15日)〉
- Clubhouseブームは本物か。その熱狂を心理学から読み解いてみた〈Agenda note(2021年3月15日)〉
- 運命の一冊との縁結び? 「taknal」はすれ違った人と“推し本”を紹介し合えるアプリ〈BCN+R(2021年3月15日)〉
- ポニーキャニオン:YourEyesで拓く読書バリアフリーの世界〈JEPA|日本電子出版協会(2021年3月17日)〉
- 米グーグル、手数料半分に 売上高1億円まで全業者〈共同通信(2021年3月17日)〉
- 『SPY×FAMILY』の快進撃 ウェブ発で累計発行部数800万部突破〈日経クロストレンド(2021年3月17日)〉
- 「少年ジャンプ+」1700万DL突破 ウェブ発人気漫画を生む仕組み〈日経クロストレンド(2021年3月18日)〉
- 日本では75.1%の検索がスマホから、調査データにみる検索とSEOの今【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ〈Web担当者Forum(2021年3月19日)〉
- 技術
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
政治
デジタル教科書、本格導入へ提言 根強い懸念の声も〈朝日新聞デジタル(2021年3月17日)〉
文部科学省の「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」から中間まとめが出た(↓)ことを受けての記事。
なんというか、その「根強い懸念の声」というのは、主に新聞業界側から聞こえてくるような気がしてならないのですが。読売新聞の社説とか(↓)。
産経新聞の社説とか(↓)。諸外国の事例と比べたら、日本の教育IT化が遅れているのは明らかだと思うのですが、抵抗している人たちはいつまで「検証」すれば気が済むんだろう?
Twitterにファンアートを投稿したらアカウント凍結 虚偽申請の被害絵師が悲痛な胸の内語る〈ねとらぼ(2021年3月20日)〉
本件、どこへ分類するか迷ったのですが、アメリカのデジタルミレニアム著作権法(DMCA:Digital Millennium Copyright Act)の悪用事例が後を絶たない「法制度の不備」という意味で、政治ジャンルに入れました。バイデン政権は、プロバイダの免責保護を定める通信品位法(CDA:Communications Decency Act)230条については見直す方針だと伝えられていますが、DMCAはどうなんだろう?
日本でも数年前から、ウォンテッドリーや侍エンジニア塾などが悪評隠蔽のためにDMCAを使ったとか、「艦これ」公式アカウントが凍結されたなど、話題になった事例は後を絶ちません。1年ほど前にheatwave_p2pさんが事例をまとめた記事を書かれていますが(↓)、残念ながら「悪用問題を解決する銀の弾丸は、いまのところ存在しない」とありました。うーむ。
社会
首都圏自治体、図書館や美術館でデジタルサービス拡充〈日本経済新聞(2021年3月15日)〉
電子図書館サービスの導入事例はもちろん、博物館や美術館等の文化施設が動画配信を行う事例も増えているそうです。良いですね。どんどんやればいいと思う。もちろん実物を見に行くことが最上ですけど、デジタル技術なら時間と距離の壁を越えられるのですから。
読書は「知識」と「思考力」を伸ばし、子どもの心の安定にも効果があることが判明【ベネッセ調査】〈EdTechZine(2021年3月16日)〉
ベネッセの進研ゼミ会員向け電子図書館サービス「まなびライブラリー」の読書履歴データ分析。2018年度、2019年度に続く、3回目の調査です。過去2回はHON.jp News Blogでも取り上げています(↓)が、1回目は読書の「量」の効果分析、2回目は読書の「質」の効果分析を行っています。
https://hon.jp/news/1.0/0/14172
今回は、コロナ禍中ということもあり、読書の心理面への効果についても調べています。電子図書館サービスで読書履歴データがしっかり残っているので、以前よりこういう分析がやりやすくなった、ということは言えるのかなと。
経済
漫画界の逆転現象…?“漫画家が編集者を選ぶ時代”のWEBマガジン「comic gift」の仕掛けとは〈ウォーカープラス(2021年3月14日)〉
4ページの短編マンガをTwitterで公開する取り組みを、出版社所属編集者が「個人で」やっているという話。ちょっと驚いたのが「100%自分のお財布からお支払いしています」との言葉。タニマチか。すごい。
この記事ではなぜか所属が伏せられていますが、本人が公開している情報なので紹介すると、ヤングマガジン編集部所属の山中/漫画編集さんの取り組みです(↓)。
Twitter、Clubhouseのような音声チャット機能「スペース」を実装へ。詳細が公開〈PC Watch(2021年3月15日)〉
これだけブームになると、そりゃ既存のSNS大手も黙っちゃいません。すでに一部ユーザーには機能解放されていて、たまにタイムラインで見かけます。チャットルームの終了後も、音声データはしばらくアーカイブされる点がClubhouseとの大きな違いのようです。
一定期間はすべてのユーザーがダウンロード可能とあるので、リアルタイムで参加できなかったチャットルームの音声を、後から確認することもできる模様。こういう形のほうが、私は好きだなあ。取り残されることへの恐れ(FOMO:Fear of missing out)を抱かずに済みます。発言も、慎重になるんじゃないかしら。
Clubhouseブームは本物か。その熱狂を心理学から読み解いてみた〈Agenda note(2021年3月15日)〉
Clubhouse推しは「イノベーション推進バイアス」ではないか? という冷静な指摘。個人で簡単にコンテンツ売買の決済が利用できる「Gumroad」が急にもてはやされたとき、ブログに「これ危なくね?」と警鐘を鳴らす記事を書いたら、実際に「新しいサービスに完全を求めるのは間違っている」といった趣旨の指摘を受けたのを思い出しました。まあ、確かに批判するだけじゃダメだよねと、続けて解決策についての提案記事を書く動機にもなったのですが(↓2012年、懐かしい……)。
運命の一冊との縁結び? 「taknal」はすれ違った人と“推し本”を紹介し合えるアプリ〈BCN+R(2021年3月15日)〉
年末にリリースされ、直後にインストールしたら誰でともすれ違わなかったので、そのまま忘れてました……人の動きが盛んになってきたこともあってか、利用する方も急に増えてきているようです。ちょうど3月15日のHON.jpブロードキャスティングで、ゲストの平山亜佐子さんから気になるトピックスの1つとしてこの「taknal」挙げられていて、話題にしたばかり。タイムリーでした。アーカイブの当該時間へリンクしておきます(↓)。
ポニーキャニオン:YourEyesで拓く読書バリアフリーの世界〈JEPA|日本電子出版協会(2021年3月17日)〉
いよいよ3月22日からサービス開始する「YourEyes」。昨年11月に発表された際、視覚障害者等向け読書支援サービスなのに著作権法第37条は使わないと断言されたことが衝撃で、それがどういうロジックなのかを解説する記事を書きました(↓)。
実はこの記事への反響で、小倉秀夫弁護士から「どうやって著作権法49条1項2号および6号をクリアしているのか理解できない」という指摘を頂いていました(↓)。つまり、仮に利用者が撮影した版面画像がボランティアに直接送信されるのであれば、「他人に享受させる目的」に該当するのではないか。第47条の5第1項第2号の「情報解析」にも該当しないのではないか。という疑義だと思われます。
当時、確かにそこは明確ではなく、私もこれで100%問題なしとまでは断言できなかったので、「最終的な判断は司法の場でなされるもの」と逃げを打っておいたのですが、仮にそうならご指摘通り。ただ、出版関係に詳しい弁護士に相談しながら進めているという話でしたし、まだサービス開始前で細かな点が明確ではない段階だったので、次の機会に確認しようと思っていました。
で、今回のJEPAセミナーで改めて詳しく紹介される機会が得られたので、この疑問点を解消してきました。今回の説明で明確になったのは、利用者の撮影した画像が直接ボランティアへ送られるわけではなく、ボランティアの手元にも本があることが大前提であること。逆に、ボランティアが修正した「読み」のデータはあくまでAIの学習用であり、直接利用者へ送られるわけではないこと。であれば、結論は「問題なさそう」です。ホッとしました。元記事にも追記しておきました。
米グーグル、手数料半分に 売上高1億円まで全業者〈共同通信(2021年3月17日)〉
Appleの動きにGoogleも追随。Epic Gamesが要求していた「ボリュームディスカウント」とは真逆の施策です。売上高1億円までなので、アプリ開発スタートアップにとっての福音、救済措置となるでしょう。助走が少しラクになるイメージかな。
『SPY×FAMILY』の快進撃 ウェブ発で累計発行部数800万部突破〈日経クロストレンド(2021年3月17日)〉
「少年ジャンプ+」1700万DL突破 ウェブ発人気漫画を生む仕組み〈日経クロストレンド(2021年3月18日)〉
編集長の細野修平さんや、『SPY×FAMILY』担当編集者の林士平さんへのガッツリインタビュー。読んだ人がウェブにすぐシェアできること。そして、それを見た人がそのまますぐウェブで読めること。そのための仕組みや仕掛けが、非常にうまくいっている感があります。思えば、アプリのダウンロードとアカウント登録が必須だった「LINEノベル」は、その辺りがダメだったのかも。なお、この記事には出てきませんが、「少年ジャンプ+」の裏方には株式会社はてなが入ってます(↓)。その知見も活かされている感。
日本では75.1%の検索がスマホから、調査データにみる検索とSEOの今【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ〈Web担当者Forum(2021年3月19日)〉
検索の4分の3がモバイル! もちろんジャンルにも依るとは思いますが、1人1台のパーソナルデバイス時代への対応がいかに重要かが改めてわかります。ちなみにHON.jp News Blogの検索流入は、まだPCのほうが若干優勢。平日昼間のアクセスが多いので、会社から見てる人が多いのかな。
技術
加熱するNFT市場、アートなどの「デジタル所有権」をブロックチェーンで、約75億円でのオークション販売事例も、Taco Bellも参入【ブロックチェーン講座】
〈INTERNET Watch(2021年3月16日)〉
先週もお伝えしたNFT(Non-Fungible Token:代替不可能なトークン)の、詳しい解説。後半の誤解されやすい点、は頭に入れておいたほうがいいでしょう。要するに、スクショ等によるコピーは防げないけど、そのデータがコピーなのかそうじゃないのかは瞬時に検証できる、という点がポイント。たとえば、NFTでチケットを発行すれば、偽造チケットによる入場は完璧に防げる、といったところでしょうか。
もし、オリジナル作品の権利者ではなく、悪意の第三者が勝手にNFTを発行してしまったらどうなるか? という心配をしている方を見かけました。それは裏を返せば「自分の悪事の証拠を、自ら、絶対改竄できない記録として残す」形になるということ。騒ぎになって「やべえ!」と思っても、消して逃亡なんてこともできないわけです。スクリーンショットは偽装可能ですけど、これは無理。もしかしたら、無断転載するような輩が激減するような事態が起きるかも? あるいは、DMCA悪用に対する銀の弾丸になり得るかも?
スクエニ、ブロックチェーンを活用した「NFTデジタルシール」を今夏発売、「ミリオンアーサーシリーズ」で展開〈INTERNET Watch(2021年3月18日)〉
コインチェック、ブロックチェーン上のデジタルアイテム「NFT」を取引するマーケットプレイスを提供へ〈Digital Shift Times(2021年3月19日)〉
というNFT関連で、さっそく日本の企業でも動きが出てきました。NFTの主な活用分野としては「アートやトレーディングカード、ゲームアイテム、ドメイン名、所有権、ライブチケット」などが挙げられていますが、スクエニの事例はトレーディングカードと言っていいでしょう。コインチェックは取引所を提供するという動き。投機的な扱われ方をする可能性が、ちょっと心配ではあります。こういうデジタル資産の税金ってどうなるんだろう?
ブロードキャスティング
3月15日のゲストは平山亜佐子さん(文筆家・デザイナー・挿話蒐集家)でした。番組前半の部のアーカイブはこちら。
次回のゲストは唐渡千紗さん(ルワンダでタイ料理屋を経営/3月28日に初めての著書『ルワンダでタイ料理屋をひらく』を左右社より出版予定)です。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。