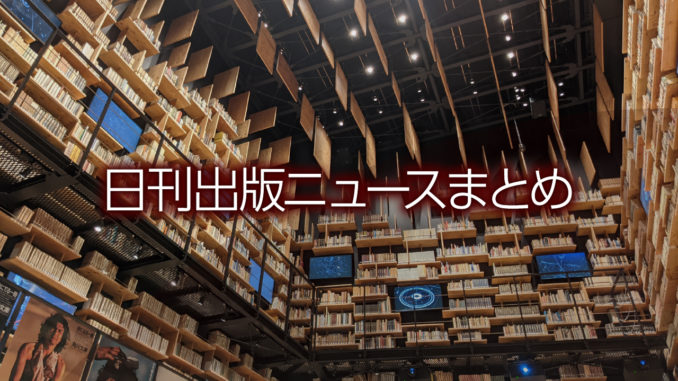
《この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です(1分600字計算)》
伝統的な取次&書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。
【目次】
- 国内
- 小中学生が無料で電子書籍を利用 鎌倉市教委と出版社など協定〈NHK 首都圏のニュース(2021年5月28日)〉
- 小学館「日本短編漫画傑作集」に少女漫画は入らない!?編集者のツイートが炎上した理由 | News&Analysis〈ダイヤモンド・オンライン(2021年5月28日)〉
- 【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】「12.9インチiPad Pro(第5世代)」で電子書籍を試す。ミニLED採用でコントラスト向上も重量増〈PC Watch(2021年5月28日)〉
- 「日本は周回遅れの先頭ランナー」、慶応大・村井純教授が語るデジタル立国への挑戦〈日経クロステック(xTECH)(2021年5月28日)〉
- 読書感想文の正体 : デスクの目~社会部 : Webコラム〈読売新聞オンライン(2021年5月28日)〉
- 広告会社が考えるNFTの可能性とは?博報堂DYメディアパートナーズ 髙橋信行氏〈Media Innovation(2021年5月27日)〉
- 世界で1冊目の「はらぺこあおむし」 実は日本で製作〈朝日新聞デジタル(2021年5月27日)〉
- 宝島社とI&S BBDO、調査プロジェクト「Mood Booster」を始動 初回は消費行動を調査〈MarkeZine(2021年5月27日)〉
- ソケッツ、集英社に感性メタデータの提供を開始〈MarkeZine(2021年5月27日)〉
- 図書館の貸し出し履歴、捜査機関に提供 16年間で急増〈朝日新聞デジタル(2021年5月27日)〉
- 世界
- 欧州委と欧州議会の米クラウド使用、欧州データ保護当局が調査開始〈ロイター(2021年5月28日)〉
- 中国政府に批判的な香港紙創業者、禁錮の刑期が計1年8月に〈ロイター(2021年5月28日)〉
- ロシアの裁判所、米ツイッターに罰金 「違法投稿削除応じず」〈ロイター(2021年5月28日)〉
- フェイクニュースの収益化を後押し、ネット広告業界に「責任を取れ」〈新聞紙学的(2021年5月28日)〉
- アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが「Amazon創業の日」7月5日に退任と発表〈TechCrunch Japan(2021年5月27日)〉
- アマゾンが掲げる「顧客第一」は“本物”なのか? 新たな反トラスト訴訟から見えた問題点〈WIRED.jp(2021年5月27日)〉
- Facebook、誤情報拡散の個人アカウントも規制対象に 投稿の表示減〈ITmedia NEWS(2021年5月27日)〉
- 変わるイギリスの読書事情〈DOTPLACE(2021年5月27日)〉
- イベント
- 旺文社のイノベーション戦略とEdTechファンド3年間の成果〈JEPA|日本電子出版協会(オンライン)/6月2日〉
- NFT(クリプト)アートと法の最前線〈Arts and Law(オンライン)/6月2日〉
- 【決定】電流協アワード2021、オンライン発表会開催〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/6月3日〉
- ジャパンサーチ連携説明会~地域アーカイブをつくる・つなぐ・つかう~〈国立国会図書館(オンライン)/6月11日〉
- 「COVID-19 : 学校図書館支援プログラム」から見える、情報組織化と検索サービスの未来〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/6月12日〉
- あしたのVivliostyle:オープンソースCSS組版システムがつくる未来〈JEPA|日本電子出版協会(オンライン)/6月15日〉
- 本の索引はコンピュータで作れるのか? ――著者・編集者・読者の視点で考える〈日本出版学会 出版編集研究部会(オンライン)/6月22日〉
- 連続オンライン講演会:「学術出版を語る」1「コロナ禍でも立ち止まらないために――学術出版の次を妄想する」講師:江草貞治氏(有斐閣代表取締役社長)〈日本出版学会 学術出版研究部会(大学出版部協会 共催・オンライン)/6月25日〉
- クラブ ライブラリー ― 小さな本の展覧会 8 ― 〈日本出版クラブ/5月14日~8月31日〉
国内
小中学生が無料で電子書籍を利用 鎌倉市教委と出版社など協定〈NHK 首都圏のニュース(2021年5月28日)〉
エラー - NHK
www3.nhk.or.jp
小学館「日本短編漫画傑作集」に少女漫画は入らない!?編集者のツイートが炎上した理由 | News&Analysis〈ダイヤモンド・オンライン(2021年5月28日)〉
【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】「12.9インチiPad Pro(第5世代)」で電子書籍を試す。ミニLED採用でコントラスト向上も重量増〈PC Watch(2021年5月28日)〉
「日本は周回遅れの先頭ランナー」、慶応大・村井純教授が語るデジタル立国への挑戦〈日経クロステック(xTECH)(2021年5月28日)〉
読書感想文の正体 : デスクの目~社会部 : Webコラム〈読売新聞オンライン(2021年5月28日)〉
広告会社が考えるNFTの可能性とは?博報堂DYメディアパートナーズ 髙橋信行氏〈Media Innovation(2021年5月27日)〉
世界で1冊目の「はらぺこあおむし」 実は日本で製作〈朝日新聞デジタル(2021年5月27日)〉
宝島社とI&S BBDO、調査プロジェクト「Mood Booster」を始動 初回は消費行動を調査〈MarkeZine(2021年5月27日)〉
ソケッツ、集英社に感性メタデータの提供を開始〈MarkeZine(2021年5月27日)〉
図書館の貸し出し履歴、捜査機関に提供 16年間で急増〈朝日新聞デジタル(2021年5月27日)〉
世界
欧州委と欧州議会の米クラウド使用、欧州データ保護当局が調査開始〈ロイター(2021年5月28日)〉
エラー
this.kiji.is
中国政府に批判的な香港紙創業者、禁錮の刑期が計1年8月に〈ロイター(2021年5月28日)〉
エラー
this.kiji.is
ロシアの裁判所、米ツイッターに罰金 「違法投稿削除応じず」〈ロイター(2021年5月28日)〉
エラー
this.kiji.is
フェイクニュースの収益化を後押し、ネット広告業界に「責任を取れ」〈新聞紙学的(2021年5月28日)〉
アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが「Amazon創業の日」7月5日に退任と発表〈TechCrunch Japan(2021年5月27日)〉
アマゾンが掲げる「顧客第一」は“本物”なのか? 新たな反トラスト訴訟から見えた問題点〈WIRED.jp(2021年5月27日)〉
Facebook、誤情報拡散の個人アカウントも規制対象に 投稿の表示減〈ITmedia NEWS(2021年5月27日)〉
変わるイギリスの読書事情〈DOTPLACE(2021年5月27日)〉
イベント
旺文社のイノベーション戦略とEdTechファンド3年間の成果〈JEPA|日本電子出版協会(オンライン)/6月2日〉

JEPA|日本電子出版協会 ページが見つかりませんでした
一般社団法人 日本電子出版協会のホームページです。電子出版・編集を考える出版界と情報産業界各社の団体。ニュース、調査報告、電子出版とは、会員限定情報など配信しています。
www.jepa.or.jp
NFT(クリプト)アートと法の最前線〈Arts and Law(オンライン)/6月2日〉
【決定】電流協アワード2021、オンライン発表会開催〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/6月3日〉
ジャパンサーチ連携説明会~地域アーカイブをつくる・つなぐ・つかう~〈国立国会図書館(オンライン)/6月11日〉
「COVID-19 : 学校図書館支援プログラム」から見える、情報組織化と検索サービスの未来〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/6月12日〉
あしたのVivliostyle:オープンソースCSS組版システムがつくる未来〈JEPA|日本電子出版協会(オンライン)/6月15日〉

JEPA|日本電子出版協会 ページが見つかりませんでした
一般社団法人 日本電子出版協会のホームページです。電子出版・編集を考える出版界と情報産業界各社の団体。ニュース、調査報告、電子出版とは、会員限定情報など配信しています。
www.jepa.or.jp




















