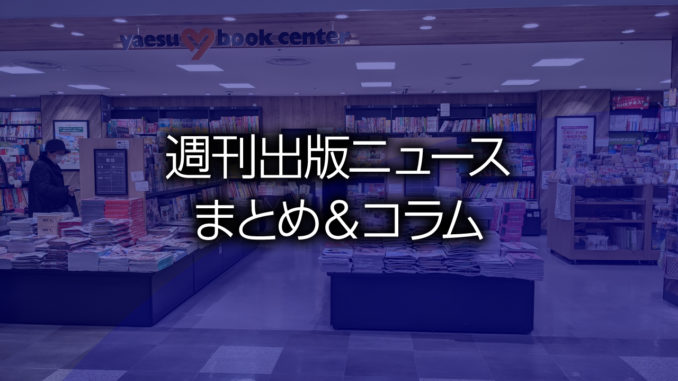
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2021年4月25日~5月8日は「TSUTAYA、メルカリ新刊買取キャンペーン炎上で中止」「美容系不愉快広告が蔓延する理由」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。今回は連休を挟んで2週間分です。
【目次】
- 政治
- 社会
- 公共図書館が人々にもたらす影響:デンマーク・ロスキレ中央図書館による調査とその報告書(記事紹介)〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年4月28日)〉
- 炎上する前に「プロアクティブ」な決断を迫られる出版社〈HON.jp News Blog(2021年4月30日)〉
- ベストセラー作家の新刊が「女学生への性加害」発覚で絶版。静観した出版社を動かす #MeToo ムーブメントの影響【連載】幻想と創造の大国、アメリカ(24)〈FINDERS(2021年5月7日)〉
- デジタルアーカイブ学会、「肖像権ガイドライン」を正式公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年5月6日)〉
- 幡野広志さんの連載終了をcakesが発表。「編集部の力量不足によりご迷惑をおかけした」〈ハフポスト(2021年5月7日)〉
- 経済
- CCC、メルカリ新刊買い取りキャンペーン中止に〈文化通信デジタル(2021年4月26日)〉
- Yahoo! JAPAN、LINEの国内エンターテインメント事業を統括する「Z Entertainment株式会社」、2021年度上半期より事業開始〈LINE株式会社のプレスリリース(2021年4月28日)〉
- ニュースリリース:米J-Novel Clubの買収について〈KADOKAWAグループ ポータルサイト(2021年4月28日)〉
- インターネットで「メディア」は生き残れるのか? JICDAQに取材して考えた〈AdverTimes(2021年4月30日)〉
- KADOKAWAの通期業績、出版の返本率良化やゲームの好調で利益が大幅増〈Media Innovation(2021年4月30日)〉
- 「いま、メディアの存在意義が問われている」ハフポスト日本版トップに聞く、BuzzFeedとの合併経緯と生存戦略〈Business Insider Japan(2021年5月1日)〉
- 「トイレ崩壊寸前」って大げさすぎでしょ? 怪しげで不快な「ネット広告」はなぜ蔓延するのか〈日刊サイゾー(2021年5月2日)〉
- 米ベライゾン、ヤフーとAOL含むメディア事業売却 50億ドル〈ロイター(2021年5月4日)〉
- Twitter、サブスク型ニュース配信に参入へ 米新興を買収〈日本経済新聞(2021年5月5日)〉
- 広がる音声SNS市場 既に群雄割拠、大手参入急ぐ〈日本経済新聞(2021年5月6日)〉
- パブリッシャーが個々の記事、動画、ポッドキャストに対する支払いを受け取ることを可能にするFewcentsが1.7億円を調達〈TechCrunch Japan(2021年5月6日)〉
- 広告収入に頼らない「サブスク型プラットフォーム」はジャーナリストの救世主となるか?〈DG Lab Haus(2021年5月6日)〉
- メディア大手、新聞事業を非営利化 広告減で存続困難―シンガポール〈時事ドットコム(2021年5月6日)〉
- 書店の倒産が急減、2020年度は過去最少を更新 帝国データバンク調べ〈文化通信デジタル(2021年5月7日)〉
- 技術
- HON.jp News Casting
- メルマガについて
政治
「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」に対する意見募集について〈e-Govパブリック・コメント(2021年4月28日)〉
まだ概要を斜め読みしただけなんですが、対ユーザーの問題点が「消費者に不快感を与える(ユーザーエクスペリエンス) 」止まりというのは、いささか認識不足ではないでしょうか。景品表示法上問題のある表記をしちゃう広告主・代理店や、事前審査をスルーしちゃうプラットフォーム、というあたりの問題まで踏み込んで欲しいように思います。意見募集の期限は5月31日まで。
社会
公共図書館が人々にもたらす影響:デンマーク・ロスキレ中央図書館による調査とその報告書(記事紹介)〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年4月28日)〉
カレントアウェアネス・ポータルの中の人がどういう思いでこの記事を紹介したのか、なんとなくわかる気がします。該当箇所を引用。
記事では、図書館の価値を語る際の言葉を「図書館は何冊の本を貸し出したか」から「市民にとって本を貸すことはどんな意味があったか」に変えていきたい、という考えが調査の背後にあったと述べています。
炎上する前に「プロアクティブ」な決断を迫られる出版社〈HON.jp News Blog(2021年4月30日)〉
ベストセラー作家の新刊が「女学生への性加害」発覚で絶版。静観した出版社を動かす #MeToo ムーブメントの影響【連載】幻想と創造の大国、アメリカ(24)〈FINDERS(2021年5月7日)〉
前者はおなじみ大原ケイさんのレポート。アメリカの出版業界で、世論が沸騰する前や、司法が動く前、さらには、刊行すら行われないうちに「プロアクティブ(能動的)」な対応を行う事例が出ているそうです。後者のFINDERSの記事は、大原さんも取り上げている「Philip Roth: The Biography」の出版停止について、渡辺由佳里さんが詳しく掘り下げたレポートです。
日本でも数年前に、アニメ化が決まった作品の著者が過去にTwitterで差別発言を繰り返していたことが掘り返され炎上、アニメ化中止、原作の単行本も出荷停止、という事件があったのを思い出しました。差別発言やセクハラを擁護するわけではありませんが、能動的な対応というより「慎重な」とか「臆病な」対応とも言えそう。出版社が著者をかばい切れなくなるラインが、だんだん後退している感もあります。
以前からよくあるアマゾンでの取り扱い停止然り、インフラに近いような大企業がこういう表現規制をやってしまうと、「検閲だ!」と言われてしまうのは避けがたい。たぶんこれから、こういう事例がもっといろいろ出てくる気がします。炎上に対応する時間はコストですから、ビジネス的に考えるとどうしても保守的なほうへ流れてしまう。せめて、本当にそれでいいのか? と問い続けたいです。
デジタルアーカイブ学会、「肖像権ガイドライン」を正式公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年5月6日)〉
デジタルアーカイブ学会が取り組んできた、肖像権ガイドラインの正式版が公開されました。あくまでこれは、非営利目的のデジタルアーカイブ機関が、所蔵している写真をインターネットなどで「公開」する場面を想定しているガイドラインです。
ただ、メディアや研究・教育機関など、営利・非営利を問わずこのガイドラインを参考にし、「自主的なガイドラインを策定することは大いに考えられるところである」としています。というか「ぜひ参考にしてね!」ということでしょう。
被撮影者の社会的地位や活動内容・立場・撮影場所や態様など、さまざまな項目に基づき加減点が付けられ、合計した結果によって「公開」しても良いかどうかをジャッジするという方式。仮に裁判になったとして、こういう根拠に基づき「総合考慮」したということが「説明できる」というのが、なにより大きいのではないかと思います。策定に尽力された関係者の方々、お疲れさまでした。
幡野広志さんの連載終了をcakesが発表。「編集部の力量不足によりご迷惑をおかけした」〈ハフポスト(2021年5月7日)〉
結局、連載終了という結果に。昨年10月に、DV被害者からの相談に対し「嘘」や「大袈裟」と回答して炎上。その後、編集長の交代など体制の見直しや、長年DV問題に取り組んできた方へのインタビュー(↓)など、信頼回復のため真摯に取り組んできたようにも思うので、非常に残念です。
経済
CCC、メルカリ新刊買い取りキャンペーン中止に〈文化通信デジタル(2021年4月26日)〉
一部のTSUTAYA店舗で実験的に展開されていた、メルカリ新刊買取キャンペーンが業界関係者の目に留まり、炎上、中止に。CCCやメルカリはともかく、取次のMPDはこういう事態を予想できなかったのか、止められなかったのか、それとも、キャンペーンの実施そのものを知らなかったのか。
しかしこれ、著者や出版社の方が反発するのは理解できるいっぽうで、一般ユーザーの反響を見ていると「なにが悪いかわからない」という声も意外と多いことに注意する必要があるように思います。ヘタをすると、世の中の受け止め方があっというまに逆転する恐れが。新刊書店がこういうキャンペーンを展開する道義的問題はあれど、ユーザーがすぐ手放すことそのものは自由ですからね。
Yahoo! JAPAN、LINEの国内エンターテインメント事業を統括する「Z Entertainment株式会社」、2021年度上半期より事業開始〈LINE株式会社のプレスリリース(2021年4月28日)〉
ちょっと気になる動き。リリースの文面に「動画、音楽、ゲーム、電子書籍、占い等の国内エンターテインメント事業を統括し」とあるのですが、ロゴの一覧にはグループの電子書籍系が無い。要するに、電子書籍の事業をやっている「ebookjapan」と「LINEマンガ」はどうなるのか? ということなのですが。
というのは、「ebookjapan」の業績は好調なのですが、「LINEマンガ」のLINE Digital Frontierは当期純損失29億円以上という、ちょっとびっくりするような決算が出ているのです(↓)。なにごとだと。
そのいっぽうで、NAVERからは「LINEマンガの大規模改編」や「Wattpadの本格統合で北米市場の力量強化」という実績発表もあったようです(↓)。動きが複雑過ぎて追いきれない。誰か整理して!
ニュースリリース:米J-Novel Clubの買収について〈KADOKAWAグループ ポータルサイト(2021年4月28日)〉
昨年7月に「米Amazonで複数ラノベ作品が販売停止 出版社が抗議、署名運動も」というニュース(↓)になっていた、ラノベを英訳して出版してる会社をKADOKAWAが買収しました。
HON.jp News Blogでこのリリースをツイートしたら、英語圏方面で拡散され「OH SHIT」「Omg」「Hmm!」などといった引用コメントが付きました。この反応、どう捉えればいいのか。ラノベの英訳がもっとスムーズになる、という歓迎の声だったら良いのですけど。
インターネットで「メディア」は生き残れるのか? JICDAQに取材して考えた〈AdverTimes(2021年4月30日)〉
本稿冒頭のパブコメとも関連しますが、正直言って「広告費が無駄に費やされたり、ブランドを損ねないよう」チェックするのが最優先というのはつまり、広告主の顔色を伺うことが最優先な団体なのだな、という印象です。順番が違うのでは無いか、なぜユーザーが後回しなのか、と思わずにいられない。まあ、「アドエクスペリエンス、広告審査にまで認証項目を広げていくことも構想にある」そうなので、いちおう少しだけ期待はしていますが。
KADOKAWAの通期業績、出版の返本率良化やゲームの好調で利益が大幅増〈Media Innovation(2021年4月30日)〉
こちらの記事は、末尾に書かれた「本記事は決算AIによって生成されました」が気になったので、決算の内容とは関係なくピックアップ。なるほど自動生成。決算短信を元に要約しているのだと思いますが、うーん……まあ、自動生成でこのレベルなら許容範囲かなあ。
決算の内容そのものは、KADOKAWAの「Financial Results」が非常によくまとまっています。「紙を買うと電子がもらえる」キャンペーンでとくに既刊の売上が伸長したとか、重点課題に電子書籍のグローバル展開で縦スクロールコミックが挙がっているとか、コロナ禍の影響で海外からのデジタル印刷機導入が遅れているにもかかわらず返品率はすでに劇的な改善をしているとか、見どころがいっぱいです(↓)。
「いま、メディアの存在意義が問われている」ハフポスト日本版トップに聞く、BuzzFeedとの合併経緯と生存戦略〈Business Insider Japan(2021年5月1日)〉
合併される側のインタビュー。ちょっと気になったのが、インタビュアーが「プラットフォームの優越性を、公正取引委員会も問題視」という文脈でヤフーにわざわざ触れているにも関わらず、竹下編集長がキレイにスルーしている点。「プラットフォームと協業はしても、依存はしないことです」なんて言われたら、「え? Yahoo!ニュースには依存してないの?」と思ってしまいます。まあ、Zホールディングスの資本も入ってますから、うかつなことは言えないのもわかりますが。
「トイレ崩壊寸前」って大げさすぎでしょ? 怪しげで不快な「ネット広告」はなぜ蔓延するのか〈日刊サイゾー(2021年5月2日)〉
サイゾーだから迷ったのですが、内容はまともなので取り上げてみました。そしてこの記事の末尾にも、不快な広告がばっちり表示されているという皮肉。記事にもあるように「美容健康系を出さない」と決めれば、変な広告はだいぶ減るのは事実です。Google AdSenseなら、「デリケートなカテゴリ」をまとめてブロックすると、かなりマシになります。収益ゴッソリ減りますが。
問題なのは、記事でも「特にひどい」と言われているコンテンツ・ディスカバリー系のサービス。HON.jp News Blogでも一時期導入してみたのですが、「カテゴリー単位で非表示」にする機能が無く、NGワードを登録する方式でした。しかも、管理画面上から入力するのではなく、担当者にメールで連絡するという、なんでそこアナログなのよ! と叫びたくなるようなシステムでした。
美容系不愉快広告は全面的にブロックしたかったのですが、残念ながらNGワード登録では防ぎきれません。巧みな業者は文言だけ変えた広告を複数登録して効果検証しているので、想定外のところを突き抜けてきます。媒体に掲載される広告クオリティを保とうと思うと、毎日のメンテナンスが必須でした。
そして毎日メンテナンスしている自分自身も、管理画面上で不愉快広告を見て精神的ダメージを受けることに。こりゃ無理だと早々に諦め、コンテンツ・ディスカバリーサービスを使うのをやめました。メディア側からすると、「売上を減らすためにわざわざ手間をかけてブロックする」状態になるので、とても不毛な戦いになるのです。元から絶ってくれないと無理。
米ベライゾン、ヤフーとAOL含むメディア事業売却 50億ドル〈ロイター(2021年5月4日)〉
買い集めたメディア事業を大放出。携帯電話キャリアがメディアにも手を出し、大失敗した事例、ということになるでしょう。日本に直接関係しそうなのは、TechCrunchとEngadgetあたりでしょうか。Flickr、Tumblr、HuffPostは、以前にもう売却済みで、Yahoo! Japanは名称だけ。
Twitter、サブスク型ニュース配信に参入へ 米新興を買収〈日本経済新聞(2021年5月5日)〉
広がる音声SNS市場 既に群雄割拠、大手参入急ぐ〈日本経済新聞(2021年5月6日)〉
パブリッシャーが個々の記事、動画、ポッドキャストに対する支払いを受け取ることを可能にするFewcentsが1.7億円を調達〈TechCrunch Japan(2021年5月6日)〉
広告収入に頼らない「サブスク型プラットフォーム」はジャーナリストの救世主となるか?〈DG Lab Haus(2021年5月6日)〉
メディアと収益源、という括りで4本まとめてピックアップ。いろんな動きがあり、追いかけるのが大変です。広告モデル以外の選択肢がもっと伸びてくると良いのですが。
メディア大手、新聞事業を非営利化 広告減で存続困難―シンガポール〈時事ドットコム(2021年5月6日)〉
非営利化によって「ジャーナリズムの維持・支援に賛同する官民からの資金調達」を狙っているそうです。日本の共同通信やアメリカの「プロパブリカ」みたいにはじめから非営利なのと、営利目的だった事業を非営利化するのとでは、ちょっと印象が違うような……うまくいくかな?
書店の倒産が急減、2020年度は過去最少を更新 帝国データバンク調べ〈文化通信デジタル(2021年5月7日)〉
帝国データバンク4月24日のプレスリリースが、5月7日に記事化。2週間経ってると、ずいぶん昔のことのような気がしてしまいます。でも、これくらいじっくり掘り下げる記事なら、これくらいスローでもいいはずなんですよね。最近とくに、私自身が情報洪水に溺れ気味な気がしていて。
技術
話題のNFT。権利関係を見てみよう 岡本健太郎|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2021年4月28日)〉
注目のデジタル資産「NFT」 本物でも権利あいまい〈日本経済新聞(2021年5月1日)〉
ちょうど「NFTって権利関係どうなるんだろう?」と気になり始めていたので、非常にタイムリーな解説2本。いくらNFTで擬似的な所有が再現されたとしても、購入時の条件に明示されていなければ「著作権」は移動しないわけで。そこはもう明らかに物理メディアを「所有」することとは異なる、という認識が必要でしょう。
「NFT」ブームをあおる、75億円デジタルアートの買い手 写真3枚 国際ニュース〈AFPBB News(2021年5月2日)〉
NFTアートを史上最高額で落札したブロックチェーンビジネスの起業家が、保有する他のNFTの価値を引き上げるための宣伝行為と批判されているとのこと。そりゃ対外的には「アーティストのためだ」と喧伝するでしょうし、そういう側面もないわけではないでしょうけど、ねぇ。
HON.jp News Casting
4月26日のゲストはグラフィックデザイナーの美柑和俊さんでした。番組前半の部のアーカイブはこちら。
次回のゲストはイラストレーターの村田善子さんで、本の内容と装画の距離感などをテーマにお届けします。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
























