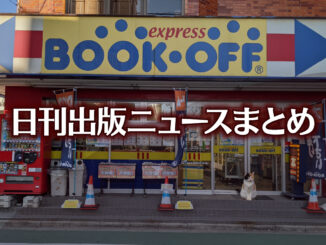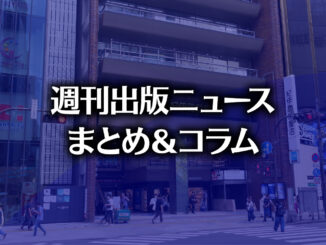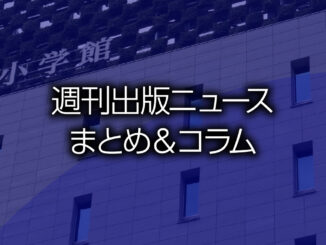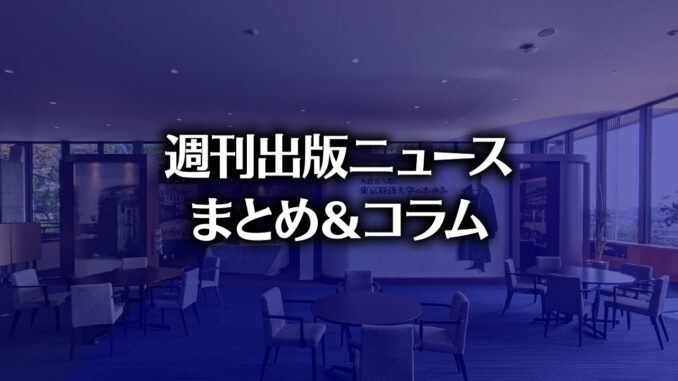
《この記事を読むのに必要な時間は約 18 分です(1分600字計算)》
2025年4月20日~26日は「生成AIは新刊の要約が出力できる?」「Adobe Fireflyで他社モデルも選択可能に」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
なお、5月5日は更新予定(大型連休のため縮小版になる予定)ですが、5月12日は前日に文学フリマ東京40出店のためお休みする予定です。あらかじめご了承ください。
【目次】
お知らせ
HON.jp Podcasting「#28 またサイトブロッキングが検討(2025年4月22日版)」を配信しました
サイトブロッキングといえば、2017年に「漫画村」などの海賊版サイトが猛威を振るって大きな問題になったときに検討されたことが記憶に新しいです。結局あのときはすったもんだの大激論の末、立法化を断念することになりました。
今回ターゲットになっているのはオンラインカジノなので、直接、本や出版に関わる話ではありません。ただ、もし、オンラインカジノのブロッキングが可能という話になったら、間違いなく次は海賊版サイトも対象にという話になるはず。政府の海賊版対策メニュー(2024年5月28日版)にも、いちおうまだ残ってますし。間接的ではあるけど、私たちにも直結する話題なので取り上げさせていただきました。
この番組ではみなさまからのお便りをお待ちしています。「こんなトピックスを取り上げて欲しい」とか「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。こちらのページでフォームから送付できます。
政治
「ニュースをブロック」したFacebookで偽装ニュースの投資詐欺広告が氾濫、カナダ総選挙を前に〈新聞紙学的(2025年4月21日)〉
カナダで2023年に成立した「オンラインニュース法(Online News Act)」で、Googleはメディアに対価還元する方策をとったいっぽう、Meta社はFacebookとInstagramでニュースをブロックするという強硬策に出ました。その結果、Facebookではいま偽装ニュースの投資詐欺広告が氾濫しているとのことです。まあ、日本のFacebookでは、ニュースがブロックされてなくても投資詐欺広告が氾濫していたわけですが。
ただし、メディア側もニュースコンテンツをキャプチャ画像で投稿するなどのブロック回避策を取っているという。
これがちょっと面白いなと思いました。つまり、日本でもよく見かける「URLはコメント欄に」という形で、カナダのメディアはブロックを回避しているそうです。日本でも、投稿内にURLがあるとインプレッションがガクッと落ちるのですよね。それを回避するためにやってる方をよく見かけます。
もっとも、アメリカではトランプ政権発足後のアルゴリズム変更により、Facebookからメディアへの流入が増加傾向にあるというニュースもありました。日本はどうなんだろう? Google Analyticsを見る限り、うちはほとんど影響なさそうですが。
オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第1回)〈総務省(2025年4月23日)〉
前述のポッドキャスト収録翌日、弁護士・中澤佑一氏がこの総務省による資料を参照しつつFacebookへ投稿しているのを見て驚きました。児童性的虐待記録物のブロッキングは緊急避難ではなく「約款に規定された契約上の措置として実行」されているそうです。緊急避難の要件はかなり厳しいので、児童性的虐待記録物でも成立は難しいとの見解。マジか。それは前提がいろいろ変わってきますね。
ちなみに中澤佑一氏は、政府がプロバイダに海賊版サイトのブロッキングが緊急避難で可能だとISPに“要請”したとき、やりますと手を挙げたNTTコムを「通信の秘密」の侵害にあたると訴えた弁護士です。結局、ブロッキングは実施されなかったため控訴審でも棄却されてますが、著作物では緊急避難の要件を満たさないという判断が示されました。政府の見解と司法の判断が大きくズレた判例を残した方です。
トランプ政権がWikipediaの運営団体を脅迫〈GIGAZINE(2025年4月26日)〉
トランプ政権が、Wikipediaは「外国の主体による情報操作やプロパガンダの拡散を許している」とし、運営団体であるウィキメディア財団の非営利団体適正に疑問符を付けているそうです。これぞ現代の焚書。そういえばトランプ政権1期目が始まる前に、こういう事態を危惧してInternet Archiveがカナダでバックアップを構築する計画を立てたことを思い出しました。
社会
新たな物語投稿サイト「Tales」、正式オープンしました!〈物語投稿サイト Tales(テイルズ)(2025年4月22日)〉
正式オープン、おめでとうございます。note株式会社の完全子会社であるTales & Co.株式会社による運営、だと思っていたんですが、noteとTales & Co.の共同運営なのですね。これまでnoteで開催されてきた「創作大賞」も、Tales & Co.との共同開催となるそうです。総勢38メディアが参加って、すごいなあ。
ただ、その「創作大賞」以外のところが、なにか既存の小説投稿サイトと大きく異なるわけではなさそうです。単に「noteからフィクションを切り離した」という印象に留まります。トップページに表示されている各作品の閲覧数を見る限り、読者をいかに増やすか? が今後の大きな課題になりそうです。
海賊版漫画の利用者への印象、アメリカでは「節約」が最多 対策組織が実態を調査〈KAI-YOU(2025年4月24日)〉
タイトルの「対策組織」は、一般社団法人ABJです。MMDLabo株式会社(MMD研究所)に委託して「海外の漫画非正規版利用に関する調査」を行ったそうなのですが、私には一次情報が見つけられない……プレスリリースも届いていませんでした。本稿執筆時点で、報道もこのKAI-YOU以外からは出ていないようです。詳細を確認したいんだけどなあ。
電子出版制作・流通協議会、「電流協アワード2025」大賞・特別賞を発表〈カレントアウェアネス・ポータル(2025年4月24日)〉
大賞は、「絵本ナビプレミアム」と「コロコロコミック」のダブル受賞です。おめでとうございます。
日本アドバタイザーズ協会がアドバタイザーによる、「広告の定義」を発表〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2025年4月24日)〉
こちら、AdverTimes.のメルマガでは“広告主企業による「広告の定義」を発表”という件名で届きました。「おや?」と思ったのですが、記事そのものでは従来通り「アドバタイザー」とカナカナ語が用いられ、「広告主企業」という表現は存在しませんでした。こういう広告業界特有のカナカナ語、煙に巻かれた印象になるから、やめたほうがいいと思うなあ。
内容的には、日本マーケティング協会が2024年に発表したマーケティングの新定義「(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。」の影響を強く受けている印象です。
経済
日販とTRC、図書館内ショップの実証実験 5月31日開始へ〈新文化オンライン(2025年4月22日)〉
昨年11月の図書館総合展で発表されたプロジェクトが、ついに動き始めました。和歌山県海南市、愛知県日進市、石川県野々市市の3館で実証実験を行うとのこと。さてどうなるか?
ゲームを超えた! LINEマンガがモバイルアプリ収益で頂点に〈マグミクス(2025年4月23日)〉
Sensor Towerのデータを使っている記事ですが、Sensor TowerはApp StoreおよびGoogle Playの収益だけを予測していることについて言及されていないので、いつものように指摘しておきます。要は、アプリ内決済以外の決済手段が多く利用されているところは、Sensor Towerのランキングに入らないのです。典型例が、アプリ内決済を排している「Amazon Kindleストア」や「楽天Kobo電子書籍ストア」などです。
日鉄ソリューションズ、インフォコムを買収 総額550億円〈日本経済新聞(2025年4月24日)〉
インフォコムは、「めちゃコミック」を運営しているアムタスを子会社に持ち、昨年、帝人グループからブラックストーンに売却された企業です。今回のこの記事、タイトルだけを読んだ段階では「えっ! ブラックストーン、もう手放すの?」と思ってしまいました。
今回の買収対象はシステム開発事業のみで、電子コミック配信事業はNSSOLへの売却前に切り離す。
つまり、「めちゃコミック」運営のアムタスは、ブラックストーン傘下のまま、ということになります。あー驚いた。ちなみにブラックストーンはインフォコムの買収に約2800億円投資していますので、「めちゃコミック」以外を切り売りして550億円回収したことになります。
漫画の無料配信サイト「マンガ図書館Z」5ヶ月ぶりに復活 クラウドファンディングが実を結ぶ〈KAI-YOU(2025年4月25日)〉
復活おめでとうございます!
技術
LINEヤフー、「Yahoo!ニュース」に生成AIによる記事選定機能「AIトピ」を導入〈ケータイ Watch(2025年4月23日)〉
ひとまず人力で選定する「Yahoo!ニュース トピックス」とは併存するようですが、そのうちすべてをAIがやるようになり、Yahoo!ニュース編集部から人がいなくなることでしょう。トピックスのタイトル13.5文字も、そろそろAIのほうが上手く作れそうですし。MSNニュースも最近、人を排してアルゴリズム選定だけに変えたと風の噂に聞きました。
まあ、GoogleニュースやSmartNewsなど、はじめからすべてアルゴリズムで選出しているサービスもありますから、もうそれほど違和感はないのでしょうけど。同じトピックスを扱う記事が複数のメディアからほぼ同時に配信されたとき、どれを選ぶか? については、人間の恣意的な判断よりむしろ公平になるかもしれません。
本を全て読むか、生成A Iが作った要約で読むか?〈岩佐 文夫(2025年4月23日)〉
個人の発信ですし本欄で扱うかどうか迷ったんですが、元ダイヤモンド社の「編集者」という肩書きで活動されている方なので、発信した情報に一定以上の責任はあるだろうと判断しました。タイトルに「A I」とスペースを入れているのはなぜか、ではなく、とくに以下の箇所について。
これをClaudeに「5000字に要約してほしい」とお願いするとものの数秒で文字が出てくる。
私の認識では、販売されている書籍の内容を生成AIが正確に要約できるケースは、「①ユーザーが購入した書籍の電子版を生成AIにアップロードする」「②その生成AIのトレーニング段階でデータセットに要約対象書籍がなぜか含まれていた」あるいは「③要約対象書籍の内容が全文一般公開されている」くらいでしょうか。購入しないと読めない本の中身は、まさに「価値ある情報がペイウォールの向こう側にある状態」なのですから。
だから私は当初、これは恐らく仮説①だと思いました。自分で購入した書籍のデータをClaudeに読み込ませるためには、紙版をスキャンしてOCR――なんて手間がかかることはやらないでしょうから、恐らく、Kindle版をCalibreなどを使ってDRMを解除して二次利用可能な形に変換してアップロードしたのだろう、と推測していました。なお、日本の著作権法では私的使用の目的であってもDRMを解除して複製する行為は違法なはずです。ご注意を。
ところが、私と同じ疑問を持ったであろう方がコメント欄で質問、著者の回答を見て目を疑いました。著者の方は、単に書名を挙げて「本の内容を5000字で要約してもらえませんか?」と入力しただけなのだそうです。つまり、本のデータはClaudeには渡していない。それって、要約を出力させたつもりで、Claudeが公開情報を元に本の内容を推測・捏造(=“要約”)したのでは? しかし、著者の方の回答後半を読んで、私は仰天しました。
claudeは半年くらい前に出た本の内容ならデータとして吸収しているようです。聞いた話ですが、chatGTPだと2ヶ月くらい前に出版された本もデータとして持っていて、上記のような指示で要約を作ってくれるようです。
うーん……伝聞調の不確か情報なので真に受けるのも、なんですが、私の知る限り「新刊の内容が学習され続けている」なんてことが、ソース付きで公になったことはないはず。仮にそれが公知の情報だったら、米国出版社協会(AAP:Association of American Publishers)や全米作家協会(Authors Guild)が黙っちゃいないでしょう。そんなのきっと、激怒しますよ。
もっとも、Claudeの運営会社Anthropic社が2024年8月に複数の著者から訴えられたのは事実です。ただしこれは、上記の仮説②「生成AIのトレーニング段階」で用いられたデータセットに海賊版電子書籍を含むとされる「Books3」がある、というのがその理由です。
これ、Meta社が訴えられているのとまったく同じ理由なのですよね。海賊版データだと知っていてトレーニングに使うことは、さすがにフェアユースの範疇を超えるような気がします。ただし、Anthropic社の裁判も、Meta社の裁判も、まだ決着はついていません。
なお、Gemini Deep Reserch with 2.5 ProとPerplexityで調査しましたが、Anthropic社の裁判でもいまのところ「半年くらい前に出た本の内容」をデータとして吸収しているといった証拠は提出されていないようです。裁判の争点はあくまでトレーニング段階の学習用データセットについて、です。
ただし、本欄の読者を混乱させてしまうかもしれませんが、こと今回の要約に関して言えば、それなりに正確なものが出力されていたみたいなんですよね。というのは、著者はClaudeによる“要約”を読んだのち、書籍そのもの(日本語訳版)も読んでいて、とくに違和感はなかったようなので。
今回この著者が“要約”させた本は『傷つきやすいアメリカの大学生たち』(日本語訳の刊行は2022年11月)ですが、原著“The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure”は2018年の刊行です。だから、その海賊版が学習用データセット「Books3」に含まれていた可能性はあります。
とはいえ、トレーニング済みのAIモデルには、本のデータそのものが含まれているわけではありません。統計的に近い内容が出力される可能性はあっても、本の内容をそのまま出力させるようなことはできないはず。だから今回の場合、やはりClaudeが公開情報を元に本の内容を推測・捏造(=“要約”)したと捉えるほうが自然でしょう。
では、それなりに精度の高い“要約”が出力されたのはなぜか? あくまで私の推測ですが、原著のWikipediaのReferencesにあるだけでも、関連する公開記事がかなりの本数あります。つまり、公開情報が豊富だから、推測・捏造だけでそれなりに精度の高い“要約”が出力できてしまったのかも。上記の③に近い(全文ではない)。ウェブにあまり情報がない本だと、恐らく馬脚を現すことでしょう。
ちなみにこれは完全に余談ですが、Claudeはデフォルトで「入力データを学習しない」設定になっているようです。Anthropic社を信じるなら、その設定をユーザーが変更していない限り、アップロードした情報は学習されません。まあ、今回の場合、そもそもアップロードはしていなかったようなので、その心配も要らなかったわけですが。
「Adobe Firefly」でアドビ以外のサードパーティー製AIモデルも選択可能に〈窓の杜(2025年4月24日)〉
ちょ、ちょっと待った。Adobeは「Adobe Firefly」を「学習データが“安全”な生成AI」とアピールしてきましたよね? だから私は、他の画像生成AIより性能が明らかに劣っているのはわかっていても、あえて「Adobe Firefly」を使ってきました。
でもこれって“安全じゃない”生成AIを組み込んで提供するって話ですよね? ユーザーが選択できるとはいえ、それってAdobeのスタンス的にアリなの? なんだかとても微妙な感じがするんですが。Content Credentialsに、どのAIモデルで生成したかの情報って入るんでしたっけ?
グーグル検索のAIによりクリック率は34%も低下・・・ahrefsの調査結果〈Media Innovation(2025年4月24日)〉
さらに、グーグルがAI Overviewに関連するクリック数や表示回数のデータをSearch Consoleで個別に提供していない点にも言及し、「グーグルは私たちにAI Overviewのクリック率を見せたくないようです」と指摘しています。
デスヨネー。これはそう思われても仕方ない。私も前から何度も言ってますが、さっさと見える化したほうがいいですよ。いまのままだと不信感が強くなるばかりです。
「こんなコンテンツはダメ」グーグル評価の傾向を50サイト分析データに学ぶ【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ〈Web担当者Forum(2025年4月25日)〉
なんて書いた直後に、Googleの見解が出てきました。なんてタイムリー。「グーグル主催の検索イベントで得たAI関連の学び×5」の4番目、「4. AIOとGemini検索の監視と追跡」です。「Search Console経由で『AIによる概要』を追跡できるようになるか」という質問に、Googleは以下のように回答したとのこと。
“現時点でSearch Consoleのパフォーマンスレポートにおいて考慮されているが、内訳は表示されていない。”
段階では、AIOの露出は変動的であるため、「詳細な情報を表示すると、助けになるよりも混乱を引き起こす」と考えているとのことである。
(※鷹野注:「段階では」は原文ママ。恐らく「現段階では」)
Search ConsoleでDiscoverを見える化したとき、Googleは同じ懸念を抱いていたのか? という疑問を覚えました。Discoverのデータを見ると、突然ドカッとアクセスが来たと思ったら、しばらく静まり返るみたいなことがよくあります。「そういうものだ」と思っているので、べつに混乱はしません。
仮に、情報を出すと混乱を招くとしても、出していない現状で招いている「不信感」よりマシだと思うのですけどねぇ……。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
個人的に、1年の中で最も快適な季節になりました。実に過ごしやすい。でももう少しすると「暑い」と感じるようになってしまうんだよなあ。(鷹野)