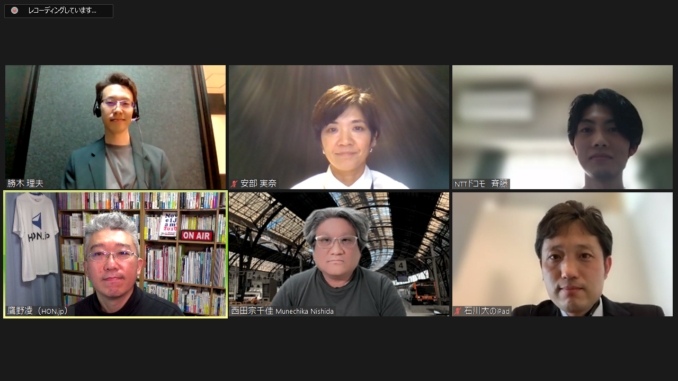
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
月額料金制の電子雑誌読み放題サービス「dマガジン」が、3月23日からAmazonの「Fireタブレット」に対応した。一方で、電子雑誌の市場は2017年を境に減少に転じており、伸びている電子出版市場の中で例外的な状況にある。dマガジンがなぜFireタブレットに対応したのか? そして、電子雑誌市場全体をどう捉えているのだろうか? 関係者に話を聞いた。
ご対応いただいたのは、NTTドコモ・コンテンツビジネス部 コンテンツサービス 書籍ビジネス 課長の石川大さん、Amazon側との折衝を担当した斉藤僚汰さん、そして、開発・運営を担当する株式会社ブックウォーカー・プラットフォーム事業部 部長の勝木理夫さんと、同 リレーショングループの安部実奈さんだ。
二極化する日本のタブレット、安さで注目されるFireタブレット
単刀直入に聞こう。Fireタブレットに対応した理由はどこにあるのだろうか? NTTドコモ・斉藤さんは次のように説明する。


この点について、ブックウォーカー・勝木さんはさらにはっきりとした表現で説明する。


ご存じのように、電子雑誌は現状、版面をそのまま固定レイアウトで提供する形。だから、スマホでも見られるが、大きな画面の方が向いている。しかし、dマガジン自体の利用者はスマホの方が多いという。一方で、快適に使うためにスマホとタブレットを併用している人の方が、「利用率やサービスの利用継続率は高い」と斉藤さんはいう。
そこで安価なタブレットとしてFireタブレットが注目され、「iPadかFireタブレットか」という市場になっていくなら、dマガジンがFireタブレットに対応するのは必然、ということになる。当然Amazonとしても、Fireタブレットの魅力を高める良い材料、と判断しているはずだ。
Fireタブレットへの対応自体は「2021年の春」(斉藤さん)には検討が開始されたものの、実装はほぼ1年後になった。理由は、dマガジンが2021年中にリニューアルを控えていたためだ。動作検証を考え、「まずリニューアルし、その後Fireタブレットに」(勝木さん)ということになったようだ。
雑誌が弱くなる中で高まるdマガジンの「露出効果」

では、その理由はどこにあるのか?
それはズバリ「雑誌そのものの市場の縮小」だ。「雑誌市場が縮退傾向で、それに伴い、電子雑誌を読むユーザーも減少傾向にある」と斉藤さんは言う。

「出版社の方々からよく、状況の変化について耳にします。書店は減り、コンビニやキオスクから雑誌がなくなってくると、『表1(雑誌の表紙のこと)をどこでも目にすることができなくなっている』。そうすると、『もう勝負の場、戦いの場にも立てない』と言うんです。だから、『数百万単位のユーザーがいるアプリの中で表紙が出ることがありがたい』、『週刊文春や週刊フライデーのような媒体と同じ土俵で戦えるだけありがたい』という話もいただきます」(勝木さん)
同じくブックウォーカー・安部さんもそれに同意する。

dマガジンがスタートした8年前は、まだ雑誌が元気だった。「紙対デジタル」の意識も強かった。そのため、まず「dマガジンに参加してもらう」ことを口説き落とすところから始まったわけだが、今はもう状況が変わり、いかに協力して「雑誌の市場を維持するか」というフェーズになっているのだ。
その観点で気になるのが、「dマガジン for Biz」の存在だ。美容院や待合室などで、ビジネスの中で雑誌を見せる必要がある場所で、dマガジンを提供するための仕組みであり、同様のサービスは他の電子雑誌サービスにも存在する。
NTTドコモ・石川さんはビジネスの現状を以下のように話す。

雑誌のみつかりやすさ=アピアランスが上がるということは、それだけ、読まれていない記事が読まれる可能性が高くなっていく、ということでもある。コンテンツを出す雑誌社との関係としても、電子雑誌サービスとの関係は以前とは大きく異なったものになっている、ということなのだろう。
そんな中、dマガジンの直接競合となっているのは「楽天マガジン」。NTTドコモ側も「ベンチマークとして意識している」(斉藤さん)と話す。両者が競いつつ、機能や見せ方、コンテンツなどが似てきている部分はありそうだ。
「電子版で読めない」問題にどう対処するのか

「記事が読めない、という声を実際にいただくことがありますが、(サービス利用継続に)クリティカルな意見というよりは、『もっと記事が読めたら良いのに』というご要望が多いです。より雑誌を楽しんでいただくためには、もちろん、コンテンツをフルで提供するのが良いかと思いますが、そこは出版社との交渉になりますので……」(斉藤さん)
サービサーとして顧客と相対しているNTTドコモ側はそのように話す。
では、開発・運営に加え、出版社との交渉を担当するブックウォーカー側はどう考えているのだろうか?
「欠損している部分に目がいきやすいのはあると思います。自社でデジタルサービスをやられるところも増えてきており、『その場合は(自社で)先に出したい』という考えはお持ちだろうと思います。ただ、そこにサービスが寄り添っていかなくてはならないと思います。やはり、雑誌文化を絶やすことはできません。今まで出していただけなかった媒体でも、今は出すページ数を増やしている、ということもあります。女性誌の場合だと、以前は(全体ページの)6割くらいしか出していただけなかったところが、8割・9割出していただけるようになってきています。それは記事へのタッチポイントを増やしたい、というところだと思っています」(安部さん)
では、紙版の販売後、追いかけてdマガジン側でデータをアップデートし、読める量を増やしていくことはできないのだろうか? この点については、サービスとしての特性をどう考えるのか、という点が絡んでくる。
「サービスを開始するとき、我々は『サービスはできるだけシンプルにしなければいけない』と思いました。後から追加することがユーザーにとっていいのか……と考えた時に、何度もサービスにアクセスしていただくことになるので、ユーザーフレンドリーではないのではないか、と考えたんです。毎日新しい雑誌が流れていく、というサービスコンセプトです。だから、配信も紙の雑誌の発売とディレイがありません。実は、サービス開始前にはバックナンバーも入れていませんでした。ただ、直前でバックナンバーは入れましたが。あくまで『最新号がフローコンテンツで読める』という発想でした。その発想は今も間違いではなかった、と思っています」(勝木さん)
若者に「記事の魅力」を届けるには
ただし、時代は変わってきている。それがdマガジンというサービスに大きな影響を与えていることもまた事実だ。
「InstagramやTikTokが隆盛の時代、フローとはいえ、dマガジンは同じフローでいいのか……という考えがあります。電子雑誌は、純粋な『デジタル to デジタル』のフローには抗しきれない部分がありますから。ただ、昨今のウクライナ情勢でもそうですが、雑誌なら数日ディレイがある代わりに、ちゃんとまとまった、質の良いものが読める。時代に『8年前と同じではいけないよ』と言われているような気がしています」(勝木さん)
NTTドコモ側の見解として、石川さんは次のような見方を示す。
「dマガジンはスタート以来、雑誌に慣れ親しんだ方々の要請に応える形で展開してきました。ただ、SNSなどの、dマガジンスタート時にはそこまで普及していなかったサービスに触れている人々にはコンテンツを届けることができていない。そこでどう変わっていくべきか、難しい点です。ですが、もう残されている時間はあまりない。雑誌の力が相対的に弱っている中で、どう抗うのか。雑誌を好む方もいらっしゃるわけで、そうした方々のニーズを守りながらどうやっていくのか。結果的に、変化には数年かかるかもしれませんが、今から始めないと追いつきません」(石川さん)
勝木さんは、雑誌の良さ・魅力を考えながら、次のように考察している。
「雑誌の強さというのは、やはり『版面に力がある』ことです。サイズの小さいディスプレイでは読みづらいからといって、簡単にリフローの世界に降りていくことはできません。ただ、雑誌の力が、数字として現実問題弱くなっているのは事実なので、そのままで良しとも思っていないです。若い人たちは、そもそも雑誌を読んだことがないんです。だから、読んでもらえるととすごく面白がってくれます。雑誌記事は宝の山なのに、出会いの場がないんです。では、誰もが持っているスマホというデバイスを使い、記事が彼らに『こんなに面白いんですよ』とダイレクトに届くようにするには、どうしたらいいのだろう……と。その方法を考えているところです。これはあくまで私見ですが、こうした要素はアプリの中だけに完結していいのか、とも思います。さらに私見ですが、『dマガジン』の冠があれば、それがNTTドコモのウェブサイトの中にあってもいいのでは、と思うんです」(勝木さん)
dマガジンは、雑誌の魅力をデジタルにするために生まれ、そこが支持されてきた部分だ。だがインタビューから分かるように、「雑誌への認知低下」そのものが、サービス利用の低下を招いている。一方でそのことは、雑誌の価値を高めるため、出版社から期待される要因にもなっている。
このジレンマをどう解決するのか。彼らもいう通り、残された時間は長いものではない上に、難しい課題である。










