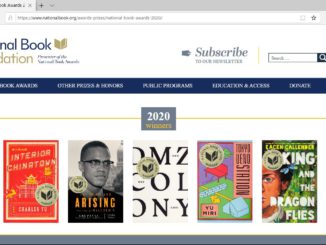《この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です(1分600字計算)》
アメリカの出版業界では今後、紙への回帰と、紙からの離脱が進むであろうという予測がなされています。これはどういうことか? おなじみ、大原ケイさんの解説です。
アメリカ出版業界のトレンド予想
米経済誌の「フォーブス」が、出版産業のトレンドを予想する記事を掲載した[1]。そこに掲げられた8項目には「小出版社がニッチに焦点を絞る」「デジタル購読者は今後も増える」といった、当たり前に思えるものもあるが、「なんのこっちゃ?」と首を傾げたくなる予測も含まれている。少し考察をしてみた。
Marketing will entail more valued content to the current audience and not so much in mainstream media.
わかりにくいかもしれないが、このセンテンスの意味はこうだろう。「これからの本のマーケティングは、既存の主流メディア(つまりは紙媒体を維持している新聞や雑誌を指す)ではなく、既に読者がいるところに向けて、付加価値のあるコンテンツを提供する形になっていくだろう。」と訳せばイメージがつかめるだろうか。
つまり、好みや嗜好が千差万別な「一般」の消費者に向けて、広く浅く(そして値段の張る)メディアに広告を打ったり、手広く漫然と販促の宣伝をする方法ではなく、その本に興味を示すであろう読者がいるコミュニティーを特定し、そこに何らか付加価値のある、つまり「お得な」「ファン向けの」情報を流すことによって、その本の存在を知らしめ、読んでもらうことにつなげるマーケティングにシフトしていくだろうというのだ。だが、それには、どんな本を出すにしろ、潜在的な読者が(主にネット上の)どこにいるのかを、本を出す側がちゃんと把握していることが前提となる。
Partnerships will take precedence over competition.
「競合ではなく、協力」という抽象的なセンテンスだが、これは出版社同士がこれからも統合され、インプリント化することを指している。2020年にも大手出版社のサイモン&シュスターが最大手のペンギン・ランダムハウスに買収されるというニュースがあった。
この傾向がこれからも続くとしたら、巨大化した出版社から刊行されるタイトルにも変化が出てくる。ヒットが予測される少数の作品に絞られ、ダイバーシティーとは逆の動きが見られるだろうことは既に懸念されている。そしてこの流れに取り残された小出版社がますますニッチ化するという、最初の予測と表裏一体の動きということだ。ちなみに、寄稿者自身が自分の名を冠した小出版社を経営している。
フォーブスのこの記事には他にも、オーディオブックが(特に自己啓蒙の分野で)さらに広まり、出版社が自社サイトやSEO(検索エンジン最適化)の予算枠を増やし、デジタルのサブスクライバー(定期購読者)が増えていくというIT対策の一方で、2025〜2030年には紙の本も勢いを取り戻すだろうという、一見相反する予測が並ぶ。
だがそれはこういうことだ。読み手が選ぶ紙媒体の本はこれからも意味のある選択肢として残っていくが、その一方で、出版社側の「本作り」と「販促」のツールがさらにデジタル化し、紙を離れていくということだ。
書く、読む、そして、話す、聞く
新型コロナウイルスで世界でも桁違いの感染者・死者を記録した2020年のアメリカだったが、本の消費は前年比で約9%成長した。近所の本屋に出向いて紙の本を買うことはできなくなったが、その分を上回るほどオンライン書店で注文したり、デジタル版やオーディオ版で本を楽しむ機会が増えたということだ。
これまで書店内でやっていた著者イベントはZoomを使った遠隔イベントに移行し、毎年5月に大勢の出版関係者が集まる「ブック・エキスポ」に至っては、リアルイベントそのものが終了した。そして、一般書に限っては、デジタル版に続き、「本」というからには、刊行時にオーディオ版もあって当たり前、という風潮になりつつある。本のマーケティングツールとして、テレビやラジオではなく、ポッドキャストが欠かせない、というのもこの1年で大きく変わったことのひとつだろう。
つまり、紙の本がなくなる、あるいはこれから極端に減っていく、という兆候はないが、本が読者の本に届く過程がバーチャル化、デジタル化、そして音声化されている。もともと、アメリカは都市の一部を除いた全土で車通勤がデフォルトであり、車中でオーディオブックを聞く「読書」が根付いている、という背景があるが、コロナ禍で自宅勤務時間が増えるのと並行してオーディオ本の消費が増えている。
本のマーケティングにおいても、新刊発表のたびに著者が自著を朗読する機会も多く、最近はオーディオ版を自分で朗読する著者が増えている。自分でポッドキャスト番組を維持する著者や、ゲストとしてポッドキャストに出演することが売り上げに直結する。
詩歌の朗読や、イベントも盛んだ。1月のジョー・バイデン大統領就任式の際に注目を集めた若き桂冠詩人が、スーパーボウルでも詩を発表したり、全米のインディペンデント書店経営者が(バーチャルに)集う「ウィンター・インスティーチュート」でも、パネルディスカッションの合間に詩の朗読で「休憩時間」を設けるまでになった。これらのことは、本がただ「読み書き」される娯楽ではなく、「話され」「聞かれ」るものでもある、という認識が強まったからと解釈できる。
デジタル化、ネットワーク化、EブックやSNSの登場、スマホやスマートスピーカーの普及……従来の「本」を脅かすとされたすべての事象に対し、アメリカでは出版社も読者もそれを「本を届けるための新たなチャンス」として捉え、変化し、対応してきた感がある。だからこそ、クラブハウスという新しいアプリが流行っていると聞いても、どこかの部屋で著者が自著を語っていたり、出版社のマーケティング企画としてのイベントがあるだろうという確信がある。
その一方で、オーディオブックのラインアップもまだまだで、書評をするポッドキャスト番組もほとんど見当たらない日本において、最近急にクラブハウスがもて囃されるのが奇妙に思えたのだが、これは読書からますます遠ざかる行為なのではないかと憂える気持ちがあるからだろうか。
注記
[1]Changing Trends In The Publishing Industry〈Forbes(2021年2月11日)〉