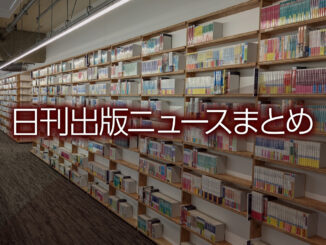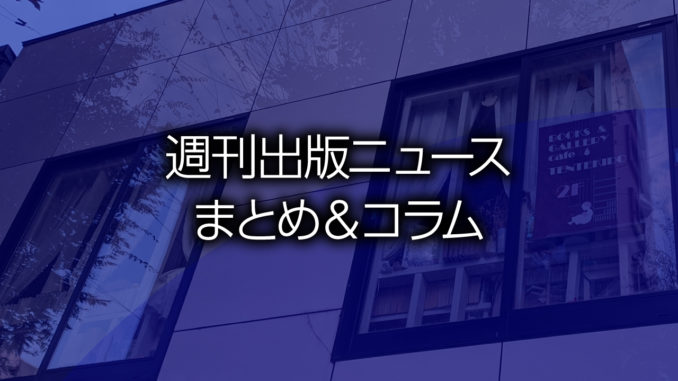
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2021年2月28日~3月6日は「図書館のネット対応閣議決定」「法改正で違法音楽アプリ利用者急減」「米出版産業のトレンド」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 政治
- 社会
- カズオ・イシグロ氏、若い作家の自主検閲を懸念 「ネットでの攻撃を恐れている」〈BBC NEWS JAPAN(2021年3月1日)〉
- 表現が過激? 「デスノート」「いぬやしき」…ロシアで日本アニメが続々禁止に〈東京新聞 TOKYO Web(2021年3月1日)〉
- ドクター・スースの6作品、人種差別描写で出版停止に〈BBC NEWS JAPAN(2021年3月3日)〉
- 黒人詩人作品めぐり騒動、白人作家が翻訳辞退 オランダ〈AFPBB News(2021年3月3日)〉
- GIGAスクール端末はAppleが首位。ChromeOS+Windowsではレノボ〈PC Watch(2021年3月2日)〉
- オトバンクとKCCSが提供する本を耳で聴く「オーディオブック配信サービス」 文京区、日進市、大津市の公共図書館が新たに導入開始〈株式会社オトバンクのプレスリリース(2021年3月4日)〉
- MITの大学出版局が学術書の持続可能な出版とアクセスを目指すプロジェクト「Direct to Open」を発表〈GIGAZINE(2021年3月4日)〉
- 著作権法改正後の違法音楽アプリ利用者は大きく減少〈一般社団法人日本レコード協会のプレスリリース(2021年3月5日)〉
- 経済
- 東浩紀さん、模索の10年 たどりついた「哲学の実践」〈朝日新聞デジタル(2021年2月27日)〉
- PayPayとLINE Pay、2022年4月に「PayPay」統合へ〈ケータイ Watch(2021年3月1日)〉
- 米出版産業のトレンドは紙への回帰と紙からの離脱なのか〈HON.jp News Blog(2021年3月2日)〉
- コロナ禍で参加者4倍のオンライン読書会「ペアドク」 サービス責任者に狙いを聞いた:「近づけない、集めない」時代を生き抜く、企業の知恵〈ITmedia ビジネスオンライン(2021年3月3日)〉
- Google、ネット広告の制限強化 個人の閲覧追跡させず〈日本経済新聞(2021年3月3日)〉
- 落合陽一×小沢高広(漫画家ユニット「うめ」)「テクノロジーを描いた漫画は現実に追いつかれる?」【前編】〈週プレNEWS(2021年3月3日)〉
- 落合陽一×小沢高広(漫画家ユニット「うめ」)「AIはまだ『漫画を読む』ことができない」【後編】〈週プレNEWS(2021年3月4日)〉
- 巨人用の「進撃の巨人」を100冊限定で販売、ギネス世界記録目指す〈コミックナタリー(2021年3月4日)〉
- ローソン、付録付き雑誌の雑誌だけデジタル化〈Impress Watch(2021年3月5日)〉
- 2021年中にSpotifyのポッドキャストリスナー数がアップルを上回るとの予測〈TechCrunch Japan(2021年3月5日)〉
- 技術
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
政治
Google、Facebook「支払い義務化法」が各国に飛び火する〈新聞紙学的(2021年3月1日)〉
オーストラリアで可決したプラットフォーム規制法が、カナダやEUなどにも波及し始めているそうです。その一方で、交渉力が不均衡であるとし、Microsoftがメディア側の後ろ盾になる動きも始まっています。
これ、言い方を変えると「伝統的で支配的だった巨大メディア企業が、新興企業と対抗するため政治を動かした」とか、「新興企業の後塵を拝したかつての巨人が、政治力を使って勢力を取り戻そうとしている」という話なのですよね。そう考えると、個人的には新興企業側を応援したくなってしまう。Facebookは嫌いですが。
図書館の蔵書、メール送信可能に テレビ番組、ネット配信簡素化へ〈共同通信(2021年3月5日)〉
著作権法の一部を改正する法律案〈文部科学省(2021年3月5日)〉
ずっと追いかけていた著作権法31条(とテレビ番組のネット同時配信)の改正案が、ついに閣議決定。この記事では複写サービスのネット対応だけが取り上げられていますが、入手困難資料の家庭配信ももちろん同時に進んでいます。前から言っているように、私は後者のほうが影響は大きいと思っています。いま「図書館送信対象」で館内の端末限定で閲覧可能な150万点以上のデジタル資料が、家から利用できるようになるわけで。ワクワクしますね!
文科省のサイトで、条文案や解説資料も公開されました。法律は大枠だけで、あとはガイドライン運用に委ねるのかと思っていたら、けっこう細かく条文に書き込んでいて驚きました。「きっちりDRMかけてね」「事前登録ユーザーに限定してね」「要ログインにしてね」と。パブコメで権利者側が主張していたことに寄り添った形です。「ここまできっちり書き込んだら、さすがに文句は言えまい」という声が聞こえてきそう。あと明確になっていないのは、「海外からの利用」と「学校図書館の扱い」あたりでしょうか。国会の審議でその辺りの話が出てくるかどうか。
文化庁長官にJASRAC特別顧問 公正中立は保てるか〈朝日新聞デジタル(2021年3月5日)〉
JASRAC前会長でいまは特別顧問の都倉俊一氏が、4月1日付で次の文化庁長官に。「指導・監督される側が、指導・監督する側に回る」ことの是非を問う記事で、反響でも「利権」「癒着」「利益相反」「ズブズブ」といった声が目立ちます。
ただ、立場が変われば考え方や行動も変わるでしょうから、きっちりJASRACと手を切った上で就任されるのであれば、一概にダメとは言えないように思います。むしろ、この立場でJASRAC寄りの発言なんかした日にゃ猛反発されるのが目に見えているわけで。毅然とした態度ができるかどうかが問われるのではないかと。
米、IT解体論者を補佐官起用 規制強化への布石か〈共同通信(2021年3月6日)〉
アメリカのバイデン新政権人事。巨大IT企業は解体すべきという論者が、大統領特別補佐官(技術・競争政策担当)に起用されたとのこと。前政権の末期に司法省から訴えられたような流れが、新政権でもそのまま続くようです。さあどうなるか。Microsoftは結局、解体できなかったわけですが。
社会
カズオ・イシグロ氏、若い作家の自主検閲を懸念 「ネットでの攻撃を恐れている」〈BBC NEWS JAPAN(2021年3月1日)〉
自主検閲というか、萎縮するのは間違いなさそう。とくにいまは巣ごもり生活続きで世の中に鬱憤がたまっていて、感情のコントロールが効きづらくなっているように思います。とくに「怒り」。これがここまで燃えるのかと驚くような「炎上」事件も多い気が。
いまは万単位でリツイートされるような拡散も珍しくないので、想定読者以外に届いてしまうことも避けられません。ある程度反発されるのを覚悟の上で発信していたとしても、大量に押し寄せる「怒り」感情の波に直接襲われたら耐え切れない。防波堤になるのが、パブリッシャーの役目の一つとも思うのですが……。
表現が過激? 「デスノート」「いぬやしき」…ロシアで日本アニメが続々禁止に〈東京新聞 TOKYO Web(2021年3月1日)〉
ドクター・スースの6作品、人種差別描写で出版停止に〈BBC NEWS JAPAN(2021年3月3日)〉
黒人詩人作品めぐり騒動、白人作家が翻訳辞退 オランダ〈AFPBB News(2021年3月3日)〉
表現の自由に関わる、海外の事例3連発。文化は地域によって異なりますし、法律ももちろん異なります。たとえばロシアや中国では、同性愛表現への規制が非常に厳しいと聞きます。だから、日本産の作品がそのまま輸出できず、カットされたり描写が変更されたりというのはよく聞く話ではあります。
2番目のドクター・スースの件も、作品を管理する会社の判断で一部の継続出版を止めたという話なので、まだ理解はできます。でも3番目のは、さすがにちょっと……という感じ。白人が黒人の作品の翻訳者に選ばれたことに対し、SNSで批判され、辞退するに至ったという話。この論理が通るなら、世界中の民族が他言語への翻訳者を自前で育てねばならないことになってしまうわけで。あり得ない。
GIGAスクール端末はAppleが首位。ChromeOS+Windowsではレノボ〈PC Watch(2021年3月2日)〉
メーカー別シェア。2月16日にはOS別のシェアが既に発表されてた(↓)ことに気付いておらず、MM総研に「OS別のシェアは?」って問い合わせちゃいました……恥ずかしい。Chrome OSが43.8%でトップシェア、iPad OSが28.2%、Windowsが28.1%とのことです。先週、「残りも、iPadの割合のほうが多いんじゃないかしら」と書いたんですが、ほぼ同数でした。
オトバンクとKCCSが提供する本を耳で聴く「オーディオブック配信サービス」 文京区、日進市、大津市の公共図書館が新たに導入開始〈株式会社オトバンクのプレスリリース(2021年3月4日)〉
公共図書館向けのオーディオ配信サービスも、導入自治体が増えてきそうな兆しです。これも電子図書館サービスの一種ですが、電流協で集計するかな? もっと普及して欲しいところです。
MITの大学出版局が学術書の持続可能な出版とアクセスを目指すプロジェクト「Direct to Open」を発表〈GIGAZINE(2021年3月4日)〉
なかなか面白い試み。図書館の規模や予算に基づき算出された参加費を定期的に払うことで、「Direct to Open」にある学術書へアクセスできるという仕組みです。ちょっと変則的なサブスクリプション・モデルといったところ。「個々の図書館が単一の学術書を購入する市場ベースのモデルから、図書館が出版をサポートするモデルへの移行を目指す」とのことで、「共助」が限りなく「公助」へ近い形に転換したとも言えそうです。
著作権法改正後の違法音楽アプリ利用者は大きく減少〈一般社団法人日本レコード協会のプレスリリース(2021年3月5日)〉
違法音楽アプリ「MusicFM」などの利用者が、昨年10月施行のリーチサイトを違法化する改正著作権法により、4分の1に激減しているというプレスリリース。これ、出版関連ではむしろ「海賊版サイトが増えている」という話が出ている(↓)ので、なぜそんなに違うのか? という検証が必要だと思います。ストリーミング配信が違法じゃないのは、映像・音声も同条件ですし。
経済
東浩紀さん、模索の10年 たどりついた「哲学の実践」〈朝日新聞デジタル(2021年2月27日)〉
東浩紀さんの『ゲンロン戦記』、大変興味深く読ませていただきました。東さんのもがき続けてきた軌跡が、私自身の試行錯誤の歴史とわりと似ていて親近感を覚えます。もちろん、私のほうがスケールはもっと小さいのですけど。成功事例は生存バイアスになりがちですが、「こういう失敗をした」という正直な記録は有益。失敗学です。
PayPayとLINE Pay、2022年4月に「PayPay」統合へ〈ケータイ Watch(2021年3月1日)〉
経営統合完了とともに、サービス統合への動きも発表。QRコード決済は乱立気味でしたが、1位のPayPayと2位のLINE Payが統合することで、趨勢は決まったと見ていいでしょう。小売店にとっても、オペレーションがラクになって良いのでは。
米出版産業のトレンドは紙への回帰と紙からの離脱なのか〈HON.jp News Blog(2021年3月2日)〉
おなじみ、大原ケイさんの解説。アメリカの出版業界では今後、紙への回帰と、紙からの離脱が進むであろうという予測です。最終段落にとても共感。「Clubhouse」が日本で急に盛り上がったこと、私も違和感あったのですよね。ライブ性が強すぎて、本の持つアーカイブ特性とは真反対。
コロナ禍でやりづらくなってる「居酒屋談義」とか「井戸端会議」の代替として伸びているようにも思うので、緊急事態宣言が明けたら急にブームが沈静化しそうな気も。真価が問われるのは、そこからになるでしょう。
コロナ禍で参加者4倍のオンライン読書会「ペアドク」 サービス責任者に狙いを聞いた:「近づけない、集めない」時代を生き抜く、企業の知恵〈ITmedia ビジネスオンライン(2021年3月3日)〉
オンライン読書会にここまでニーズがあるとは。著者へ直接質問できる機会の提供で、会場まで足を運ばなくてもいいとなると、とくに地方在住者には福音なのかも。ウチでやってるHON.jpブロードキャスティングも、もう少しゲストをメインにした方向へリニューアルしようと思います。
Google、ネット広告の制限強化 個人の閲覧追跡させず〈日本経済新聞(2021年3月3日)〉
Google Chromeでも今年中にサードパーティーCookieの利用規制が行われることは以前から表明されていましたが、改めてGoogle幹部が公式ブログで「ウェブサイトを横断して個人を追跡する代替技術を開発したり、こうした技術を当社製品で使用したりしない」と表明したというニュース。個人を追跡する代替技術ではなく、似た趣味や嗜好でグループ化する代替技術を開発していたわけですが。目処がついた、ということでしょう。
落合陽一×小沢高広(漫画家ユニット「うめ」)「テクノロジーを描いた漫画は現実に追いつかれる?」【前編】〈週プレNEWS(2021年3月3日)〉
落合陽一×小沢高広(漫画家ユニット「うめ」)「AIはまだ『漫画を読む』ことができない」【後編】〈週プレNEWS(2021年3月4日)〉
昨年秋に開講された、筑波大学の「コンテンツ応用論」を再構成した連載。漫画家ユニット「うめ」の軌跡や現状などが語られています。紙の単行本より、電子書籍のほうが3倍くらい売れているというのが凄い。
巨人用の「進撃の巨人」を100冊限定で販売、ギネス世界記録目指す〈コミックナタリー(2021年3月4日)〉
あまりに巨大。保存ケース付きで、お値段16万5000円。儲かってるから、こういう企画も通りやすいんだろうなあ、と思ってしまいました。原画よりはるかに大きいわけですが、解像度はどうなってるんだろう?
ローソン、付録付き雑誌の雑誌だけデジタル化〈Impress Watch(2021年3月5日)〉
もはや付録が商品で、雑誌がオマケ状態のような。電子版は「honto」でダウンロードする形です。ブックライブがファミマで展開している「Airbook」でも応用できそうです。
2021年中にSpotifyのポッドキャストリスナー数がアップルを上回るとの予測〈TechCrunch Japan(2021年3月5日)〉
トレンドとして。Appleも微増傾向だけど、Spotifyの伸びが激しく、2021年中に逆転する見込みとのこと。
技術
お客も店員もいない無人書店を作ったのは? 奈良から最先端ビジネス〈Lmaga.jp(2021年2月28日)〉
事前登録ユーザーのみ入店可能というのと、5台のワイヤレスカメラで24時間リアルタイム配信される仕組みで、万引きはこれまでゼロとのこと。カメラが人の歩く速度で動いて棚を映す、という仕掛けが面白い。
集英社がマンガを活用した新事業、受け継がれるべきアートにして世界へ発信〈コミックナタリー(2021年3月1日)〉
すべての作品はブロックチェーン証明書サービス「Startbahn Cert.」(↓)に登録され、ICチップが内蔵されたICタグシール付きの証明書が同梱されている、というのが技術的なポイント。作品がいつどこで展示・保管・修復され、誰の手に渡り、どのような評価を受けたのか? という履歴が、改竄の難しいブロックチェーンに記録されているというわけです。面白い。
ブロードキャスティング
次回のゲストは吉川浩満さん(文筆家・編集者)です。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。