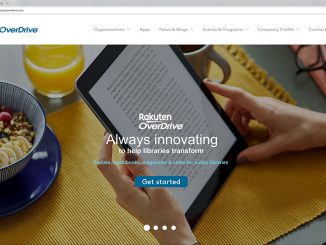《この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です(1分600字計算)》
アメリカでは、トランプ大統領暴露本の出版ラッシュが続いている。出版停止を狙ったスラップ訴訟は大半が即座に失敗しているが、例外的にジョン・ボルトン元補佐官の本だけは、司法省の横やりでいまなお裁判が継続している。それはなぜか? 大原ケイ氏に解説いただいた。
公人に対する「名誉毀損」は認められづらい
11月3日の大統領選挙を目前に、アメリカではドナルド・トランプ大統領の過去にまつわる暴露本のラッシュが続いている。現在ベストセラーリスト入りしているものでも、十分な遺産相続のなされなかった姪っ子が親戚に聞いた話も含めてドナルドの子どもの頃からのエピソードを綴った本、自称不動産王の頃からトランプの悪事に手を染めてきた手下だからこそ知り尽くしている悪行の数々を解説する元個人弁護士による本、10年以上に渡りメラニア・トランプ夫人の親友だったのに就任式献金のスキャンダルの濡れ衣を着せられた女性の本、そして9月15日に刊行されるや否や売れ行きでトップに躍り出たのが、ワシントン・ポスト紙のベテラン記者、ボブ・ウッドワードによる第2弾のトランプ政権検証本、『RAGE』だ(日本語版は12月19日に日本経済新聞出版社から刊行予定)。
2017年初頭の就任直後からトランプ大統領は、自分のことを書いた暴露本が出ると聞くとすぐに訴訟を起こして出版を差し止めようとしてきたが、ウッドワードの本に関してはノータッチだ。それもそのはず、いきなりトランプが自宅に電話をかけてきた1度以外には、10数回に及ぶインタビューで自ら喋り、ウッドワードはすべてその会話を録音し詳細なノートをとっているからだ。ウソを書かれたとか、そんな話はしていないという主張は不可能なのだ。
他の本の出版停止を求めた訴訟に関しても、瞬く間に裁判所から却下され、結局、刊行を遅らせるなどの時間稼ぎはおろか、訴訟すること自体が刊行前のプレパブとして大いに売上に貢献することがわかってきたのか、はたまた迫り来る「審判の日」を前に支持者の前で自慢話とホラ話を繰り広げる遊説に忙しいのか、とにかくようやく訴訟は無駄だということだけは理解したらしい。
このような出版社と著者相手を相手取って出版停止を求める訴訟の場合、根拠となるのはほとんどの場合が名誉毀損(libel)だ。裁判になった場合、ただ気持ちが「傷ついた」と主張してもダメで、実際にどのようなダメージ(商売の邪魔になって売り上げが落ちたとか、医者がうつ病の原因だとする診断を下したなど)を受けたかを、法廷の場で原告側が証明しなければならない。また、政治家や芸能人の場合、「公人(public figure)」として誹謗中傷を受けたとしても、ダメージのハードルはさらに上がる。
さらに、原告が大統領や議員など政府の公職にある人物の場合、全て最高裁に行き着く前に米国連邦憲法の権利章典である修正第1条(the first amendment)により却下される。この条項を訳せば「米連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、 及び国民が平穏に集会する権利及び苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を制限する法律を制定してはならない」となるが、その「出版の自由」にことごとく引っかかるためだ。
国家機密に関わる場合は公表前審査の対象に
政治家に忖度せず、むしろ三権分立に次ぐ第四階級(報道界)の一員として、出版社は権力の地位にある者のスキャンダルをむしろ積極的に暴く役割を担っているといえる。だがもちろん、ごく少ない例外もある。今回の暴露本の中では、その例外が、元国連大使で、トランプの元で国家安全保障問題担当の補佐官を務めていたジョン・ボルトンの本だ(日本語版は『ジョン・ボルトン回顧録』として朝日新聞出版より10月7日刊行予定)。昔からボルトンといえば超タカ派で、長年にわたってイランとの戦争を切望し、本著では日本の国家安全保障局長を務めていた谷内正太郎とのからみも登場するが、彼の本だけは今も米司法省の標的となっており、裁判が続いている。
これはひとえにボルトンが国家機密に関わる政務に就いていたからであり、アメリカでは元CIA捜査官や海軍の特殊部隊SEALSに在籍していた者など、政府の機密保持契約の上で仕事をしていた人物が本を上梓する場合、国防省による公表前審査(pre-publication review)の対象となるからだ。(出版物は回顧録だけでなく、スリラーなどのフィクションを上梓する場合も必要とされる。)
つまり、出版社は刊行前に国防省の調査部に原稿を渡し、チェックする必要があるのだ。しかし、ボルトンの著書の場合、そこに国家機密に関わる内容が書かれているかどうかより、トランプ政権の悪行や大統領の外交音痴ぶりの暴露を阻止しようとしていたのか、3月の刊行予定日まで許可が降りなかった。そこで、ボルトンと出版社側は独自調査で内容に問題なしと判断、刊行に踏み切った。(名誉毀損の訴訟は6月の時点で首都ワシントンの地方裁判所で却下されていた。)
さらにこの後に、本来は大統領府から独立性を保つべき司法省から横やりが入り、ボルトンの本の出版に違法性がないか調査するためと称して、大陪審により出版社サイモン&シュスターとボルトンのエージェンシーから関連書類の提出を求める召喚状が発行された。ボルトン本をチェックした国家安全保障会議(NSC)の担当者が、審査中に国家安全保障問題担当大統領補佐官のボブ・オブライエンから横やりが入り、「出版できるように」チェックするのではなく、「出版させないように」国家機密が書かれていると主張してきたと法廷に報告があった。
なお、これとは別に、ボルトンの本に関しては「出すべきではなかった」という批判が多い。というのも、ボルトンは9月9日に大統領によって罷免され(本人は自ら辞任したと主張している)、その後、弾劾裁判に証人として11月17日に米議会上院に出頭するよう要請されていたが、ボルトンは正式な召喚令状がなければ出席しないとこれを突っぱね、結局議会で証言しなかった。
このことによって、いち国民として、元政府高官として、議会で証言する義務よりも、暴露本を売って印税を稼ごうとしているかのような印象を与えた。一連の暴露本の中で、ボルトンの本の海賊版が飛び抜けて多くインターネットに出回っているのも、このことと無関係ではあるまい。刊行後1週間で78万冊を売り上げた、と宣伝されているが、弾劾裁判での証言をしていればミリオンセラーになったのか、ならなかったのかは、今となってはわからない。
この先司法省がどのような圧力をかけようとも、最高裁まで訴訟がもつれたとしても、今さら出版停止、本は回収、という事態にはならないことは原告側も出版社側もわかっているだろうが、面倒くさい書類提出と裁判にかかる費用で、トランプが間接的に自分を裏切ったボルトンと彼に手を貸した出版社を懲らしめようとしているとしか思えない。