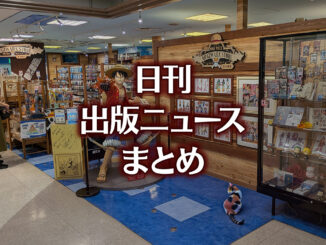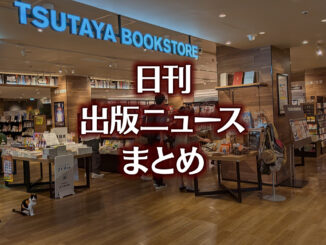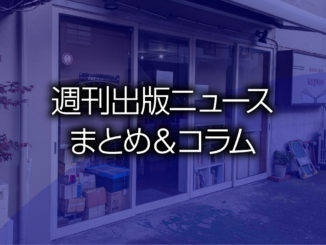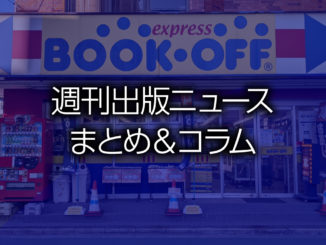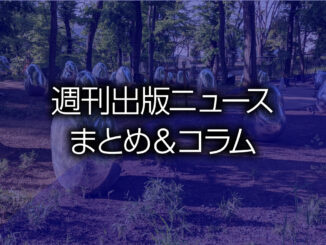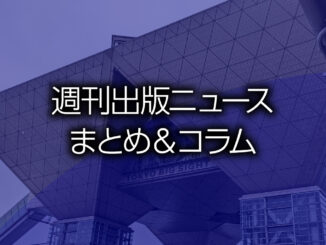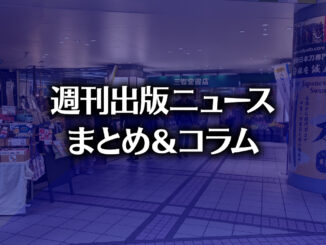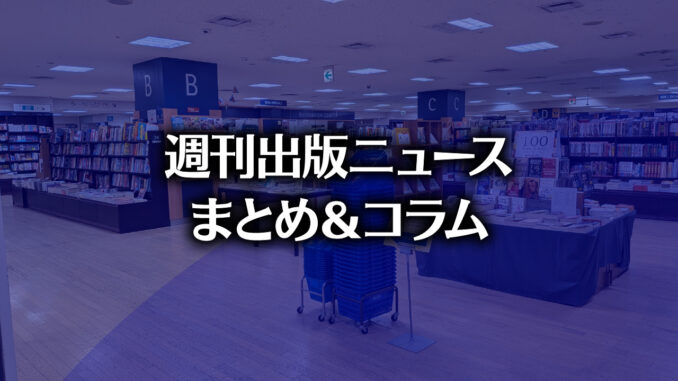
《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
2025年9月7日~13日は「Google検索AIモードが日本でも展開開始」「Anthropic訴訟約2200億円和解案が判事の承認延期」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- (社説)生成AIと著作権 人間との共存続く仕組みを〈朝日新聞(2025年9月7日)〉
- 「一方的に契約解除された」出版社訴えたフリー編集者の請求棄却、公取委が「下請法違反のおそれ」と指導も…東京地裁〈弁護士ドットコム(2025年9月9日)〉
- 「Claude」著作権訴訟、約2200億円の和解に判事が「待った」–なぜ?〈CNET Japan(2025年9月10日)〉
- Judge Delays Preliminary Approval in Anthropic Copyright Settlement(判事、アンソロピック著作権和解の暫定承認を延期)〈Publishers Weekly(2025年9月9日)〉
- Judge skewers $1.5B Anthropic settlement with authors in pirated books case over AI training(海賊版書籍訴訟で、AI訓練をめぐるアンソロピック社との15億ドルの和解を裁判官が批判)〈AP News(2025年9月9日)〉
- Anthropic’s $1.5 billion copyright settlement faces judge’s scrutiny(アントロピックの15億ドルの著作権和解が裁判官の精査に直面)〈Reuters(2025年9月10日)〉
- On Appeal, Copyright Chief Shira Perlmutter Keeps Her Job(控訴審で著作権局長シラ・パールマッター氏が職を維持)〈Publishers Weekly(2025年9月11日)〉
- 社会
- 経済
- 技術
- グーグルの画像生成AI「Nano Banana」は異次元レベル AIコンテンツの作り方を根本から変えた〈ASCII.jp(2025年9月8日)〉
- Google 検索の AI モードを日本語で提供開始します〈Google Japan Blog(2025年9月9日)〉
- 手描き原画と見紛う━━コルク佐渡島氏参画、著名漫画家も使う作画専用「AIxIPツール」〈Forbes JAPAN(2025年9月9日)〉
- 腕とテニスラケットが“一体化”――とあるアニメに注目集まる 「作画崩壊」はAIのせい?〈ITmedia AI+(2025年9月9日)〉
- グーグル「NotebookLM」神アプデ もう家庭教師はAIでいいや〈ASCII.jp(2025年9月9日)〉
- Agencies bombard journalists with ‘fake’ case studies(怪しいPR会社がジャーナリストに偽のコンテンツを送りつけている)〈Press Gazette(2025年9月10日)〉
- 検索からAIリサーチへ 企業サイト、流入減への3つの対策〈日本経済新聞(2025年9月13日)〉
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
チームで行う創作と出版のワークショップ「NovelJam 2025」を10月11日~13日に開催します。東京・札幌・沖縄の三拠点同時開催に向けクラウドファンディングを実施中! ゼロから作品を生み出すクリエイターの発掘育成活動をぜひご支援ください。
政治
(社説)生成AIと著作権 人間との共存続く仕組みを〈朝日新聞(2025年9月7日)〉
法改正は新たな価値創出につながるとの期待があった。ただ、こんなにも早く、生成AIが身近になり、文章や画像、動画が大量につくりだされる事態は想定していなかったはずだ。
これはもう何度でも指摘しておくべきだと思いますが、その著作権法改正に先立つ審議会には日本新聞協会も委員を送り込んでいて、数年がかりでの議論を行っているわけです。まるで他人事のように言わずに、まず「我々新聞社には当時想定できなかった」という反省が必要なのでは?
さらに言えば、当時審議会に参加していた弁護士・福井健策氏によると「少なくとも著作権に関する論点と負の影響予測は、現在言われてることはおおむね出揃っていた」そうです。つまり、AI登場による負の影響は当時から、少なくとも審議会では想定されていたはずなのですよね。実際にそういう事態が起きてから慌てて「想定していなかったはずだ」と他責思考をしているわけです。
ちなみにこの「柔軟な権利制限規定」ができたタイミングでは、TPPによる保護期間の延長(つまり権利保護の強化)も行われています。だから私は、保護期間延長とのバーターで柔軟な権利制限規定ができたと認識しているんですよね。保護期間の延長はそのままで、柔軟な権利制限規定だけを弱めたらバランスがおかしくなると思うのですよ。
「一方的に契約解除された」出版社訴えたフリー編集者の請求棄却、公取委が「下請法違反のおそれ」と指導も…東京地裁〈弁護士ドットコム(2025年9月9日)〉
げーっ! 公取委(行政)と裁判所(司法)の判断がズレちゃいましたよ……こういうの困るなあ。記事に書かれた状況からすると「親事業者から急な仕様変更を命じられ、下請けが対応しきれなかった」としか捉えられないのですが、どういう判断なんだこれは。マンガでの語り手を男性から女性に変えることが、容易くできると思われてしまったのでしょうか。控訴するようなので、続報を待ちたい。
「Claude」著作権訴訟、約2200億円の和解に判事が「待った」–なぜ?〈CNET Japan(2025年9月10日)〉
Judge Delays Preliminary Approval in Anthropic Copyright Settlement(判事、アンソロピック著作権和解の暫定承認を延期)〈Publishers Weekly(2025年9月9日)〉
Anthropic’s $1.5 billion copyright settlement faces judge’s scrutiny(アントロピックの15億ドルの著作権和解が裁判官の精査に直面)〈Reuters(2025年9月10日)〉
うーわ。国内では「和解」と断定している報道も多かったですが、私はあくまでまだ「和解案」だという認識でした。セーフ。和解対象とされていたのは約50万点ですが、海賊版データには約700万点の著作物があった(つまり約7%しか救済されない)という指摘があったので、もしかしたら……とは思っていたのですよね。決着にはまだもうしばらくかかりそうです。しかしこの「判事から和解案にストップがかかった」件を報じている国内メディアが少ない……まずいなあ。
On Appeal, Copyright Chief Shira Perlmutter Keeps Her Job(控訴審で著作権局長シラ・パールマッター氏が職を維持)〈Publishers Weekly(2025年9月11日)〉
トランプ政権による、メール1本での突然の解雇は無効となりました。しかしこのことにより、少なくとも半年間は著作権局の動きをマヒさせたわけですよね。仮に司法に邪魔されたとしても、遅延策としては有効だったことになってしまいます。ううむ。
社会
「自分の声が無断で生成AIに」──プリキュア声優の山村響さんが告発 とある音声合成AIが波紋 経緯は〈ITmedia AI+(2025年9月9日)〉
コナミ、「遊戯王」AI実況の動画を削除 人気声優の声“無断学習”問題で〈ITmedia AI+(2025年9月9日)〉
ぎゃーす。「AivisSpeech」は私も「HON.jp Podcasting」で使ってました。とはいえ、ここで話題になっているモデル「Anneli」は標準設定のものなので、私は使うのを避けてたんですよね。「たぶんこれをそのままみんなが使うだろうなあ」と思い、別のモデルを使っていました。ある意味、正解でした。でも、こういうアプリだと知ってしまうと、さすがにもう「AivisSpeech」は使いづらい。アンインストールしました。
著作物、不正利用相次ぐ…無断複製・共有「氷山の一角」〈ニュースイッチ by 日刊工業新聞社(2025年9月10日)〉
こういう記事には珍しく、日本複製権センター(JRRC)がしっかり取り上げられています。善哉。企業や団体内での複製・共有は「私的使用のための複製(法30条)」が適用できないのですよね。JRRCと包括契約しましょう。
しかし、記事後半のAI学習に関しては、タイトルで言われているような「不正利用」か? というと……むしろ著作権法第30条の4などにより権利侵害にはならないケースも多いわけですよね。話題として混ぜない方が良かったんじゃないかなあ。
10代は「ChatGPTで検索」が4割、Yahoo! JAPAN上回る――検索の生成AI利用、実態は? CA調査〈ITmedia AI+(2025年9月11日)〉
記事には調査概要がありません。サイバーエージェント GEOラボのリリースを確認したら「調査機関:株式会社マクロミル」とあったので、それなりに信頼性は高そうだと判断しました。マクロミルは、2000年設立のマーケティングリサーチ専門大手企業です。ちなみに、リリースには「複数回答可」と明示されているのをITmedia AI+の記事は削ってしまっているのですが、いずれの年代もGoogleが7~8割です。
サービス終了に関するFAQ〈World Maker 公式(2025年9月11日)〉
本稿執筆時点でも記事にしているメディアが見つけられないので、公式のお知らせで。JEPA電子出版アワード2022でエキサイティング・ツール賞を受賞した集英社のマンガのネーム制作アプリ「World Maker」がサービス終了となります。コンテストなどもかなり積極的に展開していましたが、ここからヒット作は出なかったか。残念。お疲れさまでした。
経済
【デジタルマーケティングの真価】06 拡大する推し活市場の正体 生活者の〝時間投資〟がカギに〈The Bunka News デジタル(2025年9月9日)〉
そういえば、私が非常勤講師をしている二松学舎大学では、今年の春学期に編集デザイン特殊研究で学生が作った本には「推し」をテーマにしたものがけっこう多かったです。去年くらいから「推し」という言葉で表現する学生が急増している印象です。
ステーブルコイン「JPYC」、クレカで買い物も 使い道広がるか〈日本経済新聞(2025年9月10日)〉
ブロックチェーン(分散型台帳)技術を土台とするステーブルコインを導入するには、高度な専門性が求められる。電算システムは決済基盤の構築にあたり、暗号資産(仮想通貨)交換業のデジタルアセットマーケッツ(東京・千代田)の支援を受ける。
JPYCについての初報に対し、ECサイトが決済手段として提供するには「実装がそこそこハードルが高そう」だとコメントしましたが、やはりそれなりに難しそう。NFTのサービスをすでに提供しているメディアドゥあたりがサポートしてくれると、電子書店への普及が広がるかも? 期待しておきます。
技術
グーグルの画像生成AI「Nano Banana」は異次元レベル AIコンテンツの作り方を根本から変えた〈ASCII.jp(2025年9月8日)〉
Nano Bananaで蘇る思い出の逆光写真。画像編集ソフトとしてのナノバナナの実力(CloseBox)〈テクノエッジ TechnoEdge(2025年9月9日)〉
Googleの画像生成AI「Nano-banana」をめちゃくちゃ活用できるプロンプトとサンプル画像実例まとめ〈GIGAZINE(2025年9月12日)〉
8月27日にリリースされた「Gemini 2.5 Flash Image(nano-banana)」が具体的にどうすごいか、作例がいろいろ出てきたので紹介しておきます。これで今後は、いわゆる「マスピ顔」のAIイラストとか、恐らくChatGPTで出力したであろう全体的に茶色っぽいイラストなどは、駆逐されていくことになると思います。
ただ、私も実際に「Google AI Studio」で「nano-banana」を使ってみたのですが、写真に猫を追加しようとしたら、言葉で指定した箇所以外のところも微妙に改変されることに気づいてしまいました。看板の文字が謎言語に変換されたり、窓に謎の写り込みが追加されたり。はい、心霊写真のできあがり。怖っ! これプロンプトで回避できるのかしら? まだ難しそう。
Google「Nano Banana」登場でアドビは戦略的転換、責任あるAI使用も課題に〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2025年9月9日)〉
AI驚き屋さんが豪語していた「Photoshopはもう要らない!」については、Adobeは「リリース当初から自社ツール内での選択肢に追加する」という形で答えています。実際、前述のようなことは、Adobeのツールなら回避できるんですよね。「範囲を選択して生成塗りつぶし」であれば、選択範囲以外が勝手に変わることはありません。
この差を許容できるかどうかが、今後はプロとアマの違いになりそう。現時点のnano-bananaだとまだ、AI製だとバレる可能性があります(SynthID透かしを確認できない場合でも)。そもそも解像度が足らないからアップスケーリングが必要で、その過程でもおかしな改変が紛れ込む可能性が高くなります。
ウェブ広告のバナーとか記事のアイキャッチ画像くらいなら無視できるかもしれませんが、さすがに印刷媒体だとまだ厳しそうです。裏を返せば、もうその域にまで達している、とも言えますが。
Google 検索の AI モードを日本語で提供開始します〈Google Japan Blog(2025年9月9日)〉
ついに展開開始。「年内」がずいぶん早かった。個人用アカウントには2日ほど、Google Workspaceのアカウントには4日ほどと、ロールアウトに少し差がありました。さっそく試してみましたが、「AIモード」は完全にチャットインターフェースの応答のみになるのですね。「AIによる概要(AI Overviews)」は検索結果一覧と一緒に表示されるので、大きな違いを感じました。
従来の検索結果一覧なら下位に表示されても地味に流入はありましたが、「AIモード」だとAIに選ばれた出典以外にアクセスが一切発生しなくなります。そのぶん、AIに選ばれた出典にはアクセスが増えたり、コンバージョンレートが増える形になりそうです。
アメリカ向けに初めてリリースされたとき、ポッドキャスト「#33 AI検索とメディアの未来(2025年5月27日版)」で「SearchからResearchにユーザー行動が変容する」「そういう変容を促している気がする」と言いましたが、実際に使ってみてもその印象は変わりませんでした。とくにモバイルからの利用は、それが顕著になる気がします。
さて、本件を報じるニュース記事で、ちょっと面白いことに気づいたので付記しておきます。私が確認できた範囲では、読売・朝日・日経・PC Watch・テクノエッジは、いずれも公開時間が午前1時ジャストです。Google Japan Blogのリリースには時間が表示されていませんが、HTMLソースを見たら“datePublished : 2025-09-09T01:00:00+00:00″で、ニュースメディアの報道と同時でした。「午前1時解禁」という報道協定だったんでしょうね。
また、テクノエッジ Google Tales(佐藤由紀子氏)の記事は、事前に用意してないとさすがに無理だろうなという内容です。ちなみに、NHKとITmediaは、お昼の常識的な時間の更新でした。事前に知らなかったっぽい? いやまあ、私も事前には知らなかったわけですが。Google広報とは接点がないからかしら? ぐぬぬ。なお、産経・毎日は本稿執筆時点でも、本件の記事を確認できません。この2社はあえて無視している感があります。
手描き原画と見紛う━━コルク佐渡島氏参画、著名漫画家も使う作画専用「AIxIPツール」〈Forbes JAPAN(2025年9月9日)〉
提供されるAI補助ツール「THE PEN」のことはさておき、Forbes JAPAN 編集部による著作権法の説明が酷い。端折りすぎ。とくに以下の箇所。
現状の日本の法律では漫画家の作品の無断学習自体は許されているものの、無断で出力し商用利用すれば違法になるからだ。
まず、AI開発・学習段階においては、ファインチューニングなど創作的表現が類似するものを生成する目的(=享受目的)で「漫画家の作品」を無断で複製・学習したらダメです。また、その漫画家の利益を不当に害することとなる場合もダメです。どちらも「無断学習自体は許されている」根拠となる著作権法第30条の4が適用されません。しかしForbes JAPAN 編集部の説明では、これらのダメなケースが無視されています。
また、生成・利用段階においては「商用利用」か否かはあまり関係ありません。ごくシンプルに、出力が類似しているか否かで違法性が判断されます(類似性)。依拠性は推認でもOK。「非享受目的」を「非営利目的」と誤認しているケースをときどき見かけますが、これもそれかなあ。いずれにしても、Forbes JAPAN 編集部におかれましては、文化庁「AIと著作権について」の資料をもう一度しっかり読み返していただきたい。これじゃ紹介しているツールが可哀想です。
腕とテニスラケットが“一体化”――とあるアニメに注目集まる 「作画崩壊」はAIのせい?〈ITmedia AI+(2025年9月9日)〉
以前ピックアップした「ラノベアニメ」のやらかしです。まあ、確かにコブラっぽいのですが、面白ネタとして昇華するのはちょっとキツイ。「ラノベアニメ」は基本的に、アニメ調3Dキャラを動かす感じの動画なのですが、これは壁(黒板?)に貼ったスチール写真のようです。要するに、背景だから手を抜いた可能性が高い。チェックもすり抜けている。そういうことをすると、痛い目に遭うということでしょう。
グーグル「NotebookLM」神アプデ もう家庭教師はAIでいいや〈ASCII.jp(2025年9月9日)〉
家庭教師どころか、学習用教材やアプリも駆逐されそう。もちろん、手元に読み込ませる元資料がないと、なんともならないわけですが。
Agencies bombard journalists with ‘fake’ case studies(怪しいPR会社がジャーナリストに偽のコンテンツを送りつけている)〈Press Gazette(2025年9月10日)〉
AI生成の可能性が高い怪しげなプレスリリースをあちこちのメディアに送りつけていて、一部のメディアはそれを採用してしまっているという警句です。どうやら、PR会社によるSEO対策らしい。検索エンジンが高く評価しているメディアで取り上げられると、バックリンクが稼げる、と。
私のところにも以前から「怪しい調査会社のレポート」は毎日大量に届いていて、引っかかっちゃったメディアもあるのを確認して苦々しい思いをしていました。こんどはPR会社ですかあ……ブラックハットSEOだと断定はできないギリギリのラインですけど、メディア側のリテラシーが求められますね、これは。
プレスリリースをそのまま転載しているようなところは危ないですよ。せめてnofollow属性でリンク先に評価を渡さないようにしておきたいところです。
検索からAIリサーチへ 企業サイト、流入減への3つの対策〈日本経済新聞(2025年9月13日)〉
3つの対策で真っ先に「AIO(AI最適化)は最低限取り組む」としていてちょっと首を傾げたんですが、以下のように説明されていて「まともだ」と思いました。「最低限」ってのがポイントですね。
対策をうたうサービスが続々と出てきていますが、正直なところ、現時点でAIOとして実施できることは、まだ限定的と言わざるを得ません。
まあ正直、であれば「対策」として挙げるより、「現時点ではアテにできない」とはっきり否定しておいたほうがいいような気がします。AIがその記事をどういう理由で出典に選んだのかは、完全にブラックボックスなのですから。そんな段階で、まともな「対策」なんか立てられるはずがない。まっとうなSEOをやってるなら、まだ変える必要はないという認識です。
電通系、グーグルのAI検索対策を支援 企業サイトの改修指南〈日本経済新聞(2025年9月9日)〉
だから、こういう動きはAI検索を単なる「ビジネスチャンス」としか捉えていないのだろうなという印象です。まあ、機を見るに敏とは言えるでしょうけど。現状でも「Web1.0時代のまま?」とか「いまだにモバイル非対応か……」とため息が出るような公式サイトになっている企業・団体もけっこうあるので、そういうところはAI対策じゃなくてもリニューアルしたほうがいいだろうとは思います。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
ようやく気温が下がってきましたが、雨続きで湿度が高い。まだエアコンの除湿に頼りっきりになっています。(鷹野)