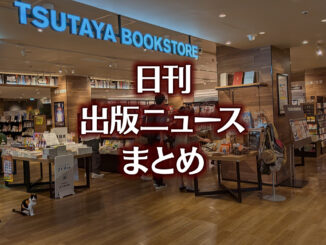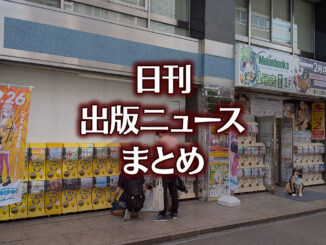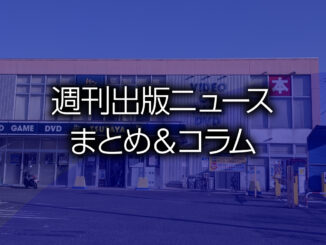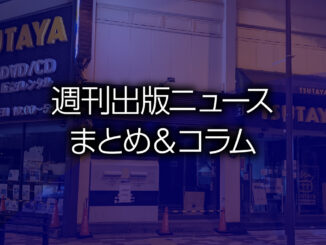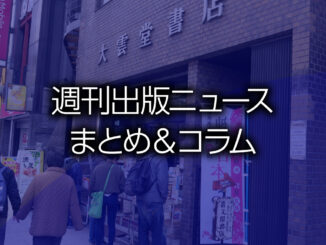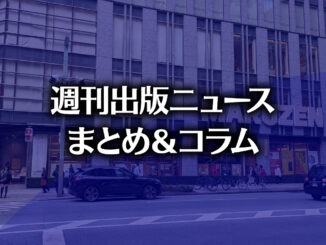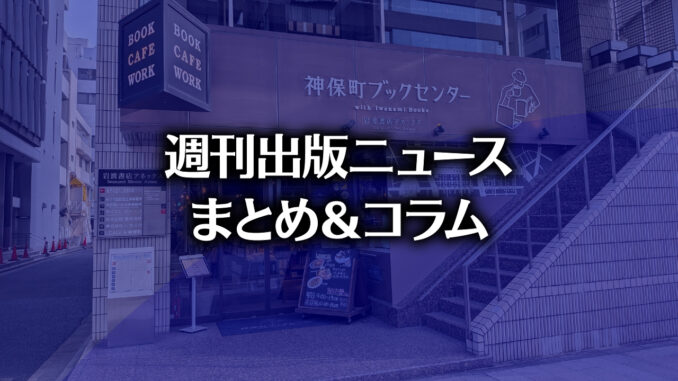
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年9月14日~20日は「出版危機に政治介入で表現の自由は守られる?」「NHK ONE10月スタートに向け既存サービス続々終了へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 社会
- 「ファクトチェック元年」広がる一方で “ジレンマ”も テレビや新聞 マスコミによるフェイク検証 現在地は|フェイク対策〈NHK(2025年9月13日)〉
- 『ぼざろ』『虎に翼』の脚本家 吉田恵里香が語る、アニメと表現の“加害性”〈KAI-YOU(2025年9月14日)〉
- ウェブサービスのリニューアル〈国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(2025年9月16日)〉
- 現行の「NHK ニュース・防災」アプリは9月末で終了、「NHK ONE」登場に伴う変更点〈ケータイ Watch(2025年9月17日)〉
- 成人向けゲームで、イラストレーターが“AI絵”を納品→契約違反で差し替えに 「著作権の所在不明」と運営元〈ITmedia AI+(2025年9月18日)〉
- マンガ・電子書籍アプリ市場は10代・20代で高い利用率、60代以上の男性にも広がる/フラー調査〈CreatorZine(2025年9月18日)〉
- AIモデルを構築するために、大量の書籍を破壊したAnthropicの功罪〈WIRED.jp(2025年9月18日)〉
- Google「オープンウェブは急速に衰退」と認める、広告技術を巡る裁判で〈Media Innovation(2025年9月19日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
チームで行う創作と出版のワークショップ「NovelJam 2025」を10月11日~13日に開催します。東京・札幌・沖縄の三拠点同時開催に向けたクラウドファンディングもそろそろラストスパート! ゼロから作品を生み出すクリエイターの発掘育成活動をぜひご支援ください。
政治
Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews(ローリングストーン誌とビルボード誌のオーナー、ペンスキーがAI要約機能をめぐりグーグルを提訴)〈Reuters(2025年9月14日)〉
「Rolling Stone」発行元のPMC、Googleを提訴 「AIによる概要」でトラフィックが激減と主張〈ITmedia NEWS(2025年9月15日)〉
GoogleのAI Overviewsも訴訟の対象に。他のAI検索サービスとは異なり、そもそもその「急減したトラフィック」というのはGoogle検索からタダで生まれていたものですよね。どうも、Googleにいま文句を言っているメディアからは、「Google検索は無料でトラフィックを送り込んでくれていた」という考え方が希薄に感じられるのですが。
ちなみに「アフィリエイト収入が急減」とあったので、site reputation abuseペナルティの可能性がある(寄生サイトはアフィリエイト収入で稼ぐパターンが多かったという認識)と思ったのですが、私の調べた範囲ではPenske Media Corporation傘下のメディアがペナルティを食らったかどうかは確認できませんでした。ここは違うのかな。
反Amazon法のフランスに学べ 出版危機の日本、重い「公共財」の覚悟〈日本経済新聞(2025年9月14日)〉
フランスのように本を国が守るべき公共財とすれば、業界の利益より国益が優先する。その重みの自覚はあるか。問われるのは政府介入の是非と覚悟だ。
この締めの言葉に思わずうなってしまいました。悪い意味で。政治が介入して表現の自由は守られますか? 私はそうは思えない。軽減税率導入前に菅官房長官(当時)が「有害図書は自主規制してもらい」などと言い出したことが私には忘れられません。隙を見せたら締め付けてきますよ。
【連載】用紙規制「EUDR」のリスクと対策① EUは本気なのか 佐藤弘志(日販IPS)〈The Bunka News デジタル(2025年9月16日)〉
EUDRの詳細な解説が始まりましたが、大半はペイウォールの向こう側です。こういう価値ある情報は、ペイウォールの向こう側で良いと思います。気になる方は契約しましょう。私はもちろん以前から契約してますよ。
社会
「ファクトチェック元年」広がる一方で “ジレンマ”も テレビや新聞 マスコミによるフェイク検証 現在地は|フェイク対策〈NHK(2025年9月13日)〉
反響を見ていると、「伝統的メディアによるファクトチェック」に対する反発がものすごく大きいことが確認できます。伝統的メディアがいつも無条件で信用できるわけではないし、ときには誤報も偏った意見ももちろんあるけど、相対的には「わりとマシなほう」だと思うのですよね。なぜ信用できる/できないの二元論になってしまうのだろう。
『ぼざろ』『虎に翼』の脚本家 吉田恵里香が語る、アニメと表現の“加害性”〈KAI-YOU(2025年9月14日)〉
大炎上しています。とくに「ノイズ」という表現に引っかかっている方が多いようです。そういう表現を求めてない作品で「胸が過剰に揺れる」とか「パンチラ」みたいな男性向けサービスシーンがあると私の好みからは外れてしまうので、個人的にはそれほど違和感のない発言です。
ですが、われわれ第三者はさておき、脚本家の今回のこの発言を原作者がどう感じているかが気になります。改変があることに原作者が同意していたとしても(結果ヒット作品になったとしても)、あとから「ノイズ」と言われてしまうことまで許容できるのか。どうしても「セクシー田中さん」の事件を思い出してしまいます。
あとは、どういう言い回しなら世の中から受け入れられたのか? が悩ましい。KAI-YOUが燃やそうとしたわけではないでしょうけど、どう伝えれば燃えなかったのか? という「編集者的観点」です。この脚本家の発言は「ANIME FANTASIA JAPAN 2025」というアニメ現場制作者にフォーカスしたイベントに登壇した際のものですから、「業界内では通じる言葉」が出てしまったように思えるのですよね。
話し言葉は普段なにげなく発している「業界内では通じる言葉」が出てしまうのもあって、そのまま書き起こすと微妙なニュアンスが伝わりづらい場合があります。話の流れ的に「ノイズ」という単語ひとつ置き換えだけではダメで、むしろ「覇権」という言い回しが悩ましいのかもしれません。
原作媒体である「きららMAX」とはターゲットが違うというニュアンスを強めにして「つまり、広く一般に受け入れてもらうには、原作者の同意のもと、原作にある要素の一部を省いたり変えたりする必要があったのだ」みたいに筆者の考えを補足する感じでしょうか。これって、海外へ輸出する際にローカライズするのと似たような話だと思いますから。
ウェブサービスのリニューアル〈国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(2025年9月16日)〉
リニューアル後、現行のアドレスは新しいアドレスに永続的に自動転送(リダイレクト)するよう設定しますので、WARPで保存されたページやファイルへのリンクを新しいアドレスに変更いただく必要はありません。
ウェブサイトリニューアル時のあるべき姿! さすが国立国会図書館。しかし、これが当たり前の対応になって欲しいものです。直近だと、日本図書館協会公式サイトリニューアルがまったく考慮せずURLを変更し、相当数あったHON.jp News Blogからのリンクもすべて404になってしまいましたから。
現行の「NHK ニュース・防災」アプリは9月末で終了、「NHK ONE」登場に伴う変更点〈ケータイ Watch(2025年9月17日)〉
あれ? 結局アプリだと最初から「NHK ONEアカウント」が必須なんですね。「NHK NEWS WEB」も「NHK ONE」に集約されますから、ウェブ空間の情報流通は10月から激変します。新聞社はしてやったりでしょう。ちなみにうちにはテレビがないのでいままでNHKは契約していなかったのですが、今後はとりあえず契約するつもりです。
いま私がいちばん気になっているのは、10月以降「NHK ONE」のウェブ記事をソースにしていいのかどうか。まあ従来の「NHK NEWS WEB」もすぐ記事を消しちゃうから、出典にしづらいとは思っていたのですが。「NHK ONE」が完全にペイウォールの向こう側へ行ってしまったとしても、世帯普及率はそれなりに高いはずですから、もし今後は記事を消さないならむしろ出典にしやすくなるかも?
成人向けゲームで、イラストレーターが“AI絵”を納品→契約違反で差し替えに 「著作権の所在不明」と運営元〈ITmedia AI+(2025年9月18日)〉
生成AIそのものの利用を当社案件では一切止めていただく旨を宣誓いただいた。
え? そういう宣誓を事前に行っていなかったのに、契約違反になっちゃうの? 「生成AIは一切使わないこと」と事前に釘を刺していたわけではない? どんな条件が提示されていたかの詳細がわからないからなんとも言えないところではありますが、下請法かフリーランス法には抵触しないのかしら? 「強い類似性を持つ出力結果が他に存在する」なら、むしろ生成AIを利用していようがいまいが、著作権侵害になるわけですが。なんかちょっと釈然としない。
マンガ・電子書籍アプリ市場は10代・20代で高い利用率、60代以上の男性にも広がる/フラー調査〈CreatorZine(2025年9月18日)〉
カオスマップの「マンガビューア」のところはさすがにおかしい。「カクヨム」は「小説・ライトノベル」ですし、「ソニーReader」「Doly」あたりは「電子書籍・総合型」で、「まんが王国」はそのまま素直に「マンガ」でいいと思うんですが。アプリ内に決済機能がないアプリの扱いをどうするか? って感じで迷ったんでしょうけど、それを言うなら「Kindle」も「楽天Kobo」もただのビューアですからね。まあ、こういうカオスマップを作るのって大変だから、あんまり文句を言うと可哀想かなとも思うのですが。
AIモデルを構築するために、大量の書籍を破壊したAnthropicの功罪〈WIRED.jp(2025年9月18日)〉
うーん……こういう「本の破壊者だ!」みたいな情緒に訴える方向性の問題提起って有効的なんでしょうか? 日本で14年前にいわゆる“自炊”代行業者が提訴されたときも、浅田次郎氏が記者会見で「裁断された本、私はあれを正視に堪えない」と情緒に訴えていて、むしろ反発されていたのを思い出します。出版社が大量に断裁処分しているのは見て見ぬふりか、と。
Google「オープンウェブは急速に衰退」と認める、広告技術を巡る裁判で〈Media Innovation(2025年9月19日)〉
すでに「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側に」なってますから、そりゃ「オープン」なウェブ空間は痩せ衰えて行きますよね。裏返せば“Garbage in, Garbage out(ゴミからはゴミしか生まれない)”です。この「オープン」があるのとないのとでは指し示す範囲が違うのに、同一視して批判している点がおかしいと私は思います。この記事が問題視している「繁栄アピール」の内容と、実はそれほど矛盾していないのでは。
経済
noteが年内に広告事業を本格化 加藤CEO語る「嫌われない広告」〈日経クロストレンド(2025年9月17日)〉
広告がないことが「note」の訴求ポイントのひとつだと思うのに、とうとう広告を入れてしまうのか……というのが第一印象です。いまのところ金融カテゴリー特化の「noteマネー」で実験的に導入しているだけのようですが、今後どうなるか。行政や学校のアカウントにも広告を入れるのかどうか。
noteが広告をやりたくないと言ったことはないんです。
そうでしたっけ? と思い、念のため初期のころ加藤氏がイベントに登壇した際のレポート(自分で書いたやつ ■ ■ ■)をいくつか読み返してみたのですが、確かに「広告をやりたくない」とは言ってませんね。「cakesが雑誌でnoteが本」という話はありましたが。基本的に、本には自社のもの以外の広告は載らないから、noteの一部が雑誌化していくということなのでしょうね。
アマゾン「Audible」CEOに聞く 耳で“聴く本”が持つ可能性〈日経クロストレンド(2025年9月18日)〉
キャリガン はい。オーディオブックをサブスクで聴けるようにしたのは、私たちのイノベーションの1つだと思っています。
えーっと、Audibleの会員プランが定額聴き放題制に移行したのは2022年からですが、audiobook.jpはサブスクを2018年からやっています。この方、以前も「日本に上陸して10年ですが、当時は『オーディオブック』という言葉すら存在しなかった」などとほざいているんですよね。日本オーディオブック協議会が設立されたのは2015年4月、Audibleが日本で開始したのは2015年7月です。先駆者に対する敬意が欠けている。そしてその発言をそのままスルーして載せるメディアの側もいい加減すぎる。
文化通信社セミナー2025 三洋堂ホールディングス代表取締役社長・加藤氏 「無人営業が広げる書店の将来展望―三洋堂ホールディングスのサバイバル戦略」〈The Bunka News デジタル(2025年9月19日)〉
「日本も書籍だけで書店経営が成り立つ業界構造に転換しなければ、書店の消滅は免れない」と危機感を示した。
私も以前「デジタル出版論」で同じようなことを書いています。書店にとって、定期刊行物の販売=定期収入だったわけですもんね。雑誌市場の急減でなにが起きるかを想像すれば、これは自明のことだったはず。あとはこういった書店側の悲鳴のような訴えを受けて、出版社側がどう動くか。
というか、流通量の多い大手出版社がいつ動くか、ですね。「買切りと引き換え条件に」というのが互いに納得しやすい落としどころだと思うのですが、その買切りを推進しているブックセラーズ&カンパニーと契約しているのは現時点で大手4社のうちまだKADOKAWAだけです。
技術
旅行計画もAIに任せる時代に Google「AIモード」を体験〈日本経済新聞(2025年9月15日)〉
現状のAIモードはホテルやレストランの予約サイトとも連携していない。そのためAIは具体的な空室状況がわからず、「12月に2人分の空きがある日付は」といった質問には答えられなかった。
確かに現時点では、デモ動画で宣伝されていたような「ショッピングとの連携」みたいなことがまだ実現されていません。アメリカではすでに試験的な導入が進められているようですが。これに広告が絡んでくると、また大きく変わりそうな気もします。
AI 検索の拡大がパブリッシャーを揺さぶる リファラルトラフィック減少の実態〈DIGIDAY[日本版](2025年9月16日)〉
ペイウォールの向こう側が読めていないのですが、ちょっと気になる記事。リファラル(referral)って、基本的に検索(Organic Search)以外の流入のことですよね。「他のサイトによる推薦」のようなものだと理解しています。GA4なら「Social」「Direct」「Email」なども別項目なので除外されているはず。「AI検索が拡大した結果リファラルが減少」というのは、どういう因果関係だと考えられているんだろう? 他のサイトも流入が減ってるから、それに比例してリファラルも減る、ということでしょうか?
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
明星大学秋学期の講義が今年も始まりました。2017年度の着任当初から依頼していた「デジタル編集論」から「デジタル出版論」への講義名変更がようやく通った! 名前が変わったからなのか、教室もいままで違う場所へ変更に。旧教室に着いてから「誰もいないぞ?」と慌てて場所を確認、新教室はキャンパスの反対側でした。開始時間には間に合ったけど、汗だくになってしまった。とほほ。(鷹野)