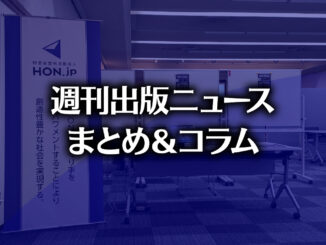《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年2月25日に配信した第20回では、書店議連と書店活性化に向けたアクションプランとICタグについて語っています。
【目次】
#20 出版とICタグ
こんにちは、鷹野です。今回は「出版とICタグ」についてお話したいと思います。他のトピックスも取り上げようかなと思ってたんですけど、台本作ってたらですね、ちょっと長くなってしまいそうだったので、今回はICタグだけ取り上げます。
ICタグ、RFIDと呼ばれたりもしますね。そもそもこのICタグとはどんなものか、モリアキさん、簡単に説明してもらえますか?
はい、モリアキさんありがとうございます。そのICタグが、出版とどう関わってくるんでしょう? モリアキさん、続けて説明してください。
また、流通・物流の最適化を図ることもできます。出版社は、必要な書店に必要な冊数だけ効率よく配本できるようになります。物流の各段階においても、仕分け、検品、保管などの効率が向上します。取寄せ、つまり、客注品の追跡管理も可能になります。
書店の店頭では、盗難防止ゲートを設置することで、会計前の商品持ち出しを抑制できます。他にも、データを分析することで、書籍の売れ筋や顧客の購買傾向を把握し、マーケティング戦略に役立てることもできると言われています。
はい、モリアキさんありがとうございます。ついでに、もうすでにICタグを導入している、先行事例について教えてもらえますか。
はい、モリアキさんありがとうございます。(今回の)このモリアキさんの回答は、ぱーぷれきしてぃしてぃ……舌噛んじゃいますね。えー、Perplexity、生成AIの検索エンジンです。これにベースを作ってもらいました。
Perplexityの出力そのまんまではなく、ちょっとこれおかしいなという部分を直したりとか、これは触れるべきではないんじゃないかみたいなところを削ったりとか。あとは、モリアキさんにナレーションしてもらうために、表現をちょっと変えたりしています。
“すべての本にICタグを”という話は20年くらい前からある
さてこのICタグ、出版業界ではいちど、ゼロ年代くらいにに大きな話題になっていたことがあるんですね。いや、えっと、あったそうです。えーっと、私はそのころのことよく知らないんですよね。もういまから20年くらい前の話です。聞く話によると、大日本印刷さんなんかがけっこう前のめりに取り組んでいて「2005年までに、すべての本にICタグを付ける」なんていう計画もあったそうです。
で、日本出版インフラセンター、JPOですね。こちらにもICタグ研究委員会というのがあって、主に書店での万引き防止とか、物流の効率化なんかを目的として、ICタグ導入の可能性が検討されていました。2007年ごろには実証事業なんかも行われていたそうです。
JPOの公式サイトには、そのころの資料がちゃんと残っています(PDF)。いまでも見ることができます。ただ、結局当時は実現には至らなかったんですね。JPOのICタグ研究委員会は、2015年1月で廃止になっています。
で、当時なにが導入への課題だったかというと、まずはICタグの単価ですね。5円以下みたいな記述がありました。あとは、性能とか精度の問題、耐久性なんかの問題とか。あるいは、そのICタグを読み取るリーダー、あるいは書き込むライターですね。そういう周辺機器の整備コスト。
あとは本に装着する、ICタグを装着するときにかかる時間とか、装着する場所によってはデザイン面なんかに影響出るよねとか。あとは古紙再生ですね。リサイクルの問題です。本にICタグを埋め込んじゃうと、古紙再生しづらくなっちゃうよねという、そんな話です。だから除去して古紙再生に回さなきゃいけない。
あるいはプライバシー保護の問題であったりとか。あとは、タグ装着費用を負担する出版社にとってのメリットがどのようなものかという、要は、費用対効果というのがあんまり明確化できていなかった。そんなようなことが、JPOの資料(出版業界における流通効率化の実証実験(PDF))には挙げられていました。まだね、課題山積という感じがしますよね。
“AIの活用とICタグの活用”というキーワード
で、その実証実験の資料が2008年のものなんですけど、そこからしばらく、ICタグの話が出てこなくなるんです。再び話題になったのが、2021年5月。講談社・集英社・小学館と丸紅が、新会社を設立する協議を始めるという発表をしたんですね。
AIの活用とICタグの活用で、出版流通を最適化する。そういうのを目指す。そんなような会社を設立しますよというよな話です。この「AIの活用とICタグの活用」ってキーワード、覚えておいてください。あとでまた出てきます。
ちなみにこの新会社の設立、最初は日本経済新聞で報道されたんですけど、取次を飛ばして書店との直接取引拡大を図るみたいなことが書かれていて、ちょっとそれで大騒ぎになったりもしたんです。後追いの報道で、文化通信なんかの後追い報道で、それは明確に否定されているという。「取次飛ばしたいわけじゃないよ」みたいな、そんな火消しも行われておりました。
その新会社が設立されたのが2022年3月。PubteX(パブテックス)っていう名前です。その後、コミックにICタグを装着する実証実験ってのが始められて、書店でのトライアルも進んでいる、と、参加する出版社の募集とか、書店の拡大というところも図られている、そんなような段階です。設立からちょうど3年経ってます。
で、たぶんこれは、JPOの実証事業のときに浮き彫りになったいろんな課題を解決するためなんでしょうけど、ICタグの装着方法というのが、本そのものには埋め込むのではなくて、「ラベルシール」とか「しおり」「スリップ」「チラシ」「A6台紙とじ込み」みたいな、そういう形が提案されてたりします。
要は、本体と簡単に分離できるんで、リサイクルの問題というのはそれで解決しやすくなるわけです。その代わり、店頭でICタグを抜き取られて盗まれるみたいな、そういう可能性は残っちゃうわけです。
あと、古本屋に持ち込まれる――新古書店みたいな言われ方をしますけど、万引きされてそれをそのまますぐ新古書店に持ち込まれたとき、ICタグが埋め込まれていればそこで阻止できるよね、みたいな構想もJPOの資料にはあったんですけど。
しおりとかスリップみたいな形だったら簡単に抜き取られちゃいますんで、その阻止するみたいな目的は果たせなくなるわけです。たぶんその辺は妥協したんだろうなという感じがします。
書店議連が官庁にICタグ活用インフラの整備促進を要望
で、このICタグ。政治に絡んできてるんですね。政治に絡んでくるようになったのがPubteX設立と同じ年、2022年11月のことです。自由民主党の議員が「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟」縮めて「書店議連」というのをやってるんですけど、その総会で、出版文化産業振興財団、JPICですね、こちらがいくつか要望をしたんですね。
で、その要望の中に「ICタグを活用した高度な商品供給インフラの整備・促進」といのがありました。要するにそのICタグを普及させるために国の補助をくださいと。そういう要望をしてたわけですね。まあ、他にもいくつか要望ありますけど、その中にICタグというのが入ってた。
その要望を受けて、書店議連が中間まとめというのを発表して、そこにもICタグが盛り込まれた、と。それが2022年12月のことです。ちなみにこのころは他にも、たとえば軽減税率。軽減税率……消費税の新聞なんかに適用されてるやつですね。軽減税率、この適用を書籍にもみたいな、そんなのを求めてたりもしてました。
ところがね、これいつのまにか消えちゃったんですよね。軽減税率の話を始めるとものすごく長くなるので今日はやめておきますが、軽減税率の提案、提言ね、消えちゃいました。まあ、あの、今回はICタグの話です。
―― この続きは ――
《残り約2800文字》