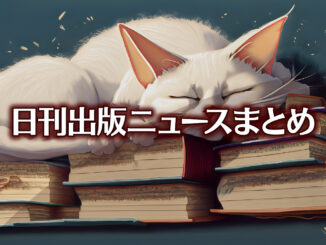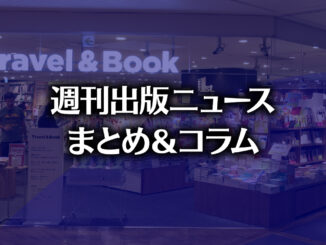《この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です(1分600字計算)》
HON.jpが9月2日にオンラインで開催したオープンカンファレンス「HON-CF2023(ホンカンファ2023)」編集セッションの様子を、出版ジャーナリストの成相裕幸氏にレポートいただきました。
創作と出版のイベントと、編集者の役割
2017年から始まった著者と編集者らが即興的にチームを組んで創作する試み「NovelJam」1 NovelJam
https://www.noveljam.org/。これまで5回実施し、地方で関連イベントが開催される広がりを見せるなかで「編集者」の役割について再考する場面がでてきた。
また、生成AIの日進月歩の進化のなかで「編集者不要論」も語られるようになってきた。作家、編集者、ディレクターとしてNovelJamに参加してきた各氏に「出版創作イベント『NovelJam』と編集者不要論」と題して語ってもらった。
執筆、編集といったプロセスもコンテンツ化
参加者は、NovelJamから派生した「阿賀北ノベルジャム」2 阿賀北ノベルジャム
https://agakita-noveljam.com/でプロデューサーを務めるジャーナリストまつもとあつし氏、NovelJamに編集者や装幀担当として参加してきた編集・ライターの波野發作氏(HON.jp理事)、同じく書き手や裏方として運営を手伝ってきた漫画家・編集者の藤沢チヒロ氏、そしてワラサン出版社代表の和良拓馬氏。

第2回からは編集者が自身のやりたいことを書き手に事前にプレゼンし、書き手が「入札」する仕組みを取り入れた。創作物を完成させるだけでなく、完成した後の販促PRの取り組みも審査に加えた。
この結果、審査員から高く評価されたのは出版社に勤める現役編集者が担当した作品が多かった。「結果を出していくのは編集の力ではないかとの仮説が立てられた」(波野氏)。

ただ、「NovelJam 2018秋」では、提出作品に誤字脱字などが散見されたことなどから審査員の作家・藤谷治氏が「編集担当の人は何をしているのですか」と発言。編集者個々の力量を直接的に叱責する意味合いは薄かったが、NovelJam運営側にとっても編集者の役割を再考する機会になった。

編集者の役割でAIに代替されるものは何か?
まつもと氏がまず触れたのが、前日の基調講演を務めた作家・藤井太洋氏がパネルディスカッションで言及した、編集者の「流通のディレクターとして役割」が重くなっていること3 生成AIの急激な進化やSNSの変容とクリエイターやパブリッシャーはどのように向き合えばよいか?【HON-CF2023レポート】
https://hon.jp/news/1.0/0/45029。書き手にとって「最終的に多くの人に読んでもらい、商業(出版)であれば売れることに関わってくるので、そこはめちゃくちゃ重要だと思っている」。

https://www.aiajp.org/2019/01/what-is-the-editor-doing_20.htmlで使用した「編集の業務として何をしたことがあるか」のアンケート結果を紹介。回答では、企画、構成、本文校正、取材同行、献本発送、作家のお悩み相談、プロフィール作成、表紙カバー、ラフ作成含めおよそ100近くの業務があげられた。
ここから参加者で「AIに任せることできるもの/任せることになりそうなもの」と「絶対人間にしかできないこと」を振り分けていく作業を行った。

AIは助手席に座っている
まつもと氏は勤務する大学で学生に「AIはあくまで助手席に乗ってもらうもの」と伝えているとし、「テキストまわりの作業はどの時点でもAIの助けを得ることができる」と現時点でも相応の汎用性があることを説明。

一方、普段は出版やメディア業界から離れた業界で働く和良氏は、第2回NovelJamに編集者として参加したときに、編集の技術の有無ではなく、チームビルディングやフォロワーシップの考え方をベースにしていたことを振り返った。