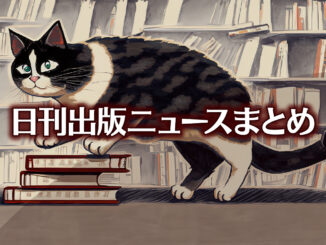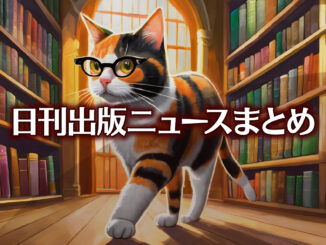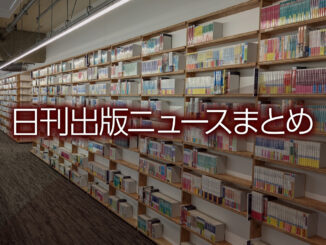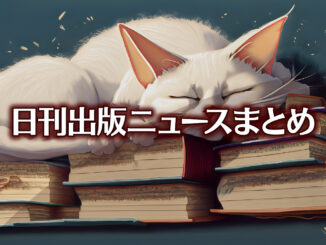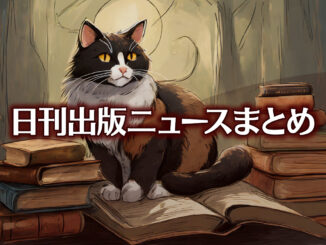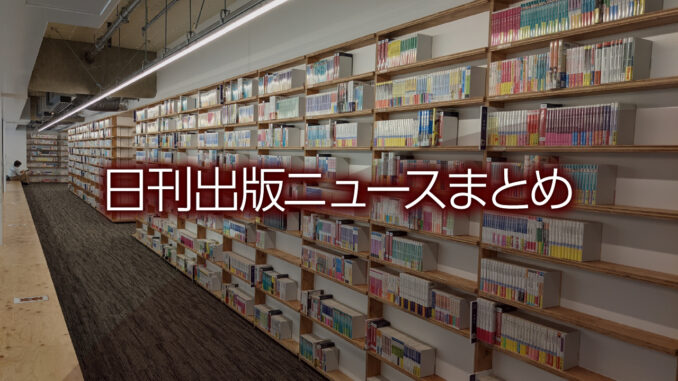
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
伝統的な取次&書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。
【目次】
- 国内
- 【決算・人事】講談社 84期売上金額ベースでは前期超え〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
- ネット投稿削除へ裁判外手続き 中傷の被害拡大防止、総務省検討〈共同通信(2023年2月22日)〉
- 企業はインボイスの「受領側」としての対応について認知が遅れている――ラクスの調査結果〈INTERNET Watch(2023年2月22日)〉
- 小説アプリ「テラーノベル」が若者に人気、マンガ化や映像化で世界的なヒットIPを目指す〈Forbes JAPAN(2023年2月22日)〉
- 盛り上がりを見せる「webtoon」制作の今 日本のクリエイターに大きなチャンスがある理由とは〈CreatorZine(2023年2月22日)〉
- プロ並みの画像を生成するAIの謎、どうやってそんなことができるのか〈日経クロステック(xTECH)(2023年2月22日)〉
- 「さわや書店」栗澤氏の初著作『本屋、地元に生きる』 KADOKAWAから発売〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
- AndroidとiOSを「独占」とする公取委の指摘は正しいか–サイドローディング解禁に潜むリスク〈CNET Japan(2023年2月22日)〉
- 「ChatGPT」メディアで活用の動きが加速 文章を書いてくれるAIはライターの仕事を奪うのか?〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月22日)〉
- 活字に親しむ新習慣 湖西高で市の電子図書館活用「デジタル朝読書」〈中日新聞しずおかWeb(2023年2月22日)〉
- トーハン 書店に体験型デジタルテーマパーク TSUTAYAレイクタウンで先行導入〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
- インターネットから始まる新たな社会像を38人の専門家が解説 『インターネット白書2023 分断する世界とインターネットガバナンス』発行 27年目を迎えたデジタル業界定番の年鑑、最新刊〈NextPublishing(2023年2月22日)〉
- 田舎に出版社を作ってベストセラーを出す方法〈版元ドットコム(2023年2月22日)〉
- ネット中傷、要求あれば原則削除すべきか 国の有識者会議が議論へ〈朝日新聞デジタル(2023年2月21日)〉
- 講談社、22年11月の税引き益4%減 漫画ヒットの反動〈日本経済新聞(2023年2月21日)〉
- インボイス制度の改正案について〈財務省(2023年2月13日)〉
- 世界
- 米国の非営利団体Library Futures Foundation、図書館と市民のためのデジタル所有権に関するポリシーペーパーを公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年2月22日)〉
- AI生成コンテンツめぐる法的責任、米最高裁が言及〈CNET Japan(2023年2月22日)〉
- ウィズコロナへ転換した中国・天津の書店や図書館を訪う〈HON.jp News Blog(2023年2月22日)〉
- Kindle Create を使用して本を EPUB 形式でエクスポート〈KDPコミュニティ(2023年2月22日)〉
- 政府によるインターネットの遮断が横行する時代、世界には新たな「デジタルノーマル」が到来した〈WIRED.jp(2023年2月21日)〉
- Authors are spamming out Kindle Books using ChatGPT〈Good e-Reader(2023年2月21日)〉
- Internet Archive Joins Library Groups at the Supreme Court〈Internet Archive Blogs(2023年2月21日)〉
- AIが書いた小説の投稿激増、ヒューゴー賞受賞SF誌が受付を一時停止〈テクノエッジ TechnoEdge(2023年2月21日)〉
- イベント
- 報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
- 令和4年度第25回日本学校図書館学会 学校図書館フォーラム「デジタル教材と書籍の未来 ―情報センターとしての学校図書館の在り方」〈日本学校図書館学会(オンライン)/2月25日〉
- 「クリエイター必見!海賊版ってなんだ?被害者だけでなく加害者になることだってあるってホント? 」〈ニコニコ生放送(オンライン)/2月26日〉
- 国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
- オンライン講演会「メタバース(仮想空間)で図書館は何ができるか~あるいはVR図書館製作奮闘記~」〈群馬大学総合情報メディアセンター(オンライン)/3月1日〉
- 第22期文化審議会第4回総会(第90回)〈文化庁(オンライン)/3月1日〉
- 電流協オープンセミナー「電子出版での海外展開の具体的な可能性 ~有望な海外市場とデジタルコミック流通の実際~」〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/3月2日〉
- 報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
- 10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
- 海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
- JPRO説明会「電子書籍活用、ためし読み、アクセシブル…JPROがもっと便利に」〈一般社団法人日本出版インフラセンター事務局(一橋講堂&オンライン)/3月6日〉
- 読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
- 本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
- 第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
- 令和4年度 ビジネス講座「本屋サミット2023 in 中之島図書館」〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
- 「デジタルアーカイブ憲章 みんなで創る総括シンポジウム」〈デジタルアーカイブ学会(御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター)/3月14日〉
- 下川和男「古い雑誌を誰でも閲覧ーーNDLデジタルコレクションをユーザ目線で」〈日本電子出版協会(オンライン)/3月14日〉
- 共同研究シンポジウム「デジタル社会は子どもの読書環境をどう豊かにできるか?〜『紙』と『デジタル』のベストミックスの模索〜」〈東京大学 発達保育実践政策学センター・ポプラ社(オンライン)/3月14日〉
- 第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
- 2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
- 宣伝
- お知らせ
国内
【決算・人事】講談社 84期売上金額ベースでは前期超え〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
ネット投稿削除へ裁判外手続き 中傷の被害拡大防止、総務省検討〈共同通信(2023年2月22日)〉

ネット投稿削除へ裁判外手続き 中傷の被害拡大防止、総務省検討 | 共同通信
インターネット上の誹謗中傷対策を議論する総務省の有識者会議は21日、問題のある投稿の迅速な削除に向け...
nordot.app
企業はインボイスの「受領側」としての対応について認知が遅れている――ラクスの調査結果〈INTERNET Watch(2023年2月22日)〉
小説アプリ「テラーノベル」が若者に人気、マンガ化や映像化で世界的なヒットIPを目指す〈Forbes JAPAN(2023年2月22日)〉
盛り上がりを見せる「webtoon」制作の今 日本のクリエイターに大きなチャンスがある理由とは〈CreatorZine(2023年2月22日)〉
プロ並みの画像を生成するAIの謎、どうやってそんなことができるのか〈日経クロステック(xTECH)(2023年2月22日)〉
「さわや書店」栗澤氏の初著作『本屋、地元に生きる』 KADOKAWAから発売〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
AndroidとiOSを「独占」とする公取委の指摘は正しいか–サイドローディング解禁に潜むリスク〈CNET Japan(2023年2月22日)〉
「ChatGPT」メディアで活用の動きが加速 文章を書いてくれるAIはライターの仕事を奪うのか?〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月22日)〉
活字に親しむ新習慣 湖西高で市の電子図書館活用「デジタル朝読書」〈中日新聞しずおかWeb(2023年2月22日)〉
トーハン 書店に体験型デジタルテーマパーク TSUTAYAレイクタウンで先行導入〈文化通信デジタル(2023年2月22日)〉
インターネットから始まる新たな社会像を38人の専門家が解説 『インターネット白書2023 分断する世界とインターネットガバナンス』発行 27年目を迎えたデジタル業界定番の年鑑、最新刊〈NextPublishing(2023年2月22日)〉
田舎に出版社を作ってベストセラーを出す方法〈版元ドットコム(2023年2月22日)〉
ネット中傷、要求あれば原則削除すべきか 国の有識者会議が議論へ〈朝日新聞デジタル(2023年2月21日)〉
講談社、22年11月の税引き益4%減 漫画ヒットの反動〈日本経済新聞(2023年2月21日)〉
インボイス制度の改正案について〈財務省(2023年2月13日)〉
世界
米国の非営利団体Library Futures Foundation、図書館と市民のためのデジタル所有権に関するポリシーペーパーを公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年2月22日)〉
AI生成コンテンツめぐる法的責任、米最高裁が言及〈CNET Japan(2023年2月22日)〉
ウィズコロナへ転換した中国・天津の書店や図書館を訪う〈HON.jp News Blog(2023年2月22日)〉
Kindle Create を使用して本を EPUB 形式でエクスポート〈KDPコミュニティ(2023年2月22日)〉
政府によるインターネットの遮断が横行する時代、世界には新たな「デジタルノーマル」が到来した〈WIRED.jp(2023年2月21日)〉
Authors are spamming out Kindle Books using ChatGPT〈Good e-Reader(2023年2月21日)〉
https://goodereader.com/blog/kindle/authors-are-spamming-out-kindle-books-using-chatgpt
goodereader.com
Internet Archive Joins Library Groups at the Supreme Court〈Internet Archive Blogs(2023年2月21日)〉
AIが書いた小説の投稿激増、ヒューゴー賞受賞SF誌が受付を一時停止〈テクノエッジ TechnoEdge(2023年2月21日)〉
イベント
報告:阪本博志(帝京大学)「大宅壮一が遺したもの」〈日本出版学会 雑誌研究部会(オンライン)/2月24日〉
令和4年度第25回日本学校図書館学会 学校図書館フォーラム「デジタル教材と書籍の未来 ―情報センターとしての学校図書館の在り方」〈日本学校図書館学会(オンライン)/2月25日〉
「クリエイター必見!海賊版ってなんだ?被害者だけでなく加害者になることだってあるってホント? 」〈ニコニコ生放送(オンライン)/2月26日〉
国立国会図書館デジタルコレクションのリニューアル〈日本電子出版協会(オンライン)/2月28日〉
オンライン講演会「メタバース(仮想空間)で図書館は何ができるか~あるいはVR図書館製作奮闘記~」〈群馬大学総合情報メディアセンター(オンライン)/3月1日〉
第22期文化審議会第4回総会(第90回)〈文化庁(オンライン)/3月1日〉
電流協オープンセミナー「電子出版での海外展開の具体的な可能性 ~有望な海外市場とデジタルコミック流通の実際~」〈電子出版制作・流通協議会(オンライン)/3月2日〉
報告:石田あゆう(会員・桃山学院大学社会学部教授)「雑誌出版とジェンダー:『婦人文藝』主宰者としての神近市子を中心に」〈日本出版学会 関西部会(オンライン)/3月4日〉
10代のマンガと読書フォーラム 座談会「ヒットマンガの裏側と読書」〈JPIC 一般財団法人 出版文化産業振興財団/3月4日〉
海外マンガ交流部会 特別講演会「フランス語圏コミックス研究」〈日本マンガ学会・専修大学現代文化研究会共催/3月5日〉
JPRO説明会「電子書籍活用、ためし読み、アクセシブル…JPROがもっと便利に」〈一般社団法人日本出版インフラセンター事務局(一橋講堂&オンライン)/3月6日〉
読書のバリアフリーを進める 「アクセシブルライブラリの開発経緯および現状と課題」「出版・図書館における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題(その2)」「ABSCの設立に向けて」〈日本出版学会 出版アクセシビリティ研究部会(オンライン)/3月8日〉
本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉

【満席につき受付終了】本屋サミット2023 in 大阪府立中之島図書館 - 大阪府立中之島図書館
近年、活字離れが叫ばれて久しい中、それでも私たちは毎日の生活の中で「本」を手放せないでいます。電子書籍やネット通販は便利で魅力的ではありますが、やはり実店舗で手に取って本を選びたい。そんな方も多いのではないでしょうか。私たちと「本」をつないでくれている本屋さん。その現状と未来について考えるため、モデレーターに梅田 蔦屋書店の北田博充氏をお迎えし、本屋の“リアル”をトークセッション形式で掘り下げてい...
www.nakanoshima-library.jp
第190回月例会「公益財団法人 大宅壮一文庫:雑誌図書館としての活動と雑誌記事索引の作成から検索まで」〈三田図書館・情報学会(オンライン)/3月11日〉
http://www.mslis.jp/monthly.html
www.mslis.jp
令和4年度 ビジネス講座「本屋サミット2023 in 中之島図書館」〈大阪府立中之島図書館/3月11日〉
「デジタルアーカイブ憲章 みんなで創る総括シンポジウム」〈デジタルアーカイブ学会(御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター)/3月14日〉
下川和男「古い雑誌を誰でも閲覧ーーNDLデジタルコレクションをユーザ目線で」〈日本電子出版協会(オンライン)/3月14日〉
共同研究シンポジウム「デジタル社会は子どもの読書環境をどう豊かにできるか?〜『紙』と『デジタル』のベストミックスの模索〜」〈東京大学 発達保育実践政策学センター・ポプラ社(オンライン)/3月14日〉
第18回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協で出会う専門図書館―そのディープな魅力に迫る―」〈国立国会図書館(オンライン)/3月22日〉
2023年4月月例研究会「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針 : 「流通」を前提としたメタデータの整備に向けて」〈日本図書館研究会情報組織化研究グループ(オンライン)/4月15日〉
宣伝
HONꓸjpの新刊が出ました。
出版ニュースまとめ&コラム2018
出版ニュースまとめ&コラム2017
出版ニュースまとめ&コラム2016
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。