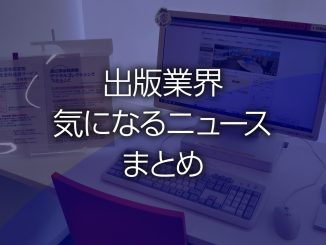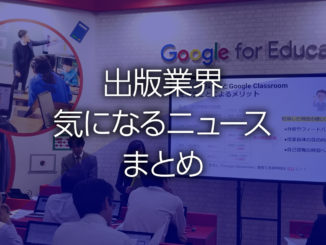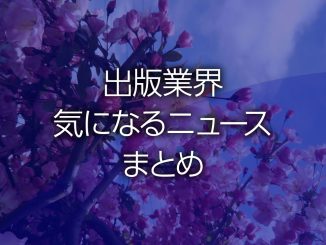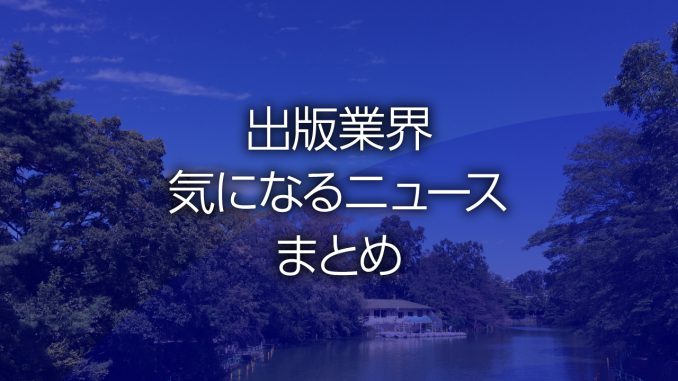
《この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です(1分600字計算)》
2018年10月1日~7日は「電子書店eBookJapanがヤフーと共同運営のebookjapanに」「インプレスR&Dの著者向けPOD出版サービス累計販売3万冊突破」などが話題に。編集長 鷹野が気になった出版業界のニュースをまとめ、独自の視点でコメントしてあります。
―― この続きは ――
《残り約3000文字》
続きは HON.jp Readers 登録ユーザー限定です。詳しくは「HON.jp Readersのご案内」をご覧ください。誰でも無料で登録できます。ユーザー登録済みの方はログインしてください。