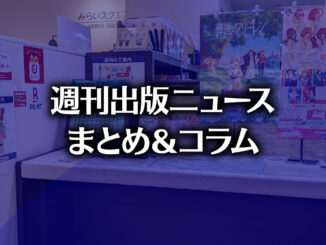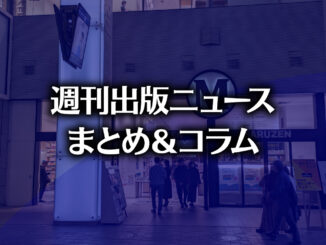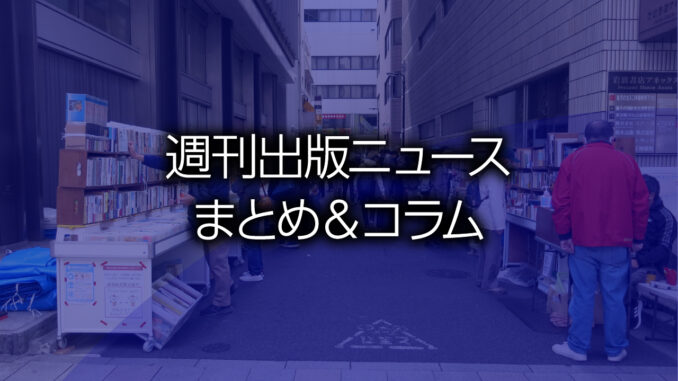
《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
2022年7月10日~16日は「漫画BANK元運営者を中国当局が処罰」「海賊版対策検討会の取りまとめ案パブコメへ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
武器の作り方のネット情報「何らかの規制を」…自民・世耕参院幹事長〈読売新聞オンライン(2022年7月11日)〉
安倍元首相銃撃事件を受け、さっそく火の玉ストレートの表現規制論が出ています。「武器の作り方を解説しているようなインターネット情報は、何らかの規制も考えていかなければいけない」との発言ですが、そういうけしからん情報が入手できるのはインターネットに限らないわけで。もしそんな表現規制を許したら、即座に書籍や雑誌へ転用可能ですし、あれも有害これも有害とどんどん拡張していくことが容易に予想できてしまいます。警戒レベルを上げておきましょう。
海賊版サイトの排除促す 総務省会議、配信事業者に〈共同通信(2022年7月13日)〉
総務省「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会」で、現状とりまとめ(案)が固まりました。傍聴しましたが、サイトブロッキングについては「他の取組の効果や被害状況を見ながら検討」というスタンスは従来のまま変わらず、ひとまずひと安心。CDNサービス事業者に対し「著作権侵害サイトに悪用されることを防止するための取組が着実に図られるよう促すことが必要」とし、ある種の原因としてクラウドフレア社を名指ししている点がトピックスでしょう。注54で田村構成員が指摘しているように、「対策を促す」だけでなく、法的根拠が必要ではないかと。なお、意見募集(パブリックコメント)もすでに始まっています。締切は8月18日。
第45回インターネット消費者取引連絡会(2022年6月23日)〈消費者庁(2022年7月15日)〉
資料掲載についてのお知らせが出ていたので念のためチェックしてみたところ、なんと議題が「NFT」でした(タイトルに入れて欲しい……)。NFTについての消費生活相談はすでに昨年から発生し始めていて、まだ件数は少ないですが、消費者庁はもう関心を寄せているようですね。法的課題や消費者保護の取り組みなどについてヒアリングが行われています。とくに「資料3 NFTと法的課題」は、NFTに過大な幻想を抱いてしまっている方に「まずはこれを読め!」と渡すのによさそうです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/internet_committee_220715_05.pdf
ネットでの誹謗中傷やフェイクニュース、総務省が規制に本腰…背景を探る〈読売新聞オンライン(2022年7月16日)〉
総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」の第二次とりまとめについて、これまでの経緯なども踏まえた詳細な解説。冒頭に挙げられているTwitter社からの「逆質問」は、私も傍聴していてライブで聞いてますが、「あーそれ言っちゃうんだ」感がありました。自主的な取り組みの要請に従う日本企業と、法的根拠が無いのになぜ従う必要があるのかと言わんばかりのアメリカ企業という、見事な対比を垣間見ることができました。それは、記事で引用されている、ヒアリング結果の評価一覧表に如実に表われています。前述の、海賊版対策でのクラウドフレア社の態度と似たような話。なお、#528でも触れましたが、構成員の方が名指しで批判していたのは、Meta社の言い分でした。
社会
電子書店は群雄割拠、競争市場で切磋琢磨 ―― デジタル出版論 第3章 第6節〈HON.jp News Blog(2022年7月14日)〉
今回のパート、昨年までの授業では「電子書籍ビジネス調査報告書2016」に載っていたカオスマップを元に、いまどうなっているか? という比較で「群雄割拠」っぷりを説明してきました。消えちゃったところ、統合されたところ、他社へ事業継承され名前が変わったところなど、10年でたくさんの変化がありました。ただ、最近は電子コミック市場が急拡大したことで経営が安定してきたのか、閉じるだの消えるだのって話は減ってきたように思います。次回はデジタル出版のメリット、その次にデメリットの話で、第3章を締めたいと思います。
経済
朝日新聞デジタル、「会員記事」を月5本まで読める「無料会員」制度を廃止。「会員記事」自体も終了【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2022年7月14日)〉
とうとう朝日新聞デジタルもハードペイウォールに。最近は無料会員が読める「会員記事」が減り、「有料会員記事」で読みたいと思う頻度が増えていたので、私は数カ月前から月額税込980円のベーシックコースを契約しています。月50本までの制限がありますが、いまのところその範囲を超えたことはありません。私にはちょうどいい感じ。あとは、古い記事を消さずに残しておいてくれたらいいのですが。
読売新聞にもデジタル限定プランがあれば契約するんですけど、こちらはまだ紙の購読が必須なんですよね……そういうやり方をいつまで続けるのか。割高だし、ゴミになるだけだから、私に新聞紙は要らない。
漫画海賊版サイト 漫画BANK 中国の元運営者に現地当局が罰金〈NHK | 事件(2022年7月14日)〉
昨年11月にアメリカの裁判所で情報開示命令が出て、前後して閉鎖された「漫画BANK」の続報です。集英社のプレスリリースなどによると「日本人向けの漫画海賊版サイトを国外で運営者していた人間に対して、現地で処罰が下されるのは今回が初めて」とのことで、画期的な事例と言えます。
ただ、犯罪収益の没収額が日本円で約33万円、罰金が約60万円と非常に安い。今後は「民事訴訟提起も含めたあらゆる可能性を検討」とのことなので、懲罰的損害賠償制度が導入された中国でどのような判決が出るか、注目しておきたいところです。
なお、7月19日のNHKクローズアップ現代では、この「漫画BANK」摘発の舞台裏について放送予定となっています。
グリー、マンガ事業に参入–縦読みマンガを主軸として企画・制作を推進〈CNET Japan(2022年7月15日)〉
子会社を設立し、プラットフォーム事業と制作スタジオ事業を立ち上げるとのこと。グリーと電子出版ってあまり聞かないなと思い調べてみたところ、2011年に「BOOK☆WALKER for GREE」、2015年に「めちゃコミック for GREE」、2021年に子会社Glossomが「ヤンマガWeb」のサービス開発とデータ分析、などが見つかりました。関わり合いがなかったわけではないようですが、さすがに「縦読みマンガの制作」となるとノウハウがないところからのスタートになるはず。どういう「人」を引っ張ってくるかがカギを握ることになるでしょう。
記事でちょっと気になったのが、「縦読みマンガを中心とした電子コミック市場」という記述。いつのまに縦スクロールマンガが電子コミック市場の中心に? と疑問になります。ピッコマの急成長とともに注目が集まっているとはいえ、日本ではまだ1~2年前からの新興市場です。調べてみたら、これはグリーのプレスリリースの記述そのまま。出典は『出版指標 年報 2022年版』とのことです。
当該号を改めて確認してみましたが「近年注目を集めている」という記述はありますけど、「縦読みマンガを中心とした電子コミック市場」といった表現は見当たりません。本件を報じているCNET以外の記事もいくつか参照してみましたが、いずれもグリーのプレスリリースにある「縦読みマンガを中心とした電子コミック市場」という記述をそのまま採用していて、ちょっと頭が痛い。言葉のアヤかもしれませんが、さすがに「中心」は無いのでは。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
善か悪か。敵か味方か。白か黒か。右か左か。ほんとうはグラデーションがあるはずなのに、単純な二分論で分断が煽られてしまっているような気がします。暴力反対! 戦争反対!(鷹野)