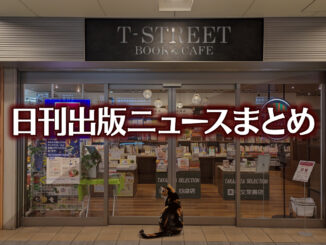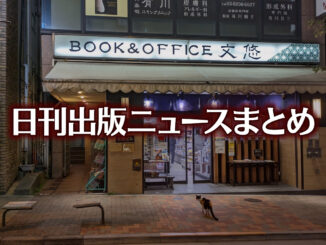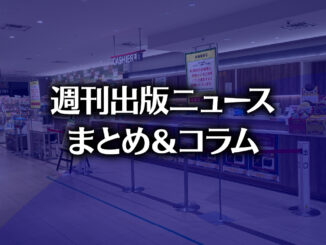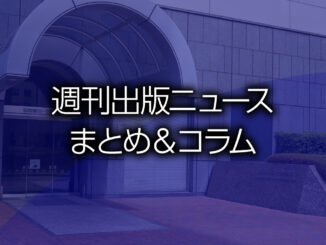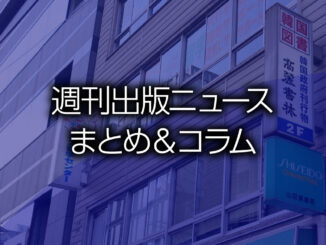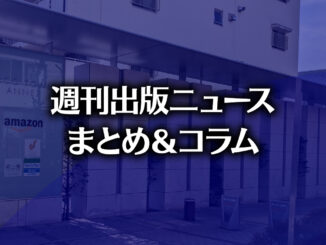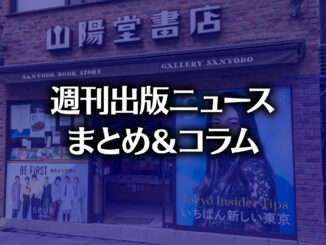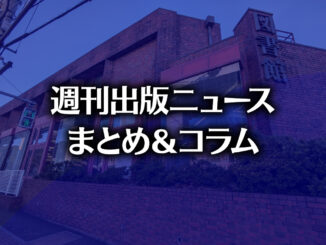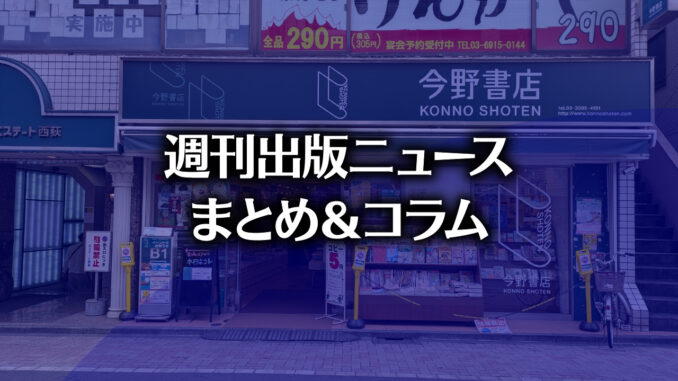
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2025年3月2日~8日は「知財高裁、海外企業への発信情報開示請求を認める判断」「クレカ表現規制は中間事業者の過剰対応が原因?」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 国立国会図書館の「遠隔複写サービス」が合法かつ便利っぽいので実際に試してみた〈KAI-YOU(2025年3月3日)〉
- 「文字量」がファン化を測定する効果指標に?ビデオリサーチ吉田氏に聞く、コンテンツメディアが抱える3つの課題とその解決策とは<後編>〈講談社C-station(2025年3月4日)〉
- GumGum、日本のデジタル広告に関する消費者意識調査レポートを公開 — プライバシー重視で高まるコンテキスト広告の信頼〈GumGum Japan株式会社のプレスリリース(2025年3月6日)〉
- クレカの表現規制、真犯人は誰か 見えてきた“構造的原因”を解説する〈ITmedia NEWS(2025年3月7日)〉
- なぜフジテレビからはCMを引き上げたのに、悪質なネット広告の出稿は止めないんですか?〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2025年3月7日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
海賊版ネット投稿者情報、知財高裁「海外企業も開示命令対象」…「国内限定」の従来判断に「柔軟な解釈必要」〈読売新聞(2025年3月3日)〉
司法判断が変わりました。「日本の業務に関するもの」の範囲が従来より広がっています。台湾企業の運営するサービスで、当該投稿が「日本語サイトに向けて行われ、投稿の一部には日本語の記載があった」ことから、台湾企業が日本人向けに提供するSIMカードを利用して行われた可能性が高いと判断したとのことです。この司法判断が定着すれば、海賊版対策が多少はやりやすくなりそう?
The Book Business Prepares for Tariff Turmoil(書籍業界は関税騒動に備える)〈Publishers Weekly(2025年3月5日)〉
いわゆる「トランプ関税」が、出版社にもコスト増をもたらすという話です。アメリカの出版社は中国の事業者に書籍の製造を委託していたり、カナダからは紙を大量に輸入していたりするので、アメリカ国内への移管の検討などを余儀なくされているようです。中も外も、1期目以上に振り回されてる感がありますね。
社会
国立国会図書館の「遠隔複写サービス」が合法かつ便利っぽいので実際に試してみた〈KAI-YOU(2025年3月3日)〉
商業メディアからこういった「実際に使ってみた」記事が出てきたのを見て、5年前のまだ法改正を検討している段階で朝日新聞が「図書館の本、スマホで閲覧可能に」と煽って大騒ぎになったことを思い出しました。
当時、慌ててカウンター記事を書いたんですよね。「入手困難資料のデジタル送信」と「複写サービスの公衆送信対応」の2つが検討されていたのに、読者には混同されていました。また、スマホで閲覧はできても、固定レイアウト版面ですから「読書」をするのは至難の業です。
実際にサービスが始まってみて、どうですか? と問いたい。「図書館の本、スマホで閲覧可能に」と書いた朝日新聞こそ、いの一番に試すべきでしょう。スマホで体験してみなさいよ。
「文字量」がファン化を測定する効果指標に?ビデオリサーチ吉田氏に聞く、コンテンツメディアが抱える3つの課題とその解決策とは<後編>〈講談社C-station(2025年3月4日)〉
うーん……その「文字の量で熱量を測っている」という情報が一般に知れ渡ると、悪用して「熱量が高いように見せかける工作」を始める人が出てくると思いますよ。まあ、ハックされたら次の効果測定手法をまた編み出せばいい、という考え方もできますけど。
GumGum、日本のデジタル広告に関する消費者意識調査レポートを公開 — プライバシー重視で高まるコンテキスト広告の信頼〈GumGum Japan株式会社のプレスリリース(2025年3月6日)〉
我が意を得たり! という調査結果。以前「コンテンツとほぼ無関係に表示される追跡型広告(パーソナライズド広告)は不快度が高いですが、コンテンツに関連した広告(コンテンツマッチ広告)は比較的許容されやすいのでは」と書いたんですが、予想通りじゃありませんか!
ただ、調査方法について「この調査は英・調査会社センサスワイド(Censuswide)が2024年10月25日から28日にかけて、日本の18歳以上の消費者1,000人を対象に行いました。」としか書いてない辺りが若干不安材料ではあります。その「日本の18歳以上の消費者1,000人」をどうやって集めたのか次第で、結果は変わりますからね。
クレカの表現規制、真犯人は誰か 見えてきた“構造的原因”を解説する〈ITmedia NEWS(2025年3月7日)〉
いわゆる「金融検閲」問題について。「見えてきた」とはいえ、まだ確定ではありません。ただ、各所にヒアリングを重ねた上での推測なので、それなりに確度は高そうです。ざっくり言うと、国際ブランドの運用ルールはそれなりに明確だけど、違反したときのペナルティーが即時取引停止&違反金請求とかなり厳しいため、中間事業者のアクワイアラや決済代行事業者が過剰な対応をしているのではないか? という推測です。
これ、3月6日のシンポジウム「金融的検閲と表現の自由」で聞いた話とも符合します。加盟店から決済代行事業者に理由を質問するだけで「そんなうるさいこと言うんだったら全部止めます」と言われるうえ「加盟店の規約違反は損害賠償請求できますからね」と脅される、という話だったんですよね。あまりに問答無用すぎて、さすがにそれは優越的地位の濫用ではないか? という気もするのですが。
その国際ブランドの運用ルール(PDF)ですが、改めて検証してみると「明確に定義」されているかはちょっと疑問です。「Visa Core Rules」の「1.3.3.4 Integrity Risk and Use of the Visa-Owned Marks(誠実性リスクとVisa所有の商標の使用)」には、以下のように記されています。
A Member must not use the Visa-Owned Marks:(会員は、Visa所有のマークを以下の目的で使用してはなりません)
・In any manner that may bring the Visa-Owned Marks or Visa Inc. or its affiliates into disrepute(Visa所有のマークまたはVisa Inc.またはその関連会社の評判を落とす可能性のある方法)
・In relation to, or for the purchase or trade of, photographs, video imagery, computer-generated images, cartoons, simulation, or any other media or activities including, but not limited to, any of the following:(写真、ビデオ画像、コンピューター生成画像、漫画、シミュレーション、またはその他のメディアまたは活動に関連して、またはその購入または取引を目的として、以下のいずれかを含むがこれらに限定されない)
– Child sexual abuse materials(児童性的虐待資料)
– Incest(近親相姦)
– Bestiality(獣姦)
– Rape (or any other non-consensual sexual behavior)(レイプ(またはその他の合意のない性的行為))
– Non-consensual mutilation of a person or body part(同意のない人または身体の一部の切断)
A Member that does not comply with these requirements will be subject to non-compliance assessments prescribed under the Visa Integrity Risk Program.(これらの要件を遵守しない会員は、ビザ・インテグリティ・リスクプログラムに規定される違反査定の対象となります)
商標利用だけの制限規程にも読めますが、最後の行の「違反査定の対象」となる点がポイントでしょう。仮に商標だけの違反だったとしても、Visaのシステム利用全体に関わってくる話になってしまうわけです。
違反のペナルティは、別の箇所に書いてありました。900ページ以上ある規約のあちこちを参照する必要があるので、読み解くのも大変です。違反の重大度や種類によって異なりますが、Visaシステムへの参加を永久に禁止(10.4.3.3)とか、月額10万米ドル(約1500万円)+不正売上金額の0.75%(セクション10.4.8.1)といった規程があることが確認できました。
また、ここに挙げられている禁止事項のうち、たとえば「Incest(近親相姦)」や「Bestiality(獣姦)」は、日本においては違法ではありませんが、他の国においては違法の場合があります。「Child sexual abuse materials(児童性的虐待資料)」は日本でも通称「児童ポルノ禁止法」で禁止されていますが、実在しない児童の性表現は対象外です。しかし、こちらも他の国においては違法の場合があります。
そして、Visaが越境取引として判断するのは、カード発行社と加盟店の国が異なる場合です[追記:当初「カード所有者」と書いていたが、正確ではなかったため修正]。つまり、日本のサービスであっても海外発行カードが利用可能で、その国で違法であれば規約違反となる可能性があります[追記:「海外から」と書いてあったが、正確ではなかったため修正]。インターネットにより越境取引が容易になったことで、他国の法律も無関係ではいられないわけです。「ニコニコ動画」が海外アクセス制限を始めましたが、恐らくこの点が理由でしょう。
他にもたとえば、どこから「Bestiality(獣姦)」にあたるのか? という問題もあります。恐らく個別に判断されることになるとは思うのですが、これが大変難しい。有名な「ケモ度の階段をのぼろう!!」の画像をご覧ください(著作者が「転載はご自由に」としています)。あなたはどこから「獣」とみなしますか?
同じように、非実在青少年(要するに被害者のいないイラスト)の性表現が違法な国において、どこから子供とみなすのか? というのもけっこう曖昧です。担当者レベルで判断が異なる可能性もあるでしょう。「明確に定義」されているようで、意外とグレーゾーンがある話だと思います。
「CSAMを無くすWG(チャイルドファンドジャパン事務局)」からの超党派議員への説明と提言。 – 山田太郎(ヤマダタロウ)〈選挙ドットコム(2025年3月5日)〉
関連して。新サイバー犯罪条約には「実在する人物に限定できる規定(14条3項)」が入れられ、国内法の制定時に限定するかしないかの選択が可能になっているそうです。前述のとおり、日本の現行法では実在しない児童の性表現は対象外ですが、これを機に「非実在表現も含めてCSAM(Child sexual abuse materials)の定義にすべき」という提言が、超党派のママパパ議連に対しなされたそうです。
チャイルド・ファンド・ジャパンは以前から「(CSAMに)マンガ、アニメ等の創作物も含めるべきである」と主張しています。ゴールポストを動かすような話ですが、もしかしたらCSAMの定義も揺らぐ可能性があるわけです。被害者がいない創作表現でも虐待とみなしたい“気持ち”はわかりますが、被害者が実在する事件の解決にこそ力を注ぐべきなのでは。
なぜフジテレビからはCMを引き上げたのに、悪質なネット広告の出稿は止めないんですか?〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2025年3月7日)〉
境治氏のコラム。電通「2024年 日本の広告費」で、「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」のうち「雑誌デジタル」は微増、「新聞デジタル」は減少傾向である点を指摘したうえで、広告主に対し「安易に運用型広告に流れすぎていませんか」と警鐘を鳴らしています。
コラムでは触れられていませんが、JICDAQの認証制度はそういう状況を変えようとしているはずなのですよね。ただ、あれだけ詐欺広告が話題になったFacebookでも「ブランドセーフティー」で認証されたままです。いいのかそれで。なんだかもうすでに有名無実化しているような気もします。
経済
売上と倫理、どっちを取りますか?「広告苦情50年史」から考えるプロマーケターの素養【JARO 川名周】〈Agenda note(2025年3月4日)〉
これは面白そうな連載。続きが楽しみです。一般論ですが、数字(予算)のプレッシャーがきつい組織ほど、倫理のタガは外れやすくなりますね。また、人事評価で数字のウェイトが高いほど、そういう組織になっていきます。目先のことしか考えられなくなっていくんですよね。
サービス開始から2年連続で300%成長 全米最大級のデジタルマンガストア『MangaPlaza』 3周年を記念したキャンペーンを多数実施!2024年の人気作品も発表!〈エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社のプレスリリース(2025年3月4日)〉
電子コミック配信サービス「MANGA MIRAI」を米国で提供開始 ~日本のマンガ作品780タイトル以上を提供!~〈株式会社メディアドゥ(2025年3月5日)〉
今年の予想で挙げている「【漫画】コンテンツ輸出の拡大」関連で2つまとめてピックアップしておきます。しかし「2年連続300%成長」って、すごいのは確かなんですけど、率だけアピールされると額が気になります。
技術
表現見直しAI「コメント添削モデル」導入後の変化をどう見るのか——山口真一・国際大准教授〈news HACK by Yahoo!ニュース(2025年3月6日)〉
グレーゾーンのコメントをAIで一律削除することはできるかもしれません。ただ、それをやってしまうと、正当な意見や批判もなくなってしまいかねません。果たしてそれは健全な言論空間と言えるでしょうか。
おっしゃるとおり! でも実際には、自社開発のAIを自慢げにアピールしている企業のプラットフォームで、そういう「AIで一律削除」みたいな雑で荒い対応をしているところも多いんですよね。そのほうが安上がりだから。FacebookとかX(旧Twitter)あたりは、誤削除被害の声があまりに多い。雑。
AI検索の要約機能でトラフィックが49%減少した企業も、これまでのSEOを無効化される悪夢にどう対応すべきか? 【生成AI事件簿】企業に求められるGAIO、AI企業によるウェブサイトのスクレイピングに課金する企業も〈JBpress(2025年3月8日)〉
AI検索の要約機能により、ソースのウェブサイトを訪問しないいわゆる「ゼロクリック」が増えていると問題視されています。なんだか、ものすごーく既視感があります。これって、AI検索が登場する前から「強調スニペット」などでも起きていたと言われてますよね。もっと前には、薄くて軽い内容のコンテンツを量産してSEO対策でPVを稼ぐ手法が問題になっていました。そういうのがアルゴリズムの改善で駆逐されていった歴史があります。
また、この「トラフィックが49%減少した企業も」という調査を行っている企業が、思いっきり本件の利害関係者であることも念頭に入れておく必要があると思いました。TollBit という企業ですが、公式サイトには以下のように記述されています。
TollBit helps over 500 publisher sites transform unauthorized AI scraping into a new revenue stream and combat ad revenue loss(TollBitは、500以上のパブリッシャーサイトが不正なAIスクレイピングを新たな収益源に変換し、広告収益の損失に対抗できるよう支援しています)
そして、記事内には「減少した分がすべて生成AIチャットボットに奪われていると仮定」と書かれていますが、トラフィックの減少要因はもちろんAI検索だけに限りません。もしかしたら、ブラックハットSEOをやっていたのが、たまたまこのタイミングで対策された結果として減少したのかもしれません。
ちなみに本件を報じているForbes誌は、商標使用権を与えた別会社にアフィリエイト目的の低品質なコンテンツをサブディレクトリで量産させる「寄生サイト」を運営していて、昨年のGoogleポリシー厳格化に伴い検索順位を急落させていることも指摘しておく必要があるでしょう。Googleを逆恨みした結果、AI OverViewsなどを批判している可能性があります。
まあ、そういう意味でも、GoogleはさっさとAI OverViews経由のトラフィックを区別できるようにすべきとは思いますが。「Discoverが大きなトラフィック源になっている」みたいな話は、Search ConsoleでDiscoverのデータが見られるようになったから出てきたわけで。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
予報通りまた急に寒くなって、雨続きでときおり雪も降り多少は積もるという不安定な気候の一週間でした。咲きかけた花がびっくりしているだろうなあ。あんまり寒いから、しばらく散歩をお休みしてしまいました。来週の予報も、昼はともかく、最低気温はけっこう低いです。寒暖の差が大きいので、お気を付けください。(鷹野)