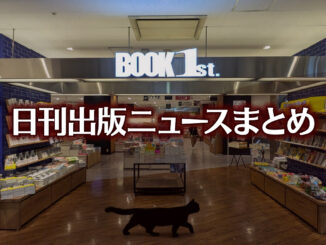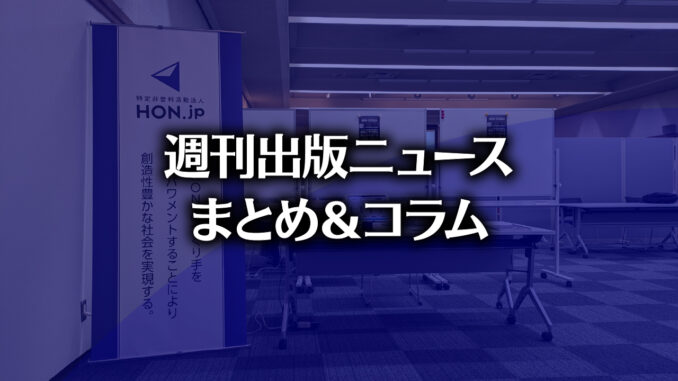
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年1月26日~2月1日は「書店活性化のための課題パブコメ結果とアクションプラン(案)公表」「Bookshop.orgが独立系書店支援の電子書籍プラットフォーム展開開始」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
「関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)」のパブリックコメントの結果を公表します〈経済産業省(2025年1月29日)〉
先週、前経済産業大臣・齋藤健氏が「パブリックコメントを踏まえた最終版が2月上旬にはできあがる」と言っていたニュースを紹介しましたが、2月に入る前に公表されました。なんとなく予想はしていましたが、書店を支援“すべきでない”側の意見も散見されます。「税金の浪費」みたいな辛辣な意見も。あと、消費税に関する意見が少ないのが意外でした(ゼロではない)。「主なご意見」とのことなので、類似意見は省略されているかもしれません。
逆に、RFIDに関する意見はけっこう多い印象です。まあ、経済産業省が補助できるのはここでしょうからね。恐らく、IT導入補助金の対象サービスにPubteXが加わる形になるのでは……と思っていたら、別件の調べ物をしていてたまたま、1月17日に開催された経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業政策研究会」第3回の資料に「書店振興プロジェクトチーム」と記載された「書店活性化に向けたアクション」プラン(案)があるのを見つけました。
ここにはすでに「バリューチェーン全体で返本を減らすため、デジタル化の支援に着手する」という記載があります。恐らくこれは、RFID関連の環境整備に補助金が出る方向で間違いないでしょう。委員名簿には野間省伸氏(講談社社長)などの名前もあります。しかし、わたくしこの研究会の存在にまったく気づいてなかった(経産省のRSSにもメルマガにも記載がない)のですが、「傍聴については、原則として認めない」ですかあ。ちょっともんにょりします。
パブコメに話を戻すと、中には「いかに返品しやすいシステムを作るか」「返品送料を、出版社も負担するスキーム」という意見もあって、びっくりしました。それ、いまよりさらに返品率が高くなるのでは? 現状でも、返本不可の注文品をしれっと返本してくるような書店も存在すると聞きます(バレると逆送され手数料もかかる行為)。なんでもガンガン返本できるようになると、出版社が一方的に在庫リスクを負う形になるから、書店は救われても出版社が潰れます。
AIが関与した動画や画像に「著作権」は認められるのか–米で指針〈CNET Japan(2025年1月31日)〉
記事を読む限り、考え方としては日本の文化庁が2023年6月時点に開催した著作権セミナー「AIと著作権」の内容と大差ない印象です。正直、いまごろここ? と思ってしまいました。まあ、昨年7月公開の1回目ではディープフェイクなどが中心だったそうですが。
文化庁は2024年3月にも法制度小委員会で取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を公表してますし、さすが“世界に先駆けて”著作権法第30条の4を整えておいただけのことはある。こと本件に関しては、世間一般の印象とは異なり、日本政府の動きは早いと思います。
社会
フジテレビ、港浩一社長と嘉納修治会長が辞任 新社長は清水賢治HD専務〈日本経済新聞(2025年1月27日)〉
隣接する業界の話なので、いちおう触れておきます。他山の石としましょう。
「接待セクハラ」、企業に責任 労働法で対応義務〈日本経済新聞(2025年1月31日)〉
関連して、こういう記事も出ていました。「取引先からのセクハラについて(勤務先)企業の責任を認めるケース」も、すでに判例があるんですね。知らなかった。
#「普通」をほどく:読まない本 タブレットやスマホでぐっと身近に〈毎日新聞(2025年1月27日)〉
読書バリアフリー法関連の話題、なのですが、見出しの「読まない本」はなんかちょっと違うぞ? と言いたい。というか、すでに毎日新聞には御意見送付済みです。だって、目を通すのも、耳で聴くのも、あるいは(点字を)指でなぞるのも、いずれも行為としては等しく「読む」でしょう。
ちなみに、漢辞海4によると「讀(読)む」は「文章を声に出してよむ。」という意味が最初で、次に「書物に目を通し理解する。」「観賞する。味わう。」とあります。昔は音読だったのが、明治時代くらいに黙読へ変わっていった歴史があるんですよね。
韓国の書店支援策と紙の本の明るい未来〈日経ビジネス電子版(2025年1月30日)〉
こちらも。ペイウォールに阻まれる手前の誰でも読める範囲に、インタビュアーがこんな質問を投げかけていて、脱力しました。
「読書」ではなく「聞書」ですか?
いやあ……「うまいこと言った」つもりでしょうけど、目で見るだけが「読書」じゃありませんよ。似たようなことが、ほぼ同時期に、別媒体で出てきたというのがなんとも言えない。これ、これから他媒体でも出てきそうだなあ。
成人向けゲームについてクレカに続いて銀行も表現規制か?日本の銀行が外国からの送金や口座開設を拒否〈Game*Spark(2025年1月30日)〉
金融庁による銀行に対するヒアリングによれば、「成人向けゲームであることだけではなく、犯収法や外為法に基づく総合判断」とのことで、
あー、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)関連ですか。反社組織が越境取引で稼いで、海外から国内へ送金するのを防がなきゃいけないわけだ。それは、金融機関側としてはガチガチな安全策をとらざるを得ないでしょう。なるほど。
「特定図書館」 私立大学中心に10機関超が登録〈The Bunka News デジタル(2025年1月31日)〉
図書館からの申込みがあるかどうかというレベルで心配していたのですが、国立国会図書館以外からも「10機関超」は申請があったようです。大学図書館だと、教授や学生からの依頼を国立国会図書館へぶん投げるわけにはいかないのかしら?
しかし、この程度の登録件数だと、SARTRASの2024年度共通目的事業・助成事業で1872万2000円の助成を受けて構築したシステムが「それ必要だった?」という話になりかねないのでは。つまり問題がSARLIBだけでなく、SARTRASにも飛び火しそうな予感。
経済
Bookshop.org challenges Amazon with new e-book platform(Bookshop.orgが新しい電子書籍プラットフォームでAmazonに挑む)〈TechCrunch(2025年1月28日)〉
ついに! ラインアップは、大手出版社すべてのコンテンツと、今春には「Draft2Digital」の自費出版タイトルも取り込む予定とのこと。書店自身のサイトを通じて直接販売した場合は、利益の100%が書店に還元されるそうです。すごいな!
あとはアプリとウェブのビューアとライブラリがどんな感じかが気になるところですが、日本からだとアプリはインストールできないっぽい。残念。Bookshop.orgはプラットフォームを提供している形なので、仮に購入した書店がなくなっても、Bookshop.orgで読み続けられる形になるでしょう。
いやー、これ日本にも来ないかな?
有料メディアの厳選記事が読めるサブスクサービス「SmartNews+」の提携メディア数が1年余りで2倍の50媒体以上に〈スマートニュース株式会社のプレスリリース(2025年1月29日)〉
ちょうどこのプレスリリースとほぼ同じタイミングに「Media Innovation Conference 2025」へリアル参加していて、「SmartNews+」の責任者の方が登壇しているセッションを聴講していました。会員数は伸びていますが、数値は明かせませんとのこと。「しかるべきタイミングに……」とおっしゃっていました。数字のない推移グラフに苦笑い。
今回加わった媒体は、毎日新聞「経済プレミア」、週刊エコノミスト、PRESIDENT Online、宣伝会議、販促会議、広報会議、PHPオンラインなど。私が「読みたいけどペイウォールの向こう側」の記事に遭遇する率がそこそこ高い媒体も多くなってきたので、そろそろ契約しようかなと思いました。
で、調べてみたら学割がある! さっそく大学のメールアドレスで契約しました。しかしこれ、有料記事すべてが「SmartNews+」で読めるわけではなく、媒体社側が選んで対象にしているようですね。ちょうどウェブで「読みたいけどペイウォールの向こう側」になった記事が、「SmartNews+」では見つけられず「ぐぬぬ」となりました。ぐぬぬ。
株式会社ドワンゴ、株式会社ブックウォーカー、 株式会社KADOKAWA Connectedによる 3社合併に関するお知らせ〈株式会社ドワンゴ(2025年1月31日)〉
これはびっくり! ドワンゴが存続会社で、ブックウォーカーとKADOKAWA Connectedは合併により消滅するそうです。これはつまり、グループ内のテック系企業(と人員)をまとめていく方向でしょうか。昨年のKADOKAWAサイバー攻撃で、ブックウォーカーとKADOKAWA Connectedからヘルプに大勢入っていたと聞いてましたが、結果的にそれが引き金になったというか、前振りみたいになってる印象です。
あと気になるのは、現・ブックウォーカー傘下を今後どうするのか。電子出版系ではちょうど1年前に、ACCESSのPUBLUS事業をブックウォーカーが子会社化しています。PUBLUS Readerはサービスにがっつり組み込まれてますから、手放すことはまずあり得ないので、いずれこちらも吸収合併していくのかな?「読書メーター」はすでに吸収合併しているからそのまま移行で問題なしでしょう。
株式会社ドワンゴ等との合併のお知らせについて〈電子書籍ストア – BOOK☆WALKER(2025年1月31日)〉
ドワンゴのプレスリリースには取引先との契約は今後も存続する旨しか記載されていなかったためか、ユーザーから「BOOK☆WALKER」の先行きについて不安視する声が散見されていました。それもあってか、当の「BOOK☆WALKER」から「サービス提供は今まで通り変わりません」というお知らせが出ていました。
技術
AI 検索経由の流入拡大、ブランドはどう適応すべきか〈DIGIDAY[日本版](2025年1月27日)〉
トラフィックの急増は主にGoogleの「Gemini(ジェミニ)」とオープンAI(OpenAI)の「ChatGPT」で無害な生理用品を検索した結果のレコメンドによるものであることがわかった。
AI検索が大きなトラフィック源になっている事例が出てきました。非常に興味深い。ちなみにGoogle Analyticsでの流入元は、「集客」→「トラフィック獲得: セッションのメインのチャネル グループ」で、アイテムを「セッションの参照元 / メディア」に切り替え、ドメイン名で検索すれば正確な数字を把握できます。
ウチの場合、GeminiもChatGPTもPerplexityも直近3カ月間のトラフィックは2桁以下と、誤差の範疇でした。トホホ。むしろGoogle DiscoverがX(旧Twitter)やYahoo!検索より上になっていて驚きました。「Media Innovation Conference 2025」では、Google検索での流入よりDiscoverからの流入のほうが多い事例も紹介されていたから、まあ、不思議ではないか。
問題は、大きなトラフィック源であるGoogle検索が、AI Overview経由か否かを区別できない点です。Search Consoleでも、まだ分かれていません。AI Overviewがメディア各社のトラフィック源として貢献しているとわかれば批判の声も小さくなると思うんですが、なんで分けないんだろう?
ChatGPT超えの中国AI「DeepSeek-R1」の衝撃〈ASCII.jp(2025年1月27日)〉
先週のAI界隈はこの話題で持ちきりでした。
「DeepSeek」ショック? 高性能な中国産AIの登場で、アジア株・米国株先物とともに下落〈ITmedia AI+(2025年1月27日)〉
DeepSeekが集める個人情報は「中華人民共和国にある安全なサーバに保存」〈ITmedia NEWS(2025年1月28日)〉
DeepSeekがデータ不正利用か OpenAIとMicrosoft調査〈日本経済新聞(2025年1月29日)〉
DeepSeekにサイバー攻撃、中国メディア「全て米国から」〈日本経済新聞(2025年1月29日)〉
……と、すでに「米中AI経済戦争勃発」の様相を呈しています。データの不正利用については「蒸留」という手法が疑われているのですが、利用規約違反ではあっても著作権法違反ではありません。罰則規定もないから、抗議する以上のことはできないかも。「そもそも、OpenAI自身が他人の著作物を無断でAIに学習させたくせに」などといった声も目にしました。うひゃー。
【PubteX】RFIDタグで出版流通を可視化、書籍トレーサビリティシステム「BOOKTRAIL」商用サービス開始〈BookLink(2025年1月30日)〉
講談社・集英社・小学館と丸紅、ICタグで本の在庫管理 100店へ導入〈日本経済新聞(2025年1月30日)〉
商用サービスが開始されました。恐らく政治的な動きと連動しているのでしょう。なお、BookLink(文化通信社の媒体)は無料で読めますが中身が薄い。日経はかなり詳しく書かれてますが、ペイウォールの向こう側です。ざっくり言うと、RFIDの装着は出版社負担ですが、書店で使うレジやリーダーは書店負担とのこと。恐らくそこへ経済産業省が補助金を出す流れになるのでしょう。書店側には棚卸作業の短縮や万引き防止、出版社側には出荷数量の調整に役立てられる、と。
お知らせ
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
父親が入院、手術には8時間以上かかったそうです。無事に終わったとの連絡は受けたけど、ちょっと心配だったのでお見舞いに。すると「明日、退院する」とのこと。はやっ! ちょっと拍子抜けしましたが、元気そうでなによりでした。「手術がうまくいったってことだね」と笑い合えたのでよしとします。(鷹野)






















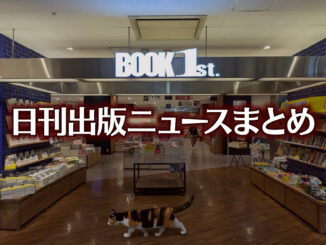
![米独立系書店支援のBookshop[.]orgが電子書籍プラットフォームを発表など 日刊出版ニュースまとめ 2025.01.30 Photo by Ryou Takano(+Adobe Firefly生成塗りつぶし“歩いている黒猫”)](https://hon.jp/news/wp-content/uploads/2025/01/news-headline20250130-326x245.jpg)