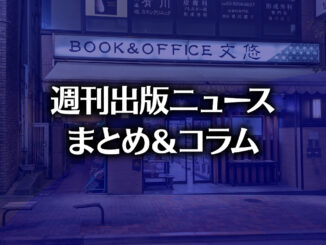《この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です(1分600字計算)》
フランスでは毎年秋に何百という文学小説が売り出される「ラントレ・リテレー(文学への回帰)」が行われ、マスコミが新刊本のニュースで埋め尽くされるが、果たしてこのカンヌ映画祭の小説バージョンともいえるお祭りが著者や出版社にとって望ましいことなのか、とニュースサイトの「フランス24」が問いかけている。
書店や図書館では9月になると文芸小説が並ぶのがフランスの秋の風物詩となっている。地下鉄メトロの広告には新刊の表紙であふれ、バスやカフェで買ったばかりの本をひもとく人が見られ、テレビをつければゴンクール賞(Prix Goncourt)は誰が取るかといった番組が相次ぐ。
この読書の祭典は8月半ばから10月の終わりまで続き、この間に576タイトルもの小説(うち翻訳書が186タイトル、94タイトルがデビュー作)が発表される。フランスでは、クリスマスの時期も合わせ、年末の4ヶ月に年間売上の半分以上が集中する。その中でもこの時期に発表されるゴンクール賞を受賞すれば、クリスマスギフトとして年末までに50万部の売り上げが見込めるという。
だが、いいことずくめではない。多くの本が集中することによって注目されずに埋もれていく小説もまた多いからだ。Actus Sud社のエディター、マリー=キャサリン・ヴァシェルは「お祭りであるとともに、悲劇でもある」という。フランスには2000店、パリだけで200店の本屋がある。ラントレ・リテレーに合わせて本をレビューするのに、書店員1人あたり21タイトルを抱えることになる、と指摘する。
多くの書店がインディペンデントであるフランスでは、どの本屋も推薦するタイトルを並べるが、在庫が足りなかったり、新人の作品が見過ごされがちになったりする。出版サイクルが早まっている昨今、鳴かず飛ばずの新人に忍耐強くつきあってくれる出版社が減っているという声もある。
ヴァシェルは「理想のシステムがまだあるはず。こういう大きなお祭りはちょっと旧いのかも、と考え直す余地もあるでしょう」という。
参考リンク
France24の記事